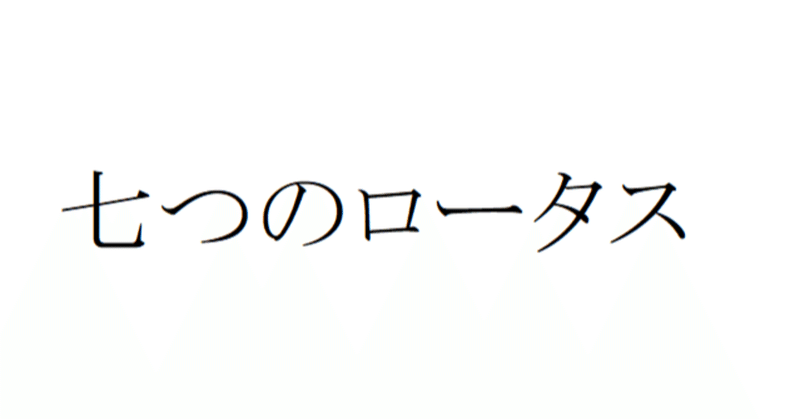
七つのロータス第5章 アルタスIII
アルタスは身を潜めた丘の頂きから、サッラの様子をうかがい、顔をしかめた。
「いけない、もう始まってるよ」
サッラの街をめぐる高い城壁の周囲は、おびただしい兵士たちに取り囲まれていた。市城の四方に向いた城門は固く閉ざされ、城壁の上には弓兵がずらりと並んでいる。
「これは、簡単には帰れそうにないなあ」
硬い土の上に身を伏せ目を凝らす。多くの兵士達は短い腰布だけを身につけた半裸で槍と小さな盾を身に付けているが、長衣を身に着けている者や、わずかではあるが革の小板を連ねた鎧を帯びている者もある。
アルタスは敵の陣立てを見定めようと、見つからぬよう大きく距離を置きながら移動する。歩兵、弓兵、騎兵、戦車、荷馬車…。偵察を続ければ続けるほど、敵のおびただしさを思い知らされる。
「一万以上はいるぞ」
「いや、三万はおります」
包囲された街を大きく半周してからアルタスが囁くと、最年長の従者が応える。
「冗談じゃない!三万もの兵隊を養える国が帝国以外にあるものか!」
「草原の彼方には、我等の知らない国があります」
アルタスはもう一度、敵の方に目を向けた。古兵の従者だから、その目算は信用できるだろう。一方、サッラの兵力はと言えば、平時には牧畜に従事している戦士階級が従者も含め約一千。戦時にのみ武器を取る市民階級を総動員しても、せいぜい五千がよいところ。これ以外にサッラの族長に臣従する非定住の遊牧民もいるが、草原のあちこちに散らばる彼等にうまく連絡がついたとしても、十あまりの部族から合計数百ほどの騎兵がやって来れば上出来だろう…。五倍以上の兵力差は簡単に埋められるものではない…。
「信じられない…。いったい連中、どこからわいて出たというんだ!」
答える者はない。この問いが意味の無いものであることは、アルタスにもわかっている。問題はこの敵を前にして、いったいどうするのか、なのである。
ほとんど丸一日かけて、大回りにサッラを取り巻く敵陣を一回りしたところで日が暮れた。敵はサッラから矢が届かぬ距離を置いて陣を張り、攻城戦の準備を進めている。一方のサッラ側も、敵が多すぎて容易に手を出せないのと、帝国からの援軍を待とうという思いがあるためだろう。互いに睨み合いながらも、全く戦闘は行われなかった。
暗くなるのを待って、身を隠した丘の陰から敵陣を覗う。敵は城門の前には多くの歩哨を配し、かがり火を焚いて警戒している。しかしそれ以外では、敵兵は天幕の中で寝静まっているようだった。月の無い夜のことである。たとえ闇の中に見張りがいたとしても、簡単に見つかる事はないだろう。従者の一人がアルタスに頷く。アルタスは従者に幾つかの刻み目を入れた矢を手渡した。これを城壁の内側へ射込むことができれば、城内の人々はアルタスの置かれている状況を知ることができる。従者は矢を帯に挟み、弓を肩に背負うと、丘を越えて城壁へと走った。這うように身を低くして走る姿は、すぐに月の無い夜に吸い込まれる様に見えなくなった。後に残ったアルタスらには、もはや待つ事しかできない。やがて敵の天幕の間をすり抜けて戻ってきた従者を、アルタスは無言で出迎え肩を叩いてねぎらった。
朝霧を透して朝日がほとんど水平に大地を照らす。アルタスは夜の寒さに強張った体を動かす事もせずに、何の動きも無い城壁をただ一心に見つめていた。やがて東門近くの城壁から狼煙が上がった。
「よし、行こう」
アルタスら五人は馬に跨った。東門に狼煙ということは、西門から味方が打って出るということだ。
サッラの分厚い城壁の四方に設けられた城門は、自体が小さな砦のような櫓門となっている。城壁から張り出して造られた建物がまたぐ通路の奥に、頑丈な両開きの扉が控えている。その扉が、見かけの重々しさにまるで似つかわしくないほど素早く開いてゆくのを見て、敵の見張りが叫び声をあげた。城門の外で城攻めの準備をしていた軍勢は、慌てて武器を取り隊列を整えようとする。城門が開ききるのも待たずに飛び出した百騎あまりのサッラ騎兵が、城門の外を固めていた歩兵の薄い隊列を突破し、矢を避ける置盾を組み立てていた兵士達に襲いかかった。
アルタスは西門の周りの敵が騎兵の襲撃に気を取られているのを確認すると、白銀の背から後に従う四騎を振り返った。
「こんな序盤戦で死ぬんじゃないぞ」
歴戦の兵でもある従者たちから返ってきたのは、無言の笑みである。アルタスもまた笑顔を返すと正面に向き直り、両の内腿で馬の腹を叩いた。白銀はすぐさま、矢のように駆け出す。開け放たれた城門に向かって、一直線に。城門、その内側で槍を構えて敵の侵入を防ぐ味方の歩兵、城門の外側で駆け回る敵兵、それらがみるみる近づいてくる。左右を振り返れば、従者たちは楔形の隊形を一歩も崩すことなく従っていた。
風を顔に受けながら、抜き身の太刀をぶら下げていた右腕を振り上げる。立ち止まった馬に跨ったまま、敵味方の戦闘を眺めていた敵兵が、後方から来た蹄音が敵だとは思わなかったのだろう、まったく無防備に振り返った。その顔面にアルタスの持つ銅の刃が、日の光に輝きながら打ち下ろされた。アルタスはたった今打ち倒した敵を振り返ることも、新たな敵に立ち向かうために白銀の脚を緩める事もしない。ただ自らの進むべき道を切り開くためにのみ太刀を振るい、脚はひたすら愛馬を急かし励まし続ける。
挟み撃ちを受けたと思った敵軍は混乱を増し、そこかしこで同士討ちが始まっていた。それを尻目に敵陣を駆け抜け、城内に突入しようと門に押し寄せる敵を背後からなぎ払って城内に転がり込む。それに続いて城内から出陣したサッラの騎兵、さらには城門を占領する好機と見た敵が入り乱れたまま城門へとなだれ込む。その瞬間、砦をくぐる門への通路でもみ合う敵味方の一団の背後で、轟音とともに土煙があがった。通路の入り口で、建物の中に隠されていた巨大な岩の一枚板が落下したのだ。重い落とし扉は、数人の敵兵を押しつぶしたのみならず、功を焦って城門に迫っていた敵を閉じ込めた。サッラの騎兵は待ち構えていた歩兵の隊列の間をすり抜けて城内に去り、狭い通路に取り残された敵は、整然と隊伍を整えた歩兵隊の長槍の餌食となるよりほかなかった。
やがて岩の落とし戸が引き上げられた時、城を囲む敵兵の目の前にあった物は、通路の奥で元通り固く閉ざされた城門、城門に押しつぶされた兵士の死体、そして通路に残る約四十人分の血の名残であった。
白銀号は全速力で城門を駆け抜けたそのままの勢いで、城門から真っ直ぐに伸びた大路をしばらく突き進んだ。ようやく脚を緩めて立ち止まった時には、城門の内側で戦う兵士達が小さく見えた。ゆっくりと馬の向きを変える。すぐ後ろには四人の従者が傷一つ負わずに控えている。アルタスは全身から力が抜けてゆくのを感じた。喉が干上がって、唾をうまく飲み込めない。
従者たちのほかにもう一人、門の方から並足でやって来るのは、五十騎を束ねる騎兵隊長。アルタスも顔を見知っている武将であった。
「よく、お戻りになりました」
「ありがとう。援護してくれたのはイッポ殿の部隊でしたか。感謝します。そちらには被害はありませんでしたか」
「幸いにも。負傷した者が二人ほどおりますが、心配するほどのものでは」
「良かった。私が戻るためだけに命を落とした兵がいては、申し訳無いですからね」
「お優しいお言葉、兵たちも喜びます」
アルタスはもう一度隊長に礼を言うと、宮殿の厩へと向かった。門の上で陣頭指揮を取っていると言う父の所へ報告に行くのが筋であろうが、早く白銀をねぎらってやりたかったので、そちらへは従者の一人を差し向けた。
厩の外の洗い場で、貴重な水をたっぷりと白銀にあびせてやる。冷たい水が愛馬の体ばかりか、アルタスの衣服をも濡らしているが、そんなことは頓着しない。従者たちは馬を厩番に任せて、早々に引き上げてしまった。彼等の馬は既に馬房に収まって、飼い葉桶に顔を突っ込んでいる。力をこめて体を拭きあげてやっていると、白銀が甘えてアルタスの肩を咥えた。
「おいおい、痛いってば」
笑いながら言ったって、馬は理解しないことはわかってはいるが、自然とこぼれてくる笑いは止めようがなかった。
「全く、乗ってる時は、真面目すぎるくらいなのに、仕事が終わったらこれだ」
そう言った途端、白銀が水桶を勢いよくひっくり返してアルタスを水浸しにした。本当はきつく叱らねばならないのだろうが、そんなことはできそうもなかった。
いつまでも白銀と戯れていたくとも、そういうわけにはいかない。館の中に足を踏み入れると、待ち構えていた館の人々から次々に声をかけられた。それぞれに一言二言返事を返しながら自室に引っ込むと、服も取らずに寝台の上に倒れこんだ。明日からはどれかの部隊の指揮を取る事になるだろう。気ままに振舞えるのも今夜限り。そう思えば眠るのは惜しいような気もするが、とにかく疲れていた。もう起き上がることはできそうにない、と思う間もなく眠りの中に滑りこんでゆく。
七つのロータス第5章について (著者による解説が不要な方は6章へお進みください)
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
