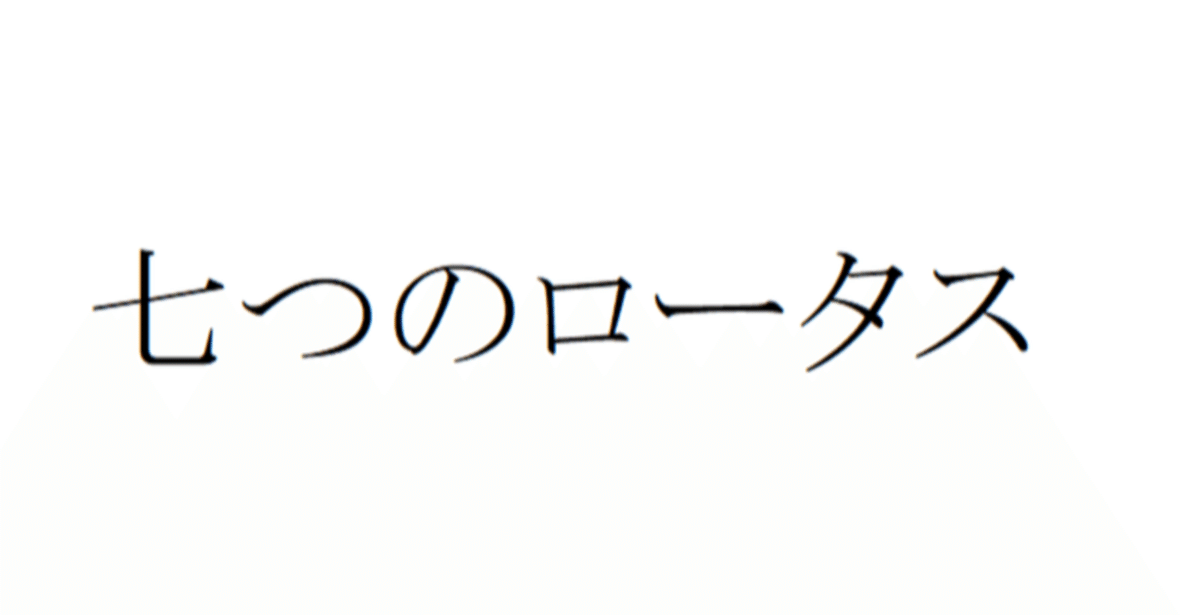
七つのロータス 第22章 パーバティII
砂埃を蹴立てて、五十頭もの馬が縦横に駆け巡る。先頭に立つのは、草原の民であるラムダ。今はパーバティが私費で買い与えたサッラ産の去勢馬に跨っている。草原の民とサッラ馬の組み合わせ。帝国騎兵の誰一人として、ラムダに触れることもできないのも無理はない。ラムダの配下の騎兵も同じ事。縦横に駆け巡る草原の民を、帝国騎兵は武器の間合いに捕らえることすらできはしない。草原の騎士たちは、帝国騎兵の一隊、五十騎が取り囲む中を縫う様にしてすり抜け、瞬く間に包囲は破綻してしまう。
「そこまで!」
パーバティの声がとんだ。帝国騎兵も草原の民も、等しく馬の脚を止める。帝国の誇る騎兵たちは人馬ともに息を荒げ、激しく喘いでいるが、ラムダたちはと言えばわずかに顔が紅潮しているかと思われる程度。馬にしても僅かな汗に湿った肌が輝いてはいるものの、滴になって流れ落ちる様子はない。
「ラーナ、ダイバ、どうだ。まだ文句があるか」
一言も返事がないのは、二人が口もきけぬほど息を切らせているばかりではなかった。捕虜である筈のラムダたちに教えを乞う事に誰よりも反発していた二人も、今となっては何も言う事はできまい。
皇軍の騎兵たちは、屈辱感をあらわにしながら、足早に兵舎へと向かっていた。ラムダたちは無言で、ただ馬の上からその姿を見ている。パーバティは馬を歩かせ、ラムダに進み寄った。
「見事なものだ…、が、その割には浮かない顔だな」
ラムダは無表情なままで、遠くを眺めていた。視線は皇軍騎兵の後姿を越えて、遥か彼方に向けられているようだ。
「俺たちは弱い立場にいる。帝国の騎兵をやむなく、とはいえここまで辱めたのだ。その上に勝ち誇って見せたりしても、得な事は一つもあるまい」
「それは道理だな」
パーバティは頷き、ラムダと同じ方向に視線を遣る。すこしばかり西に傾いた太陽が大地を炙る光の中、馬をそれぞれの従僕に預けた騎兵たちは、兵舎の屋根が作る日影の下へと逃げ込もうとしていた。
プハラ陥落の報せは突如として舞いこんできた。既に就寝していたパーバティは、寝巻きの上から部屋着を羽織っただけの姿で現れ、広間にいた人々を仰天させた。パーバティは使者が戸惑っているのも構わず、帯を結びながら、詳しい報告をするように求めた。
「夕刻、バグダに参った伝令の報告によりますと、昨夜深更、草原の民の大軍が突如プハラに襲来、これを陥落させたとの事。敵襲に際し、草原の民の行商人などが城壁の内側から呼応して門や櫓を襲ったため、城市は夜明けを待たずに陥落。市内に乱入した敵は暴虐の限りをつくしているとの事でございます」
パーバティはようやく衣服を整え終え、敷物の上に胡座をかいた。
「スカンダル殿は、当然兵を整えておられるのだろうな」
「勿論でございます。バグダの太守閣下は、バグダ駐留軍三千をただちに動員され、五百人隊ひとつを城市に残し、ほか全軍を率いてプハラに向かわれました。パーバティ将軍にも、可能な限りの兵力をもってプハラ救援に向かわれたし、との要請です」
パーバティは頷き、視線をめぐらせた。この駐屯地の主だった指揮官やほとんどの騎兵、さらにはラムダまでがここにいる。
「よかろう。駐屯地の全部隊に命令を出す。軽歩兵百を残し、全軍でプハラに向かう。出発は明朝黎明。ただちに全将兵を叩き起こして準備させよ」
各部隊の指揮官たちが、了承の返事とともに駆け出して行く。
「伝令の騎手も全員用意させよ。各屯田に分散している部隊にも兵を整え、各自プハラへ向かう様に伝えよ」
「こちらで編成を整えてから、向かうべきではないのですか」
「時間が惜しい」
ラーナが反論の声をあげたが、パーバティは一言で切って捨てる。
「ラムダ、君たちにも働いてもらう。早く行って、準備を整えておいてくれ」
「お待ち下さい!」
もう一度ラーナが遮った。
「この者は敵と同じ『草原の民』ではありませんか!」
面白い。パーバティは命令を下す将軍の表情は崩さなかったが、胸の中では密かに楽しんでいた。ラーナが自分に対して、これほど激しい口調で異議を唱えたのは初めてだったのだ。
「それがどうかしたか」
ごく何気ないふうを装って問い返す。さあ、どう答えるかな?
「この者は必ず敵に寝返ります!火を見るよりも明らかではありませんか!」
パーバティは思わず口元がほころびそうになるのを、必死で押しとどめねばならなかった。自分に対してはいつも極めて従順で、自己主張しないラーナが、このように激しく意見する事を嬉しく思ったのだ。
「ラーナはこのように言っているが、何か言う事はあるか」
ラムダは今まで黙ったまま、二人のやりとりを聞いていた。
「俺は別に将軍に忠誠を誓ったわけでもなんでもない。寝返るもなにも、やりたいように、得だと思うようにやるだけだ」
ラーナは咎めるような目でパーバティを見たが、女将軍は視線を返す事もしなかった。
「それで構わない。一緒に来て欲しい」
「承知した」
パーバティはラムダからラーナへと視線を移す。女騎兵は目を見開き、口を半ば開いたまま将軍を見ていた。
夜明けの冷気が、大河の水面から霧の糸を紡ぎ出し、幾重にも重なる紗に織り上げて、大地を覆っていた。蹄の音、人の足音、車輪の音、押し殺した囁き交わす声、武具がぶつかり擦れ合う音。汗の匂い、革の匂い、馬の匂い、青銅の匂い。行軍の緊張感に包まれて、パーバティは幸福だった。戦いに臨む前の、昂揚感。これこそが自分の求める物だと、パーバティは思った。心臓が僅かに早く打ち、普段は意識しない血の流れが、全身に感じられる。体の内側から何かが膨ら んでくるような感覚。パーバティは馬の上で、声なく笑っていた。
ラーナはパーバティの真横を馬で行く。もはや将軍による裁定は下っていたのだが、だからといって不愉快な思いがやわらぐことはなかった。
「どうした?まだ腹を立てているのか?」
パーバティが優しい声で尋ねた。
「わたしは、そんな個人的な感情で、どうこうと言っているのではありません!いつ裏切るかわからないような者を、側に置くのは危険だと申し上げているだけです!」
ラーナの怒気を含んだ言葉に、パーバティは笑顔を返した。
「思いもしなかった者に裏切られれば確かに痛手だが、あらかじめわかっていた者に裏切られても問題はない。わかっていて側に置くぶんには、色々と使い道もあるものだよ」
メロからプハラまでは十日かかったが、事態はけっして好転してはいなかった。グプタからガズニ将軍率いる一万二千、バグダからは太守スカンダル率いる二千五百がプハラ奪回のために集結していたが、堅固な城壁に囲まれた都市を前に、手を出しあぐねていた。
「皮肉なものだ。帝国が建設した城壁が、そのまま敵を利することになるとは」
パーバティが呟く。帝国軍の将軍たちは、指揮官用の陣屋の外に集まって、プハラの城壁を見上げていた。
プハラは帝国の七大都市の中では、最も南のヤマについで第二と言われる守りの堅さを誇っている。大河に沿って広がる平野のただ中、まるで水面に浮かぶ島のように孤立した岩山の上に築かれた街。自然の断崖の上に人工の城壁を巡らし、いかなる長大な梯子を作ろうとも、その上にまで届かせることは不可能。城門は三箇所に開かれてはいるが、北に向かう街道への門、同じく南への街道に通じる門、大河の船着場へと通じる西の門、いずれも荷車がすれ違うのがやっと、という道幅の斜面が平地に繋がっているだけで、大軍で攻め寄せる事など論外である。
「高名なパーバティ将軍なら、どう攻めますかね」
スカンダルが面白がっているような口調で尋ねた。最前から右手に握った杖を、繰り返し繰り返し左の掌に打ちつけている。パーバティはこの男が気に入らなかった。値踏みをされているような質問もさることながら、その口調に不誠実なものを感じたのだ。
「兵糧攻め、しかないでしょう?」
「多くの人々が街の中に捕らわれていると言うのに!敵が飢える前に、帝国の臣民が飢える事になろう!」
ガズニ将軍が声を荒げたが、パーバティは冷静な態度を崩さなかった。
「それは百も承知。だが、他に何か手段がありますか」
ガズニ将軍は言葉を返さなかった。ただパーバティを睨みつけるばかりである。
「まあ、取りあえずは厳しく包囲する他ありますまい。時が経てば、新たな知恵が浮かぶ事もありましょう」
スカンダルは笑っていた。ガズニの視線が、細面の太守に向けられた。その眼差しを見れば、今までパーバティに向けられていた苛立ちの矛先までもが、スカンダルに向かったことが見て取れる。自分の意見に賛同してもらえたとは言え、パーバティ自身もけして愉快な気分ではなかった。
二人の将軍が不愉快に思っていることを知ってか知らずか、スカンダルは薄笑いを口元に浮かべたまま、指揮杖を弄んでいた。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
