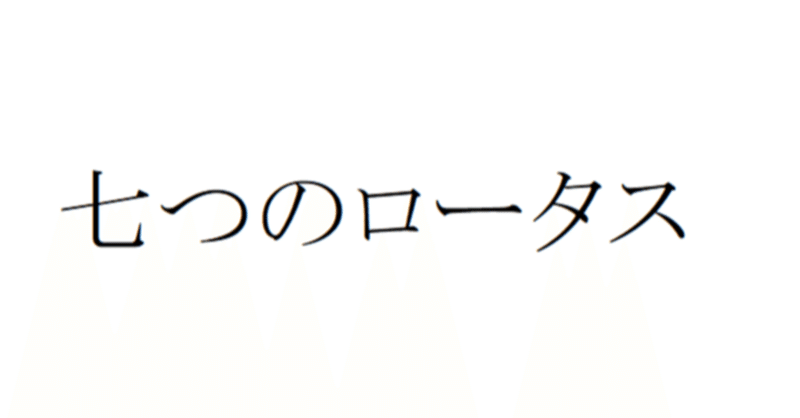
七つのロータス 第58章 カスタ
遥か地平線上に、黒く兵士たちの姿が見える。城門に向かってくる五人の騎兵は、そこからやってきた使者だ。ゲラは刺激しないよう三騎の護衛を連れて門を出た。戦車を駆る御者と、自分自身を併せて同数になる。
「カーナの代官、カスタの長子ゲラ」
投槍が届くほどの距離を置いて戦車を止め、名乗る。相手は明らかに草原の民。拙いながらも習い覚えた草原の言葉を使った。カーナは帝国の領土とは言え、周囲は国境などおかまいなしに遊牧民が草を求めて移動する土地。ここでは草原の言葉は絶対に必要だった。
「ゴブ支族の族長、ライウ。『代官』と言うのは、王のことか?」
名乗った相手はいかにも腕力で部族を統率している、という面がまえだ。ゲラは気圧されまいと、自らを鼓舞した。相手がどれほど獰猛な男であろうと、帝国の臣がたかが蛮族に怯むわけにはいかない。
「違う。諸王の王たる皇帝に代わり、この地を治める者だ。貴様ら、何ゆえ皇帝陛下の国土を侵さんとするのか」
相手の目から視線を外さずに、言葉を叩きつける。
「よくわからんな」
ライウは不機嫌そうな顔をして、吐き捨てるように言う。
「まあよい。貴様は胆が太そうだ。俺が今から言う事をよく聞け。俺たちは貴様ら泥の民たる農耕民に、人間として正しい生き方を手に入れる機会を与えにやって来た。今すぐに城壁に囲まれた街を壊し、畑を踏み潰して俺たちに加われ。そうすれば貴様らは、少しは人としてまともになれる」
わからんのはそっちが言っていることだ。口の中で呟いてみる。
「そんなことはできん」
「貴様らができないのならば、俺たちが代わりにやるまでだ。だがその時は人として扱ってもらえると思うな」
相手の視線が、ひと刹那、後ろに向けられる。ゲラもつられてそちらを見ると、食事を用意していると思しき兵士たちが、動き回っている。遠すぎて数は定かではないが、少なくとも一万はいる。あの大軍に街が襲われたら、撃退することも逃げ延びることも不可能だ。
視線を相手に戻し、やけばちな度胸で睨み据える。
「時間をくれ、父と話し合わねばならん」
ライウが声をあげて笑った。ゲラの耳には、その笑い声が酷く不快に響いた。
「明日の朝まで待とう」
蛮族の長は答えたが、まだ何か言いた気な笑顔を浮かべている。
「言いたいことを言ったのなら、もう行ったらどうだ」
暫くの睨み合いの末、ゲラは耐えきれずに言葉を洩らした。ゲラの言葉に次いで、またしても不快な笑い声。
「では、また明日な」
蛮族は馬を翻すように向きを変え、ゲラに背を向けながら悠然と去っていった。
「屈辱だ!」
戦車の縁に置いた拳を震わせながら、ゲラはただ一言吐き捨てた。
日が暮れ、灯かりが点されてから長い時間が経った。父の老いた顔は、この半日で更に皺の深さを増したようだ。
「住民の脱出は順調か」
「はい。車も騾馬も驢馬もあるだけ使って、多くの民が街を出ました。夜中までには、全員が街を出るはずです」
代官は静かに頷き、大きく息を吸いこむと静かに目を閉じた。
「後は運を天に任せるのみ、か」
そう言うと今度は、長々と息を吐き出す。カーナの代官を勤めるカスタの身には、今やとてつもない重荷が負わされているのだ。
沈黙があまりにも長く続いたので、ゲラは父が疲労のあまり、座ったまま眠り込んでしまったのだと思った。無理もない。心身ともに疲れ切っているのだろう。そう思いかけた時、カスタは再び口を開いた。
「もうよい。お前も行け」
ゲラは固く拳を握った。もう決まったことだ。そう思っても、身を裂かれる思いは変わらない。残るともう一度言ったとて、父の叱責を受けるだけだともわかっている。それでも敵を目の前にしてこの街から逃れ去るなど、容易には納得できなかった。拳を開き、また握り、視線を床に落として目を瞑り、また開いてようやく決心がついた。
「父上、ご武運を」
それだけ言うのが精一杯だった。強い意思で無理やり足を部屋の外へと向け、ゆっくり歩を進める。足取りはやがて速くなり、いつしか駆足になる。もう二度と父の姿を見ることはないだろう。沸き上がってくる叫びを噛み殺し、ゲラは廊下を急いだ。
城壁に沿う櫓の上から見下ろすと、日干し煉瓦の城壁の外を埋める大軍の姿が見て取れた。大きな街ではないので、城壁はただ日干し煉瓦を積み重ねた壁だ。ところどころに建てられた木組の櫓を除いては、見張りや弓兵を配置する事もできない。
カスタはゆっくりと視線を巡らせる。見える程近くはないが、少し北には皇軍の五百人隊が駐屯するための砦がある。もしもサッラの救援のため部隊が出払っていなければ、カーナの民もこのような悲壮な決意を固めなくとも済んだかもしれない。多勢に無勢とは言え、敵を牽制して帝都から援軍が来るまでの時間を稼ぐ望みがあっただろう。
西に目を転じれば、ただ草もまばらな荒れ野が広がっている。オアシスを伝って騎馬で五日も行けば、帝都グプタに至る。だが危急の報せが帝都に届いても、今のカーナには援軍が来るまで持ちこたえられる望みはない。
大きく息をつき、運が悪かったなと呟く。不思議と心の乱れが収まり、腹がすわってきた。
もう一度、城壁の下の軍勢に目を落とす。
「ライウとやら、皇帝陛下よりこのカーナの街を預かる代官、カスタである」
門の前に陣取った騎兵の一団の中から、とりわけ体の大きな騎兵が進み出た。
「ゴブ支族の族長、ライウ。昨日の坊やのお父上だな」
「いかにも」
「我らの配下になろうという気はないようだな」
カスタは答える代わりに片手を上げた。全部で十二の櫓に五人ずついる弓兵が、弓に矢をつがえ、狙う間もなく放つ。街の四辺を囲む一万を超える大軍に僅か六十の矢。それが戦いの始まりを告げた。
下向きに射降ろす矢の十倍以上の矢が、櫓めがけて射かけられる。カスタは跳ぶように梯子を踏んで櫓から降りた。街の中央にあるもう一つの物見櫓に向かう。あの上からなら、街全体を見下ろす事ができる。
日干し煉瓦と土でできた城壁に、木製の門扉。この程度の防御を踏みにじるのはたやすい事だ。ライウが命ずるまでもなく、服属民の兵士たちが門に 殺到する。門扉に穴を穿ち、門の脇の城壁を削って、綱を通そうというのだ。内側からも若干の妨害があるようだが、兵士たちは怯まず作業を続けた。やがて太い綱が数頭の牛に繋がれると、大きなきしみ音がして門扉が門柱ごと引き摺り倒された。重い響きとともに、土埃が舞いあがる。視界が晴れるよりも早く、待ちかねていた兵士たちが喚声をあげて城内に流れこんだ。
しかし待ち構えていたのは、城内の兵たちも同じこと。先頭で門をくぐった兵士たちを、次々と無数の矢が襲う。それでも草原の民の服属民たちは、戦友の遺骸を、あるいはまだ息のある負傷者を踏みしだいて城内へ城内へと進んだ。功労者は征服者と同等に扱い隷属の身から解放するというライウの言葉以上に、長い忍従の生活の憂さを晴らす略奪への欲望が彼らを駆りたてていた。
城門の内側で狙いをつけていた弓兵は、三回連続で矢を浴びせると、建物の陰へと姿を消した。統率を失った服属民の兵士たちは、ある者は弓兵の姿を追い、ある者は略奪品を求めて建物の中を探しにかかった。
カスタは中心から街全体を見下ろし、敵の動きを一人残さずとらえていた。
「よし、北側からやるぞ」
敵の一隊は目ざとくも食糧庫に向かっていた。二十名ほどの敵兵が食糧庫に入ったところで、潜んでいた兵士が、食糧庫の入口を閉ざし枯柴を積み上げて火を放った。
それが合図となり、街中に潜んでいた兵士たちが、敵の周囲に次々に火をつけてまわった。建物の陰に隠され、あるいは堂々と積み上げられた柴や薪の山が燃え上がる。松明を持って忍び足で駆け寄る者、狙い正しく火矢を射ち込む者。幸いにも強い風が炎を煽り、侵入者を分断した。
炎が木材を飲み込んでゆく音を貫いて、人の声が響く。恐怖や憤怒や困惑や興奮を、敵も味方も叫び声にして吐き出しあっているかのように。
なかなかやる。味方の兵士たちが炎に閉じ込められ、焼かれてゆく臭いが漂う中、ライウは笑顔を浮かべていた。壊れた門を通して見える内側は、い まやすっかり火に包まれている。にもかかわらず門から外に逃げ出してくる兵士は、驚くほど少ない。多数の兵士たちは互いに逃げる邪魔をしあって火に巻かれたか、あるいは炎で巧妙に分断されて各個撃破されているのだろう。服属民が何人死のうが知ったことではないが、敵の戦い振りは見ておきたいものだ。入口の内側で炎がおさまったなら、部族の戦士を連れて城壁の中へ入ってみようか。ライウは心が浮き立っているのを感じた。久しぶりに楽しめそうな戦いだ。
天に黒々とした煙が上がる。ゲラは戦車の上で身をねじって、煙を見上げた。
「父上……」
昨夜のやりとりが脳裡に甦る。残って戦おうとする息子に、カスタは避難民の護衛を命じた。長い議論の末にその勤めを受け入れたゲラが、必ず仇を討つと言ったが代官はそれも禁じた。敵討に目を曇らせず、帝国の為に最善と思えることをせよと、カスタは諭した。ゲラはこれも受け入れるほかなかった。
天に昇る煙から目を引き離すには、強い気力が必要だった。それでもゲラは前を向き、避難民たちを励ます仕事に戻った。青空を覆おうとしている煙が目を向けずとも感じられて、背を追いたてられている気分と、引きとめられる気分を同時に味あわせた。
今や城壁の内側全体が燃えさかり、炎を上げている。カスタが十名ほどの兵士と篭もる物見櫓にも、いつ火は燃え移るかもしれない。それでも退路も ない炎の中で、戦いは続いていた。街の守りに志願したのは引退した元兵士が中心だったが、古兵たちは巧みに矢を射掛けては炎の後に紛れこむ戦法を繰り返し、矢が尽きれば剣を抜いて数に勝る敵に突っ込んでいった。
「どうだ!わずか二百の手勢で、一万の敵を半日足止めしてやったぞ!」
代官が満面の笑顔を浮かべると、疲れきった兵士たちの顔にも笑みがこぼれた。カスタは城壁の外に目をやる。外で待機している部隊に動きはない。敵は全住民が街に立て篭もって抵抗しているのだと誤認したのだろうか。とにかく街から避難した人々を追う者はいない。命を捨てた甲斐があったというものだ。
それでもカスタの目は、自己満足に酔ってばかりはいなかった。炎の中で右往左往している敵の中で、整然と物見櫓に向かってくる一隊がある。また火勢の衰えた門の内側には、新手の敵が入り、隊列を組みなおしている。
「そろそろ終わりか」
カスタが呟くと、櫓の上に詰めていた兵士の半数が、敵を食い止めるため梯子を降りていった。やがて敵が梯子を登ってくると、更に三人がその前に立ちはだかる。
皇帝の代理人たる代官は、懐から短刀を抜き己の首筋に当てて、最後に残った兵士を見た。
「我々は良く戦ったな」
そう言って軽く笑うと、大柄な兵士は黙って頷いた。
カスタの手に力が入る。と、カスタはもう一度力を抜き、刃を首から離した。
「やめた。自害などつまらぬ」
代官は刃を両手でしっかりと握りなおすと、叫びながら走った。全ての兵士を片付けて櫓に登ってきた敵は、槍を構える暇もなく、代官の体当たりを受けた。体が宙で傾き、足が踏み板を離れる。四人、五人と敵が転落に巻きこまれ、遥か下の地面に叩きつけられた。
最後に残った兵士は、敵がなおも梯子を登ってくるのを見て、材木を繋ぎとめる綱に幾度も剣を叩きこんだ。右へ左へと櫓は大きく揺らぎ、敵兵を梯子から揺り落とす。繊維の千切れ飛ぶ音、材木の避ける音、悲鳴と怒号、そして櫓は既に土台を焼き始めていた炎の中へ崩れ落ちた。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
