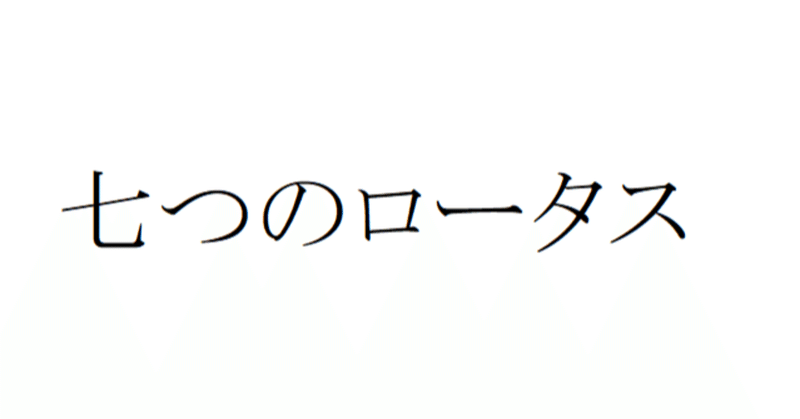
七つのロータス第4章 カライ
皇宮の広間は、サッラからの新たな知らせに色めき立った。同盟国が攻撃されれば、当然、皇軍を出して救わねばならぬ。しかし実際には敵の軍勢はまだ姿を見せてはいない。とは言え他の都市が攻略された勢いから言えば、敵の出現がグプタに伝えられるころには、すでにサッラは攻め落とされているかもしれない。援軍を求めるカライの弁舌は冴え渡ったが、摂政の発言に導かれて会議は次第に慎重論が優勢になっていった。
「先ほどからサッラの危険と、軍を動かす金とを天秤にかけるような議論ばかりだが」
議論の流れを変えたのは、若い武将の発言だった。
「帝国の威信はなにものにも替えられないのですぞ。ここでサッラをみすみす攻め落とされるような事があれば、他の同盟国の離反を招く事は必定。さすれば、今日惜しんだ金の何十倍、いや何百倍という金が必要となりましょう。そればかりではない!かつての同盟国との間に干戈を交えるという悲劇は、帝の国土を荒らし、多くの兵士たちの命を無意味に失わせる事になりましょう。この場で、国中にその智慧を称えられる人々が、わずかの金を惜しんだばかりにそうなるのです」
若い武将は立ちあがり、身振りを交えて熱弁を振るった。
カライは若い武将の顔を眺めながら、名前を思い出そうとしていた。初めて見る顔だということは、ここ一、二年のうちに宮殿の会議に参加できるようになったばかり、だということだ。それはこの武将の年齢からも不自然ではない。突然、暗い洞穴から陽光の輝く大地に顔を出したような感覚があった。帝国全十四軍の指揮官中で最年少と言えば、帝都の東方を守護する鎮東軍の将軍、二四歳のサイスである。なるほど、あれがパーバティの息子か。そう思えば顔立ちなど、よく似ている。カライはずっと昔、今のように軍議の席で出合った人物の姿を思い浮かべた。
「征東軍とわが鎮東軍になにとぞ出陣の命令を頂きたい。それに近衛軍にも遠征の準備をさせておくべきです。重ねて申し上げますが、例えサッラの危機が杞憂に終わったとしても、皇軍の迅速な行動を見せる事は、他の同盟国に対して帝の力を示す事になるでしょう。いったいどうして、このまま手をこまねいている、 などという事が得だと思われるのか、逆に伺いたい!」
帝国の常備軍は帝都グプタ以外の六都市を守護する各一軍。帝都の北・東・南を守護する鎮北、鎮東、鎮南の各一軍。帝都の西は大河に面しているため、これを守護する一軍は水軍と称する。更に大河下流の同盟諸国の中に駐屯する征北、同じく上流の征南、帝国の東方に広がる平原の同盟諸国を守護する征東、大河の対岸に基地を置く征西の各一軍。以上一四軍がそれぞれ三千の兵力からなる。これとは別に帝都に駐留する近衛軍があり、一万の兵力を持つ。サイスが自分の鎮東軍と一緒に征東軍の名を出したのは、持ち場の問題だった。
「口が過ぎはしないか、サイス殿」
摂政が低いしかし鋭い、凄みのきいた声で言った。人々はこれで議論の行方は決したと考えた。ところが摂政ジャイヌはしばし無言で、考えをめぐらせているようだった。
「よかろう。鎮東軍は明日までに準備を整え出陣せよ。サッラに敵があれば、征東軍と合流し救援。全体の指揮権は征東軍のマライ将軍に委ねよ。敵を認められぬ場合は、サッラ城外に軍を留め、別命あるまで警戒にあたれ」
滅多に自分の考えを曲げない摂政の口から、サイスの提案を追認する言葉が漏れると、一同の間にざわめきが広がった。
「よろしいかな。陛下」
ジャイヌは肩越しに皇帝を振り返り、承認の言葉を受けた。それが形式だけのものであることは、その場の誰もが知っている。
「将軍は早く功を立てたくてならぬようだのう」
ジャイヌが散会を告げた直後、近衛将軍のプトラが含み笑いとともに呟いた。サイスはプトラを一瞥したが、無言のまま立ち去った。
カライは列柱を配した回廊を少しばかり軽くなった心で歩いていた。穏やかな陽射しと、涼やかに吹き抜けてゆく風が心地よい。日の当たる場所に立っていても、汗一つかかないのがなにやら不思議な気がする。砂と小石の荒れた大地に囲まれたサッラとは、太陽自体が別物であるかのようだ。
帝国から援軍を派遣させるという大任を、首尾よく果たすことが出来た。うまく敵を撃退して、そのままタラスを解放することができればいいのだが…。タラスが帝国の同盟国となれば、長年帝国防衛の最前線を担ってきたサッラの負担も軽くなるというもの…。カライの物思いがそこまで進んだところで、二人の男が話す声が聞こえた。
「あやつはジャイヌ派というわけでもあるまいに!帝都から鎮東軍を離せば、それだけで近衛を押さえているジャイヌに逆らいがたくなるというくらいのことがわからぬのかのう」
「あれはただの、いくさバカですからな。政治的な事には頭が回らぬのでしょう」
話題になっているのが、若き将軍サイスのことであるのは明らかだった。カライは興味をそそられて、声のする方に目を向ける。声の主は宮廷における反ジャイヌ派の中心と言われているネ・ピアとハジャルゴの二人だった。二人とも廷臣というわけではなく、帝都の城外に持つ広大な荘園を地盤とする地主貴族である。それ故、宮廷からの禄以外に経済的基盤を持たない廷臣たちに比べ、自由にものが言える立場にあった。それにしても、誰が聞いているかも知れない場所で、ここまでおおっぴらにこのような事を口にするとは…。カライは柱の陰に身を潜めて聞き耳をたてながら、宮廷内の微妙な空気の変化を感じ取った。
「いくさバカか、うまいことを言う。思えば奴の親もそんなふうだったな。親子揃って、困ったものだ」
ネ・ピアは愉快そうにそう言いながら笑った。
「人の親の悪口とは、あまり趣味が良いとは言えませんな」
険を含んだ新たな声に、カライは柱の陰から頭を突き出して覗きこんだ。噂話に興じていた二人の前に立ちはだかっているのは、鎮東軍の将サイスその人だった。
「おお、これは失敬。ご本人が聞いておられるとは!」
ハジャルゴは悪びれる様子もなく、笑いながらそう言って見せた。
「まあ、事あるごとに親の名を出されるのが嫌なら、早く乳離れすることだな」
二人の高官は笑いながら立ち去り、後には屈辱に震える若者が残った。
皇宮の庭園はそろそろ真上にかかろうという太陽の光を受けて、目も眩むばかりの緑色の輝きに包まれていた。柔らかな下草の間に不規則に植えられた様々な果樹が、「緑滴るグプタ」と詩人の謡う帝都の豊かさを見せつけている。
「ここでは皆、わたしが将軍になれたのは親の力だと思っているのです」
サイスが力のない声で言った。それはほとんど呟き、と言ってもいいようなものだった。憐れに思って庭園の散策に誘ってはみたものの、カライにはこの若者を慰める言葉も見つけられず、ただ隣に座って空を見上げるばかりである。
「大河の下流で五百人隊長として手柄を立ててきたのに、ここでは誰もそんなこと顧みてもくれない…」
「征北軍で?」
「はい」
「それでは、パーバティ殿の下で戦ってきたのだね」
「それも良くなかったのかもしれません。親の指揮下で戦っても、その武勲は正当に評価してもらえないのです。誇張されているのではないか、と」
「しかしそなたの武勲は事実なのであろう」
「勿論です!」
「ならば、しばし武勇伝を聞かせてはもらえまいか?」
大河の下流に点在する同盟諸国の間に駐屯する征北軍は、皇軍で最も忙しい部隊である。同盟国同士の間での諍いを調停し、同盟国内の政争に介入し、他国や蛮族の侵入に目を光らせ、山賊の跳梁に対してはこれを鎮圧する。それでいて屯田制をとっているのは他の部隊と同じなので、食料は自ら耕作することで賄わねばならない。
征北軍時代の苦労と殊勲を語るサイスの舌は、止まる事を知らないかのようだった。カライはそんな若者の姿を微笑ましく思い、また喋るにつれて相手の心から憂いが抜け出して行くのが感じられる事も喜んだ。やがて若武者は話を締めくくった。
「わたしは今度の戦いで、自分の武勇を示すつもりでおります。そうすれば、多少は敬意をはらってもらえるようになるでしょう。私自身のためばかりでなく、母の名誉のためにもそうしなくては!」
「サッラの人間として、頼もしく思いますぞ。パーバティ殿は良き子息を持たれた」
カライはかつて帝都で会った事のある女武者・パーバティの姿を思い浮かべていた。美しく気高かったパーバティは今も変わらずにいるのだろうか。柔らかな微笑の後に、皇軍のどの将軍よりも猛々しい魂を隠し持っていた乙女。カライは遠い昔の記憶と共に、かつて抱いたほのかな恋慕の情までが蘇ってきたことに苦笑する。自分は年老いた。パーバティだっていつまでも乙女ではあるまいに…。その証拠に、今、目の前にいる青年は何者だ?
「では、わたしはもう行かなくては。そろそろわたしの部隊にも、早馬で出陣の命令が届いている事でしょう。将軍が待たせたために部隊の出陣が遅れたというのでは、示しがつきません」
サイスの言葉がカライの物思いを破った。戦いに向かう直前とはとても思えない、穏やかな笑顔が自分に向けられている。カライは慌てて立ちあがり、別れの口上を述べた。果樹の葉は陽を受けて燃えるように輝き、風はあくまで軽く穏やかだった。
七つのロータス第4章について(著者による解説が不要な方は3章へお進みください)
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
