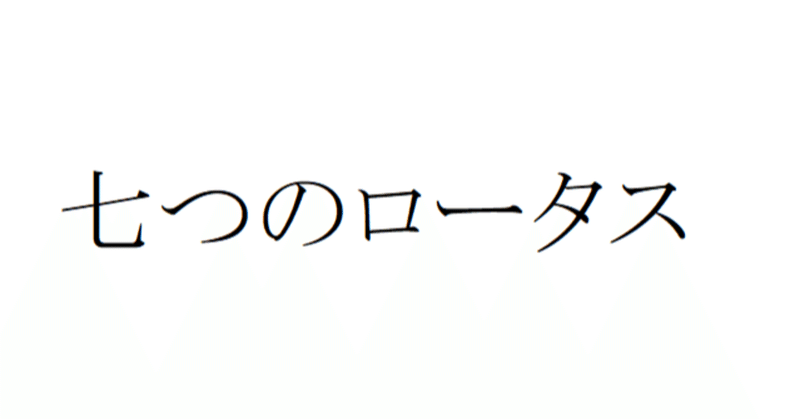
七つのロータス第6章 無名の兵士たち
城壁の上から見下ろすと、まるで真っ黒な水をたたえた海のように、闇が実体を持って感じられる。わずかな灯し火と星明りがささやかな抵抗を試みてはいるが、月の無い夜は闇が支配していた。城壁の上を足元に気を配りながら、ゆっくりと進む。二階建てになった門の部分をはじめとして、要所要所に配されたかがり火の明かりが頼りだ。次のかがり火の所まで辿り着いたら、火の番をしている見張りと二言三言言葉を交わして、もう一度来た道を戻る。それを十何回か繰り返せば、交代がやってくる。寝床につくまでは、まだまだ時間がかかりそうだ。兵士は高い城壁の上を吹き抜けてゆく風に身を縮めた。昼間の暑熱を裏返しにしたような夜の寒気である。麻の短衣の上から毛織のマントを体に巻きつけてはいても、剥き出しの足元や首筋から寒気が入りこんでくる。
視界の端で、かすかに闇が揺らめいたような気がした。気になって足を止めて、そちらの方に目をこらす。遠くのかがり火も届かぬ闇の中で、またしてもかすかな揺らめきがあった。炎熱の荒野で見かける陽炎によく似ていたが、一瞬で消えてしまう。それにそもそも、この寒い夜中に陽炎のたつ筈も無い。耳が痛くなるほどの無音の中で、息を殺してこの不思議を見届けようとする兵士の目の前に、更に新たな不思議が姿を現した。さっきよりずっと近いところでゆらめきが起こり、二つの白い小さな物が宙を浮かんで滑るように動いた。一対の白に一度気がつけば、もう少し遠くにも同じ物が二組飛んでいるのが見分けられる。見張りの兵士は、それがいったい何物なのか確かめようと、城壁の上で歩を進めた。
突然、腹から胸の内側へ向かって、恐ろしく冷たい感覚が走り抜けた。両腕に鳥肌が立ち、驚いて立ち止まる。その瞬間、白い物の正体を思い知らされた。視界の中、手を伸ばせば届きそうな距離に突然現れたそれは、人間の目なのだとわかった。そして、それを悟った途端、もう一つの不思議も解決してしまった。さきの冷たい感覚が、突如として耐えがたい痛みに姿を変えたのだ。刃で傷つけられると最初痛みではなく冷たさを感じる、というのは聞いた事があった。しかし、まさか自分で体験する事になろうとは。気がつくと足に細かい震えが走っていた。震えは次第に振れ幅を増してゆき、遂に膝が折れる。思わず前に差し出した両手に、固くて柔らかな物が触れた。煤で真っ黒く塗った、人間の体。
「敵だぁ!敵だぁ!」
必死で相手の体にしがみつこうとする腕は、荒々しく振りほどかれ、兵士は城壁上の通路に倒れた。胸の中の息を使い尽くしてしまったのか、もはや声は出ない。新たに息を吸い込むことができない。ただ傷口を手で押さえたまま、空気を求めて口を開け閉めし、苦悶にのたうちまわるばかりである。涙にじむ眼では、 頬を擦りつけている通路に、敷かれた煉瓦すら見ることはできなかった。
敵襲を報せる声が城門の櫓に届いた。待機していた兵士たちが、手に手に槍や松明を持って城壁の上へと現れる。一団となって進む兵士たちにも、最初は事態が飲みこめてはいなかった。
「何かが動いている」
一人の言葉に全員が目をこらす。松明を手にした者は、前方を照らそうとして差し出す。確かに暗闇の中でうごめく物があるようだ。
「あれが、敵か?」
兵士たちは槍を構え、通路を一線に並んで、ゆっくりと進む。用心しながらも、前方にある物を見定めようと。突然、悲鳴をあげて兵士の一人が倒れた。長い投槍が兵士の体に刺さったまま、ゆっくりと角度を減じてやがて軽い音をたてて床を叩いた。
「敵だ!」
一人の兵士が援軍を呼ぶよう命じられて走る。他の兵士たちは再び隊列を整え、前方の人影に向かった。
最初は整然としていた隊列も、あっという間に混戦となって消滅した。はっきりと見分けられぬ敵と、松明の明かりと気配を頼りに戦う。城壁から落下する者の叫び声が聞こえたが、それが味方のものか、敵だったのかわかった者はいなかった。一人の兵士が城壁の外から敵が現れたのを見て、槍で突いた。敵は体勢を崩して、城壁の外へ転がりおちる。兵士はたった今、敵が立っていた場所を覗きこんだ。
「梯子だ!連中、梯子で登ってくる!」
別の兵士も、それを見にやってきた。二人がかりで梯子をひっくり返そうとしてみるが、びくともしない。
「斧だ!斧を持って来い!」
また一人の兵士が駆け出していく。それを追いかけようとした敵を、背後から槍で貫いた兵士がいる。いったい敵が何人いるのか、自分たちが有利なのか不利なのか、それすらわからない。
隣にいた兵士が血しぶきをあげて倒れた。宙に浮かぶような一対の目と、かろうじて見分けられる人型の輪郭。敵の武器が剣であることが、初めてわかった。 思い切り突き出した槍の先に、強い手応え。くぐもった叫び声と共に、敵が倒れる。もぎ取られそうになった槍を慌てて引っ込める。また一人の敵が梯子を上ってくる音に気付いて、振り返りざまにその敵も倒す。息が上がって座りこみたくなるのをこらえて、もう一度向き直る。敵も相当倒した筈なのだが、味方もまた半分ほどに減ってしまっている。いくつかの松明は煉瓦の上に落ちて、弱々しい炎をあげていた。
怒号と悲鳴が支配する中で、姿の見えない仲間の名を呼んでみたが、応える者はなかった。息が整うのを待ってもう一度槍を構えてはみたが、まだ身動きする気にならない。二つの人影が近づいてくるのに気付いて、ともかくもそちらに槍を向けようとしたが、敵が間合いを詰めるほうが早かった。一方の剣が左肩に食いこみ、もう一方の剣が真横から脇腹を貫く。腕から力が抜け落ち、槍を取り落とす。槍の柄の上に、兵士自身も崩れ落ちる。全ては暗黒の中に引き込まれた。 武装を整えた隊が援軍にやって来るのも、瀕死の兵士にはわからなかった。
東の空に青みがさしてから、どれほど経っただろう。徐々に空は明るさを増し、日の出まではまだいくらか時間があるとは言え、城壁の上から闇は払われ、隠されていた物事を明らかに照らし始めている。長く恐ろしい夜が、追い払われつつあるのだ。城壁の各所、各々の持ち場で警戒していた兵士たちは、自らの周囲に危険が無い事を実感して安堵の息をつく。敵と遭遇して傷ついた兵士にとっては、朝日は新たな命に等しい価値があった。城壁の上、そこかしこにうずくまり、あるいは横たわっていた負傷者、そして死者は安全を確認してやって来た人々によって運ばれていった。
族長のゾラが宮殿の広間から、南門の近くの天幕に移った時には、既に朝日が姿を現し城壁をほとんど真横から照らしていた。市城の周囲を囲む敵も既に動き出しており、城門を破ろうと破城槌を打ちつける轟音が街中に響いている。
「まさか、こんなことになろうとはな」
ゾラは黒々とした顎鬚に手をやり、誰に言うともなく言った。
「門の二階に立て篭もった連中以外には、もう敵は全く残っていないのだな」
「はい。武装した敵は城壁上や、城内にはおりません。ただ、どこかに潜んでいたり、ということが無いとも言えませんので、ただ今手空きの兵士全員で捜索中です」
「厄介なことだな」
幕僚の一人の言葉に、ゾラは呟いた。
夜の間に全ての梯子は壊してしまうことができた。長い梯子がそれだけしか用意できなかったのか、七本という少数であったのが幸いだった。これがもし二十本も梯子があれば、とうてい防ぎきれなかっただろう。大きな被害を出しながらも、ほとんどの場所で敵を全滅させることができた。たった一つの例外が、この南門なのである。
門扉に巨大な破城槌が打ちつけられる音が、また天幕を揺るがした。壊れかけた門がたてる軋みが、攻撃される毎にいよいよ大きくなっているような気がする。門を破られるのは時間の問題であると、その場の誰もが感じていた。
「このまま手をこまねいているくらいなら、騎兵を出すべきじゃないんですか」
騎兵隊長たちの一員として参加していたアルタスが発言した。
「無茶を言うな、多勢に無勢だ」
アルタスの意見を一蹴したゾラは、顎鬚に手をやりじっと考え込んだ。結局の所、門の二階を取り戻す事ができるかどうかに全てはかかっている。今はただ待つ事しかできないのだった。
城門の二階では兵士たちが、必死に堅固な扉を打ち破ろうとしていた。一抱えもある丸太を、数人がかりで勢いよく扉に打ちつける。それはちょうど階下で敵が城門に破城槌を打ちつけているのを、そのまま小規模にしたものだった。幾度か打ちつけると、扉の板に破れ目が生じた。兵士たちはそこに金梃がわりの剣を差し入れ、破れ目を広げる。内側のかんぬきを外そうと破れ目に腕を差し入れた兵士が内側から切りつけられ、悲鳴を上げて退いた。兵士は血まみれの腕を押さえて床にうずくまる。
「どけ!かんぬきごとぶち破る!」
百人隊長の声で、扉にとりついていた兵士たちが散る。そこへ再び丸太が叩きこまれた。木材の裂ける音、金具のきしむ音が響く。
「よし、もう一度いくぞ!」
兵士たちが叫び声とともにぶつかってゆくと、遂に扉の内側のかんぬきが折れ、扉は内側にはじけ飛んだ。
部屋の中には三人の敵兵が残っていたが、更に内側の部屋への扉は閉ざされていた。三人は果敢にも剣を手にサッラの兵に立ち向かったが、瞬く間に片付けられた。最奥の部屋への扉は石材を組んだ頑丈な通路の奥に横向きに取りつけられており、通路の幅が狭いため先の扉を破った丸太は使えない。大槌を持った兵士が何度か扉を叩いてみたが、頑丈な扉を破ることができるとは思えなかった。
「火だ。火をかける」
百人隊長の言葉に、焚き木と油が用意される。油をふくんだ焚き木が扉の下で燃えあがり、油をかけられた扉が炎に包まれる。扉が大槌で破れるほど脆くなるのに、どれくらい時間がかかるだろう。百人隊長はもどかしい思いを押し殺しながら、立ち尽くしていた。せっかくの頑丈に造った砦も、無傷のまま占領されてしまっては敵を利するばかりである。不意打ちだったとは言え…。隊長は消極的な思いを振り払った。今はただ、この奥の部屋を取り戻す事だけを考えればいい。 それさえできれば、城門に隠された岩の扉を落とすことさえできれば…。
兵士たちは誰に言われるでもなく交代で大槌を手にし、炎が身を炙るのも構わずに扉に打ち下ろし続けている。扉が大槌を撥ね返す鈍い音は、そのままサッラの運命の危うさを告げていた。
城門の内側で隊列を整えるサッラ兵たちの目の前で、いよいよ城門が破られようとしていた。人間の胴体二つ分ほどもある閂にはひびが入り、二枚の門扉の間には既に人一人通り抜けられそうな隙間が開いている。肩と肩が触れ合うほどに密集した歩兵達は槍を前方に構え、城門が破られるその時に備えている。その頭上を僅かな隙間を狙って放たれた矢が越えて行く。アルタスは自分が率いる事になった五十騎の騎兵とともに、歩兵隊の後方でその様子を見つめていた。門が破られたら、どれだけ持ちこたえられるだろうか。狭い門の入口を歩兵が押さえている以上、そうたやすく突破されることはないだろうが、三万の敵が次から次へと押し寄せてくれば、結局は時間の問題ということになるだろう。
破城槌が門にぶつかる音に続いて、ひときわ大きな破壊音が響いた。巨大な閂が真っ二つに裂けた。半ば破壊された門扉はきれいに開ききることはなかったが、大軍が城内に流れ込んでくるには充分だった。傾いた門扉とその後で不気味な姿をさらす破城櫓をすり抜けて押し寄せる敵兵が、槍を構えて待ちうける歩兵隊とぶつかる。歩兵隊の後に位置する弓兵も、次々と矢を放つ。兵士たちのあげる雄叫びと悲鳴、弓弦の鳴る音、武器と武器のぶつかりあう音。多くの音が一体となって戦場を覆う。剣を持った敵は槍を構える歩兵隊の前面にいては不利と、側面に回りこもうとしていた。それを騎兵隊が阻止する。嵐の夜の豪雨のように降りそそぐ矢に倒れた死体の山を乗り越え乗り越えやって来る敵は、剣ばかりではなく、小さな投槍や棍棒、投石器などを使って、じわじわとサッラの歩兵にも 被害を与えていた。
今日は太刀ではなく騎兵の正式装備である騎槍を振るうアルタスは、歩兵の戦いを横目で見ながら、側面攻撃を試みる敵を次々と仕留めていた。有利な位置で待ちうける味方の損害は、不利を覚悟で押し寄せる敵に比べて遥かに少ない。それでも投槍で倒れた兵士の位置に、別の兵士が後ろから進み出て隊列を維持する、という歩兵の戦い振りには悲愴なものを感じずにはおれなかった。それは圧倒的な大軍を前にしては敗北は時間の問題、という思いを新たにさせられたことにもよる。しかし最も大きな要因は、定住生活に入ってから百年を経ているとはいえ、本来騎馬民族であるサッラの戦士階級にとってこのような戦法が肌に合わない、という生理的なものであった。
戦士階級のそうした思いとは裏腹に、戦時に動員されない限り武器を手にすることも無い市民階級からなる歩兵隊は善戦していた。それでも時間とともに疲労と損害が目立つ様になってくる。日が真上に昇る頃には、百人を越える兵士が、傷つき、あるいは死体となって隊列を離れた。別の場所を持ち場にしていた兵士たちも応援にやって来る。日暮れまで持ちこたえることができるだろうか。アルタスはこの自問に全く意味が無い事に気付いた。開け放された城門を前にした敵が、夜になったからといって攻撃の手を緩める筈がなかった。
疲労の激しいサッラ兵の前に、次々と新手を送りこむ敵。戦局は徐々にサッラ側に不利となっていった。サッラ歩兵の隊列が徐々に後退するにつれて、無傷のまま城内に入りこむ敵が増えてくる。側面に回りこもうとする敵の勢いを、騎兵隊も押さえられなくなってきていた。
アルタスの部隊にも投槍で倒された者、あるいは乗馬を先に倒され落馬したところを取り囲まれた者、と次第に損失が大きくなっている。味方の悲鳴が聞こえるたび、わが身が刃を受けたような気がする。これは、今日一日もつかもたないかってところかな。アルタスは背後に目をやる。城門からオアシスまでは一直線に大路が通っている。オアシス周辺には武器庫も穀物庫も族長の館も、まるで無防備で集まっている。ここを突破した敵にとっては、それぞれの建物を囲む塀など障害とはならないだろう。
突然、今まで周囲を包んでいた物音とは別の音が轟き、味方歩兵の歓声がそれに続いた。
何事かと門の前に目をやれば、味方歩兵が敵を押し返し始めている。アルタスの耳に、先の轟音が蘇ってきた。思わず城門の二階を見上げる。窓一つ無いその内側をうかがう事はできないが、そこで何がおきたのかは明らかだった。
城内に閉じ込められ狼狽した敵に、士気を取り戻したサッラ兵が襲いかかる。歩兵隊は敵を城門まで押し戻し、騎兵隊は歩兵の前面から外れた敵を一人一人倒してまわった。
敵は出口を岩の落とし戸で塞がれた通路に追い詰められた。破壊された門や、破城櫓といった障害物の多いところまで歩兵方陣を進めるのは危険とみたゾラは歩兵隊に停止を命じた。弓兵の矢で敵を一掃した後で、剣を持った軽装歩兵を投入する。軽装歩兵たちは、障害物の陰に隠れていた敵にとどめをさしてまわっ た。
夜中から日暮れまでの戦いで八百あまりの敵を倒したが、サッラ側でも死者は二百を超えていた。死体を片付けるために忙しく働く兵士たちに、赤みを帯びた夕陽が射しかかっている。ゾラ、アルタス、幕僚たちは黙って立ち尽くしたままその様子を見守る。まだ戦いが始まったばかりだということは皆わかっている。 それでもようやく訪れた小休止の時に、暗くて苦い安堵を感じてもいたのだった。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
