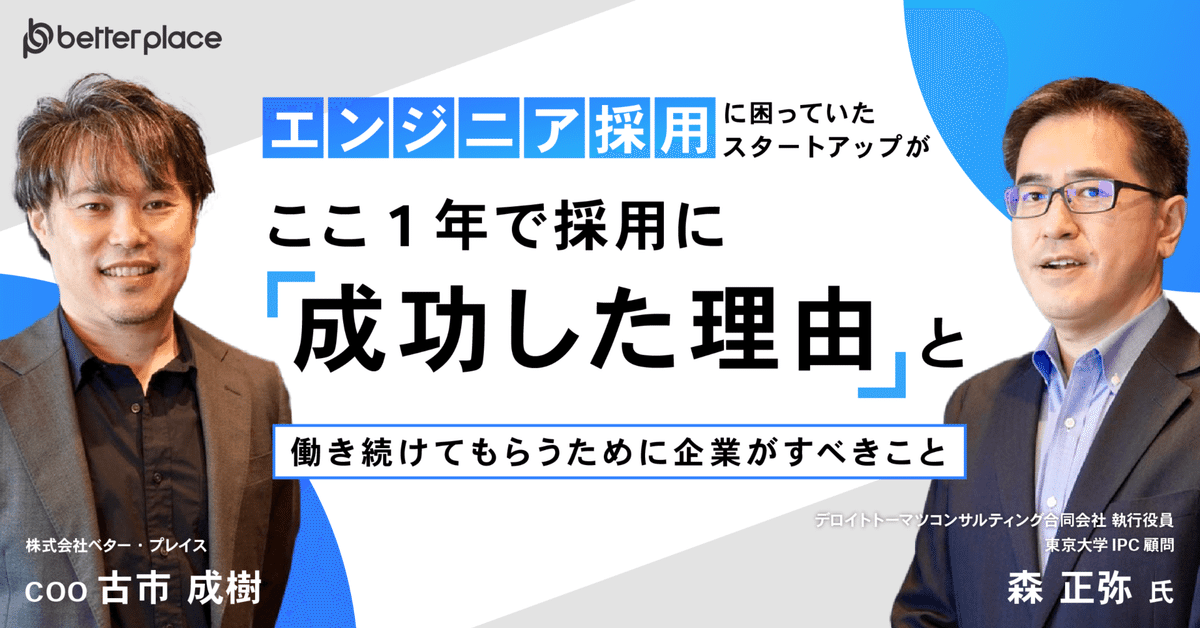
エンジニア採用に困っていたスタートアップが、ここ1年で採用に成功した理由と、働き続けてもらうために企業がすべきこと。
「ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会をつくる。」という企業理念のもと、現在および将来にわたり、人々が「お金の心配なく」「自分らしく働ける」社会を目指す株式会社ベター・プレイス。医療、保育や介護など、人々の生命と社会生活を支える人たちの資産形成や福利厚生を支援するための「はぐくみ基金」の普及推進のほか、DXにより企業年金を刷新し、初心者の方でも手軽に老後の資産形成ができるような取り組みを行っています。
ベター・プレイスはフィンテック企業として、エンジニア採用に力を入れています。しかし、採用を強化し始めた当初は、エンジニア採用に非常に苦戦していました。そんな時出会ったのが、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社の執行役員、東京大学IPC顧問であり、エンジニア領域に詳しい森正弥氏です。森さんからアドバイスを受け、さまざまな施策を実行に移すことにより、この1年で7人のエンジニア採用に成功しています。
今回は、ベター・プレイスで採用領域の責任者を務める代表取締役COOの古市成樹が、森正弥氏と、ベター・プレイスはエンジニア採用のために何を実行したのか、そしてエンジニアを採用し、働き続けてもらうために企業がすべきことについて語り合いました。
採用成功の秘訣は、「エンジニアカルチャーに取り組む姿勢」を見せること

古市:ベター・プレイスはフィンテック企業として欠かせないエンジニア採用に非常に苦戦していました。2年半前にエンジニアをひとり採用したものの、二人目がなかなか採れない。採用してもすぐに辞めてしまう。そんな時に、弊社取締役から森さんを紹介してもらったことが、出会いのきっかけでしたよね。
森:1年くらい前ですね。
古市:森さんにご相談するようになって、この1年で7人採用できました。それにしても、なぜこうもエンジニア採用は難しいのでしょうか。
森:やはりDXが進み、業界によらず多くの企業がいわゆるデジタル人材の取り合いをしているからでしょう。2015年来、エンジニア採用は熾烈な戦いになっています。
ベター・プレイスでは色々な取り組みをされた結果、1年で7人のエンジニア採用ができ、採用フローもうまく動き始めましたね。
古市:森さんのアドバイスをもとに、弊社も「従業員に提供できる価値」について、さまざまな取り組みを行ってきました。
スカウトでは経歴をしっかり見て、なぜ会社にとって必要な人材なのか理由を説明し、反応があれば人事はカジュアル面談をする。「働く理由」と「あなたに来てほしい理由」をきちんとマッチングさせる。そのようなフローを丁寧に行っていくことによって改善されてきました。
しかし、エンジニアの採用プロセスは他の職種と違うと感じますが、森さんはどうお考えでしょうか?
森:通常の採用との違いですが、エンジニア採用では「エンジニアカルチャーに取り組む姿勢を見せる」ことで採用の確率が上がります。
具体的には、エンジニアコミュニティにつながるとか、募集要項でもエンジニアだから刺さる、響く言葉や条件を考えて載せるとか、そうしたことをベター・プレイスは続けてきた結果、エンジニア採用がうまくいくようになったのではないでしょうか。
古市:エンジニアカルチャーは採用において重要なキーワードですね。
森:エンジニアカルチャーの鍵として、2つのポイントがあります。
ひとつは、パソコンなども含めてパフォーマンスを発揮できる環境を整えられるかどうか。
従前の企業ですと、これまでも型落ちしたパソコンでやってきたからこれで作業しろとか、エンジニアが当たり前に使用しているGitHubは使用禁止だとか、エンジニアにとっては居心地の悪い環境というケースは珍しくありません。
エンジニアにとって、仕事をする環境はキャリアに直接結びつく大事な部分です。「この会社はエンジニアのことを大切にしている」と思えるような環境を用意することが重要です。
もうひとつは、エンジニア用のキャリアパスが用意されているかどうか。
たとえばカンファレンスや勉強会、草の根コミュニティ、そうした場へ参加や発表を基本的に禁止としている会社がありますが、エンジニアの成長機会を奪う環境はマイナスです。
まとめますとITやインフラの環境、積極的なエンジニアのキャリアアップ支援、社内・社外コミュニティの形成、これらがエンジニアカルチャーを構成する部分です。
古市:ベター・プレイスでは森さんのアドバイスをもとに、パソコンなどのインフラを変えました。それからエンジニア定着のために、社外コミュニティ形成のフォローやエンジニア同士で語り合う文化を少しずつ形成しているところです。こうした様々な取り組みによって、エンジニア採用が進んできたように思います。
ロールモデルとなるシニアエンジニアの存在が重要
古市:我々の会社は、介護や福祉業界など、社会に必要な仕事に携わる人たちの将来の経済基盤を支える社会貢献性の高い事業を行っています。このビジョンに共感して入社を決めたという社員がほとんどです。
しかしエンジニアは「ビジョン」だけでは採れないというのが僕の実感です。もちろん、ビジョンは大切ですが、それにプラスして、技術的な成長を支援するとか、エンジニアのコミュニティの重要性を理解しサポートするとか、そうしたことを行わないとエンジニアは採用できない、たまたまできたとしても定着してくれないことをこの2年間で痛感しました。
森:おっしゃる通りです。付け加えると、ロールモデル的なシニアエンジニアがいるかどうかも採用にあたっては大きなポイントになります。
自分のエンジニアとしてのスキルアップ、キャリアの道が先輩の姿を通じてしっかりと見えていると「この人にいろいろ教えてもらえてキャリアを磨ける」と思えます。
古市:まずシニアエンジニアを先に採用することが大事なのですね。
森:なかなか難しいとは思いますが、今後のエンジニア採用を考えると大事ですね。
古市:森さんからいただいたアドバイスで、印象に残っているのが最初の頃に言われた「エンジニアが楽しく働ける環境が整っていますか」という言葉です。かつては、課外活動のバックアップや技術を向上するための資格手当などを用意しなくても、楽しく働いてもらえる環境があると思っていました。
でもエンジニアの視点で「楽しく働ける環境」は考えていなかった。それを痛烈に感じたのは、福井にある有名なアジャイル開発の会社を見学したときです。
どのチームが何の開発をしているかひと目でわかるようになっていて、プロジェクトの進行表もただのガントチャートではなくマンガ形式になっていたり、あだ名で呼び合ったり「ああ、楽しそうだな」と感じました。
さらにその企業カルチャーを外部に積極的に発信していて、だから「あそこはすごいよ、エンジニアにとって最高の環境だ」となり自然と良いエンジニアが集まる、好循環が生まれているんですね。
森:エンジニアにとって重要なことは「クリエイティビティを発揮できる環境」と「それが許容されるカルチャー」が会社にあることです。
作るものが決まっていても、どう作るかをエンジニアに任せられるかどうか。任せることでシステムの生産性もアップし、エンジニアにもドライブがかかってきて、さらに発想がふくらむ。そうした実績はアセット(資産)となり、積み重ねていくことで生産性はさらに上がります。
それからエンジニアとひとくくりで話していますが、領域は非常に広い。基本的に全部の専門家はいませんから、エンジニア同士で相談したり、共有したりして進む必要があるわけです。企業内でも隣の人に「ここ、どうしたらいいのかな」と気軽に話し合える雰囲気、知識や技術を共有しようというスタンスがもてる企業文化、エンジニア文化を醸成するのが大事です。
古市:楽しい環境がエンジニア採用に必要というだけでなく、それが生産性向上や能力開発にもつながるというのは深いですね。
エンジニアに定着してもらうためにできることは
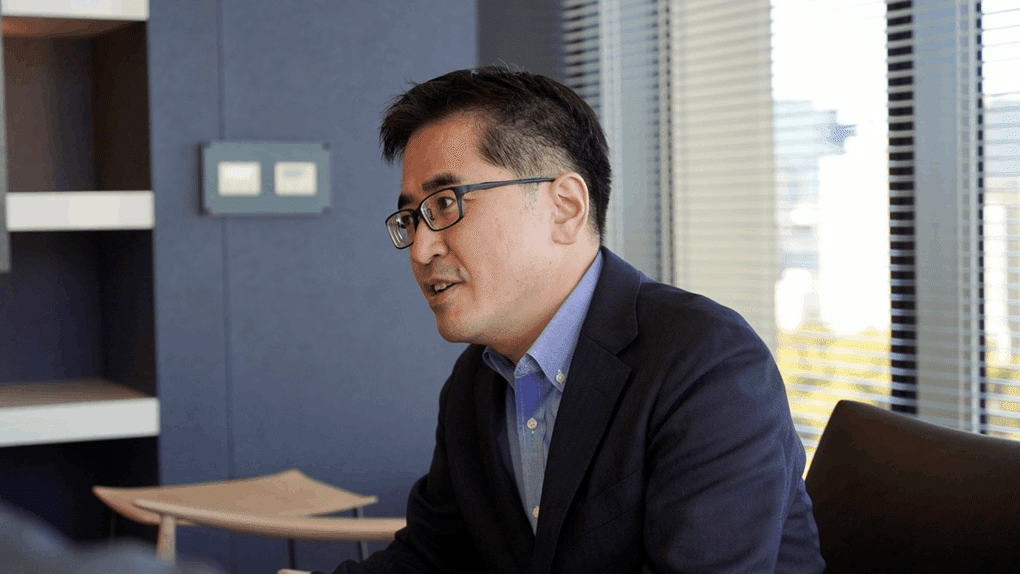
森:働き方においては、リモートや出社のどちらか一方というよりも、いわゆるハイブリッドを好むエンジニアは多いですね。
古市:弊社内のエンジニアも、100%リモートがよいという人は少数派で、月のうち数回は出社したいという人が非常に多いです。
今、エンジニアは全部で8人いますが、次のフェーズでは集まった8人が上手に機能するチームにしていくことが必要だと考えています。もちろん一人ひとり得意・不得意がありますので、そこを踏まえた上で活躍できる体制を作ろうとしているところです。
あとは、エンジニアに継続して働いてもらうためにどうしていくかですね。
森:長期的に働いてもらうという面では、先程お話をしたシニアの先輩がいるとか、会社におけるエンジニアのキャリアパスが可視化されているとか、会社の成長と共にどのようなキャリアパスがありえるのか、そこがカスタマイズされていく必要性があります。
シニアのキャリアパスがなかったとした場合、自分のマーケット価値を上げていくために最新の技術に触れることができる環境があれば、会社に定着するのではないかと思いますね。
古市:最新の技術に触れられるというのは、仕事の内容ということですか?
森:仕事の内容もそうですが、要するに何かを開発しようとして「この技術を使いたいです」と言っても「いや、この技術だけで作ってくれ」みたいな縛りがあると、なかなか新しい技術を使う機会がないわけです。
古市:法人側としては、その環境を提供するのは難しいですね。
森:CTOが新しい技術を導入するロードマップを示すことは重要です。勉強会のほか、サンドボックス(仮想環境で技術等を検証する)などで新規事業を生み出すとか、いろいろ方法はあると思いますよ。
人事担当者がエンジニア採用で考えなくてはいけないこと
古市:エンジニア採用について、人事責任者が一番に考えなくてはならないことは何でしょうか?
森:人事担当者が考えるべきなのは「人事制度等の仕組みもエンジニアカルチャー寄りにできるか」ですね。
従来の人事制度とか福利厚生の考え方は、エンジニアにとってはマイナスになる面もあります。ですからエンジニアのキャリアを踏まえたカルチャーや制度が作れるかどうかが鍵になります。
ただ、それがエキストラとかスペシャルな感じだと、エンジニアは例外なんだと思われてしまいます。できればエンジニアの組織はまったく別物として、働く場も違うところに設置し、就業規則からすべてエンジニアカルチャー寄りに再構成するのがベストです。
古市:それは正直なところ、かなりの企業規模でないとできません。そこまで行きつかない小さな規模では、どうしたらいいのでしょう?
森:エンジニアカルチャーと自社のパーパスを結びつけて、エンジニアに限らず、働く人みんながクリエイティブな職場環境に持っていく方法もあります。エンジニアにフィットさせる環境を整えておくと、結果的にZ世代やミレニアル世代が求めるものにもマッチするはずです。
古市:これまでの経験からいくと、たとえば営業が強い会社にエンジニア組織ができると、ちょっと仲が悪くなる傾向がある。「なんでエンジニアだけフルリモートなんだ」「エンジニアは最新のパソコンと高機能な椅子でいいな」みたいな(笑)古株の営業スタッフとの間で起きやすい軋轢のひとつだと思うんですよ。
そうならないように、営業には最新の資料やスマホを用意したり、飲み会や部活みたいなことを通じて仕事以外の接点を持つように配慮したりしています。
ただ、先程の会社見学で、社長さんに伺ったら「営業にも良い影響が出ている」とおっしゃっていた。つまりエンジニアカルチャーが会社全体に浸透することで、営業も含めてみんながクリエイティブに働くようになる。
森さんのお話ともあわせて、やはり、ベター・プレイスもエンジニアカルチャーを強化していきたいなと改めて思いました。

森:そうですね、重要なのはクリエイティビティとダイバーシティですね。
エンジニアの話が解決しないうちに、次に必要となる人材のテーマがのしかかってきます。それはデザイナーですね。デザイナー向けのカルチャーやスタイル構築はもっと大変ですが、会社全体がクリエイティブで多様性があり、挑戦を受け入れてくれると、あえてそこでデザイナーのカルチャーをわざわざ構築しなくても、すでに対応できる企業体になっているわけです。
結局、エンジニアに適した環境を整えることで、Z世代やミレニアル世代の採用やデザイナーの採用もうまくいくようになるということです。
デジタル人材の採用・育成・外部人材の活用
森:エンジニアの採用についてお話ししてきましたが、ここから社内の人材育成とDX化をもっと大きい戦略として考えてみましょう。

古市:こちらの図はどう読み解けばいいのでしょうか?
森:従来型のエンジニア人材と現代型のエンジニア人材ではタイプが違います。厄介なのは、左右のバランスです。左の従来型はどちらかといえば伝統的な管理と計画で着実に進むスタイルで、工業的な考え方に近い。たとえるならマラソンランナーです。右は顧客価値にフォーカスしたフレキシブルかつ適応的なスタイルになります。たとえるならスプリンター。デジタルというキーワードでは右の人材が求められますが、左の人材も企業にとっては大切です。そして、右に寄りすぎると左の人材がとれなくなります。マラソンランナーとスプリンター、両方を採用していく必要があります。
古市:なるほど。弊社は今、IPOの準備段階でウォーターフォールからアジャイル側に寄ろうとしているものの、IPOでは左に寄せないといけない面もあってジレンマはありますね。皆さん、その辺はどう解決していらっしゃるのでしょう?
森:入山章栄先生の「両利きの経営」と通じるものがありますね。従来の価値パターンの効率化と新規のところを探索していくバランスの議論ですが、同じようなことが言えます。どうしても左8割と右2割みたいなバランスになってしまうのですが、良い会社は6割、4割ぐらいのバランスになっている印象があります。
左のモード1の仕組みを走らせながら、きちんと右のモード2も確保していくことですね。

さらに、テックカンパニーは内部人材のテックスキル・テックカルチャーを高めていくこと。内部の人こそ、自社のビジネスを一番理解しているので、その人材のスキルをアップし、外部のチームときちんと連携できれば、企業の力が大きく伸びます。
内部のリスキリングと外向けの取り組みを行う二重のループが大切です。
フィンテック企業をめざして!ベター・プレイスの展望
森:ベター・プレイスはエンジニア比率をどれくらい高めたいのですか?
古市:将来的には半数にしたいと思っています。
エンジニア採用面だけでなく、今後のベター・プレイスへの期待をこめて、ぜひ最後にひと言いただけますか?
森:そもそもベター・プレイスはミッション・パーパスに共感して入社する社員が昔から非常に多い。ここにクリエイティビティ、ダイバーシティが結びついたら、非常に強い企業カルチャーになるはずです。今まさにその目指したい姿へ向かって挑戦し進まれているところで、もっとも苦しく大変なフェーズかもしれませんが、ぜひやりきっていただきたいと思います。
他のスタートアップ企業にとって「ベター・プレイスの歩んできた道をフォローしていくべき」みたいな事例になると期待しています。
古市:我々が本当に企業理念を実現して日本社会に貢献するミッションを達成するためには、今のカルチャー、今のスタッフだけでは簡単ではない。エンジニアを増やして、クリエイティブな環境を準備する必要があると改めて思いました。
今日はたいへん有意義なお話をありがとうございました。
