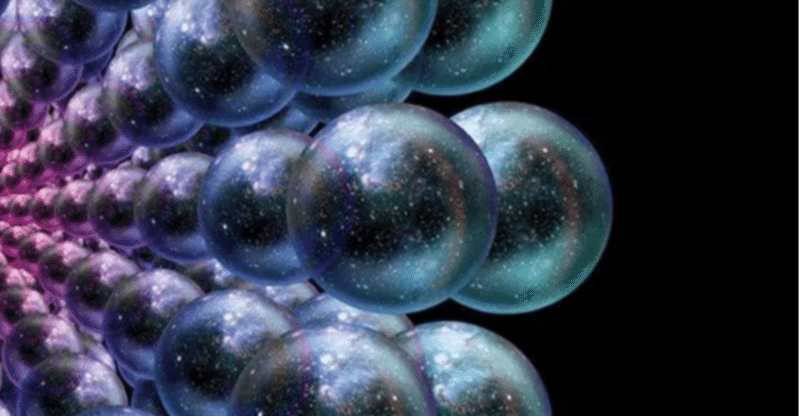
1919年5月29日の日食
アーサー・エディントン「アインシュタインは言ったのだ、諸君、それぞれで時間は同じではない。それを納得するのは難しいかもしれない。しかし、これは新しい重力理論の始まりだ。これが相対性理論だ」
この皆既日食は南アメリカ大陸の西側から始まり、赤道を超えたアフリカ大陸の西側で最大食を迎え、アフリカ大陸の東側で終わった。皆既日食の継続時間は6分51秒で、20世紀中の皆既日食では5番目に長かった。
さらに、この皆既日食は、アルバート・アインシュタインの一般相対性理論が正しいことを実証した日食として有名である。特にプリンシペ島でアーサー・エディントンが行った観測が有名である。
一般相対性理論によれば、重力場によって時空がゆがむと、そこを通過する光はそのゆがみに沿って曲がる。これを観測者からみれば、見かけ上、光源の位置がずれているように見える。これは、重力がまるで凸レンズの役目を果たすことから重力レンズ効果と呼ばれている。
理屈上は、太陽のすぐそばを掠めるようにやってきた恒星の光も曲げられ、見かけの位置がずれているように見えるはずである。しかし、太陽は極めて明るいため、そばにある恒星を観測するには、太陽が暗くなる皆既日食しかないのである。
理論上、1.75秒というわずかなずれが発生する。これは、ニュートン力学で予測されるずれの2倍である。観測の結果、1.61秒というずれが観測され、一般相対性理論とニュートン力学で、一般相対性理論の方がより正しい値を予言したことから、一般相対性理論が正しいという結論となった。
後のアインシュタインの名声に比べて、エディントンの評価は低かった。しかし、それがどうなのであろう。大英帝国のサーの称号を持つ物理学者者が敵性国家ドイツの物理学者の理論を、それも一般相対性理論を証明するために尽力したのである。
サポートしていただき、感謝、感激!
