
第十七回:あの夏の向こう側(のロシア)
川崎大助『スタイルなのかカウンシル』
Text & Photo : Daisuke Kawasaki
ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY で好評だった連載が復活。「音楽誌には絶対に載らない」音楽の話、その周辺の話など

なにかとロシアが話題となっている昨今、ひとつの記憶が蘇ってきた。ロシアではなく、ソヴィエト連邦の記憶なのだが。そのときの僕は、船の上にいた。連邦が崩壊する、そのとっかかりの瞬間を僕は、サハリンから稚内を目指してひた走る、フェリーの旅客のひとりとして体験した。
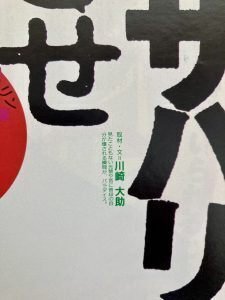
1991年、8月のことだ。雑誌〈i-D JAPAN〉の創刊2号である11月号(ページ最上段の写真、宮沢りえの表紙)に掲載する特集記事のために、僕はソ連邦の辺境の地であるサハリン州に潜入していた。「潜入」というと大袈裟だが、わりとこれは本当で、当局に対して取材許可は一切とっていなかった(だから「絶対にバレるんじゃないぞ」と厳命されていた)。


かの地の街と人を取材して記事にするという企画だったのだが、観光ツアー客の一員として入国する。だから「観光客らしく」当時流行していた使い捨てカメラを使用する――ということで、スーツケース一個ぶんいっぱいの『写ルンです』を持ち込んで、それで写真撮影をおこなった。別の雑誌で幾度か組んだことがある編集者の発案で、この企画が生まれた。「パラダイス・イシュー」だから、国境の向こうの、北の別世界のパラダイスに行くのだ、というよくわからない理由から思いついたものだという。広告タイアップも付いてないのに、よくこんな企画が通ったものだと、当時はもちろん、いまでも僕は思う。当時の日本には、未曾有のバブル景気の積み残しが、まだ残っていたのだろう。
すべての取材を終え、サハリンのホルムスク港から船が出てから、10分後ぐらいだろうか。すごく大きな音声で船内放送があった。そのとき僕は、タラバガニのカニ缶を開けて食べていた。ソ連製のその缶詰は、たぶん密輸品のさらに抜け荷ということだったか、と思うのだが、船長自らが船内で販売していた。一個150円ぐらいだったから、つまりは狂ったように安い。それでツアー客はみんな、我も我もと注文しては、次から次へとカニ缶を空にしていたわけなのだが――そこでこの放送があった。
ロシア語の放送だったから、僕は内容がわからなかった。だから同じ船室にいた人に訊いた。世界各地を放浪しているという彼は、基礎的なロシア語を理解することができた。
「んーと、クーデターがありました、と。そんなこと言ってたよ」
カニ缶を食べながら、彼はそんなふうに教えてくれた。
「ゴルバチョフさんが、あぶないみたい」
つまりこれが、8月19日、世に言う「ソ連8月クーデター」の幕開けだった。カニを頬張りながらも僕は、あとすこし出港が遅れていたら、ちょっと嫌な感じだったかも……と想像せざるを得なかった。すでに入国の際に、同行していた編集者が別室に連行されて取り調べを受けていたからだ(パスポート確認の際、ロンドンに行き過ぎているところが不審がられた)。軍服を着てAK突撃銃を肩に担いだ兵士が何人もいる入管に、ただひとり残されたときの気分は、ちょっとしたものだった。しかも「バレてはいけない」目的を抱えて共産圏にもぐり込もうとしているところだったから……。
肝心の取材は、なごやかに楽しいものだった。たぶん僕は、この旅のあいだに、残りの一生分以上のキャビアを食べた。取材でお邪魔させてもらったお宅のどこでも、ウォッカも出るのだが、とにかくご馳走をふるまってくださるのだ。つまり物資は「あるところには、ものすごく」あった。スーパーマーケットにはなにもない、場合も多かった。しかし闇市のネットワークが、大盛況だった。当時の同州民の所得は、連邦平均の2倍だという話もあった。ならば「闇」を加えたなら、その数値はもっと跳ね上がったことだろう。
サハリン男性の最強ファッションは、なんと言ってもアディダスの「ぴかぴかに新しい」トラックスーツ上下で決めることだったのだが、そんなスタイルの若い連中とも知り合った。ウクライナから越してきたんだけど、サハリン最高、との声もあった。また、朝鮮系の方々が使う日本語の古式ゆかしい丁寧さ、典雅さには、心洗われる思いがした。
次回もお楽しみに!


かわさき・だいすけ。作家。
その前は雑誌『米国音楽』編集長ほか。
近著は『日本のロック名曲ベスト100』『僕と魚のブルーズ 評伝フィッシュマンズ』。
ほか長篇小説『東京フールズゴールド』『教養としてのロック名盤ベスト100』、翻訳書に『フレディ・マーキュリー 写真のなかの人生』など。Yahoo!ニュース個人オーサー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
