
秀司さん&儀三郎さんwith Be
最近、SNS上で天理教道友社編『"逸話のこころ”たずねて』という本の朗読を始めた。
人様の前で朗読をした経験は無い。声は通らない、息も続かない。おまけによく噛む。我ながら酷いものだと朗読しながら笑ってしまいそうになるが、思うところがあり、恥を忍んで続けている。
さて、『”逸話のこころ”たずねて』で取り上げられているのは、タイトルからもお分かりのように『稿本天理教教組伝逸話篇』に登場する先人たちである。
天理教を信仰する方であればその名を聞けばすぐにピンとくる、道の黎明期を生きた綺羅星の如き方々ばかりだ。
本の中では『逸話篇』に記される逸話の要旨に解説が加えられているのだが、紙面の関係からか非常にコンパクトにまとめられている。そこで朗読に若干の補足説明を加え、いま少し一人ひとりの人物像を浮き彫りにしたいと考え、事前にあれこれと調べるようになった。
すると、今まであまり意識していなかった、先人たち同士の関係性などが鮮明になってきた。それは新鮮な気づきであった。
たとえば、中山たまへさん、上田ナライトさん、増井りんさんという、初期の信仰者でありながら、今も女性信仰者のアイコンとして輝くお三方が、37年という長きにわたってお屋敷内に同居され、おやさまのお側近くにいらっしゃったという事実が鮮明になった時など、言葉に表すことのできない感動を覚えた。
あるいは高井直吉さんと宮森与三郎(岡田与之助)さんのお二人が、お屋敷での住込み青年第一号として、ともにおやさまに可愛がられ、秀司さんをはじめ多くの先輩方に仕込まれ、競うようにして育っていった姿に、まるで爽快なロードムービーを観るような気分になった。
一方で教外の方の手による文章も目にした。その中で特定の先人を痛烈に批判する、あるいは誹謗するような記述にも出会った。しかしそれらの文章は以前から目にしていたものであり、過去に自分のnoteの記事に引用したことのあるものも多かったので、さほど驚くこともなかった。
たとえば大平隆平(大平良平)氏が発行した雑誌『新宗教』の中に記述される、飯降政甚氏からの聞き取りを元に秀司さん・まつゑ(”まつえ””松枝”とも)さんについて書かれた記事などは、初めて読んだ時には驚愕したものだが、その記事ですら、僕の中ではすでに色褪せてしまっている。
政甚氏が天啓を継ぐ本席飯降伊蔵の嫡男という「言うに言われぬ」難しい立場に、否応なく置かれたことに同情の余地もあるが、氏の教団内での特殊な立場を思えば、『新宗教』の大平氏に問われるままに語ったと思われる言葉は浅慮の誹りを免れないと感じた。
大平隆平氏や政甚氏のことは、この記事の論旨から外れるので、これ以上は触れない。
さて、宮森与三郎さん(当時は岡田与之助)について調べていた時、彼がおやさまの厳しい反対を押し切って金剛山地福寺へ向かう秀司さんに同道した件を記述したテクストに出会った。以前に読んだ記憶はあったが、内容については失念していたので幸運であった。
秀司さんに関しては、おやさまの思いに反する行動が多かったことから、あまり良いイメージを抱いていない方も多いのではないかと想像するが、かつての僕もそうであった。しかし現在では秀司さんにシンパシーすら感じている。それは僕自身が年齢を重ね、家族を持つに至って「今の自分が秀司さんの立場ならどうしただろう」と考えられるようになったからだと思う。
何不自由ない裕福な家庭の惣領息子であるというだけでなく、人並み以上に聡明だった秀司さんが、突如神懸かりとなった母親の常識にかからぬ施しに起因して、夢想だにしなかった”赤貧洗うが如き生活”に甘んじなければならなかったのだ。その彼が、長いどん底の生活から抜けだし、ようやく人並みの暮らしができるようになった時、「二度とあの時代のような苦労をしたくない。させたくない」と思うのは、家庭を持つ一家の主としては至極当然のことだろう。
「お道が徐々に栄えはじめ、御供という日銭を得ることで安定しはじめた生活を手放したくなかたったのではないか。」という意見も聞く。その指摘も間違っていないのかも知れない。秀司さんは中山家の全責任を背負う立場にある。”全責任”とは「月日のやしろ」となった母であるおやさまの"なさること"、"説くこと"の一切合切を含むものである。
神懸かりした母と家族、そして”中山”の血統、さらにはおやさまの教え、すなわち「お道の信仰」をも守らなければならない立場にあったのだ。
つまり、地福寺の配下としての認可を得ようとする行為は、それらすべてをを守ろうとする気持ちの発露であったと僕は思っている。
そして明治13年、秀司さんは「親神は退く」とのおやさまのお言葉に反してまでも、地福寺配下「転輪王講社」の許可を得るべく、金剛山地福寺へと赴き、それを認められた。

9月22日(陰暦8月 18 日)には、転輪王講社の開筵式が行われたが、おやさまの警告どおりに、中山秀司さんは翌明治 14 年4月8日(陰暦3月 10 日)に61 歳で出直している。
当時の状況を見直してみると、明治12・13年当時の
寄り集う人々は、日一日とその数を増し、親神の思召に励まされて、いよ/\勇み立ち奮い立ち、道は八方へ弘まった。
しかし、村人達の間では、尚反対が強く、天理さんのお陰で、親族や友人が村へ来ると、雨が降ったら傘を貸さねばならぬ。飯時になったら飯を出さねばならん。店出しが出たら子供が銭を費う。随分迷惑がかゝるから、天理さんを止めて貰いたい、さもなくば年々「ようない」を出して貰いたい。と、言った。又、夜参拝する人々には、頭から砂をかける、時によるとつき当って川へはめる、というような事もあった。
という厳しく切ない状況の中での
秀司は、教祖に対する留置投獄という勿体なさに比べると、たとい我が身はどうなっても、教祖の身の安全と人々の無事とを図らねば、と思い立ち、わしは行く。
という秀司さんの思いに嘘はなかったと僕は思っている。
橋本武氏は
地福寺へ出掛けた宮森与三郎の思い出として、「秀司先生は何とかして表向きにお参りの出来るようにしておかんと、自分の母親にあたる80の御老体の教祖をば、警察へ引かれたりさせんならんので、強いて行こうとされたが、誰も秀司先生のお供をするものがないので、私がついていった。」「『神さまはあんなに止めやはるけど、警察が喧しういうもの、仕方ない』と仰っておられた。」
と地福寺へ同道した宮森与三郎さんの言葉を紹介しているが、
「『神さまはあんなに止めやはるけど、警察が喧しういうもの、仕方ない』と仰っておられた。」
との秀司さんの言葉は、宿泊したお寺の風呂で宮森与三郎さんに肩を流してもらっている時のものだ。
与三郎青年に背を向けたまま、うなだれて嘆息する秀司さんの姿が目に浮かぶ。断じて、おやさまの心を分かろうとせぬ息子などではない。秀司さんは誰よりも、おやさまが月日のやしろであることを確信していたし、母と同時にお道をも護らなければならないという自覚があったのだ。
宮森与三郎さんのこの述懐は、朗読の補足をするための資料を探していたときに知ることとなったのだが、秀司さんに肩入れしている僕にとってはとても嬉しい発見だった。先人の足跡をたどることで得られるものは実に多い。そして自らの信仰を見つめ直すきっかけにもなったと、しみじみと感じている。
橋本武氏は言う。
秀司先生がおやさまの思召に不明であられたことは絶対にない。
しかし、秀司先生は何ものをも投げ去って、真一文字に神意のままに従えぬものを持っていられたのであった。それは秀司先生のみが持たれたおやさまの子としての立場、さらに、中山家の戸主として当然おやさまの教に関する一切の責任を取らねばならぬという、教団の代表者としての立場であったのである。
その両面の責任感に強く立たれたからこそ、あえておやさまのお言葉に逆ろうたと見ゆる道を自ら歩み行かれたといっていいのである。
母を月日のやしろと信じ、その身を誰よりも案じ、同時に中山家の家督を繋ぐ者としての責任感に殉じたのが秀司さんだったのではないだろうか。
不敬な物言いになるが、そこには何びとたりとも立ち入ることのできない「母と子の物語」もあったと僕は信じたい。
秀司さんの人となりについては、ほこりまみれの信仰者こーせー氏のnote『243、秀司氏の最期の言葉』に詳しい。是非ともご一読していただきたいnoteである。
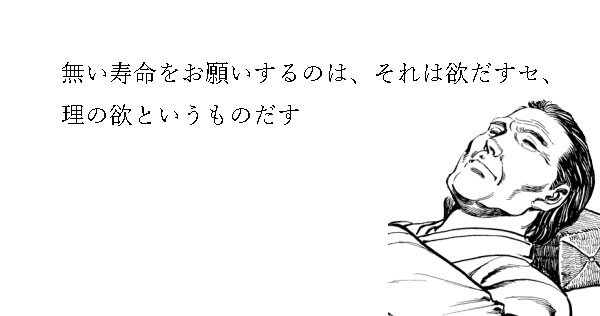
さて、先人に関する朗読をしていると、時折思いがけない質問や意見をいただくことがある。
仲田義三郎さんについて朗読した際に、天理教を深く研究されている既知の方から「仲田義三郎さんは唯一の殉教者である」とのご意見をいただいた。”殉教者”という強い響きに驚きながらも、「なるほどそういう見方もあって当然だ」と思った。
儀三郎さんはおやさまの「一番弟子」とも「一の子供」とも言われた高弟中の高弟である。
官憲の厳しい迫害干渉にも節を曲げることなく、限りなく獄死に近い出直(拷問死であったとも考えられる)をされた偉大な先人の死を「殉教」と表現することは、たとえば隠れ切支丹の例に照らして考えれば、あながち間違いではないのかも知れない。
だが、そう感じつつも僕は儀三郎さんの死を「殉教」と表現することに意味や意義を感じることができなかった。Youtubeの「先人の足跡」で語られたご子孫の言葉に、仲田家の信仰の祖である儀三郎さんがおやさまに特に可愛がられ、信頼されたことに対する喜びと感謝、そして慎ましやかな誇りを感じたからかもしれない。
さらに包み隠さずにいうと、僕は「殉教者」という言葉を冠することが儀三郎さんに対して失礼ではないか、と感じたのだ。それは僕の中にある天理教信仰者としての直感であって、理由を論理的に説明することはできない。また「殉教者」との位置づけを非難するつもりもない。
今思うことは「殉教」か否かは亡くなった本人のみが決め得るのではないだろうか。ということだ。
余談
前段で述べたことと矛盾しているのを承知で書くが、仮に儀三郎さんが「殉教者」であるならば、妻を神のやしろに差し出しながら、遂に”門前に市をなす”がごときお道の栄えを目にすることもなく出直していかれたおやさまの夫、善兵衛様。そして立教以来、理と情の狭間で苦悩し続けた長男秀司さんも、広義では「殉教者」といえるのではないだろうか。
ことに秀司さんは理と情に悩み抜いた末、究極の選択をされた。その選択の善し悪しを語る以前に、彼が本気で命を賭した、ということを忘れてはならないと思う。
さて、儀三郎さんの死に接した当時の高弟たちは、獄中で傷つき衰弱しきった最期の姿を目の当たりにしたがために、明治二十年陰暦正月二十六日のおつとめになかなか踏み切ることができなかったという解釈もある。
おやさまが
教祖の右の親指が少し歪んでゐましたが其れは奈良の監獄へ行きました時親指二本括って釣り上げられたと云って曲つたと云ってゐられたが其んな目に逢はれたこともありました。
と仰ったという宮森与三郎さんの口述記もあることから、やはり拷問は行われていたのであろう。高齢のおやさまですらそうであったのだから、儀三郎さんが拷問を受けていないとは考えにくい。なので、官憲の暴力によって命を落とすことさえあり得る拘引を人々が恐れたとしても当然だろう。
だが、過去に記されたテクストや口承を元に、先人のパーソナリティを脳内に作り上げてきた僕たちは、先人の心の内までは知ることができない。たとえば瀕死のおやさまを気づかいつつも、心の中に生まれていたやも知れぬ暴力を伴う公権力への恐怖と神の思惑に反することへの畏れなど、その逡巡の在処にいたっては、どこまでも想像するほかはないのだ。
そもそも、今僕が書いているこの記事ですら想像を元に書いているわけであり、これまでも想像逞しく、あれこれとnoteに書き散らしてきた僕が語るのは卓袱台返しのようで気が引けるが、過去のテクストを元に想起した仮説を、同じく過去のテクストをもって否定したり肯定したりすること自体が意味の無い営みなのかも知れない。
大事なのは、記されたテクストから何を抽出するか。ということなのだろう。
もっとも、教内・教外を問わず、研究ということであれば仮説をもとにどんな結論を導こうとも自由だ。むしろ僕は新しい説やユニークな論を聞きたい、とさえ思っていることをお断りしておく。
さて、研究よりも信仰に重心を置く現在の僕は、お側の人々が陰暦正月二十六日を前につとめの勤修を躊躇った理由を、居合わせた人々が数ヶ月前の儀三郎さんの(拷問)死を目の当たりにし、官憲による拘引や暴力が自らの身に及ぶかも知れぬという「我が身可愛さ」からではなく、一にかかっておやさまの御身を案じるが故のことであったと信じている。
しかし、僕の信仰にとっては人々の躊躇いの理由は問題ではないのだ。
そこにあるのは、仲田儀三郎さんという稀代の高弟が、三十年来という極寒の中、櫟本分署でおやさまと共に肉体的にも精神的にも耐えがたい責めを受け、釈放された後もただただご高齢のおやさまの御身を心配しつつ出直していかれた。という事実だけで充分なのだ。
もちろん、こんな結論が「殉教」という言葉に対して何の反証にもなっていないという自覚はあるが、そこにこだわらなくなった僕は、少し成長したのかもしれない。
僕の中には「真実が知りたい」と明言し、教義・教理・教史の探求と同時に、教団組織への批判や指摘に血道を上げてきた僕とは別に、ただただ「眼前の一人を助けたい」という信仰者としての僕も存在するのだ。教会長なら当たり前なのかもしれないが、恥ずかしながら”たすけ人”としての僕はそんなレベルでしかない。
前者の僕は理論武装をしていても、ただの一人も救うことができなかった。教団教理に翻弄され、苦しく辛い信仰を続けてきた方が口にする批判や指摘に同調し、あるいは慰めたとて、決してその方の救いにはならなかった。
信仰とはなんだろう。僕は何のために信仰しているのだろう。そうした泥沼のような自問自答に答えを見いだすため、遅まきながら努めて”人”に向き合うようになった。意識して始めたわけではないが、朗読もまたその一環なのかも知れない。
もちろん、教団教理の誤りや組織の方向性などについての指摘は今後も続けていくつもりだが、最近では「教理なき信仰は空虚であり、信仰なき教理は無力である」という言葉の深遠さに慄きながらも、同時に勇気ももらっている。
随分とまとまりのない文章になってしまったが、これが僕の現在地なのだろう。
では、またいずれ。
writer/Be weapons officer
proofreader/N.NAGAI
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
