
【宿題帳(自習用)】「「わかる」とはどういうことか」をやり直してみる(その2)

[テキスト]
「畑村式「わかる」技術」(講談社現代新書)畑村洋太郎(著)

[参考図書]
「ものがわかるということ」養老孟司(著)

[ことばの疑問]
[ 内容 ]
なぜ「わからない」のか、どうすれば「わかる」のか。
『失敗学』『直観でわかる数学』の著者によるまったく新しい知的生産の技術。
[ 目次 ]
第1章 「わかる」とは何か(「わかる」とはどういうことか 『直観でわかる数学』を書いた理由 学校の教科書や授業はなぜわかりにくいのか ほか)
第2章 自分の活動の中に「わかる」を取り込む(まず身につけておくべきもの 「わからない」けどつくりだす 自分でテンプレートをつくる)
第3章 「わかる」の積極的活用(「面白い話」をする人は何がどうちがうのか 絵を描くことの意味 「現地・現物・現人」が、わかるための基本 ほか)
[ 発見(気づき) ]
「わかる」とはどういうことなのか、「わかる」と感じる仕組みを解説する。
世の中の事象は、「要素」と幾つかの要素が絡み合って作り出す「構造」、異なる構造がまとまった「全体構造」から成る。
人間は、頭の中に要素や構造、過去の経験や知識を基にしたテンプレート(型紙)を持っている。
目の前の事象とテンプレートを比較して、一致すると「わかる」と感じる。
合致するテンプレートがなく、理解できない場合には、要素や構造を使って、新しいテンプレートを作り理解しようとする。
現代社会で必要とされるのは、
「課題解決」
ではなく、事象を見極めて問題を探る
「課題設定」である。
知識・解法パターンを詰め込むだけではなく、自分の力で、テンプレートを作る訓練を続けることが重要と説いている。
本書の中では、理解の仕組みを解説しているのだが、それほど新しいということや、これまでにはなかった解説、ということもなく、言われてみれば、みながわかっていながら、日ごろ意識することなくすごしているようなことを、ことさらに説明しているものだともいえなくもない。
もちろん、人が意識しなかったことを、意識して考えるのはすごいことである。
[ 問題提起 ]
この本の価値は、
「原点に立ち返ること」
を思い出させてくれたことである。
本など読まなくても、よく考えれば、たいていのことは理解・実践可能という、高慢極まりない考え方もある。
だが、反面、表層的な知識、勉強法、処世術など身につけたところで、何の役にも立たない、という点では、真理をついていたとも言える。
毎日、無意味にニュースをチェックする必要などどこにもない。
そんなことより、頭と体を使って、論理的に考える訓練を繰り返すことのほうが重要である。
そういう原点に返り、自信を取り戻すきっかけになってくれればと思う。
表層的な情報過多人間の主張など容易に論駁できるという自信である。
当然、きっかけになってくれるかどうかは、今後の私の知識ではなく、思考の量に依存する。
「知らないけど、それが何か?」と言えるように戻りたい。
「直感」のみが論理の飛躍がないショートカットであり、「直感」であれば、論理的に他者に説明できるはず。
できないものは「直感」か「勘」。
ショートカット自体が悪いのではない。
むしろ効率的でよい。
だが、「直感」であるべき。
「直感」は、どんどん蓄積し、活用すべき。
蓄積するために、一度は、それを深く考える経験が不可欠。
熱力学や統計力学のよくないところ。
現象面、表層的、表面的に熱と仕事の関係を記述した学問。
「なぜそうなのか」がわからない。
いくらやっても熱力学や統計力学がわかった気がしない理由が、わかった気がする。
妥当な課題設定は、絶対的ではなく、立場等によって異なる。
平社員が、全社組織の改革を考えることは、過大な課題設定で、現実的ではなく、一方で、目前の問題を解くだけでは、不十分。
本書では、より、一般性のある課題設定を目指すべきという側面にウェイトがある。
面白かったのは、むしろ前者。
過大な課題設定もやはり机上の空論であり、そこには陥らないように。
それを解くことによって、最大のパフォーマンスが得られるようなポイントを模索すべき。
「見ない」「考えない」「歩かない」の三ナイ主義。
陥りやすい。
気をつけたい。
メモの取り方。
人によって違うと思う。
発言をそのまま記録したメモが生の声だからよい、という人もいるが、あまり賛成できなかった。
自分は、畑村派メモの取り方。
少なくとも、前者だと、読み返す気がしない。
[ 教訓 ]
世の中のすべての事象はいくつかの「要素」が絡み合う形で、ある「構造」を作り出している。
多くの場合は複数の構造がいくつかまとまって「全体構造」を成す。
そして、構造同士を組み合わせ、何らかの「機能」を持っている。
乗用車ならば、いくつかの部品(要素)で製造されるエンジンやタイヤ、ハンドルやアクセルが構造で、走るや曲がる、止まるなどの機能が実現されているわけだ。
わかるというのは、次の3パターンなのだという。
・要素の一致
頭の中の要素のテンプレートと目の前の事象の要素が一致した状態
・構造の一致
頭の中の構造のテンプレートと目の前の事象の構造が一致した状態
・新たなテンプレートの構築
自分がすでに頭の中に持っている要素や構造を使って新しくテンプレートをつくることで理解すること
動的な構造の理解ではさらに次の3パターンがあるとされる。
「構成要素の摘出」
静止させた状態で構成要素を確認する。
「構造化」
要素同士を組み合わせて別の大きな働きをする構造を頭の中につくりあげる。
「試動」
頭の中のモデルに刺激を与えて動かしてみて現実と比較する。
わかるプロセスがあきらかでも、現実の事象は複雑である。
すべての要素の組み合わせを逐一考えて試していては、現実的ではない。
3つの選択肢から、正解を3回連続で選ばねばならないようなケースでは、しらみつぶし式では、27通りを試さねばならない。
これが逐次思考。
しかし、3回の選択を、次はAだろう、次はBだろう、次はCだろうと、3回選ぶだけならば、9通りを試すだけですむ。
これを著者は、飛躍思考と呼んでいる。
もちろん、飛躍思考で、正解を得るには、全体の構造を理解できていなければならない。
それには、過去に徹底的にそのことについて考え、演習して、答え合わせまで行う経験をしていることが大切である。
経験と知識に裏付けられた飛躍思考を、
「直観」
と呼んでいる。
直観でわかるのが理想である。
直観と似て非なるものが、直感や勘である。
これは刺激を受けて思い浮かべたもの。
なんとなくサイコロで、次に5が出るような気がするという論理的根拠がない思考だ。
自分の持っているテンプレートが不完全なのに、目の前の事象と一致しているように見えて、すべての説明ができるように思えてしまう錯覚にも気をつけよという。
では、直観でわかる力を鍛えるにはどうすべきなのか。
「現代社会で本当に必要とされていることは、与えられた課題を解決する「課題解決」ではなく、事象を観察して何が問題なのかを決める「課題設定」です。
課題解決と課題設定のちがいは「HOW」と「WHAT」のちがいと言ってもいいでしょう。
そして何よりも「WHAT」が社会で必要とされる時代なのです。」
それは、本当にそうだと思う。
「HOW」は、今は、ネットで検索すれば、誰でも、すぐにみつけられる時代でもあるからだ。
変化が激しい状況では、解決すべき課題が何なのかを、見抜く人が求められている。
見ない、考えない、歩かない、の3ナイがいけないと、著者は指摘する。
現地、現物、現人を観察し、自分で考えることが、直観を鍛える上で、大切だと結論している。
逆演算の重要性という章もあったが、ネットで検索すると、「HOW」がすぐに見つかってしまう現代では、手を動かして検算する疑い深さが、ますます重要になってきているように思われる。
わかるという当たり前のプロセスを、根底から解き明かそうとする一冊。
[ 結論 ]
ある事象(ことがら)が「わかる」ということは、事象を理解するための自分なりの頭の中のテンプレート(型紙)と比較して、一致していることが見つかったときに、その事象が「わかる」と感じる、と説明されている。
古い本ではあるが、ブルーバックスで「分かりやすい」3部作を書いた藤沢氏の本にあった、スキーマい言われているものであろう。
「「分かりやすい説明」の技術 最強のプレゼンテーション15のルール」(ブルーバックス)藤沢晃治(著)

「「分かりやすい文章」の技術―読み手を説得する18のテクニック」(ブルーバックス)藤沢晃治(著)

「「分かりやすい教え方」の技術―「教え上手」になるための13のポイント」(ブルーバックス)藤沢晃治(著)
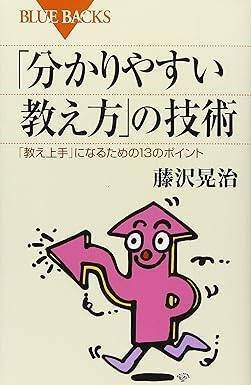
ウェブページのエッセンスだと、脳内辞書とか呼ばれているが、とにかく脳味噌の中にある、既存の知識、経験のデータベースだという風に、理解できる。
幼児が、トマトとリンゴを区別できるようになるのも、学生が、実験を通して教科書にあることを理解していくのも、頭の中に経験を通して、テンプレートができていく、と考えると「ああ、なるほどね」と思える。
これも「わかる」ってことである。
つまり「わかる」ためには、それなりの準備が、頭の中になければいけないわけである。
算数や理科は、
「足し算がわかってた方が、掛け算がわかりやすそうだよね」
とか、
「イオンの話をする前に、原子が陽子と中性子と電子だってこと話しとかなくちゃね」
とか、頭の中の準備ができるような順番で教えている。
頭の中の準備ができてるかどうかを、レディネスと、その教育的役割から説明することができる。
学習者が何かを学習しようとするとき、それを学習し、身につけるために必要な条件が準備されていなければ、十分な学習の効果があげられないという。
レディネス(教育準備性)とは、学習者があることを学習するとき、それを習得するために必要な、精神的、身体的な条件が用意され、準備されている状態をいう。
あることがらの習得に、学習者の身心の条件が準備されているとき、すなわち一定のレディネスが成立していれば、学習者は、その学習に興味を持ち、進んでこれを習得しようとし、学習の効果をあげることができるが、レデプネスがなければ、彼はその学習に興味がなく、学習の効果をあげることはできない。
これまでのレディネスについての考えかたは、成熟と、ほぼ同じ意味に解かされていて、外界からの刺激や影響とは無関係に、内発的に現れるものと考えられていた。
このような事実を示すものとして、ゲゼルとトンプソンの実験がある。
彼らは、一卵性双生児による実験から、
「神経の成熟により一定のレディネスができていなければ、練習は無意味である」
と結論づけた。
これに対し、
「レディネスは成熟によるだけでなく、積極的につくり出すことができる」
との見解がヴィゴッキーにより提唱された。
また、ブルーナーは、
「どの教科でも知的性格をそのまま保ち、発達のどの段階の子供にも効果的に教えることができる」
と述べている。
この見解をもとに、彼は、前に学習した基本的観念を、上級学年では、複雑なかたちでの学習をくり返すことにより、諸観念の理解を深めるという、ラセン形教育過程を提示した。
発見学習は、教師が説明や講義をするのではなく、学習者が自分自身で新しい知識を習得したり、問題解決の方法を身につける方法である。
その方法を、次のような問題を例に考えてみる。
12×43+12×57を計算しなさい。
この問題を提示すると、ほとんどの子ども達は、
12×43=516
12×57=684
516+684=1200
として計算する。
ここから発見学習に移るわけである。
教師は、
「もっと能率的な方法はないか」
と具体的にわかり易い問題を数多く与える。
2×6+2×4
7×3+7×7
5×2+5×8
このような問題から、直観的に、問題解決の手がかりを発見させる。
子ども達はやがて、
2×6+2×4=2×(6+4)=20
の形に変形して求められることに気付く。
さらに、ここから、
2×6+2×4=2(6+4)
という分配法則を発見し、最初の問題を、振り返るのである。
学習の成立にかわる要因として、忘れることのできない動機つげには、内発的動機と、外発的動機とあるが、前者の方が学習効果に大きく作用する。
その方法をるとめてみると、次のようになる。
1)興味に訴える
2)欲求に訴える
3)学習の目標の設定と明確化
4)学習効果を知らせる
5)成功感に訴える
6)賞罰を用いる
7)競争に訴える
「どの教科も、知的性格をそのまま保って、発達のどの段階の子どもにも効果的に教えることができる」という仮説は、様々な波紋をもたらしたが、そもそも、このような考えが論じられるようになったのは、アメリカの原子爆弾独占の夢が破れ、また、ソヴィエトのスプートニック発射の成功により、ソヴィエトの高水準に短期間に達し得た教育が注目されたからである。
しかし、結果としては、才能児と児のギャップを目立たせ、英才児の重点育成に利用されるなど、様々な問題を残した。
[ コメント ]
このレディネスは、小学校、中学校あたりだと比較的簡単に検討がつけられる。
教科書もわかってるし、何を教えてるかも決められているから。
もちろん理解の早い遅いがあるわけで、楽勝な作業ということではない。
何をもって比較的と言ってるかと言えば、例えば大学にくる学生は、今までに勉強した内容がマチマチである。
受験科目にないものは、まったく勉強してこないから、タンパク質はアミノ酸がつながってできているとか、押したら押しかえされる作用・反作用の法則とか、知っていたり、知らなかったりする。
微分積分とか確率統計は、すがすがしいほど知らない学生も多く、ある意味、これは先生にとっては楽である。
そのマチマチな頭の中に「わかる」瞬間を演出するのが、先生の仕事である。
そして、この本からよくわかったのは、学生の頭の中に、いろんな意味でテンプレートがないこと。
つまりは、知識も経験もない。
受験用のつめこみ知識だとしても、定着していてくれれば、つなぎようがある。
知識がなくても、おはじきとか、ビリヤードとかして遊んでいてくれたら、ベクトルも少しはピンとしてくれたりするんじゃないか?
何でもいいのであるが、要は、身のまわりで起こってることを観察して、覚えていてほしいということ。
無論、経験なしに知識だけで、論理展開して賢くなることもできるが、はっきり言って、超人の術である。
十次元のヒモとか言われて納得できるのは、本当にすごいことだと思う。
凡人には、ボールとヒモで近似された原子が、波動関数にくるまれてボンヤリと霞がかるあたりまでが限界。
手を叩くとくっつくかもしれない、ということぐらいまでが、納得のリミットである。
手を叩くとくっつくことも納得できない多数の人々は、経験というテンプレートをもとに、知識を身につけていくのが、早道とは言いないが、長持ちする良い方法なんじゃないかと思う。
何かに詳しくなることは、様々な経験があるからである。
しかしながら、
「どんな経験も意味がある」
という言い分は、教育で金もらっている人間のするものじゃない。
なるべく、意味のありそうなことを実験なり演習なりで経験させていく必要がある。
「わかる」ためには、頭の中にテンプレートがないといけないし、そのテンプレートは、知識や経験からつくられる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
