
【なぜ、あなたは本を読むのか?】「未来形」と「過去形」の読書について
「未来形の読書術」(ちくまプリマー新書)石原千秋(著)

【参考記事】
「世界は言語である」と石原さんは言います。
「言葉の外には世界はない。
ぼくたちはまるで言葉の世界に閉じ込められているようなものだ。」
「モノや現象(行為)が先、名前(名づけ)は後」と一般的には思われているが、実は違う、と具体例を上げて説明しています。
「日本では雨のあと空にかかる虹は「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」の七色に見えるが、英語には「藍」に当たる一単語がないので六色に見えると言う。
アフリカには三色や二色に見える部族もあると言う。」
同じ虹を見ても、使っている言語で見える色が異なるとのことです。
もう一つの例です。
「ヨーロッパ文化圏には「肩こり」に当たる言葉がないので、「肩こり」という病気(?)の状態がないらしい。
「背中が痛い」と言うのだそうだ。
「肩こりという言葉がなければ、肩はこらない」のである。」
そう言えば、以前、関連記事で紹介したことがあるのですが、エスキモー語では、「雪」という単語がないのだそうです。
「あんなに雪があるのに、雪、がなければ会話に困るだろうに」と思いましたが、エスキモー語には、
降る雪
積もった雪
氷のように冷たい雪
解けかけの雪
等々、それぞれ、様々なシチュエーションに応じた雪の単語があるとのことです。
「雪」というざっくりとした総称ではなく、細かい場面に応じた単語があるんだよね(^^)
【関連記事】
雪、たくさんの言葉達。
https://note.com/bax36410/n/nbc4960fdbe29
また、石原さんは、評論の書き方をこう説明しています。
「ごく簡単に身も蓋もない言い方をすれば、「ふつうはこう思っているだろうが、僕はこう思う」と書くのが評論である。」
そして、
「常識と、批判的検討(批評)、評論はこの二つの要素がうまく組み合わさってはじめて成功するのである。」
「一番惨めなのは、常識の把握が間違っている場合で、これがずれていると何に対して異議申し立て(批評)を行っているのかさっぱりわからないピンぼけの文章になってしまう。」
「次に惨めなのは常識の批判的検討(批評)が実は常識そのものでしかなかった場合で、実に凡庸な評論になってしまう。」
と言っておられており、
・常識と批判的検討の二項対立
・寄りと引きの視点
これらを意識して、読んだり、書いたり、していきたいなと、そう思っています(^^)
テレビやスマホで、情報は手に入りますが、情報と言葉は、違います^^;
まとめると、
豊富な言葉をもてば、その分、豊富な思考や観念、概念をもつこととなるので、
言葉を知った方がいいし、
言葉を知るための、手っ取り早い方法に、読書がある、
ということになるのでしょう(^^)
さて、本書に拠れば、読書には、
「過去形」
と
「未来形」
の二つの読み方があるそうです。
【「過去形」の読書】
まずは、過去形について。
人は、本を読む前から、本の周辺の情報(パラテクスト)を元に、ある程度、本の内容をわかっている。
もしくは予想している。
人は、知っていることや、わかっていることが書かれている本を読み、自分の知識や考え方が合っていることを確認して、安心するところがある。
物語であっても、人の成長物語や、恋愛成就物語など、最初から、結末がわかっているにもかかわらず、読んで納得する。
ダメな主人公が努力して成功する。
ひたむきな愛が相手に届き成就する。
等々。
これがいわゆる過去形の読書。
今の自分を、肯定するために読む読み方だ。
言い換えると、「曖昧は嫌い、明確な答えをちょうだい!」的、もしくは、、曖昧さを嫌い答えがハッキリとしたものを好む性質である「認知的完結欲求(Cognitive Need for Disclosure)」型読書とも言えるかもしれない。
これまでの自分の知識や世界への理解が、正しいということを確認している。
【「未来形」の読書】
次に、未来形について。
わからないことが書いてある本を読むということは、読み終わった時には、自分は、それをわかっている人になっているはず。
わからなかったことが、わかるようになっている。
そういう知的な成長を、期待もって読むのが、未来形の読書である。
そして、その本を、読もうと思って手に取って選んだ、ということは、その読書には、自分が、そういうことをわかっている人物になりたいという、期待する自分の未来像が、反映されていることになる。
ここに、自分のアイデンティティの問題が浮上する。
ここに、イーザーの空所理論が挿入される。
【参考資料①】
人は、本の内容を、そのまま理解して、自分に取り入れるわけではなく、解釈の余地(空所)が、さまざまにある本を前にして、自分なりの解釈を施しながら、読み進め理解する。
自分が、どんな人間になりたいのか、という思いが、読書内容(理解、解釈)に投影されるというのである。
石原さんの言う
「本は読者の鏡である」
ということだ。
そして、この過去形と未来形の読書術について、ヤウスの「期待の地平」理論(期待の地平とは、受容者が、今までの経験や歴史的所産、伝統によって、作品の展開において「こうであろう」という予測によってテキストを読むときの、その一歩先に存在するものである。)が持ち出される。
【参考図書】
「挑発としての文学史」(岩波モダンクラシックス)ハンス・ロベルト・ヤウス(著)轡田收(訳)

「「空白」を読む―受容理論の現在」R.C. ホルブ(著)鈴木聡(訳)

「虚構と想像力 文学の人間学」(叢書・ウニベルシタス)ヴォルフガング イーザー(著)日中鎮朗/木下直也/越谷直也/市川伸二(訳)

「解釈の射程 〈空白〉のダイナミクス」(叢書・ウニベルシタス)ヴォルフガング イーザー(著)伊藤誓(訳)

「行為としての読書 美的作用の理論」(岩波現代選書 特装版)W.イーザー(著)轡田收(訳)

「文学的芸術作品」ローマン・インガルデン(著)滝内槙雄/細井雄介(訳)
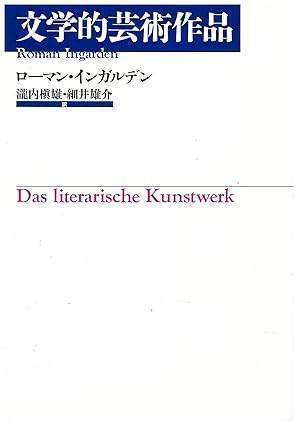
「レンブラント聖家族 描かれたカーテンの内と外」(作品とコンテクスト)ヴォルフガング ケンプ(著)加藤哲弘(訳)

【参考資料②】
自分が知っている通りだった(過去形の読書)というのは、地平の変更の幅が小さい=大衆的な受容である。
一方で、未来形の読書は、自分が知らない知識を得、知らない世界を見ることができるという意味で驚きがある。
つまり、地平の変更の幅が大きい=美学的な受容だ、ということである。
ヤウスの理論がそうであるように、石原さんの言う、過去形の読書と未来形の読書の間にも、優劣があるというわけではない。
どちらも、それぞれ効用がある。
だが、やはりタイトルが「未来形の読書術」とあるように、石原さんが強調するのは未来形の方である。
数ある本の中から、その本を取り出し、読み始める。
そして、何らかの理解を得るという行為は、自分のアイデンティティと深くつながった行いなのだ。
読書の中には、
自分はなにもので、
これから、
なにものになるのか、
なりたいのか、
なろうとしているのか、
という問いが自然に投影される。
自分が知らない知識世界を得ようという未来形の読書をする人は、自分がどうありたいかという問題に向き合っている人なのだといえる。
石原さんは、知識欲を持っている状態を、(年齢問わず)精神的に若いという。
逆に、例え、実年齢が若くても、知識欲や好奇心がない状態を、精神的老人という。
未来形の読書を通して、精神的な若さを保つこと。
そして、決して精神的老人になってはいけない。
これも石原さんのメッセージの一つだろうと思う。
従って、自分の詠んだ本は、自身のアイデンティティにつながっている。
ここで、以下の通り、東洋経済/「今週のもう1冊」のコーナーで、さまざまな分野の専門家が、幅広い分野から厳選した書籍を紹介しているが、この中に、読んでみたいと思う本はありますか?
■攻殻機動隊論(藤田直哉 著/作品社/2970円/354ページ):全作品を対象に全体像を探る。通底する「ゴースト」とは?
■mRNAワクチンの衝撃 コロナ制圧と医療の未来(ジョー・ミラー、エズレム・テュレジ、ウール・シャヒン 著/柴田さとみ、山田 文、山田美明 訳/早川書房/2530円/432ページ):なぜ88日で開発できたのか。新奇なものは傍流から。
■ホームレス救急隊 フランス「115番通報」物語(オド・マッソ 著/川野英二、川野久美子 訳/花伝社/1870円/129ページ):排除された人々を救う救急隊の姿をリアルに描写
■偽装同盟(佐々木 譲 著/集英社/1980円/384ページ):露軍統治下舞台の警察小説。「下向きのif」の面白さ。
■ルポ 路上生活(國友公司 著/KADOKAWA/1650円/240ページ)生活保護を断るホームレス?私たちの知らない路上の現実。
■小鳥と狼のゲーム Uボートに勝利した海軍婦人部隊と秘密のゲーム(サイモン・パーキン 著/野口百合子 訳/東京創元社/2860円/388ページ):英国流リアリズムが細部にあふれる人間ドラマ。
■菌類が世界を救う キノコ・カビ・酵母たちの驚異の能力(マーリン・シェルドレイク 著/鍛原多惠子 訳/河出書房新社/3190円/284ページ):思い入れたっぷりにその生態を語り、筆致も印象的。
■むりなく、むだなく、きげんよく 食と暮らしの88話 茶呑みめし(大原千鶴 著/文芸春秋/1870円/208ページ):ロールキャベツは「作業対効果」が低いメニュー。
■生殖技術と親になること 不妊治療と出生前検査がもたらす葛藤(柘植あづみ 著/みすず書房/3960円/352ページ):技術の進歩が生命の選別につながるおそれ。
■ヒクソン・グレイシー自伝(ヒクソン・グレイシー 著、ピーター・マグワイア 構成、棚橋志行 訳/亜紀書房/2530円/320ページ):本当の強さとは何か、答えは誰の人生にも通じる。
■昭和天皇拝謁記2 初代宮内庁長官 田島道治の記録 昭和二五年一〇月〜二六年一〇月(田島道治 著/古川隆久、茶谷誠一、冨永 望、瀬畑 源、河西秀哉、舟橋正真 編/NHK 協力/岩波書店/3300円/291ページ):戦前的なるものへの郷愁、徹底した反共主義。
■世界を変えた12の時計 時間と人間の1万年史(デイヴィッド・ルーニー 著、東郷えりか 訳/河出書房新社/2970円/294ページ):日時計からスマートウォッチまで、12の時計。
■新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義(安西洋之、中野香織 著/クロスメディア・パブリッシング/2068円/319ページ):「旧型」と異なる、新しいラグジュアリーの意味。
■母親になって後悔してる(オルナ・ドーナト 著/鹿田昌美 訳/新潮社 /2200円/320ページ):苦悩する女性たち、社会が沈黙を促進している。
■命のビザ 評伝・杉原千畝 一人の命を救う者が全世界を救う(白石仁章 著/ミネルヴァ書房/2420円/275ページ):「命のビザ」の杉原千畝、われわれの知らない側面。
■越境と冒険の人類史 宇宙を目指すことを宿命づけられた人類の物語(アンドリュー・レーダー 著/松本 裕 訳/草思社/3850円/494ページ):人類の宇宙への進出、宇宙人の存在の可能性。
■1冊で学位 哲学 大学で学ぶ知識がこの1冊で身につく(ピーター・ギブソン 著、上野正道 監訳/屋代菜海 訳/ニュートンプレス/3300円/250ページ):複雑に絡み合う「概念の海」を泳ぎ、何かをつかむ。
■「歴史総合」をつむぐ 新しい歴史実践へのいざない(歴史学研究会 編/東京大学出版会/2970円/285ページ):衣食の話題など、29の角度から見る近現代史。
■エヴァンゲリオンの精神史(小野俊太郎 著/小鳥遊書房/3190円/406ページ):ファンからも非難された特異で難解な作風。
■進化を超える進化 サピエンスに人類を超越させた4つの秘密(ガイア・ヴィンス 著/野中香方子 訳/文芸春秋/2750円/408ページ):火の使用は遺伝子レベルでの変化をもたらした。
■マイホーム山谷(末並俊司 著/小学館/1650円/245ページ):「困っている人のために」と人が集まる磁力。
■したいけど、めんどくさい 日本のセックスレス現象を社会学する(パッハー・アリス 著/晃洋書房/3520円/288ページ):オーストリア出身の若手研究者が深層を探る。
■失われた時、盗まれた国 ある金融マンを通して見た〈平成30年戦争〉(増田幸弘 著/作品社/2640円/272ページ):「派手な接待」も「週末の社員旅行」も今や過去。
■科学は「ツキ」を証明できるか 「ホットハンド」をめぐる大論争(ベン・コーエン 著/丸山将也 訳/白揚社/2970円/325ページ):精密な「データ解析」導入で、揺らぎ始めた通説。
■秘録 齋藤次郎 最後の大物官僚と戦後経済史(倉重篤郎 著/光文社/1650円/248ページ):「10年に一度の大物」と呼ばれた官僚、齋藤次郎。
■ストーリーが世界を滅ぼす 物語があなたの脳を操作する(ジョナサン・ゴットシャル 著、月谷真紀 訳/東洋経済新報社/2200円/320ページ):TVドラマ、都市伝説、陰道論…物語は「消費財」に。
■デマの影響力 なぜデマは真実よりも速く、広く、力強く伝わるのか?(シナン・アラル 著/夏目 大 訳/ダイヤモンド社/2420円/589ページ):フェイクニュースは真実より速く遠く拡散する。
■パンデミックなき未来へ 僕たちにできること(ビル・ゲイツ 著/山田 文 訳/早川書房/2640円/364ページ):ある意味平凡な提言、問題は「やる気」の有無。
■両手にトカレフ(ブレイディみかこ 著/ポプラ社/1650円/271ページ):社会から見えない「ヤングケアラー」は日本にも。
■ヒトは〈家畜化〉して進化した 私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか(ブライアン・ヘア、ヴァネッサ・ウッズ 著/藤原多伽夫 訳/白揚社/3300円/334ページ):「協調」する力は、危機の時代に淘汰圧となるか
■人はなぜ握手をするのか 接触を求め続けてきた人類の歴史(エラ・アル=シャマヒー 著、大川修二 訳/草思社/1980円/223ページ):西洋的文化に思えるが多様な形で世界中に存在。
■そのとき、日本は何人養える? 食料安全保障から考える社会のしくみ(篠原 信 著/家の光協会/1650円/183ページ):コメを生産するためにも化石燃料が使われている。
■過剰権利主張ケーススタディーズVol.1 エセ著作権事件簿 著作権ヤクザ・パクられ妄想・著作権厨・トレパク冤罪(友利 昴 著/パブリブ/2750円/544ページ):イチャモンや妄想が訴訟につながるケースも。
■進化するトイレ 快適なトイレ 便利・清潔・安心して滞在できる空間(日本トイレ協会 編/柏書房/3300円/348ページ):「おしり安全保障」を担うトイレの歴史や多様性。
■SF作家の地球旅行記(柞刈湯葉 著/産業編集センター/1760円/264ページ):一般の旅行者にはない視点で世界を観察する。
■魅惑の生体物質をめぐる光と影 ホルモン全史(R.H.エプスタイン 著 坪井 貴司 訳/化学同人/260円/350ページ):人間を人間ならしめている「ホルモン」の歴史。
■中二階の原理 日本を支える社会システム(伊丹敬之 著/日経BP 日本経済新聞出版/1980円/296ページ):日本社会、日本企業で重要な役割を果たしてきた。
■アイスランド 海の女の人類学(マーガレット・ウィルソン 著、向井和美 訳/青土社/3520円/382ページ):自立と生存のため海に出た、アイスランド「海の女」たち。
■もっと気になる社会保障 歴史を踏まえ未来を創る政策論(権丈善一、権丈英子 著/勁草書房/2530円/392ページ):国民的議論のスタートラインにやっと立てた日本。
■地球をハックして気候危機を解決しよう 人類が生き残るためのイノベーション(トーマス・コスティゲン 著/穴水由紀子 訳/インターシフト/2530円/320ページ):地球環境に人為的な介入を行うとどうなるか。
■切手デザイナーの仕事 〜日本郵便 切手・葉書室より〜(間部香代 著/グラフィック社/1980円/192ページ):志望動機はまちまち、異業種からの転職も多い。
■プロトコル・オブ・ヒューマニティ(長谷敏司 著/早川書房/2090円/296ページ):科学技術と介護を「人間性の手続き」を軸に描く。
■不穏な熱帯 人間〈以前〉と〈以後〉の人類学(里見龍樹 著/河出書房新社/2970円/450ページ):文化人類学者が熱帯の社会に潜む「不穏」に迫る。
■建築と触覚 空間と五感をめぐる哲学(ユハニ・パッラスマー 著/百合田香織 訳/草思社/3300円/208ページ):「視覚中心主義」への批判、眼は皮膚にこそある。
■大江健三郎の「義」(尾崎真理子 著/講談社/2750円/320ページ):大江健三郎を知り尽くした批評家の大胆な解釈。
■人はなぜ物を欲しがるのか 私たちを支配する「 所有」という概念(ブルース・フッド 著/小浜 杳 訳/白揚社/3300円/320ページ):所有欲という「悪魔」が「共有地の悲劇」を招く。
■AGELESS(エイジレス) 「老いない」科学の最前線(アンドリュー・スティール 著/依田卓巳、草次真希子、田中 的 訳/NewsPicksパブリッシング/2530円/408ページ):「老化を治療」することは可能か、最前線に迫る。」
■賢い人の秘密 天才アリストテレスが史上最も偉大な王に教えた「6つの知恵」(クレイグ・アダムス 著/池田真弥子 訳/文響社/1848円/344ページ):アリストテレスの教えを基に「思考の本質」に迫る。
■現代の奴隷 身近にひそむ人身取引ビジネスの真実と私たちにできること(モニーク・ヴィラ 著/山岡万里子 訳/英治出版/2640円/308ページ):今も行われる邪悪な人身取引、日本も当事者だ。
■「地方」と性的マイノリティ 東北6県のインタビューから(杉浦郁子、前川直哉 著/青弓社/2200円/272ページ):性的マイノリティーが「地元」に抱く複雑な葛藤。
■ザ・パターン・シーカー 自閉症がいかに人類の発明を促したか(サイモン・バロン=コーエン 著/篠田里佐 訳/岡本 卓、和田秀樹 監訳/化学同人/2640円/328ページ):「システム化」の力、自閉症は発明を促してきた。
■書籍修繕という仕事 刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる(ジェヨン 著/牧野美加 訳/原書房/2200円/232ページ):世界に1冊の大切な本を「修繕する」という仕事。
■日本AV全史(安田理央 著/ケンエレブックス/2970円/440ページ):猥雑で生真面目、「性規範の変遷」映し出すAV研究。
■ウクライナ通貨誕生 独立の命運を賭けた闘い(西谷公明 著/岩波現代文庫/1232円/300ページ):ウクライナはいかに「ルーブル圏」から脱出したか
■悪意の科学 意地悪な行動はなぜ進化し社会を動かしているのか?(サイモン・マッカシー=ジョーンズ 著、プレシ南日子 訳/インターシフト/2420円/272ページ):正義と表裏一体の関係、「悪意」はなぜ存在するか。
■イーサリアム 若き天才が示す暗号資産の真実と未来(ヴィタリック・ブテリン 著、高橋 聡 訳/日経BP/2420円/440ページ):94年生まれ、暗号資産界のカリスマが描く未来。
■強欲資本主義は死んだ 個人主義からコミュニティの時代へ(ポール・コリアー、ジョン・ケイ 著/池本幸生、栗林寛幸 訳/勁草書房/3850円/320ページ):個人主義は行き過ぎた、コミュニティーの復権を。
■会話の科学 あなたはなぜ「え?」と言ってしまうのか(ニック・エンフィールド 著/夏目 大 訳/文芸春秋/2420円/264ページ):「話者交代」のタイミング、世界一速いのは日本人
■リベラリズムへの不満(フランシス・フクヤマ 著、会田弘継 訳/新潮社/2420円/224ページ):F・フクヤマ、極論を排したリベラリズムの議論。
■リアリティ+(プラス) バーチャル世界をめぐる哲学の挑戦(上・下)(デイヴィッド・J・チャーマーズ 著/高橋則明 訳/NHK出版/上・2640円/416ページ、下・2530円/336ページ):SFオタクの哲学者が「マトリックス」の問いに挑む。
■三省堂国語辞典から 消えたことば辞典(見坊行徳、三省堂編修所 編著/三省堂/2090円/256ページ):「消えた言葉」の向こうには辞書を編む人々の苦悩。
■同和のドン 上田藤兵衞「人権」と「暴力」の戦後史(伊藤博敏 著/講談社/1980円/352ページ):同和のドン・上田藤兵衞を「表と裏」両面から描く。
■〈絶望〉の生態学 軟弱なサルはいかにして最悪の「死神」になったか(山田俊弘 著/講談社/2420円/288ページ):地球の歴史には過去5回の「大量絶滅」、今は6回目。
■小津安二郎(平山周吉 著/新潮社/2970円/400ページ):「戦争」抜きに語れぬ小津映画、その核にあるもの。
■ビジネスと空想 空想からとんでもないアイデアを生みだす思考法(田丸雅智 著/クロスメディア・パブリッシング/1738円/264ページ):作家が物語を構想する手法で「常識」の枠を外す
■創始者たち イーロン・マスク、ピーター・ティールと世界一のリスクテイカーたちの薄氷の伝説(ジミー・ソニ 著/櫻井祐子 訳/ダイヤモンド社/2420円/656ページ):異端児が集い、「ペイパルマフィア」という伝説に。
■明治大正昭和 化け込み婦人記者奮闘記(平山亜佐子 著/左右社/2200円/288ページ):明治末期から流行、女性記者たちの変装潜入取材。
■ゲーム理論の〈裏口〉入門 ボードゲームで学ぶ戦略的思考法(野田俊也 著/講談社/1980円/208ページ):趣味はボードゲーム、異色のゲーム理論入門書。
■ことばのくすり 感性を磨き、不安を和らげる33篇(稲葉俊郎 著/大和書房/1650円/208ページ):現代医学と伝統医学の「あわい」に立つ医師の言葉。
■ドーピングの歴史 なぜ終わらないのか、どうすればなくせるのか(エイプリル・ヘニング、ポール・ディメオ 著/児島 修 訳/青土社/2860円/288ページ):「ドーピング」はどのように始まり、広まったのか。
■郵便局の裏組織 「全特」――権力と支配構造(藤田知也 著/光文社/1980円/368ページ):郵便局の裏組織「全特」、鉄の掟による政治活動。
■もしニーチェがイッカクだったなら? 動物の知能から考えた人間の愚かさ(ジャスティン・グレッグ 著/的場知之 訳/柏書房/2420円/284ページ):「なぜ」の専門家、人類は知性で幸せになったか?
■栗山ノート2 世界一への軌跡(栗山英樹 著/光文社/1650円/296ページ):スター集団どうまとめるか、栗山監督の「虎の巻」。
■臨床現場のもやもやを解きほぐす 緩和ケア×生命倫理×社会学(森田達也、田代志門 著/医学書院/2640円/212ページ):人生の最終局面のケア、医師と社会学者が対話。
■毒殺の化学 世界を震撼させた11の毒(ニール・ブラッドベリー 著/五十嵐加奈子 訳/青土社/2640円/304ページ):緻密な計画なしに成立しない、「毒殺事件」に迫る。
■「協力」の生命全史 進化と淘汰がもたらした集団の力学(ニコラ・ライハニ 著/藤原多伽夫 訳/東洋経済新報社/2640円/354ページ):ヒトの集団の力学、「協力」と「競争」の緊張関係。
■わっしょい!妊婦(小野美由紀 著/CCCメディアハウス/1870円/312ページ):妊婦の生きにくさは、明日の私たちの生きにくさ。
■RISE ラグビー南ア初の黒人主将 シヤ・コリシ自伝(シヤ・コリシ 著、岩崎晋也 訳/東洋館出版社/2090円/304ページ):ラグビー南ア初の黒人主将、その波瀾万丈の人生。
■ぼっちな食卓 限界家族と「個」の風景(岩村暢子 著/中央公論新社/1870円/256ページ):自由を優先し正月も「個食」、家族の食卓の変化。
■民間諜報員(プライベート・スパイ) 世界を動かす“スパイ・ビジネス”の秘密(バリー・マイヤー 著/庭田よう子 訳/晶文社/2420円/416ページ):諜報機関から独立・転職した「民間諜報員」の姿。
■イーロン・マスク(上・下)(ウォルター・アイザックソン 著/井口耕二 訳/文芸春秋/上2420円/480ページ、下2420円/464ページ):2年間の密着取材が伝える、イーロン・マスクの姿。
■闇の精神史(木澤佐登志 著/ハヤカワ新書/1122円/320ページ):新たな運動の背後に、SFをテコにした自己の確立。
■匂いが命を決める ヒト・昆虫・動植物を誘う嗅覚(ビル・S・ハンソン 著/大沢章子 訳/亜紀書房/2860円/324ページ):究極のセンサー「嗅覚」、新たな活用法にも期待。
■教養としてのアントニオ猪木(プチ鹿島 著/双葉社/1870円/320ページ):アントニオ猪木は他のスターと何が違ったのか。
■数の値打ち グローバル情報化時代に日本文学を読む(ホイト・ロング 著/秋草俊一郎、今井亮一、坪野圭介 訳/フィルムアート社/4400円/432ページ):文学作品の構造探る、人文学のデジタル化の挑戦。
■50代で一足遅れてフェミニズムを知った私がひとりで安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと(和田靜香 著/左右社/1980円/248ページ):大磯町の男女同数議会、「ここではふつう」の理由。
■焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史(湯澤規子 著/角川書店/2420円/368ページ):日米女性労働者たちの『女工哀史』と異なる一面。
■怪物に出会った日 井上尚弥と闘うということ(森合正範 著/講談社/2090円/440ページ):敗者の視点から、"怪物"井上尚弥の強さに迫る。
■外事警察秘録(北村 滋 著/文芸春秋/1760円/296ページ):前国家安全保障局長による重大事件の答え合わせ。
■サイエンス・フィクション大全 映画、文学、芸術で描かれたSFの世界(グリン・モーガン 編/石田亜矢子 訳/グラフィック社/4620円/288ページ):「SFとは結局何なのか?」、その歴史や最先端を一望。
■栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24(中井由梨子 著/幻冬舎/1760円/256ページ):脳腫瘍と闘う中、野球選手が見つけた"生きる道"。
■n番部屋を燃やし尽くせ デジタル性犯罪を追跡した「わたしたち」の記録(追跡団火花 著/米津篤八、金李イスル 訳/光文社/2640円/356ページ):史上最悪のデジタル性犯罪、韓国社会の抱える闇。
■小山さんノート(小山さんノートワークショップ 編/エトセトラブックス/2640円/288ページ):何十冊ものノート、女性ホームレスの思索の営み。
■行為主体性の進化 生物はいかに「意思」を獲得したのか(マイケル・トマセロ 著/高橋 洋 訳/白揚社/3410円/272ページ):能動的に行動する力、人と他の生物で何が違うか。
■MOCT(モスト) 「ソ連」を伝えたモスクワ放送の日本人(青島 顕著/集英社/1980円/264ページ):ソ連国営ラジオ、「鉄のカーテン」を越えた肉声。
■科学文明の起源 近代世界を生んだグローバルな科学の歴史(ジェイムズ・ポスケット 著/水谷 淳 訳/東洋経済新報社/3520円/566ページ):近代科学は欧州が独力で成し遂げた偉業ではない。
■ツレが「ひと」ではなかった 異類婚姻譚案内(川森博司 著/淡交社/2310円/224ページ):「人外」との婚姻譚、そこに刻印された社会の姿。
(出典:東洋経済/今週のもう1冊(さまざまな分野の専門家が、幅広い分野から厳選した書籍を紹介します。【土曜日更新】)
そのようなアイデンティティへの意識がなければ、この本を、自分から手にし読むこともなかっただろう。
本棚を眺め、これまで、自分が読んできた本(あるいは積読状態で読んでいないものも含め)は、自分自身の未来形なのだと気づく。
これらの本にある知識や世界を知った自分でありたい、という自我が、本棚には反映されている。
だから、その人の本棚を見れば、その人なりが理解できるのだと思うから、人に本棚を見られるのは、少し気恥ずかしいのだろう。
そして、一方で、少し誰かに見せたい気持ちも確かにあって、そんな本棚を共有しながら、色んな会話ができたら、とても愉しいだろうなと思う(^^)
【「現在形」の読書】
「過去形」と「未来形」の読書が存在するなら、こんな感じの「現在形」の読書も存在しているので、
・幼児は本を聞く→自分で音読→大人は黙読
・体で読む→意識で読む→意識消し読む
・本を買う=未知を買う
・本を選べる=自分の無知を既知
・自己肯定確認読書↔自己否定発見読書
・回帰↔成長
・言語論的転回
・世界は言葉
・言葉が世界
・世界が言葉↔意識が言葉
・ズレ→言葉が使える=嘘が使える=言葉否定形使える→嘘でない現実ある
・自分=言葉からこぼれた世界
・文学かの判断基準=現在文学との相似性群
・物語はパターン
・現実↔境界↔異界
・浦島↔かぐや↔成長↔退行↔未了
・物語で退行→失敗でなく批評として読む
・期待の地平→成就通俗か裏切芸術
参考までに、安原顯さんの本書を紹介しておく。
「現在形の読書」安原顯(著)

①「読書への抵抗」→楽しむための読書を中断して、宝を探すための読書にすること。
②迷うことを楽しむ読者を「精読者」と呼ぶ。
ついつい、何冊読んだか?という数を追う読書をしがちである。
だからこそ、スローリーディングを意識して、本を読んでいる。
これも、自分なりの「読書への抵抗」なのかもしれないと思った(^^)
「本の読み方 スロー・リーディングの実践」(PHP文芸文庫)平野啓一郎(著)
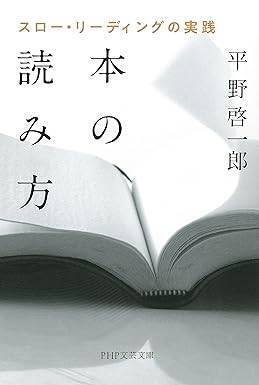
【参考記事】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
