
【元義と朝を、立春】うた・俳文。
山陰ソトモにも春し來ぬらし伯耆ハハキのや大山オホヤマの雪に霞棚引く 平賀元義
流石の"吾妹子先生"も、いつときは女を忘れ、春の訪なひを遠景に詠んだ。まさしく萬葉調で雄大であり、この歌人の優れたオールマイティぶりを見せつけてゐる。江戸時代末期に、これが詠めた人は、恐らくは彼しかゐまい。名利を棄てゝの作にこそ宿る詩心である。
大木戸に冷え遺しけりけふ春立つ くにを
俳句だが、愚作を。どうしても元義と並ぶには遊郭の景物は欠かせないやうな氣がした…大木戸は開門となりこの傾城の街にも朝が來た。木戸番は冷たい戸をかこつけれど、それが風流に繋がる事、には薄々氣づいてゐたらう。粋な商売である。自然、身につくものもあるのだ。
朝の俳句が文藝をスポイルしてゐるんぢやないかと散々悩まされたのである。別に俳句ぢやなくとも、朝歌でもよいし、朝詩でも悪くはない筈。-叛抗してみた譯ね、ちよびつと。それでもそこから先、当たり前に皆さんの自由である。何をやられても私に存念はないのだ。もう一句、
冷えびえと朝刊に洟けふの春 くにを
説明的だな。それでも立春だ。皆さんは恵方巻きなんてくだらねえ儲け主義に引つかゝつたりしてない?ま、何もかも自由の世間ではあるね。擱筆。©都築郷士
たゞ歌は目出度き春を総勢にてするぞ呆れるゆかしきものよ 郷士
個性個性。アデュー。
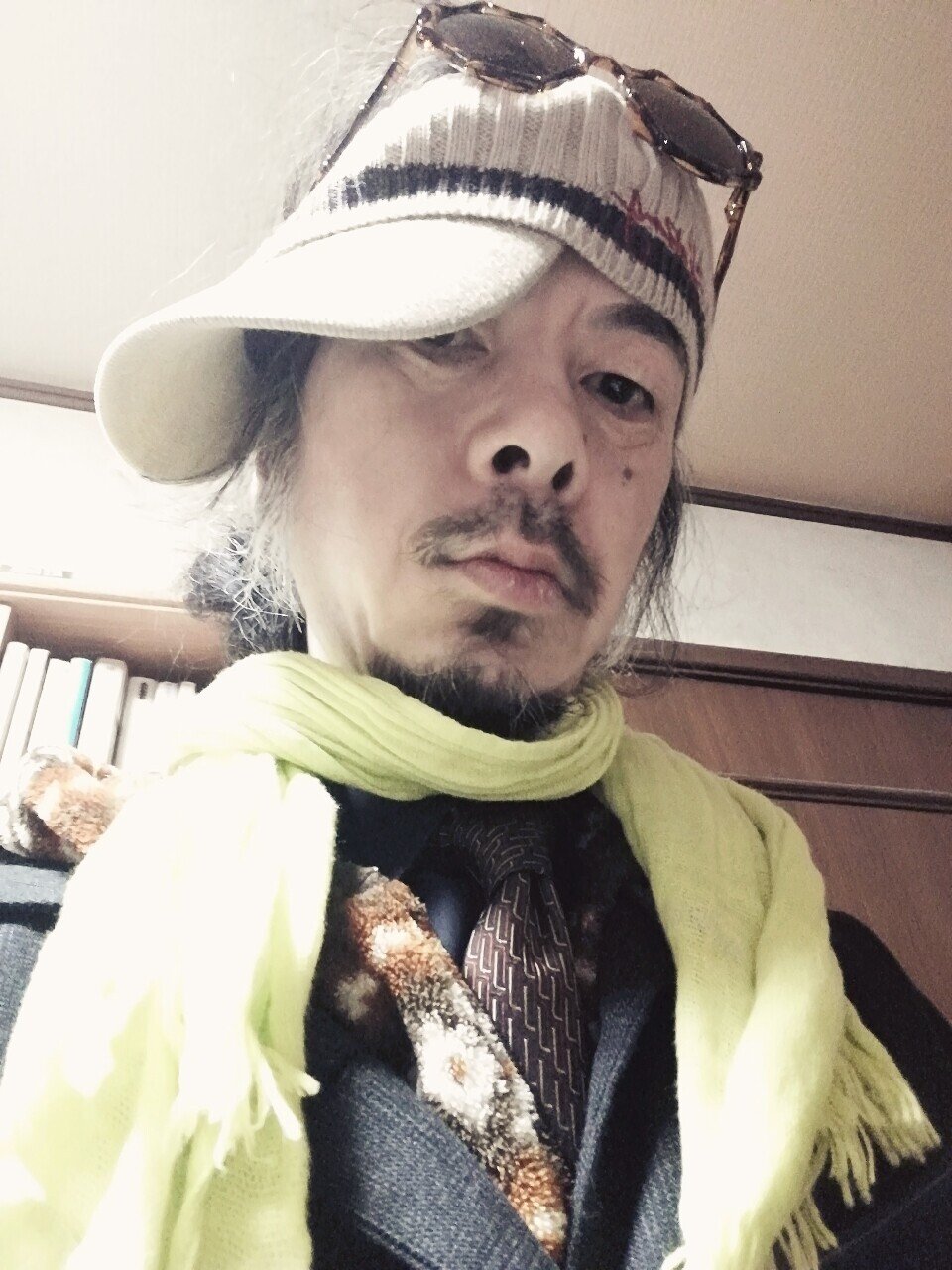
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
