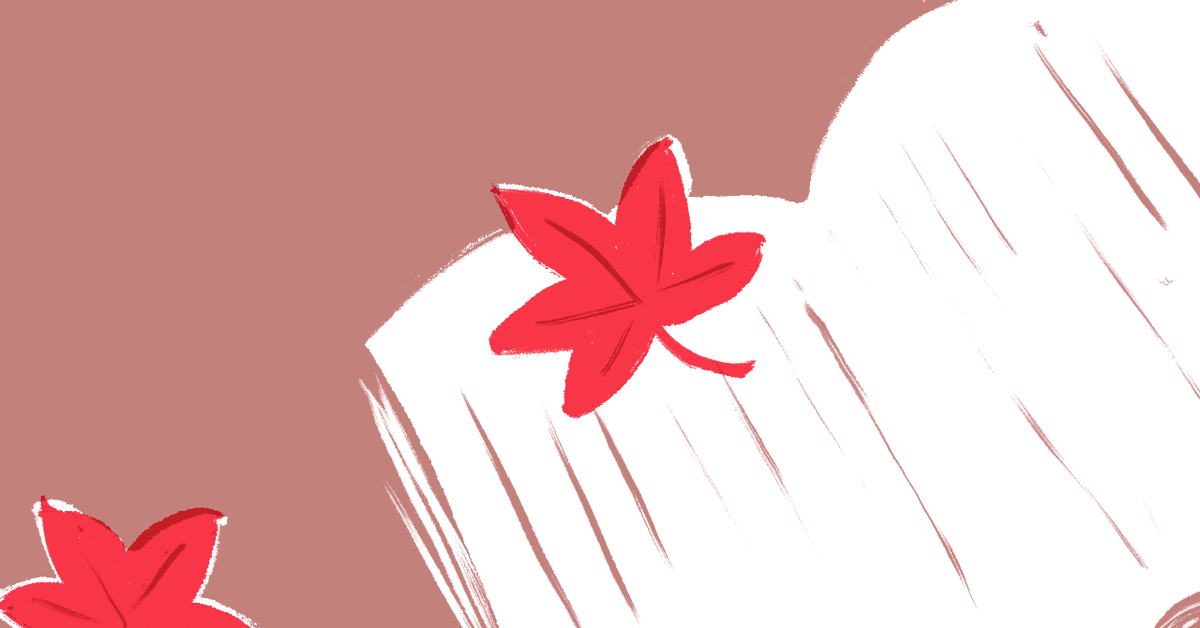
ナショナル・ジオグラフィック「観光の力 世界から愛される国、カナダ流のおもてなし」を読んで
カナダ観光局日本地区代表、半藤将代氏による「観光の力」を読み終えた。
この本では経済的、地理的条件、歴史的流れなどによって存続や本来ある自然などのリソースが侵される危機を「観光」という業界が救った事例が愛情を込めて描かれている。
内容はカナダの観光事業事例にも関わらず本のタイトル最初に「カナダ」という文字が入らず「観光の力」としているところが興味深い。半藤氏が「観光」という事業がいかに幅広い危機を救う事が出来るのかを力説してるかのように思えた。
漁業が衰退し、島のコミュニティー自体が存続の危機にさらされたカナダ東端にあるファーゴ島のホテルを中心にした地域再生物語、官民一体となって観光開発と自然保護のバランスを保って来たバンフ国立公園、失われた先住民の文化を徹底して保護するハイダグアイ。舞台は半藤氏が得意なカナダであるが、本質は「観光」という産業が本来持っている力とSDGsにおける更なる可能性を深くえぐった内容だと感じる。
1990年のバブル崩壊直後に旅行業界に入った私は、今では古い体制のツーリズムが最も幅を利かしていた時代を多感な若い時に経験している。
90年代前半、旅行会社は絶大な力を誇っていた。大学生に一番人気のある企業にはJTBやJALなどが常にベスト5に入っていた。
絶大な力を持っていたが故に旅行のトレンドを作り出すのは常に大企業と電通を代表とする広告代理店だった。代表的なものであれば「わたしをスキーに連れてって」でお馴染みのスキーブーム。JRが湯沢に新駅を作るほどの大盛況ぶりであった。
旅行業界以外の一般の方には忘れ去られているかもしれないが、ロンパリローマと呼ばれるヨーロッパ周遊、ドイツの古城を巡るロマンチック街道、コアラブームに乗ったオーストラリアへの新婚旅行ブーム。これらはすべて大企業か旅行会社、広告代理店が主導となりバス一台へ40人以上ぎっしり大量送客することによって莫大な利益を生んでいた。
旅行代理店や広告会社のおエライさんと社員が、
「ウ~ン次は東欧あたりはどうかね?キミぃ〜。」
「は、まだ誰も手をつけてないので目新しく、うまくブームをつくりだせるのではないかと!ハイッ!」
なんて調子で流行が作り出される。(嘘のようで本当の話である。実際、旅行業者の宴会の席にて真横で聞いていた事がある。)
もちろん現地の観光資源も重要だがそのブームはしっかり土地に根ざしているかどうかはあまり関係なかったりした。
ちなみに私の住むカナダもかつて赤毛のアンの人気に乗ってカナダブームが到来し大盛況であった。今は懐かしい海外旅行のバイブル的雑誌「ABロード」ではカナディアン・ロッキーの町、バンフが世界で最も訪れてみたい町ランキングで1位を獲得し、北海道にはテーマパーク、カナディアンワールド公園がオープンした。60歳以上の人に「バンフ」といえばいまだに「あ〜いつか行ってみたいわね〜。」と遠い目をする人も多い。
そして今は2021年、20代の若者にバンフの事を聞いてもほぼ誰も知らない。企業が作ったブームは一過性のもので広告代理店が手を抜けば一気に知名度は下がる。私の住むバンフでは10件以上あった日本人目当てのお土産屋さんは現在皆無である。
今回読んだ「観光の力」に登場するストーリーは日本のバブル期とは正反対の事例ばかりだ。
その土地に住む住民が自らそこに住む住民すらも認識していなかったような観光資源を掘り起こし、一過性のブームにならないよう十分注意しながら大切に長い時間かけて育てていく。そんな地元愛に満ちたストーリがあふれる本である。
かつて生産性を上げるのが至上とされた工業などは公害・環境汚染を経験後、それを克服しながら成長を続けてる。観光も進化成長し、違った形でまだまだ人類に貢献出来る産業だということを深く認識させたくれる一冊だった。
毎日更新予定。フォローをお願いいたします。ペコリ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
