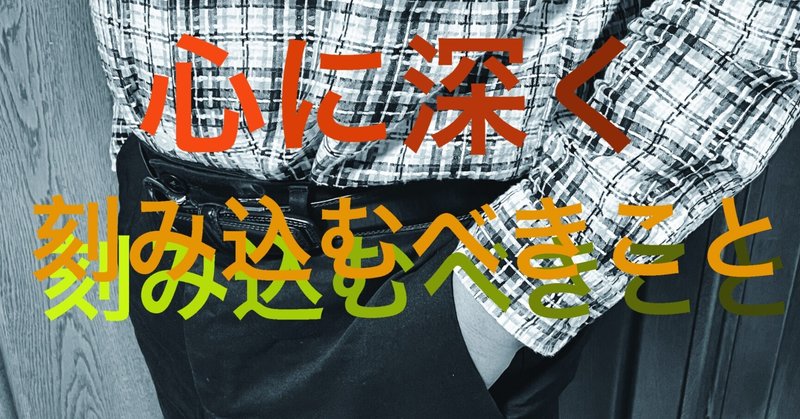
心に刻み込むべきこと
僕自身が 心に刻み込むべき と思っていること・・・
なかなか自分自身では出来ていないと気づくこともあること。
大きな声での指導を続けると、より大きな声の指導だけしか聞こえない子どもを育てることになる。
大きな声は、ある意味、騒音です。騒音も慣れると、耳の機能が麻痺してしまい、大きな音が気にならなくなります。大きな音の中で過ごしている人に何かを伝える時には、より大きな音が必要になってしまいます。また、一部の子どもは、自らが大きな声だけでしゃべり始めるようになります。そうなると、教室はいつも大声の飛び交う場所になってしまいます。そこで、教師は授業中に、意識して小さな声と普通の大きさの声・ささやく声等を使い分けるようにする必要があります。そうすれば、いろいろな声をしっかり聞く子どもが増えます。
乱暴な言葉での指導を続けると、より乱暴な言葉の指導にしか反応できない子どもを育てることになる。
乱暴な言葉も慣れてしまうと、気にならなくなります。そして、大きな声と同様に聞き続けた子どもは、乱暴な言葉を学び、意識せずに自ら使いこなすようになります。これまた、殺伐とした教室になってしまいます。そこで、教師は、意識して丁寧な言葉を使う必要があります。そうすれば、心安らかな子どもが増えます。
乱暴な行動を感じさせる指導を続けると、より乱暴な指導にしか反応しない子どもを育てることになる。
乱暴な行動も慣れてしまうと、気にならなくなります。そして、大きな声や乱暴な言葉と同様に、乱暴な行動を学び、意識せずに自ら使いこなすようになります。これまた、殺伐とした教室になってしまいます。そこで、教師は、乱暴な行動を排除する必要があります。そうすれば、心安らかな子どもが増えます。
脅しを感じさせる指導を続けると、より凶悪な脅しの指導にしか反応できない子どもを育てることになる。
「大きな声」「乱暴な言葉」「乱暴な行動」での指導が通用しないと、教師は知らずと「脅しの指導」をしていたりします。子どもは、脅しを学び、意識せずに自ら使いこなすようになります。これまた、殺伐とした教室になってしまいます。そこで、教師は、子どもを脅すようなことをどんな場合もしてはいけません。
ちょっとした「ずる」に気づかぬ指導を続けると、「ずる」はどんどんエスカレートし、収拾がつかなくなる。
子どもは無意識に教師を試し続けています。ちょっとしたルール違反に気づかぬと、それはどんどんエスカレートしていきます。教師の指示に従わない子どもがどんどん増えていきます。いちど身に付けた指示に従わないというルールは、場が変わっても継続してしまいます。何か落ち着かない集団が形成されてしまうのです。
細かな心の動きに気づかぬ指導を続けると、もの言わぬ無気力な子どもを育てることになる。
いろいろなサインを出し続ける子どもも、教師の適切な反応がないと、意欲を失います。「助けてほしい」「誉めてほしい」etc. 生き生きとした子どもの姿を大切にしたい。それが出来ないと無気力集団が形成されてしまうのです。
理想を追い求める
これは僕の夢であり永遠の課題です。
より短い、適切な言葉で一言だけ指示をし、徹底させ実行させたい。
子どもの育ってきた環境は、それぞれが多様です。どの子にも全く同じ言い方・やり方が通じるという訳ではありません。とは言え、「大きな声」「乱暴な言葉」「乱暴な行動」「脅し」「ずるに気づかぬ」指導は、そういう経験がなかった子どもを萎縮させ、おびえさせてしまいます。そんな失敗を僕は、たくさんしてきました。
失敗に気付かされる時、いつも海より深く反省していますが反省の機会は今も度々あります。だからこそ「より短い、適切な言葉一言で、徹底させ実行させたい」というのが夢となるのです。
中体連スポーツの大会を見に行くと、ポケットに手を入れたまま指導している教師の姿を見ることがあります。また、乱暴で荒い言葉で選手に指示を繰り返している教師の姿を見ることもあります。部活動の大会は、他地域の保護者等様々な方々が観戦しています。何時、誰に見られても素敵な指導の姿を見ていただけるよう、自分自身の姿を振り返っていただきたいものです。
2016(平成28)年7月19日配布の文章を再構成
部活動大会中に教師の感心できない姿を何回も見たなあと思っていた時期に書いた文章です。強いと言われる部活動の有名指導者と言われる人の姿にもいただけないことが複数回ありました。外部指導者や競技関係者の言動にも課題を感じることがあり、競技団体や管内中体連責任者に伝えたこともありますが、多くはその指摘に対して改善をする必要があると思っていただいたようには感じることが出来ませんでした。
「外部の者が事情をわからずにあれこれ言わないでね。」って思われたのかなぁって僻んでいます。
writer Hiraide Hisashi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
