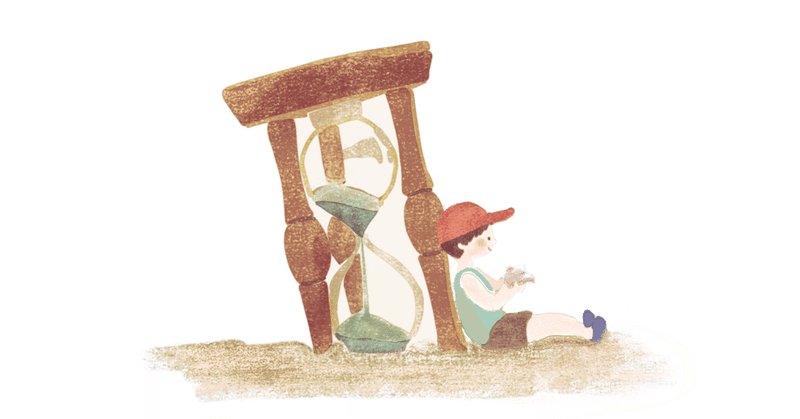
私と息子の場面緘黙物語①少しの違和感
あなたは
「あたまお花畑だったかも…」という時代がありますか?
とても良い意味での
もう頭がふわふわ幸せで
たまらない
そんな思い出…
わたしにとってそれは
「 0歳の育児 」のときがそうでした
振り返るあの頃…
わたしは子どものときから
赤ちゃんや子どもが大好きだった
歳の離れた兄弟がいたこと
不登校のとき、いとこの3歳児をマンツーマンで預かって面倒をみたことも
きっかけになったとおもう
いとこのママは育児ノイローゼで
本気で動物になりきってしまう
おかしくなってしまうということを
子どもの私は聞かされた。
いとこのママの息抜きタイムと
不登校で時間を持て余し、
子どもの世話をしたい(というか遊びたい)私のニーズがマッチしたものだった
3歳児は
両手を広げると飛んで駆けてくる
ギューと抱きしめるとニッコリ笑顔になる
そんな無垢な子どもの姿に
子どもながらに愛おしさが溢れた
幼児教育にも早くから興味があった
学生時代の数少ない愛読書には
育児書がまぎれていた
そんなわたしが我が子を産むことは
パラダイスでしかなかった
どんな時でも赤ちゃんを遠慮なく
好きに抱っこできて独占できる
パラダイス!!
そしてその赤ちゃんもいつでも自分を
求めてくれる
ファビラス!!
笑って可愛い
泣いても可愛いのだ
もちろん大変なことはあった
両家遠方で頼りどころのない子育て…
この頃から少しずつ不安定に病症する夫…出産で腰をやられて数ヶ月は激痛で歩くことが辛かった
でも暗黒の不登校時代を過ごした私は
あの時代より辛いものはない!
ちょっとやそっとの辛さは
ケでもなかった
もちろん辛いことって本当は嫌だ
誰だって逃げ出したい
でも人を育てる前向きな辛さというのは
耐えれるようにできているんだと
不思議に思う
まさに
お花ばたけ どころか
お花バタ子 状態で
赤ちゃんの可愛さに
とろっとろに溶けきっていた
そう、ここでいうお花畑とは
悪口のことではない
アルプスにいるハイジのように
広大な野山でブランコこいで
あははは〜
人生にこんな幸せなことがあったなんてね〜生きててよかった
そう思える出来事だった
自分の命と引き換えに
この子のためなら死ねる!
とよく聞くが
わたしはこんなか弱い子を
残して死ねるわけない
10秒でも1分でも貴重な時間
何がなんでも自分の手で
守り育てねば死にきれん
変な全能感がみなぎっていた
話を進めなければ…
息子、0歳のとき。
目が合うだけでとろける笑顔をくれる
抱けば泣き止み安心したお顔
きっちり3時間でおきる夜泣きも
きっちり30分のお昼寝も
長く続いたが苦痛ではなかった
お昼に自分のごはんの時間がなく
冷やし中華のきゅうりを切らずに
麺の上に乗っけて口に押し込んだこともいい思い出
こんなテキトーな人間を
親にしてくれて幸せな日々
本気で感謝した私は
毎日、息子が産まれてきたことに
ありがとうございますと
3回唱える
この子がおじいちゃんになって
人生を終えるときに
良い人生だったと
思えますようにと
お願いせずにはいられない
自然と日課になっていた
赤ちゃんの子育てはとても神秘的だ
授乳のため半裸族で過ごす
どこか野生的でもあるが
遺伝子のプロセスに導かれながら
細胞はすごい速さで分裂する
点のようなたまごから
爆発的なエネルギーを発し
あなたは胃ね
あなたは目ね
とお互いがお互いを支え
刺激しながら細胞たちは
自ら成長していく「らしい」
それは神様が書いたプログラムのよう
産まれてからも人は成熟するまでに
本人の意思や環境要因では
コントロールできない領域として
人それぞれグンと成長するタイミングが
あることを忘れてはならないと思う
緘黙に繋がる
「少しの違和感」を深掘りしたい
発育や発語は標準だった
よだれがとんでもなく多い子だったが
そんな赤ちゃんもよくいるだろう
毎日のように息子と児童館に通っていたときのこと。
仲の良いママ友は
「マイペースだよねぇ」と
息子のことを言った。
0歳の赤ちゃんのマイペースって
どんな?とは思ったけど
後にこの言葉は私の中に残った
又、ギャンギャンと
豪快に泣くタイプではなく
ふえ〜ん…シクシク…ぐっすんと
悲しそうに
情緒的な堪え泣きもする子だった
またある日、胡蝶蘭をいただいたときのこと
息子はソレにハイハイしながら近づいた
「これはめーよっ、だいじ、だいじ」
と貴重な贈り物を無駄にしたくなかったわたしは軽く言った。
そのたった一言で息子は
胡蝶蘭が枯れて片付けられるまで
一度たりとも絶対に触れなかった。
手狭なマンションで息子の遊び場に
置いていたのに。全く近づかなかった。
よちよち歩きのときには
わずか数センチの段差を
後ろ向きでお尻降りしていた
これも慎重とはいえるが
歩行能力の段階においては
よくある行動だろう
でも2人目の育児をした後で
こうした息子のちょっとしたところは
結構なレベルの慎重派であったことを
思い知った
段差をみればやたらとジャンプしたがる
2人目の育児も後に経験したからだ
そう。
危ないもの、未知のものには触れない
石橋を叩いて…叩いて…叩いて
渡らないんかーい!となることに
確信をもつのはもう少し後のことだった
行動範囲が広がるよちよち期。
緘黙息子は公園やお散歩が好きだった
遊んでいる少し年上の子に興味があった
後ろで様子を伺ったまま
自ら入ってはいけないが
あわよくばと遊んでもらってた
遊具も好きだが
チャレンジしきれない様子は
長い年月で見られた
食は偏食も量が少なめなところも
あったが人並みの範囲だった
入眠や起床もご機嫌でスムーズだった
父の豪快なくしゃみには
よく泣きだしていた
息子は1歳で保育園に入った
先生から言われたことは
「他の子を叱っていても、自分が叱られていると感じてしまうようです」
後に引越しをすることになったとき
新しい保育園先の
アドバイスをいただこうと
相談していると
「転園先は少人数の方ができればいいかも」といわれたことがあった
先に触れた、いろんなことを敏感に感じとってしまうというのが理由のようだった
運動会では、先生に手を繋がれ泣きべそで口に人差し指を添えて、導かれるまま動いたり、固まったりしていた
でもみなさんお分かりのように
1歳児の運動会なんて
むしろそんなものである
まとめると繊細、慎重な
性格が見え隠れしている程度だった
これが0歳〜1歳ちょっとまで
息子の緘黙に気づく前
私と息子の物語のはじまりだった
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
