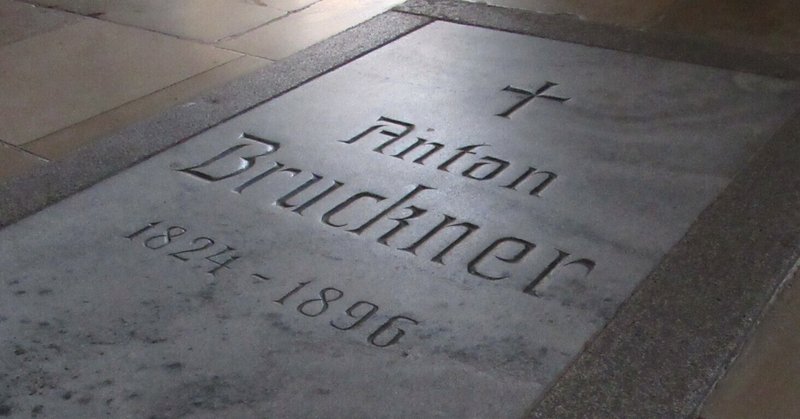
ブルックナーの交響曲は本当にアルプス的かという問いから見えてくるもの
ブルックナーの交響曲が語られるとき、しばしば「アルプス」という固有名詞が持ち出されることがある。これは日本に限った話ではない。ヨーロッパにおいてもそのような認識が一部にはあるようだ。
しかし、これは本当なのだろうか。ブルックナーの交響曲はアルプス的だと言ってしまっていいのだろうか?
1.ブルックナーとアルプスが結びつけられるワケ
前提となる地理的条件
ひとくちにヨーロッパと言っても、たとえば北大西洋や北海の沿岸国の人々(フランスやイギリス、オランダの人々、いわゆる西欧文化圏の人々)にとって、ヨーロッパの内陸に位置する南ドイツやオーストリアは地理的にかなりの距離がある。
ぜひ地図アプリで実際に確かめてみてほしい。ちなみに、アムステルダムからウィーンは鉄道だと12時間以上かかる。もちろん高速鉄道で、である。
このように相当の距離があるため、往々にして南ドイツやオーストリアといったアルプスに近い内陸エリアの人々は良くも悪くも「アルプス方面の人々」としてひとくくりにされてしまう。
日本で言えば近畿地方(実際には二府五県もある)の人が「関西の人」とひとくくりにされてしまうのと同じである。
後期ロマン派という歴史区分
さて、西洋音楽史における後期ロマン派を代表する二人の作曲家はいずれも「アルプス」という地理的表象をローカルアイデンティテイとして、むしろ自らの創作に巧みに取り入れている。
アルプス交響曲を作曲したR.シュトラウス(南ドイツのミュンヘン出身)は、この作品でストレートにアルプスとの結びつきを表明している。作曲者自身の登山経験が作曲の原点にあるというのだからこれ以上のものはない。
マーラー(旧オーストリア帝国内チェコ出身)は夏の休暇をアルプスの裾野のザルツブルク周辺の保養地で過ごしていたという。また、交響曲第一番『巨人』にはまぎれもなくアルペンホルンが登場する。
こうして、同じく後期ロマン派と目されるブルックナー(オーストリア中央部のリンツ周辺出身)も彼らと一緒くたにされてしまう。
そう言われてみると、ブルックナーの交響曲で壮麗に響き渡るホルンの響きはアルプスのそれに近いものがあるような、そうでもないような・・・?
(注)ブルックナーがアルプスを明確に意識して書いたとされる作品は存在しない。また、夏の休暇はたいてい故郷リンツ周辺かバイロイトだった。
2.ブルックナーの原風景は山ではなく丘
2018年の初夏、私(大賀須知院)はブルックナーの故郷リンツ周辺にいた。ウィーンからドナウに沿って西へ、鉄道で1時間半。聖地巡礼の旅である。
実際に現地に行ってみてどうだったか。
リンツ周辺にこれといって高い山はない。あってもそれはせいぜい丘である。ブルックナーの原風景は山岳ではなく丘陵なのである。
丘陵地帯といっても日本人にはなかなかイメージが湧かない。
日本の国土のほとんどは山だが、祖先の多くは山を下り、水田稲作のために狭い平野に密集して生活するようになった。
そこで、これである。
私が見たことのある風景で、リンツ周辺の景色にもっとも近いと思われるところがここである。
実際、リンツ郊外の丘陵地帯には田畑が延々と広がっており、美瑛の農業景観と相当似ているのである。
3.聞き方や演奏の仕方への影響
はっきり言って、ブルックナーの交響曲はアルプスとは無関係である。
しかし、そうかといってウィーンのような都会的な洗練さには程遠い。(それはR.シュトラウスやマーラーの音楽と比べてみれば明らかであろう。)
では、いったい何をイメージすればよいのだろうか?
ブルックナーの交響曲にふさわしい修辞は存在するのだろうか?
一つの提案は、「ゆったりと広がる丘陵」である。
つまり、「丘陵地に広がる美しい田園風景」である。
もし仮にそのように考えてみるとすると、ブルックナーの交響曲の聞き方も変わってくる。演奏スタイルもおのずと変わってくる。
交響曲を聞きこんでいくとこんな疑問にぶつかることがある。
・美しく朗々と歌い上げるようなメロディなのに、作曲者はどうしてここで音量をフォルテ方向ではなくピアノ方向へもっていくのだろう?
・歌ごころにあふれた素晴らしい旋律なのに、作曲者はどうしてここをテュッティにしなかったのだろう?
それは、力む(りきむ)必要がまったくないからである。
丘陵地に広がる美しい田園風景を前に、人は緊張を強いられることも、畏怖の念を覚えることもない。どこか無理をして振る舞うということもない。ただ悠然と穏やかに、自然の赴くがままにすべては流れゆくのだ。
ブルックナーの音楽は至極、自然体なのだ。無理に大きく見せようとしなくてもよいのだ。
してみると、演奏する際の音の出し方もおのずと変わってくる、というより、音を出す前のブレスから変わってくるのだ。
深くゆったりと、しかし自然体で、無理のない範囲で、穏やかに、静かに、美しく。
ブルックナーの交響曲は決して、頑張らなくてよいのだ。
フォルティッシモだからと言ってホールを埋め尽くす大音響をひねり出す必要はない。一方で、ピアニッシモだからと言って音楽の自然な流れが阻害されてはいけない。
ブルックナーの音楽は、いついかなるときも、泰然自若として悠然たる歩みでもって自ずから進んでいくのである。
