
共感と共有
自助グループのイベントで衝撃的な言葉を聞きました。「行動した結果、恨みになっていたり、恨みにつながってしまっていた」という話をしていた仲間がいました。
恨みによる犯罪や行動はわかるけど、逆になるってどういうことだ?と思いながら話を聞いていると、その理由として「一所懸命になりすぎるとそうなっていた」という話をしていました。
その言葉を咀嚼するには時間がかかりましたが、自分の過去と照らし合わせて振り返りました。

そうすると自分にも当てはまることがありました。入寮中の仲間に「あなたが一所懸命になると人の入り込むスキがない」という話をされる事が多かったので「どういう意味だろう? 」と思っていたのですが、最も付き合いの長い仲間が「相手に正論を伝えすぎて、混乱と不安を与えている」と教えてくれました。

つまり、当事者が気づいていない先のことを話しすぎているという話だったのです。私が物事に集中しはじめると情報を掘り下げる度合いが強すぎて、人が知りたくない領域にまで入り込んでしまうクセがありました。
その行為が相手を傷つけてしまっていることや、自分が”潜在的に抱いている恨み”に気づくきっかけになりました。

私自身も「恨みによって」というより「恨みたくない気持ちの抑圧」からの行動が逆に恨みに変化していたことがありました。
特に私が親にしていた事がピッタリ当てはまります。潜在的に抱き続けていた恨みの元は「親子関係」が発端でした。
私の場合、自我を通して情報を明確に処理できない幼少期から夫婦喧嘩を見て育ったので、自分に関係あるのかないのかわからないまま、わかる言葉や目に見える情報だけで情報を処理していたようです。もともと自分の気質に物事を突き止めたいという強い衝動が背景にあるので、メッセージとメタメッセージの互換性に悩んだのだと思います。

正当化・理由づけ
無意識の関連付け(理由づけ)が
第三者に影響を与え
悪影響を及ぼす可能性がある

良心
自分自身に尽くすので
自分が正しいと思うことを
第三者に示す必要はない
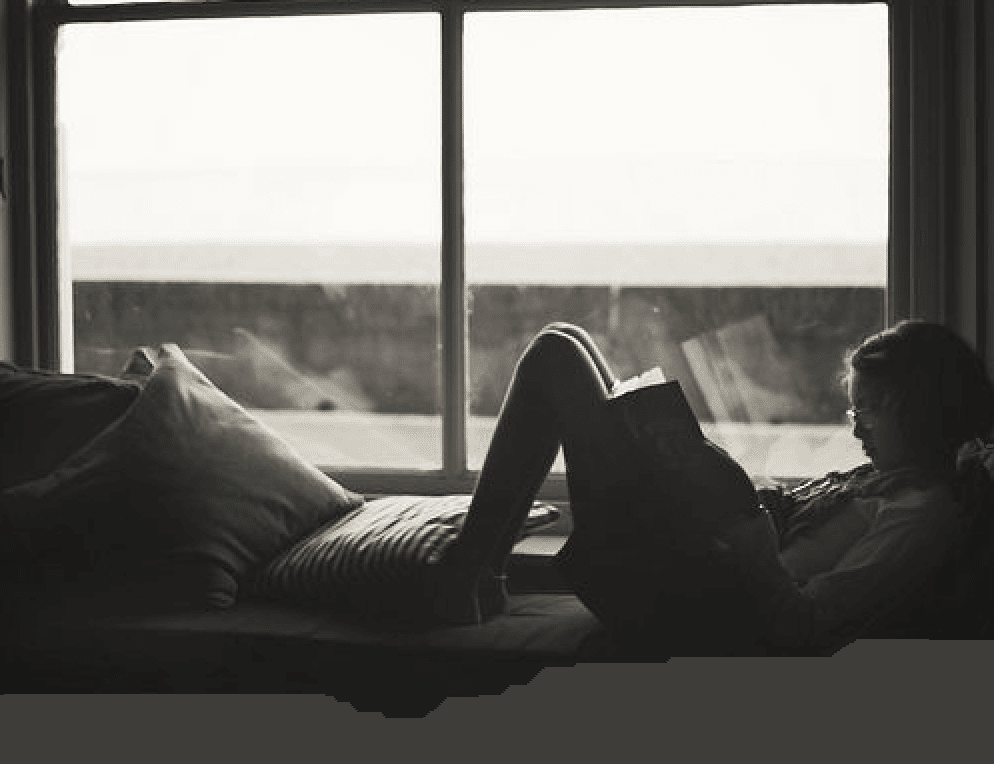
そこで私は「正しさは対象を必要とするが、良心は対象を必要としない」と考えるようになりました。
対象を判断材料として見るのではなく、なるべく尊重して見るように心がけています。そしてイマヌエル・カントの名言にも救われました。
あらゆる可能な行為について、それが正しいか正しくないかを知ることは必ずしも必要なことではない。しかし、私がなそうとしている行為は、私はそれが不正でないことを判断し、思念しなければならないだけでなく、それをまた確信もしなければならない。

たとえ自分のある面を抑圧し、見せかけを装って存在させたとしても、その面は自分のものであることに変わりはありません。
仮面(ペルソナ)や影の投影は幻想的な現実でありながら、実際にそう見える性質を持っています。なぜなら心の投影であるからです。このようにして、心配は不安になり、そして恐怖になったのだと思います。

また、一時的にある側面を捨てたとしても自分の認識そのものを変えようとしない限り、それはブーメランのように戻ってきて、影のように追いかけてきました。
いつのまにか自分を知る過程で、母の私に対する思いの強さも、同じだったのかもしれないと思うようになってきました。

親は不安と期待の矛先を過度に私に向けていたため、私はさらに親の不安や期待に応えようと「良い子でいる」ことを演じようとしました。
そうしているうちに、自分にウソをつくことを覚えて家族の中で孤立しないように自分を守ろうと試みましたが、私が守ろうとしていたのは自分ではなく「父と母の夫婦関係」であることに気がついてしまい、それが「恨み」につながっていました。
人が神と同じ力を行使できる唯一の手段が生殖行為であり、その神聖な行為の結果、子供が誕生すると言うこと。故に子は神聖であり御大切にして然るべき。ただし気をつけなければいけないことは、渇愛と御大切を履き違えぬこと。これがポイントです。
そして施設では、同じ問題を起こし続ける人に対する見方を変えられずに苦しんでいる仲間や、施設に異動してくるたびに新たな問題で苦しんでいる仲間を見て自分と比較してしまい、さらに苦しむことになりました。
しかし、見方を変えれば一定の共通パターン、法則、習慣がすべての領域で繰り返されながら、自他ともに成長のプロセスを歩んでいるといえます。

しかし、ここで気をつけないといけない事として、自分と意見を同じくする仲間で固まらないようにしています。
なぜかというと、自分の意見を正当化して仲間を増やす行動に走ると、ますます「心の中で相手を裁く」ようになり、相手の居場所を物理的に奪う行為につながってしまう恐れがあるからです。
こうしたことは、集団生活を送る施設では頻繁に起こります。SNSなどのデジタル空間でも同様のことを垣間見るので、施設生活で経験して良かったと思いました。
AIをフル活用したSNSは、人々の動物的本能を活性化させ、知性を働かせないようにするために、ユーザーの欲望や感情を刺激することに重点が置かれている。そして欠乏感を抱いているユーザーに対し、AIベースのアルゴリズムが空白を埋めたいという欲求をさらに刺激して、見せたい情報に誘導している。 pic.twitter.com/Bc5kmp2RcL
— あいひん (@BABYLONBU5TER) June 24, 2023
特にSNSを運営する企業は、AIを活用してユーザーに依存するように働きかけていると思います。そういった背景を知りながらSNSを利用しないと「ある目的」で始めたはずのSNSが、いつのまにか「手段」に変わってしまい、心身に負担をかけてしまうことになりかねません。

施設生活で積極的に取り組んでいた事は、悩みを解決するために相談するのではなく、悩みを仲間に共有してもらい、現在どのように悩んでいるかを伝えることに留めておくようにしています。
つまり、悩んでいる間も自分の成長になっているので解決を焦らず、自分と向き合う時間として大事に過ごすようにしました。

そういった時間を過ごしたり相談したりすることで、自分だけでなく他者にも余裕を与えるようにしました。そうすることで施設内で人と会話する機会が多くなり、情報を共有している仲間が状況を悪化させないよう自立的に働きかけながら生活していたのです。

つまり、情報の共有と共感から提示される自己修正が、施設のルールや個人のモラルを越えて問題解決していくようになったのです。
もしかしたら今までの人生の中でくり返されてきた「破壊と再生」や「失敗と成功」という二元的思考からの脱却になるのではないか?と手応えを感じました。
人間という分子は他の分子からできるだけ遠ざかろうと努めることによって個性化する。我々自身の極限、我々の独創力の極致は我々の個性ではなく、我々の人格である。我々が結合して一体になる場合にのみ、我々の人格を見出すことができる。簡単にいうと
— あいひん (@BABYLONBU5TER) June 25, 2023
個性=分離
人格=統合 https://t.co/fCdbmJDdyP
その後の施設生活は、過去の負の連鎖を断ち切り、仲間との人間関係で紡いだ思考の糸、つまり「縁起」という関係によって成り立っていきました。
万物は複雑に入りくんだ現象の織物としてその姿をあらわす。そこではさまざまな種類の結びつきが交錯し、重なり合い結びつき、またそうすることで、その織物の姿が決定されていく。
私の人生、みなさまの良心で成り立っております。私に「工作費」ではなく、「生活費」をご支援ください🥷
