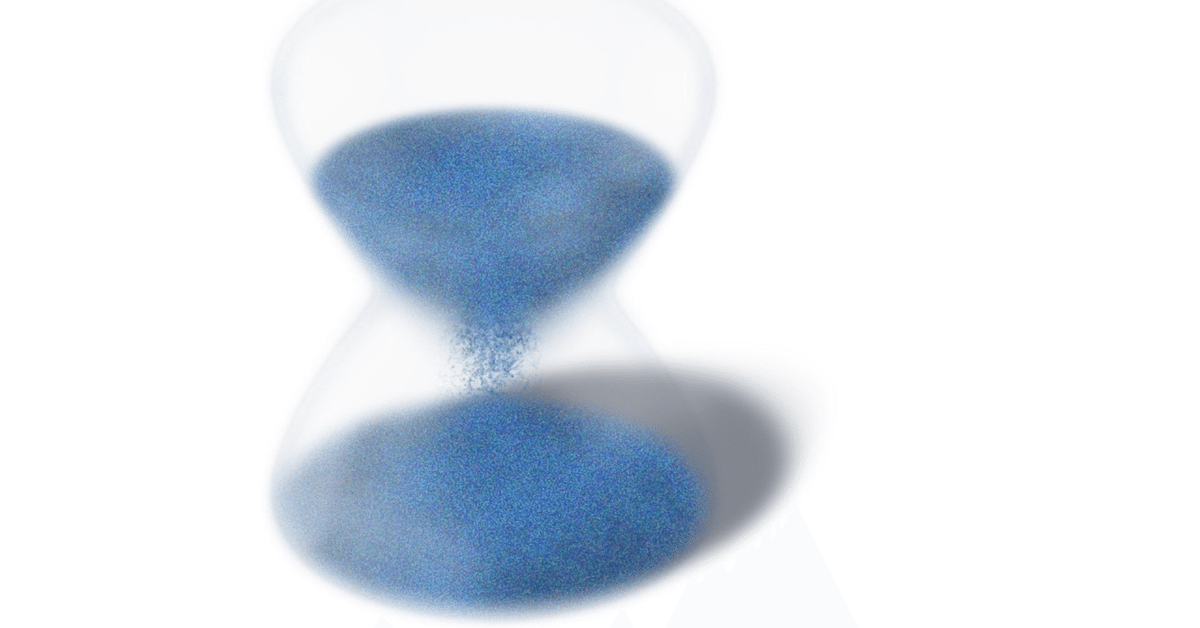
世界は時間でてきている 平井靖史著(読書メモ)
目の前のリンゴの赤い感じや空を飛ぶ鳥の動きを、私たちは自分の体験から、確かな現実だと信じている。ところが、脳科学で主流の表象主義という考え方によれば、私たちが外界のものを見聞きするときに直接アクセスしているのは、物自体ではなく、全て脳の中に生じる表象である。夢や幻覚を見たりする時のように外界に対象が実在しない時でも、私たちは表象を持つことができるので、最終的には、知覚は幻覚と根本的に変わらないものとして「主観のうちに囲いこまれてしまう」(p.196)ことになる。
ベルクソンは、こうした表象主義的な認識の捉え方に異議を唱え、「私たちの知覚はちゃんと世界へと直接アクセスしている」(p.198)という立場をとった。思弁に終始しがちなクオリア・意識・知覚・記憶・人格といった主観・心に関わるテーマについて、ベルクソンは「主観を客観へ、心を自然界に接地させる」ことを旨とした哲学を目指した。独自の時間概念に基づくその理論は、複層的で一見常識に反する概念を含む複雑な体系であり、その全貌を理解することは容易ではない。人の話や理論を理解する・腑に落ちるということは、ベルクソンによれば、表現を「自分自身で再発見し、いわば新たに創りなおせる場合だけである」(p.214)というが、本書は、私のような全くの初心者でも理論の道筋を自分自身で辿れるように、考え抜かれた構成と直観的な理解を促す巧みな比喩を使った説明で道案内してくれる。
このメモは、私が本書で特に関心を持ったポイントについて、自分なりに理解したこと、よく理解できてないところを確認するために書いた。また、私がベルクソン哲学に興味を持つきっかけとなったイアン・マギルクリストの著作「The Matter with Things」*と呼応する点についても少し触れた。私の読み違いや理解を助けることがあれば是非コメントいただきたい。
*読書メモ参照 https://note.com/baba_blog/n/nc1e8e01e7857
1. <時間的拡張>と<運動記憶>
本書において、ベルクソンの時間哲学の鍵となる概念として説明される<拡張>と<運動記憶>という二つの時間変形の働きを、大雑把ではあるが、まず押さえておきたい。
<時間的拡張(マルチタイムスケール)>
「途方もないミクロな時間スケールから、マクロな時間スケールまで、多層的なスケールの時間が同じ一人の人間のうちに走っていて、そしてその構造が、私たちが意識や心を持つこと、想像し発明する知性を立ち上げるための条件になっている」(p.50)
生物の進化において、神経系が登場し、構造が複雑化するにつれて、生物と環境との相互作用システム(感覚‐運動システム)は、より大きな時間幅を持てるようになってきた。私たちの体験する時間は、点ではなく幅を持っている。この時間的拡張によって、私たちは、物質同士では瞬間的に完結してしまう相互作用の瞬間を膨大な数、保持し現在のうちに取り込むことができる。知覚の時間分解能の制約により、私たちは物質レベルの速すぎる量的な変化を識別できないが、拡張された時間に含まれる膨大な数の物質レベルの刺激は「凝縮」されて質的な識別が可能になる。知覚の最小時間単位(2~20ミリ秒のオーダー:階層1)での「凝縮」によってクオリア(感覚質)が生まれる。凝縮が感覚‐運動システムの一周期の幅 (0.5~3秒のオーダー:階層2)で起きると流れの体験(体験質)、人生のタイムスパン(数十~百年のオーダー:階層3)で起きると人格質(私であるという感じ)が生まれる。
<運動記憶>
運動記憶とは、自転車に乗ることを覚えるように反復・学習によって安定化した運動回路であり、そこでは表象を介さない知覚がなされている。これに加え、中枢神経系が発達した人間は、表象を伴う豊かな認識を行っている。しかし、人間においても表象なしの知覚は健在であり単純で日常的に繰り返される活動を支えてくれている(自動的再認)。表象的な認識においてもその土台には運動記憶がある。それは、運動記憶に基づいて特徴を検出、対象を推定し、手持ちの心的イメージを投射するハイブリッドな認識(注意的再認)として実現されている。
さらにベルクソンは、生物が「本能」として生まれつき持っている知覚や運動の機能も、進化というタイムスケールで反復と更新を通じて獲得された種レベルでの「運動記憶」として捉えている。このプロセスは「斜面を繰り返し流れる水が、次第に決まったルートをとるようにして、生物と環境の相互作用回路が世界に彫り込まれ」(p.232)ていく「水路づけ」と呼ばれている。
2. 流れの体験
私たちが体験する現在(階層2)は、感覚‐運動システム一周期分の幅をもっており、そこには数多くのクオリアの瞬間が含まれている。この現在の幅で、どのように流れが経験されるのかを、本書(3章)では「相互浸透」、「未完了相」、「折り合いモデル」といった概念を使って説明してくれる。(幅を持ち流れとして体験される時間をベルクソンは「持続」と呼んでいる。)
「相互浸透」は、相継いで起こる事象が互いになめらかに継続していて、その境界が分かれていない時間の流れの性質を示している。各瞬間に体験されるクオリアは、前後から切り離して単独では決まらない。メロディーの中の一つの音は、それに先立つ音だけでなく、後続の音によってその印象を変える。さらに前後の関係だけでなくメロディー全体によっても印象が変わる。一つ一つの瞬間のクオリアの知覚は、全体のメロディーを作る要素でありながら、全体のメロディーができるまで、定まらず「宙に浮いて」いる。この、部分同士、そして部分と全体の相互的な決定の「決まりきらない・決まりつつある」プロセスが「折り合い」であり、その現在進行形な時間のあり方が「未完了相」である。流れの体験はここで生まれる。
本書では、この「未完了相」が出てくるのは瞬間(感覚質・クオリア)の「並び」を決めなければならなくなったからと説明されているが、ここのところは私にはまだよく理解できていない。瞬間の「並び」というと、一つ一つの瞬間が互いからはっきり分離していることを想定してしまう。常に変化する「未完了相」という様相そのものが、流れを体験するということだという理解では不十分だろうか。
3. 記憶
記憶は、脳神経ネットワークに残された痕跡だというのが、現在でも主流の考え方である。しかし、痕跡説は、過去の特定の一場面を想起するエピソード記憶が、どうして現象経験を再現できるのか、それがどうして過去に由来するものだと分かるのかということを説明できない。現在の幅(階層2)で生まれる現象体験を含む体験質こそが、実はすでに記憶であり、知覚と共時的に成立しているというのがベルクソンの純粋記憶理論である。階層1の時間スケールでは既に過去になった瞬間も、階層2ではまだ現在の内にあり、直接アクセスできる。階層2の現在の幅を超えてこぼれ出る過去も、階層3ではまだ終わっておらず、表象を介さず直接想起できると考えられる。単純な生物では、感覚入力に対して直ちに運動の反応があり、感覚と運動のカップリングはその時間幅で閉じているが、人間のように時間の多層化が進んでくると、今見たり聞いたりする全てのことに、すぐに運動反応が取れず、ほとんどは繰り越されることになる(凝縮されて変形されるが)。しかし、これらは時を経て、そしていくつかの加工を経て、いつかの行動に利用される。このようにシステムが未来に向けて開いているのが人間の記憶のあり方である。
「ある階層で過去であるものは、別な階層でなお現在」(p190)であり、私たちは「実物の過去そのものに直接アクセス」(p.152)できるという、ここでの記憶の捉え方は、私にとってまさに目からうろこだった。
4. 時間の空間化
記憶のおかげで、「私たちは『今ここ』の現在の幅を超えて、過去や未来へと大きく時間展望を繰り広げることができようになる。さらに様々な出来事が、互いにどのように順序づけられるか、「直線的な時間像」(時間の空間化)も記憶を加工することで作り出される。この能力のおかげで、人間は過去を振り返り、計画を立て、環境をコントロールする力を持つことができるようになった。しかし、時間の空間化は、相互浸透的な時間の流れを、離散的な瞬間が並んだ順序系列に仕立てる操作である。瞬間が記号に置き換えられ分離することで肝心の流れは消えてしまう。体験される時間の流れよりも、空間化された時間の方を、現実だとみなしてしまうと、ゼノンの「アキレスと亀」や「飛ぶ矢」の話のようなパラドックスが生まれてしまう。
私がベルクソンの時間論に関心を持つきっかけを作ってくれたイアン・マギルクリストによれば、時間を空間的な拡がりをもつモノとみなす考え方は現代の文化に深く浸透している。時間を管理されるべき「リソース」とみなされ、なるべく少ない時間になるべく多くのものを詰め込むことが要求される。多くのことを一度にやろうとすることで、意味、楽しさは失われ、逆に時間の価値は失われてしまう。私たちは「いまここ」ではなく、常に過去や将来ばかりに目をむけており、本当の経験を見失っている。
5. 進化の時間スケールでの「水路づけ」:概念の起源
生物と環境の相互作用の反復と更新によって次第に運動記憶が回路として彫り込まれていく過程をベルクソンは「水路づけ」と呼んだ。「水路づけ」によって生物は種としての行動のレパートリーを獲得していく。そして「どんな運動が可能であるかが、その生物が何を知覚するかを決める」(p.237)。行動レパートリーによって、知覚の対象の選別、対象との距離、類似などが定義される。「食べる」や「逃げる」という行動が発動できるかによって、「食べもの」、「逃げもの(?)」という知覚対象のタイプ・カテゴリー化(類似したものとしてまとめること)が生まれる。ここに、意味や一般抽象概念の起源が見いだされる。
「水路づけ」のプロセスは、流れの体験が「未完了相」の時間で「折り合い」を通して生まれるように、機械的なメカニズムでは説明できない性格をもっている。生物と環境の相互作用によって水路が次第に掘られていくというが、最初の時点では、何が知覚対象なのか、何が類似の尺度になるのか、さらに何が中心となる身体なのかも分かっていない。無数の相互作用が、やがて互いに「重ね合わされる」ように類似と距離で絞り込まれてくる。
ベルクソンは物質に、こうした自生的な秩序を形成する働きがあると認めている。このことは、物質と生物の境目は思ったほどはっきりしたものではなく地続きであることを示しているように思える。ただし、生物は無生物にはないスピードで多様な進化を世界にもたらすという大きな違いはある。
6. 物質と意識
すでに見てきたように、ベルクソンはクオリア、流れの体験、人格質(私である感じ)といった様々なレベルの意識(=経験)の成立ちを、「時間的拡張」の働きから説明した。時間拡張とは、物質同士では極微の現在のなかで完結してしまう相互作用が生物の登場によって遅延されることであり、意識は遅延によってもたらされると言い換えられる(意識の遅延テーゼ)。同じことを「運動記憶」の観点から見ることができる。運動記憶に従った意識的知覚は、物質の相互作用の全体から、有用なものだけを切り離す。この切り出しによって意識が生まれるというのが、意識の減算テーゼである。一部切り出すということは、一部の相互作用を遅延させていることに他ならず、減算テーゼは遅延テーゼと組み合わさって意識の成立ちを説明する。
しかし、減算説は、物質と意識の関係に新たな洞察をもたらしてくれる。物質システムは瞬間的相互作用の総体である。ここでは常に相互作用はひとつの瞬間の中で中和・相殺されている。意識とは、そこから一部の相互作用が遅延することにより、この中和・相殺が解除されることの効果である。ベルクソンは、自然が「引き算」によって産出を行う例として「光の混色」の事例をあげている。無色(白色光と呼ばれる)の太陽光から青色を抽出するには何かを付け加えるのではなく、他の波長域の光をカットすれば良い。太陽光が無色であるのは、色が足りないからではなく、むしろ全てが揃っていることで互いに打ち消し合い「中和」されているためだ。ベルクソンは同様のことを、物質と意識の関係に見ている:物質が意識をもたないのは、意識の素材を欠いているためではなく、むしろ持ちすぎて互いに相殺されているからで、物質から意識を取り出すためには、余計なものを減算すればよい。
ここでのベルクソンの議論は汎心論に通じていると考えて良いだろうか? マギルクリストは、意識と物質は同じ現実の異なった様相であるという。意識と物質は全く異なるものと感じられるが、氷と水や水蒸気と全く異なる性質を持つように、物質は意識の一つのフェーズと考えている。減算という考え方についても、マギルクリストは、「脳の機能は許可によって創造すること、言い換えれば一種のフィルターとして働くこと」であり、「意識は彫刻される:ミケランジェロの手が、形のないブロックから石を取り除き、他の石を残すというプロセスによってダビデ像を誕生させたように、あるものに「ノー」と言うことによって、他のものが前に立って存在することを可能にする」と述べており、ここでのベルグソンの議論に呼応している。
7. 時間的拡張と運動記憶の掛け合わせ:人間の創造性
本書第6章では、さらに「タイプ的イメージ」、「エピソード想起」、「探索的認知」といった人間の知的創造に関わる高次の能力の成立ちが時間的拡張と運動記憶の掛け合わせによって説明される。
運動記憶が「重ね合わせ」によって外界について「タイプ的知覚」を形成するように、記憶に対して「重ね合わせ」が起きることで「タイプ的イメージ」が形成される。タイプ的イメージは、想像や想起に用いられ私たちの探索的で創造的な知性の基礎条件をなしている。
「エピソード想起」は階層2と階層3のスケールギャップに相当する恐るべき桁数(8~10桁)の純粋記憶からの絞り込みとイメージ現実化のプロセスであり、意識を現在の窓から上の階層へ移行させる大きなリソースを要し世界との接地を危険に晒しかねない活動である。しかし、それは行動選択の合理化や学習効果などのメリットを持つばかりでばく、自分でも思いもよらない発明と創造につながることもある。
「探索的認知」は注意的再認を別の角度からやり直すことで、対象のディテールを増やし、時に関連する別の対象にまで範囲を拡げ、文脈を多様化させる活動である。注意的再認は知覚から記憶の想起につながるプロセスだが、知覚に既に思い出が入り込んでいることによって、私たちは示唆を受けさらに探索的な想起を続ける。これが人間の創造性にとって必須な、文脈をこえた連想やひらめきに基づく知性の働きである。
ベルクソンが100年以上も前に、このように人間の創造的な知性の成立ちに関して整合性を持ち説得力のある理論を展開していたことは驚きであった。
8. 自由の定義:既存の枠を超えた創造性
「ベルクソンが考える自由な行為とは、『人格を書き換える変容的な経験』である。この変容は、その時点での過去全体の参照を要求するため事前に定義できず、現象質の力学を要求するため外から定義できない。以上から『予見不可能』な『新しさ』が帰結する」(P.355~366)。
自由が問題になるのは、どちらでも良いようなことについてではなく、没入的なコミットと全人格の問い直しが必要な場面である。自由であるとは、そうした場面で、今の私によってしかなしえない、私の全人格を表現した行為をなしえることだとベルクソンは言っているのだと私は理解した。本書で展開されたベルクソンの時間哲学は、確かに、そうした場面で、私たちが「予見不可能」な「新しい」(単なる新しい組み合わせではなく真に創造的な新しさ)行動をとる能力を持っていること教えてくれる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
