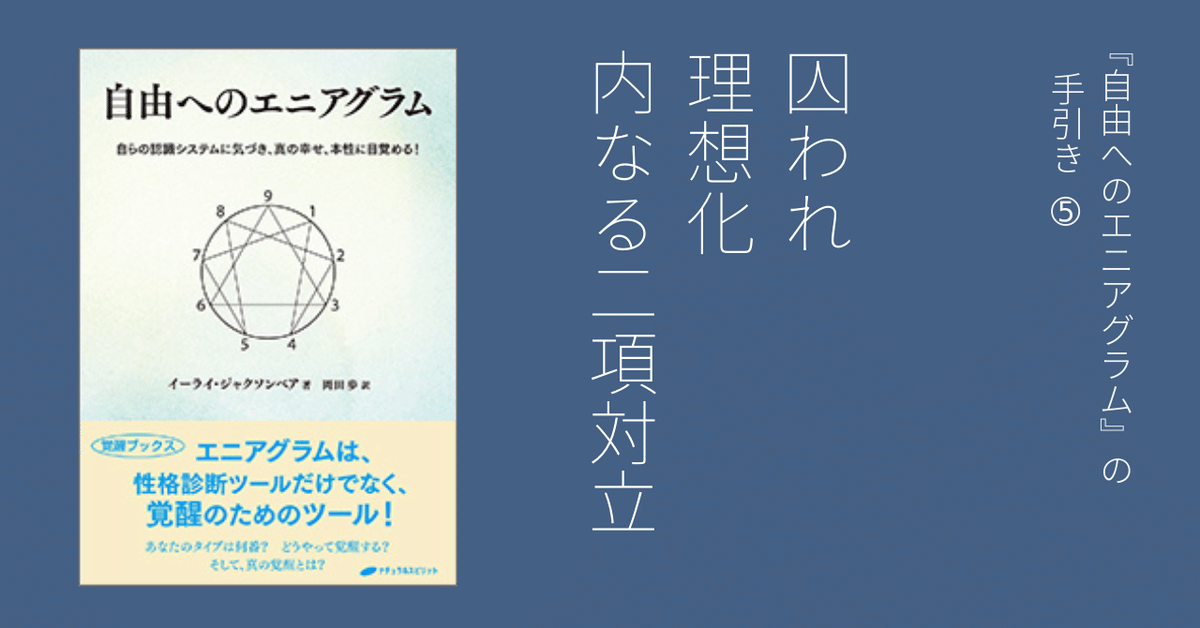
『自由へのエニアグラム』の手引き ➄
『自由へのエニアグラム』(イーライ・ジャクソンベア著)を読むための手引き➄です。(手引き①、手引き②、手引き③、手引き④)
囚われと理想化と内なる二項対立
手引き➄ではサブタイプについて解説します。
囚われと理想化は、認識システムがどのような仕組みで世界を歪んで捉えるように催眠をかけるのか、内なる二項対立は認識システムが振る舞いや態度、容姿として現象化するときのスタイルを教えてくれます。
囚われ
『自由へのエニアグラム』では囚われという用語を選びましたが、エニアグラムを教える人によっては情熱という言葉を使う人もいます。もともとの英語は passion (パッション)です。
情熱を感じる何かが持てることは、一般的には好ましいとされますよね。何に対しても情熱を持てない毎日は、味気ないかもしれません。こうした意味での情熱を感じるものは、ちょっと脇に置いてね。
passion はもともと、ラテン語の patior(苦しむ、我慢する、服従する)から来ていて、語源としては「つらくなるほどの強い感情」を表わします。
こっちの感じです。
囚われは、その認識システムが、そこに激しく駆り立てられてしまう何かです。どうしてもそうなっちゃうような、選択肢がないような感じなのです。
人間も動物なので、動物的な衝動・欲動があります。
動物的衝動が認識システムの囚われを焚きつける
→
囚われに従って感じたり、考えたり、行動したりするしかなくなる
という仕組みです。
動物的衝動の力って本能的なものなので、ものすごく強く働きます。それが引き金におなるので、囚われが私たちを動かす力もものすごく強いのです。
(動物的衝動の話は、手引きの⑥のサブタイプのところで改めてしますね)
衝動とは、刺激が加えられたら、考えることなしに瞬時に反応することです。とくに、本書の中では、動物の本能的な動きによるもの衝動のことを言っています。ライオンがきたら、シマウマは本能的に走って逃げる、というあれです。
なので、各認識システムにとっては、それぞれの囚われに該当するものは、本能的で、コントロール不可に感じます。
コントロール不可どころか、囚われに自分の方がコントロールされているような状態です。まさに囚われてますね。
たとえば、ポイント1の囚われは怒りです。ポイント1の怒りって、基本的にイライラとか不満とか、自分の中でくすぶるタイプの怒りですが、イライラを生じなくさせるなんて、無理に感じるはずです。
ポイント4の囚われは妬み。妬むなんて、自分にとって心地の良いことではありません。できることなら、そんなことはしたくないんだけれど、どうしても妬んでしまう。
そんな感じです。
囚われは本能的な衝動に焚きつけられるから、自動的に生じてしまうもの。認識システムにとっては、そうした感じがするのだけれど、実際は、無意識下でナノ秒(適当に言ってます)レベルのプロセスを踏んで、怒りや妬みが起こっています。
エニアグラムで自分の認識システムを知ることで、この普通では気がつけない無意識下のプロセスに自分で気づくことができるようになります。
あとね、囚われてしまうようになった原因は、自分が育った環境とか、体験にあるととらえる人がめっちゃ多いんだけれど、そうではないんです。
9 - 怠惰
8 - 欲望
1 - 怒り
3 - 偽り
2 - プライド
4 - 妬み
6 - 疑い
7 - (体験の)暴飲暴食
5 - 強欲
たしかに、体験は認識システムの開花を助けはするけれど、その体験のせいで囚われが生まれた/備わったわけではなくて、
囚われはもともと体質的に備わっているんです。
認識システムは体験で形成されるのではなくて、おそらく遺伝的なものだかららです。
本書で認識システムと呼んでいるものを、幼少期のある時点で発現するパーソナリティーとみなしてエニアグラムを教えている人たちが多いようですが、たくさんの人たちとのワークをとおして、私は認識システムとその傾向は子宮にいるときからすでに現れていることを発見しました。エゴの構造が発達するのは三歳から五歳頃です。この時期に起こった出来事がきっかけとなって認識システムが結晶化したのを覚えている人も少なくありません。確かに、決定的に結晶化したのはその時期かもしれませんが、その前は表に出てくる機会を待っている潜伏期なのです。
サクランボの種を植えたら、サクランボの花が咲いて、サクランボの実がなります。それは決まってますよね。種の成長過程の体験によって、サクランボの種が途中で大根になったりしません。体験というのは、サクランボに水や肥料が与えられることや、日光が当たることなのかなって、わたしは捉えています。水をもらえなくても、肥料がなくても、サクランボはやっぱりサクランボの種で、その中にサクランボの実の情報はすでにそこに入っているのです。いくら大根と同じように育てたとしても、あなたは大根だよーって心を込めて声をかけても大根になったりしない。
認識システム1の種の中には怒りが、認識システム4の種の中には妬みが、すでに仕込まれているのです。
あ、そうそう、囚われって、語源が苦しみだし、本人にとっては不快に感じられるように思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
8の欲望とか、2のプライドとか、6の疑いとか、7の暴飲暴食なんかは、本人にとって表面的にはよいことのようにすら感じることも少なくありません。
理想化
認識システムごとにそれぞれ独自の理想像があります。
認識システムは、この理想像こそ「正しいものだ」と思わせるストーリーを頭の中で語り続けます。脳内アファメーションというと聞こえがいいかもしれませんが、妄想・洗脳ですね。
各認識システムの理想化の言葉をみてみると「私は大丈夫」だとか「私は快適だ」だとか「私は有能だ」とか、いかにも、アファメーションとか潜在意識の書き換えとかで使われそうな文句ですね。
ですが、この理想像を追いましょう!っていう話ではまったくありません。理想化によって、自分を洗脳することによって、ただそこにあるリアルが見えなくなります。
そして「そうすべき・そうあるべき」という観念を強固に作り上げます。
自分の価値観とも関係してくるはずです。
あなたの価値観、大切にしていることも、もしかしたら、認識システムの理想化によるものなのかもしれませんよ。
自分の理想化に気づき、理想像を掴もうとする手を離し、それが落ちたときに、深い安らぎや安心感、ピュアな喜びが感じられるんです。
内なる二項対立
内なる二項対立は、認識システムが現象(思考、感情、態度、行動など)として表れるときのスタイルです。
たとえば、熱だったら、冷たいと熱いの二極があります。熱という何かには冷たいと熱いの両方が含まれますが、現象化するときには、いろんな程度があるとはいえ、冷たかったり、熱かったりします。
認識システムが現象化されるときのスタイルにも、それと同じように極性があります。
たとえば、ポイント2の極性は闘士/放蕩者なんですが、闘士はバリバリと仕事をしそうな雰囲気で、肩書上は一番上には立ちませんが、人に明確に指示を与えることもできます。お堅い服装で、パーソナリティもそれに見合ったものになるでしょう。一方、放蕩者はセクシーな容姿だったり、依存的なパーソナリティが全面に出ています。服装も露出が多めだったりします。
体つきも、服装も、態度も、パーソナリティも全然違うんだよね。
本当はどちらの極も自分の中にあります。
闘士の人でも、放蕩者の要素も持っています。
とはいえ、だいたい、どちらか一方の極が全面に出ています。
ただ、二つの極が割と日常的に入れ替わりがちな認識システムもあります。ポイント2の闘士/放蕩者はそうでもないかもしれないけれど、ポイント6の強引/降伏なんかはしょっちゅう変わるという人も少なくないんじゃなかな。闘士/放蕩者は体形とか服装にも関係するから、コロコロ変わるものじゃないんだけれど、強引/降伏は服装とか体形にはあまり関係がなくて、態度に関してなので、目の前にいる相手が変わればサッと変えられちゃうんですよ。相手が怖そうだったら降伏して、怖くなければ強引になります。
内なる二項対立は、ポイントを見分けるヒントになりやすいんじゃないかなぁ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
