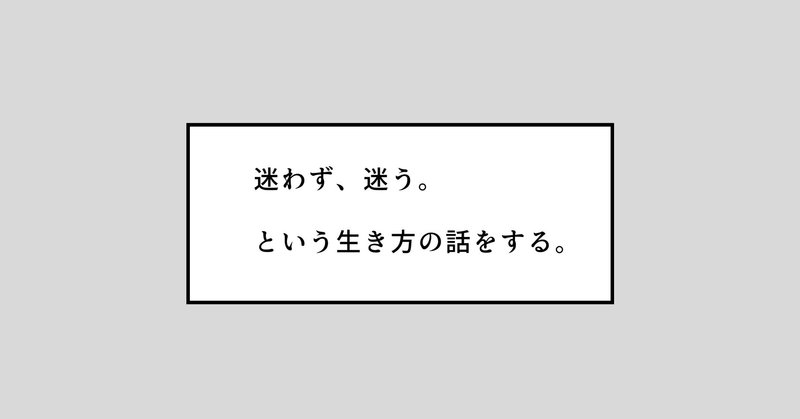
迷わず、迷う という生き方。
中学3年生のとき、原稿用紙1枚分のエッセイを書くという授業があった。「誰が読むわけでもないのだから好き勝手書こう」と、あることないこと書き連ねたら、原稿用紙をはみ出すくらい大きな花丸をもらった。ちょうど進路に悩んでいた時期だったので、「俺には文系の才能があるのかもしれない」という自信が生まれ、公立高校の文系クラスを目指すことにした。
ちょっと成績が足りなかったので、けっこう一生懸命勉強して、なんとか合格した。当時の自分は非常に楽観的な人間だったので、将来の夢を「男版さくらももこ」か「最年少芥川賞受賞者」のどちらかにすることにした。なんてかわいい15歳。誘拐されそう。
背伸びして滑り込んだ高校の進学クラスでは、しっかりと落ちこぼれた。定期テストのクラス内順位は40人中39位とかで、数学の小テストでは人生で初めて0点を取ったりした。押し入れを開けてもドラえもんはいなかった。
しかし、受験勉強の反動なのか、いくら悪い点を取っても成績にあまり興味が持てなかったので、昼休みに登校したり、1限に間に合う電車に乗ってもわざと乗り過ごしてみたり、気が済むまで京都駅を散策したりと、悠々自適な高校生活を続けた。
結果、生徒指導部の先生にネチネチといじめられるようになった。指導部の先生は本当にヤなヤツで、にやにや笑いながら「学校辞めた方がええんちゃうか?」「来ても意味ないやろ」などといったバリバリの罵詈雑言を浴びせてきた。憤慨した僕は「ヤなヤツ。ヤなヤツ、ヤなヤツ、ヤなヤツ!」と連呼しながら校門前のコンクリートロードを歩いて帰った。
生徒指導部の定期的な呼び出しは続いたが、「呼び出されても行かなければいい」という画期的なアイデアを思い付いたおかげで、どうにかこうにか3年生になった。国語の先生が担任になった。長浦先生という。
長浦先生は、10年前の当時、すでにおじいちゃんだった。白髪でメガネで、いつも渋いスーツを着こなしていたが、夏場はまるまるとした体形を強調する白いポロシャツを着ていて、同クラスのギャルからは「ナガウ(愛称)かわいい~」とゆるキャラ扱いされていた。
長浦先生の授業は面白かった。授業の合間に文豪たちのくだらないエピソードを披露してくれたり、美しい日本語の話をしてくれた。ロックが好きだという話をしてくれた。文学を愛する人だった。
僕のクラスは進学クラスだったので、やはり3年生ともなると本格的に受験勉強が始まる。そんな中でも、文化祭の出し物、演劇に情熱を燃やす青春バカは何人かいて、そのうちの一人が僕だった。しかしそんな僕に負けず劣らず、やたらと暑苦しかったのが、長浦先生だった、僕は彼の熱量に助けられて(乗せられて)脚本も監督も出役もやった。
「文化祭に悔いを残したら、生涯取り戻せない」
ベテラン教師の言葉には、ずしりと来る重みがあった。いま振り返っても、あの数か月は本当に楽しかった。創作の喜びを知った、かけがえのない時間だった。結果は割愛するが、最高の文化祭になった。
文化祭が終わってから、今度こそ受験一色になった。僕はクソがつくほどツマラナイ毎日の息抜きとして、学級日誌に小話を書くことにした。「誰が読むわけでもないのだから好き勝手書こう」とあることないことを書き連ねていた。
ある日、長浦先生が「大村の学級日誌、面白いからコピーして、クラスメイトに配ってもいいか」と声をかけてくれた。死ぬほど恥ずかしかったので断ったが、ちょっと嬉しかった。断ったのに先生はコピーを配って(名前は隠してくれたが)、やはり死ぬほど恥ずかしく、やっぱりちょっと嬉しかった。
受験シーズン、僕が進路に悩んでいると、長浦先生は文学部を勧めてくれた。先生のことを信頼しきっていたので、お導きの通りの道を進むことにした。長浦先生は卒業式の日に、中島みゆきの「糸」を、ギターで弾き語ってくれた。感極まる僕の隣では、ギャルがガラケーで動画を撮っていた。
大学での毎日は、決して文学性の高い日々ではなかった。しかし、友人と酒を飲んだり飲まなかったり、講義をサボったりサボらなかったりした毎日は、非常に文学的だったと思う。高校の苦い思い出もいい思い出も、ほとんど忘れて楽しんでいた。
大学3年、就職活動。その頃には、男版さくらももこにも、最年少芥川賞作家にもなれないことは重々わかっていた。それでも文章を書く仕事をしたいと思って、いろいろ調べた結果、コピーライターに行きついた。しかしコピーライターは狭き門で、誰でもなれる仕事ではないという説明を受けた。
折衷案として「広告業界なら何でも良いか」と営業職も受けた。普通に内定が出た。そのときに、激しく後悔をした。本当に営業職でいいのだろうか。悩みに悩んで白髪が生えてきたことに気が付き、そのときに長浦先生のことを思い出した。先生に相談しよう、と思い立った。
卒業振りの先生は、さらにおじいちゃんになっていた。もとからおじいちゃんだったので何が変わったのかはわからないが、おじいちゃん感が強くなっていた。酒を奢ってくれた。
進路で悩んでいること、営業職が務まるか不安なこと、本当は文章を書く仕事がしたいこと、本当は小説家になりたかったのに、それを忘れてしまっていたこと。あらゆることを相談した。すると先生は、渋みのある声で答えてくれた。
「営業職、一回やってみたらいいよ。大村はいい文章を書くけど、もっといろんなことを知れば、もっと深い文章を書けるから、人生をかけて迷い続ければいい」
人生をかけて迷い続ければいい。今まさに進路を、人生を決めようとしていた僕にとって、それは面白い答えだった。
4月、僕は代理店の営業マンになった。紆余曲折あって、翌4月には無職になった。その数か月後にご縁があって、何のスキルも経験もない、肩書だけのコピーライターになった。それからも職場を転々として、今の会社にいる。肩書は、コピーライター/プランナー。
これでよかったのだろうか。今でも十日に一度くらい、ぼんやり不安になることがある。でも、これでいいのだ。人生をかけて迷い続けることが、これから僕が書くであろう文章やコピーを、一段も二段も深くしてくれる。そう思うと、今まで出会ったすべてのトピックに、ラブを贈りたくなる。それってかなり幸福な人生だと思っている。
「回り道してるねえ」「もったいないねえ」と、よく言われる。新卒から大手で働き続ける友人や、大手で磨いたスキルを生かして独立した友人を見ると、憧れと嫉妬で気が狂いそうになる。
とはいえ、うろちょろしながら歩き続ける方が自分の性に合っているのだから。その嫉妬や憧れも、引きずって生きていくしかない。そっちの方が「いい文章が書けるようになる」らしいので。
迷わず迷う。長浦先生は、いい生き方を教えてくれた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
