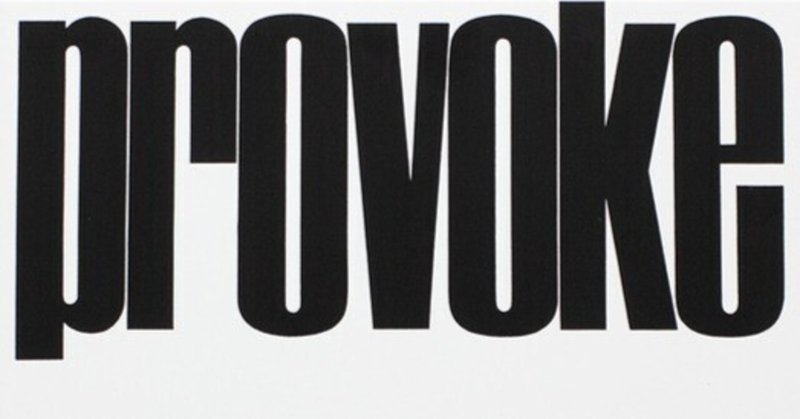
PROVOKEな写真とは
PROVOKEの時代
かつて、PROVOKEという同人誌が存在しました。
「アレ・ブレ・ボケ」で写真の時代を切り開き、海外で日本の写真を説明する際の資料として用いられ、今も影響を与えている同人誌と言われています。
その歴史背景についてはアサヒカメラをまとめたWeb記事「アサヒカメラの90年」にはこうあります。
社会派が活躍する一方、それと異質な表現が誌面に登場していた。メディア産業の発達にともない写真表現が高度にパターン化するなかで、そのイメージが現実を疎外することに反抗する写真家とその作品群である。
その嚆矢(こうし)は、68年10月号のリレー連載「日本の生態」に登場した、中平卓馬の「終電車」である。本作は東京から中平の自宅のある逗子までの終電車において、日常的に見る光景を撮影したものだが、画像はひどくブレていて粒子もきわめて粗い。(中略)それは終電車内の印象的な描写ではなく、人々が持っている終電車に対するビジュアルイメージの解体を狙うものだった。
「写真はピンボケであったり、ブレていたりしてはいけないという定説があるが、ぼくには信じがたい。第一、人間の目ですら物の像をとらえる時、個々の物、個々の像はブレたりピンボケだったりしているのだ。それをイマジネーションが統一し、堅固な像に固定している、ということではないか」
(中略)
中平の写真観に決定的な影響を与えたのは、東松の企画で、68年6月に開催された日本写真家協会主催の「写真100年 日本人による写真表現の歴史展」に編纂委員として加わった体験である。幕末の写真渡来から敗戦に至るまでの写真表現を振り返るなか、中平は撮影者さえ判然としない多量の写真記録の直截(ちょくせつ)さのなかに、本来的な写真力がみなぎっていることを見いだし、それがイメージを拒否する根拠となった。

当時の時代背景について説明しているWebサイトでは、以下のような記述となっています。
戦後写真界は土門拳のリアリズム(個人から見る社会への問題定義)、後の写真集団VIVOの造形や記録など、一種盲目的とも言える写真の世界への没入する事を半ば強いる作品が溢れていた。そんな60年代後半、VIVOの一人で写真家東松照明の弟子・森山大道は東松の紹介で写真史の編集をしていた中平卓馬と知り合い。中平はまた東松の紹介で写真展の委員会の仕事をする際知り合った建築系評論家・多木浩二と同人誌発行の企画を持ち上げる。
時に世界中で同時多発的に「コンテンポラリー(同時代)写真」という分野が成立した時期でもある。日本では「コンポラ写真」と呼ばれ、日常の風景を撮影した意味性が薄い写真をいう。しかし実体は感覚的という意味の、当時賛否両論の写真ジャンルの通称であり、プロヴォークはその筆頭とされるに至った。
また別のWebサイトでは、もっと詳しく書かれています。
長々と引用するのはアレなのでぜひサイトでご覧ください。
以上3つのサイトを見ると、写真表現における「主観」に対して認識が揺れている状況でPROVOKEが創刊されたものということがわかります。
そして、PROVOKEは新たなる表現「アレ・ブレ・ボケ」で、写真の表現を変えようとしました。
PROVOKEとは何だったのか
それでは、そのPROVOKEとはなんだったのでしょうか。
創刊には上の引用文献にも出てきた中平卓馬という写真家が深く関わっています。しかし、中平はもともと写真家だったわけではなく、左翼系思想雑誌の編集者で、「詩人になるか写真家になるか迷った」人でした。編集者として活動する中で、写真家の東松照明と出会い、結婚祝いでアサヒペンタックス一式をもらってから、写真にどっぷり浸かるようになっていきます。
PROVOKE創刊以前に中平はJPSの仕事で日本人による写真表現の100年を題材にした展覧会に関わりました。その中で、中平の写真家として、そして評論家としての方向性を深く決定づけた写真家がいます。
田本研造や山端庸介といった「いわゆる芸術家ではない」写真家です。
田本は進行中の北海道開拓を記録した写真家であり、山端は原爆投下直後の長崎を「対敵宣伝」のために撮影した写真家です。中平にとって田本と山端の写真は作家性のある芸術写真ではない「記録」写真のモデルとなっていきます。
また、この展覧会に関わったことで、中平は評論家の多木浩二と出会い、親しく付き合うようになります。
そして中平は1968年に多木と連帯してPROVOKEを創刊します。創刊号には、中平が『現代の眼』の編集者時代に知り合った写真家の高梨豊、詩人で評論家の岡田隆彦が同人として参加。そしてクレジットはありませんが柳本尚規も制作スタッフとして協力していました(『現代の眼』の編集者時代の同僚の弟だった)。
第二号では、中平が『現代の眼』の編集者時代に知り合った森山大道も同人として参加。最終号の第三号では詩人の吉増剛造も寄稿しました。予想よりも早い終結を総括すべく、彼らは写真と文章による『まずたしからしさの世界をすてろ』を刊行し、活動を総括しました。その刊行と同じ年に中平は『来たるべき言葉のために』を刊行します。
PROVOKEは大部分が写真を占める雑誌でしたが、同時代に写真家として知られていたのは高梨・森山だけであり、中平は写真を始めたばかり、多木は「いわゆる」写真家ではありませんでした。
それではPROVOKEとは何か。「挑発する」を意味するこの雑誌は、その副題に従えば、「思想のための挑発的資料」です。第一号の冒頭には、中平と多木が起章した宣言文が残されています。全文は以下の通り。
映像はそれ自体としては思想ではない。観念のような全体性をもちえず、言葉のように可換的な記号でもない。しかし、その非可逆的な反応ーーカメラによって切り取られた現実ーーは言葉にとっては裏側の世界にあり、それ故に時に言葉や観念の世界を触発する。その時、言葉は、固定され観念となったみずからをのり越え、新しい言葉、つまりは新しい思想に変身する。
言葉がその物質的基盤、要するにリアリティを失い、宙に舞う他ならぬ今、僕たち写真家にできることは、既にある言葉ではとうてい捉えることのできない現実の断片を、自からの眼で捕獲してゆくこと、そして言葉に対して、思想に対していくつかの資料を積極的に提出してゆくことでなければならない。PROVOKEが、そしてわれわれが<思想のための挑発的資料>というサブ・タイトルを多少の恥かしさを忍んで付けたのはこのような意味からである。
何が言いたいのかというと、
写真は被写体のコピーなので、世界(現実)により内容は規定され、その記録として存在しているので、現実に縛られており、「思想」ではない。
写真は世界の一部分しか切り取れないので、観念がもつ「全体性」とは異なる。
写真は被写体を撮るので被写体と関係するイメージになるため、言語のように恣意的な記号とは異なる。例えば「りんご」という言語から想起されるイメージは様々だが、りんごの写真は「被写体としてのりんご」の写真でしかない。
つまり、写真は思想でも観念でも言葉でもない。しかし現実と物質に基盤をおく写真により、来たるべき思想と言葉を呼び寄せることはできないだろうか、という可能性を意味する宣言になっています。写真を思想や言葉と接触させて、その接合面から新たなるものを生み出すこと、PROVOKEはその資料集となることを目指していました。そのために、従来のやり方で撮った写真を自己批判して、自己批評的な再検証を行い、来たるべき写真とならなければならない、という実験の必要性がこの宣言なのです。
それ(引用者注:PROVOKEのこと)が目指すものはすでにある言葉から帰納的に映像を引き出すのではけっしてなく現実的な映像を言葉にぶっつけて、それを蘇生させる、そのような挑発を映像に求めようとしている。
それでは、その来たるべき写真とは何か? PROVOKEに掲載されている写真は「アレ・ブレ・ボケ」と形容される写真になっています。通常のプロが撮る写真が”被写体を思うがままに写真化するもの”であれば、PROVOKEに掲載されている写真は失敗作とも言えるものでした。写真という技術が被写体の複製を光学的に製造する技術であるとすれば、それらの写真は写真の使命に抵抗しているかのようです。しかし、その抵抗は、写真の写真性そのものを露わにしています。
写真は通常単なる被写体の技術的複製と考えられているため、被写体を意識することはあっても、写真の物質性(光が感光性物質へ残した傷跡)そのものを意識することはあまりありません。ですが、アレ・ブレ・ボケ写真は、写真が写真であることを提示します。手ブレ・被写体ブレ・露光過多・露光不足・高温現像液による長時間現像といった手法により生み出されるアレ・ブレ・ボケ写真、「写真は実在のイメージそのものではなく、技術的複製である」という写真の写真性を露呈させて、われわれにあらためて写真の存在を意識させる批評性を備えていました。
PROVOKEの写真家達は、ブレボケを方法論として採用していましたが、彼らにもモデルとした写真家がいました。中平たちは、ウィリアム・クラインの写真集『ニューヨーク』が与えた衝撃についてしばしば語っています。中平は、クラインの『ニューヨーク』から、自分自身の問いを独自に抽出して、それに応答する探究を、写真と言葉によって並列的に実行していくことになります。
中平がPROVOKE当時に執筆していた文章では、写真家の作家性・表現性を批判し、写真家の消滅と写真の無名化を要請しながら、表現的ではない記録写真を肯定していました。
アベドンの写真と医師が撮影したと言われるこのケロイドの写真はむろんその目的も意図も異なった別箇のものである。普通の意味でそこに一切の共通点はないと言えるかもしれない。だがこの二枚の写真を見、体験する世界はどこか一点、それを見、体験するぼくの心の深奥において、どこか一点つながり、重なり合ってくようにぼくには思えるのだ。またまさしくそのこととの対応において、この二枚の写真は写真とは何か、写真家とは何かを根源的に問いかけてくるように思える。それはこの二枚の別種の写真がいわゆる<表現>をねらったものではないということ、また世界とそれを目撃した人の驚きによって、その衝撃の強さによってこれらの写真が支えられているということである。他の点ではすべて異なるこの二枚の写真がただ一つ共通してもったものは、この写真を撮った人がけっして世界をわかりやすく解説してやろうとか、すでにある観念や思想や価値を外界にある事物を借りて、あるいはそれに仮託して展開しようとした結果ではないという事である。
それは写真という一つの虚構をかりて、直接見る者を、露出した世界そのものへ、(写真であることを忘れさせて)結びつけている。この時、あるいは写真家の、そしてその写真を撮った者の意識などは消し飛んでしまうかもしれない。むろんそれでかまわないのだ。
このような写真を積み重ねて生まれるものを中平は「沈黙」と呼び、PROVOKEに関しても次のように書いています。
ぼくは、五人の仲間で小さな写真の同人雑誌を発行している。ぼくたちはそこで、いま世界を支配する言葉を越え、言葉を支える「沈黙」にじっと目をそそいでゆきたいと考えている。ぼくたちがめざしているものは、一枚一枚の写真に完結性を求めないこと、また一枚の写真に世界の全貌を予感させるというような、写真にとってはあまりにも荷重な役割を求めないこと、そして「沈黙」へ向かって断片的な映像をいくつもいくつも積重ねてゆくことである。そのとき写真は、映像は「作品」であることをやめ、来るべき「言葉」のために用意された匿名の資料になることができるのではないか。
表現的ではない記録写真の例として、中平は冒頭の田本研造や山端庸介をあげます。もちろん両者とも完全な匿名性・記録性で写真を撮っていたわけではありませんが、両者の写真は、北海道開拓・対敵宣伝といった視線の力学による意図をこえて撮れてしまった記録であると中平は言います。そしてさらに自分達の使命として、この記録性を意識化して、方法論化することを要請します。では、中平の記録論とはどういうものなのでしょうか。
そもそもアレ・ブレ・ボケ写真は明確に写真家の存在を意識させるものです。それと、上の写真家の消滅は矛盾するように聞こえます。しかし、中平にとってそれは両立できないものではなく、それらを連動した問題として理論的に構築していきます。つまり彼は、記録性を要請するが、その記録は単なる客観的な記録ではないのです。彼にとっての記録とは記録者の目を排除するものではないからです。もっと言えば、彼にとっての記録は、外部の記録であると同時に、撮影者の生の記録なのです。では撮影者は消滅してないじゃないかと言われそうですが、大丈夫なのです。なぜなら、この生の記録と同時に撮影者は消滅するからです。
意味がわからないと思うので以下にまとめます。
アレ・ブレ・ボケ写真は被写体の記録という意味では欠陥があるが、シャッターを押す寸前に動いてしまった手、特殊な現像、求心的な構図に収められない被写体…といった撮影者の意図が働いた「撮影者の生の記録」である
だが、それらは撮影者の生の記録であると同時に、撮影を完全にカメラ任せにし、主体性を失い、無名化していくという「撮影者の消滅」でもある
撮影者はアレ・ブレ・ボケがあることで記録され、同時に消滅する
つまり、アレ・ブレ・ボケ写真は、写真家を記録し、同時に消滅させることができる写真なのです。
中平の写真はPROVOKE第二号以降アレ・ブレ・ボケの強度を増していきますが、基本的に風景を撮影しています(そして基本的にはどこかにピントを合わせた写真を撮影しています。おそらく松江泰治の「絶対ピント」のような手法にしていた作品が多いのではないかと個人的には考えています。ちなみに、中平の写真集『Documentary』には、はっきりとピントが合った写真しか掲載されていません。もともと中平はピントに厳密な作家だったのです)。この理由としては、当時松田政男らが主張していた「風景論」が影響していました。「風景論」とは、次のような主張です。
中央にも地方にも、都市にも辺境にも、そして<東京>にも<故郷>にも、いまや等質化された風景のみがある。
(中略)
私たちは、こうしてオホーツクの沿岸にも東北の平野にも、永山則夫を育んだであろうところの<故郷>を発見することはできなかったのだ。私たちは、まさに小さな<東京>を見たにすぎぬ。永山則夫が小学校時代に住んでいた板柳町の一隅にある入福住宅と呼ばれる小スラムでさえ、私たちは東京の任意の場所に措定しうるのだ。
(中略)
<東京>対<故郷>という図式は、六〇年代のどんづまりにおいては、ついに通用不可能となってしまったことを私たちは確認しなければならない。わが独占の高度成長は、日本列島をひとつの巨大都市として、ますます均質化せしめる方向を、日々、露わにしているのではないか。
(中略)
永山則夫の軌跡に沿うて四ヵ月にわたる列島縦断の旅を再現した私たちの眼には、すべての地方もしくは辺境の街並みは、すでに繰返し述べたように、均質化された風景としてのみ映じたのであった。
失われてしまった始原的なる<故郷>を求める旅は、かくて、何処まで行っても相似した風景の発見として常に終わりを告げることとなる。(中略)わが日本列島にあっては、おそらく、「見知らぬ街」と「生まれた街」との間に生じてしまう、どうしようもない時間と空間のひずみは、風景の均質化としてのみ眼前せしめられるにちがいないのだ。これを、風景ではなく、自然とか、風土とかいうコトバで置き換えることはできない。天然的なるものと人工的なるものとの思いがけぬばかりのスピードによるぶつかりあいが、或る一定の風景を切り取ってしまうからだ。果てしなくつづく<始原への旅>のなかで、だから、永山則夫は、この「風景を切り裂くために、弾丸を発射したに違いない」と、かつて私が『薔薇と無名者』(芳賀書店刊)において断言したのも、この理由に基づいているのである。
(中略)
私たちは、高度独占集中の真只中で、日本列島全体がさらに巨大な都市に変貌しようとしている転換期に生きている。私たちには、そこに帰るべき<山>を、もはや所有していない。しかし、にもかかわらず、私たちが私たちの都市を占拠し、解体し、私たちの共同の空間として革命してしまう長い戦いにおいて、ひとりのゲリラ戦士として生きようと欲するならば、私たちにとっての<山>を、この「住み心地のよい煉獄」のど真中に聳立せしめねばならないのである。第三世界に対する収奪と殺戮の原罪を負うてしまっている反革命の<祖国>日本に住む私たちは、私たちが生きていることを余儀なくされているこの場所を、魂の浄化装置として、語の真の意味における煉獄たらしめねばならぬのだ。
(中略)
私たちは、おそらく、初めて、わが下層プロレタリアートが階級として形成されつつある転形期に際会している。彼らは、流浪という存在態において都市を占拠しつつ、資本主義の墓掘人として、いま、ゆったりと浮上を開始した。<不可視の故郷>は真制の祭りへの試行のうちに徐々にせりあがりつつある。「必要なものはうっかり出来てしまった偶然的な隙間なのである。”隙間”がありさえすれば、人間は何かを始めるに違いない。人間の欲望と欲望がぶつかりあって、混沌たるカオスの中で、人間は生きる」と水木薫が喝破した条件は、不可避的に到来せざるをえない。
必要なのは、下層大衆に「劇的想像力の復権」とやらをお説教することではない。私たち自身が、自らを真理として実現する戦いの渦中へと、風景を超えて旅立つことである。
要するに、日本各地が東京と大差のないステレオタイプな都市になっていて、地方と中央の二項対立自体が失効して、全てが中央の複製となっており、風景の背後に死滅せざる国家が控えている、つまり風景そのものに権力の偏在を見出していたのです。インフラ整備が進み、同じような建物、同じような都市構造が都市から全国へと波及していくなかで、権力を体現する風景が、強固な境界を明瞭に見えるものとして画定するならば、中平の写真はその風景を不鮮明化し、不定形化していく。そうして中平は、写真行為によって能動的に風景を引き裂き、生成変化へと導きました。「たしからしさの世界」(=風景)が写真により引き裂かれる時、我々が目を閉ざしていたリアルな現実が垣間見えるのではないか。こういった考えは、中平が左翼系思想雑誌の編集者をしていたことと無関係ではないと思います。
中平は、PROVOKE終刊後の文章で、自分達の写真的手法が既にファッション化、デコレーション化してしまったことについて自戒しています。中平が典型的な例として挙げるのが、国鉄のDISCOVER JAPANの広告です。以下のページの下部に、ブレ・ボケたポスター広告が見られます。
実はこの広告はPROVOKEとは全く関係なく、1964年の東京オリンピックの時に日本IBMの広告で用いられた手ブレしてピンボケした写真のアイデアをもとに作成されたものです。そして、カラーで発表された写真は、白黒で発表されたPROVOKEの写真とは、実は全く似ていません。しかし、中平にとって、大量に撒かれる手ブレしたボケ写真は、自分達の方法がもはや形骸化している証左でした。中平は苛立ち、次のように書きます。
ある友人が冗談まじりに《PROVOKE》もたいしたもんだね、国鉄までブレてるよ、と言ったことがある。冗談ではない、それはむしろ逆の証左なのだ。彼らはあらゆるものを骨抜きにし、しかもその形だけ残すのだ。
しかしながら、中平の思想をよそにアレ・ブレ・ボケという表現は一人歩きしていき、PROVOKEは、その目的よりも手段(アレ・ブレ・ボケ)の印象が強く残るものとなったのです。
まとめ:PROVOKEな写真とは
PROVOKEで中平は、アレ・ブレ・ボケにより写真家として消滅しながら写真家の生を記録しました。
そしてその記録は権力が虚像であるという、写真に写らない風景を見せようとするものでした。
つまり中平にとってアレ・ブレ・ボケは、写真に写らない新たな客観を、写真家の主体を排した上で写真家の生まで記録して写真にするという、全く新しい方法でした。
PROVOKEで撮影された写真をまとめると以下のようになります。
被写体と共に写真家も写真に記録されていなければいけないが、写真家は同時に消滅しなければいけない
現実の別の側面を(写真家自身がなんらかの意図を持って)映し出すものであり、現実を覆い隠してはいけない
アレ・ブレ・ボケやノーファインダーで撮るのは以上2つの実現により言葉や思想を生み出すための手段であって目的ではない
何かの参考になれば幸いです。
参考文献
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
