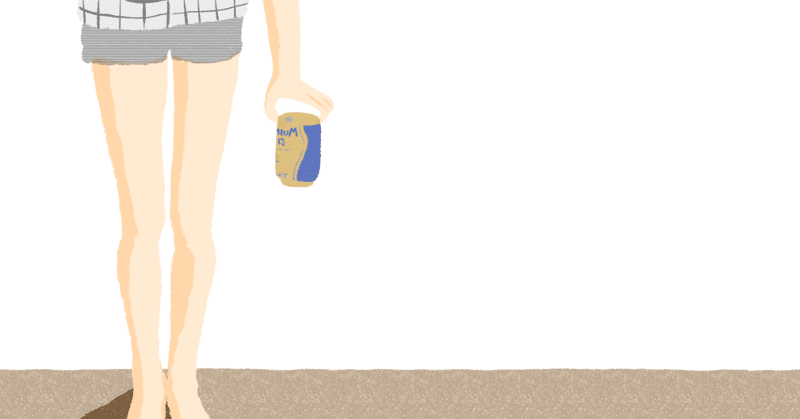
創作小説『ビッチのハイライトLINE-B面-』
「あー、またやっちゃった。」と、全裸でさやかは昨夜の記憶をたどる。隣には同じく全裸のややぽっちゃりな男が大イビキをかいている。
「こっちは、たしか先輩の方だよね。」二日酔いの頭は起動するにも時間がかかる。アプリで知り合った男が職場の先輩と飲んでいるから3人で飲もうと誘ってきた。1軒目がタパスが楽しめる店で、ハッピーアワーで安くなっていたハイボールをみんなで飲んだ。2軒目は、和食テイストの店で刺身をつつきながら日本酒に手をつけた。それがいけなかった。
「仕事は公務員って言ってたし、しかも3人飲みなら大丈夫かなと思ったんだけどな。」と、自分のツメの甘さを呪う。
「昨日はどんなだったっけ?」と、ぼんやり昨夜のベッドでの試合内容がよみがえる。いつものように、スピーディーなK.O.をお見舞いしたようだった。「いつもはこんなに早くないんだけど、久しぶりだからかな。」とか使用済みのコンドームを処理しながらごにょごにょと男たちは言い淀む。
「出来ることなら、男になって自分とヤリたい。」それが、さやかの絶対に叶わぬ(しかも理解されることのない)願いだった。毎回さっさと昇天していく男たちの満足気な顔を見るたびに、さやかの心はシラけていく。「ブルータス、お前もか。」
新卒で入った会社を6年で辞めた。辞めてから心底自分が『組織』に向いていなかったことがわかった。業務後に自腹で行く決起会という名の勢いだけの飲み会も、時間をずらさないと一人でランチに行けないことも、ヘアスタイルを好きに出来ないことも(一度金髪メッシュで行ったら翌日直してくるよう怒られた。)、全部全部嫌だったと辞めてからわかった。
もうどこに行っても同じだろうと会社に守ってもらう人生は諦めて、一人で生きていく人生を模索し始めた。「ペンギンが飛ぼうとしても無理なのよ。って自分のことをペンギンて、可愛すぎるか。」飛べないことがわかったペンギンは、数年のアルバイトのかけもちなどを経て、なんとかフリーのライターで食べていけるまでになった。
主に、さやかの仕事は飲食にまつわるメディアでの取材記事がメインだ。編集側に回ることも最近は多くなってきた。収入の波は多少はあるものの、会社の看板を背負う苦しさもなく、飲むことも食べることも好きなさやかにとっては、悪くない仕事だった。
OLのときは、周りも会社員ばっかりだったが、フリーランスになると周りもフリーランスの人間が増えた。まりに初めて会ったのもそんなフリーランス界隈の飲み会でだった。
飲み会の主催の森田とは仕事に関わるイベントで知り合って、一度寝た。2軒目の店を出たあと、どうするかと聞いたら、「ウチにおいでよ。」と誘われた。本人曰く先月めでたく(?)離婚が成立したそうで、いずれ売りに出すつもりの広い部屋を持て余しているようだった。
「このベッドで奥さんともヤってたんだろうな。」とダブルベッドの上で森田から滴る汗を眺めながら、やるせない気持ちで昇天する様子を見守った。
久しぶりに連絡をもらって「今夜も、誘われたらめんどくさいな。」と思って参加した飲み会で、出会ったのがまりだった。カメラマンをしてるらしい。肩くらいまでの伸ばしっぱなしの明るくベージュに染めた髪、化粧っ気のない顔に、動きやすそうなモノトーンのパンツスタイルに足元は白のスタンスミス。やたらピアスの穴が多く、細々したピアスは全部シルバーだった。
ちょっと近寄りがたいオーラを出す女。それがまりの第一印象だった。周りと楽しそうに談笑はしているし、ふわっとおっとり柔らかい印象なのに、絶対踏み込ませない一線を死守している。その静かな戦いっぷりが気になった。
派手な顔に、凹凸の強めについた身体。さやかはすごく恵まれたルックスやスタイルというわけではなかったが、より自分を魅せるための術は身につけてきた。メイクやファッション、コミュニケーションの取り方など自分なりの正解がわかってきた。
そうすると、自然と相手が好む言動がわかるようになった。もともと空気は読める方だし、言葉でもボディランゲージでも相手を気持ちよくさせるのは難しいことじゃなかった。そうやって懐に飛び込んでいく戦法とはまた違うまりのやり方が新鮮だった。
解散時のLINE交換タイムに乗じて、しれっとまりの連絡先を聞き出した。男とはちがい、セックスを介さない分、女と仲良くなる方が難しいとさやかは常々感じている。どうやってまりとの距離を縮めようかと思案していたが、彼女の事務所兼スタジオが、田園都市線沿いの駅であることがわかって、そのエリアに取材で行くことが多いさやかにとっての朗報となった。
飲み会の時に、まりがビール党であることをちゃんと見抜いていたさやかは、まりの仕事が終わる頃を狙ってビール数本と軽いつまみを持ってスタジオに押しかけた。
最初こそ嫌な顔をされたが、お互いフリーランス同士で気軽な30代独身同士ということも相まって、突撃を重ねるごとに打ち解けていった。話してみるとまりは、さやかからすれば、なんでそんなこと悩むのかと思うほど小さなことでいつまでのぐずぐず悩むタイプだった。そこに曖昧な慰めを踏み入れさせないための一線が最初に感じたそれだっだ。
さやかがいつもの戦法で、グズグズするまりの話をバッサリ一刀両断して笑い話として消化するのが、だんだんと二人のテンプレになっていった。
また新ネタがあれば、酒のつまみにさやかは面白可笑しく男たちとの情事をまりに話した。「本当にいつものごとく天晴ね、さやかちゃんは。」とまりは感心した様子で話を聞いてくれる。
こんなにたくさんの男と寝てしまう自分について、さやかだってすんなり手放しで受け入れてるわけではない。でも、一杯目のビールや、網の上で焼かれた肉のように、目の前で魅力的に映るそれを試さずにはいられない性分なのだ。ただ性欲にも等しく正直なだけなのに、経験人数が増加するにつれ、理解者は反比例して減っていった。
周りのように一人と添い遂げるイメージを全く描けない。それでいてデートの相手には困らない。30代になっても新規案件は全く減らない。自らの恋愛のカテゴライズのしにくさに、さやか自身がもどかしく思うこともあった。
だから、どんなゲスな夜の情事を話題にしても、ケラケラと笑い飛ばしてくれるまりは救いだったのだ。
目覚める気配のないぽっちゃりしたお腹を横目に、シャワーを浴びて着替えを済ませる。「ねぇ、わたし仕事があるから、先に行くね。」と、出る準備を完全に整えて男に声を掛ける。「え、あそっか。・・・うん、またね。」とまだ状況に頭が追いついてない状態で男が返事をする。
「また、はないかなぁ。」と、始発電車の中であくびをしながらスマホを見る。先に飲みに誘ってきた男からLINEが数件入っていた。2軒目で酔ってさやかがキス魔に変身して、店内でベタベタしすぎて店員に怒られた事実が判明した。「よくやるよねー。」と、他人事みたいにつぶやいてみる。
家について少し眠る。「自分のベッドで一人で寝るのが一番よく眠れるんだよな、結局。」ひとりごちる。今日は取材がないから在宅で問題ない。朝9時過ぎに起きたとき、心がモヤっとした。
「昨日のは、やっぱやらなくてもいいヤツだったなぁ。お酒飲みすぎると『美味しそう』のハードル一気に下がるんだよね。」自己嫌悪だった。覆水盆に返らず。脳みそがマイナス思考でいっぱいになる前にスマホに手を伸ばす。
中野の役所に勤める二人の男性と、アプリで繋がって飲んでいたのですが、相手は2人だし、大丈夫だろうと思っていたら、二軒目から記憶をなくし、ホテルで全裸で目覚めたわたしです。
相手はそのうちの先輩の方で、二軒目からキス魔になったわたしは、そういうお店じゃないんでと、お店の人に怒られていたらしい。
しかも、左足の親指、ぶつけたみたいで爪が少し青くなってる。いたい。
そんなわたしのハイライトよりも、今日もお仕事おきばりやす✨
こんなときはお得意のビッチのハイライトLINE。わたしだけの懺悔室。でも、暗く重くしたら飲み込まれる。痛いのは親指だけじゃない。せめて、まりちゃんに笑ってもらいたい。
さやかちゃんが、今日もさやかちゃんらしくいてくれることが、わたしの幸せだよ。
しばらくして、まりちゃんからの返信が来る。いつも通りお咎めも非難もない。ただ受け入れてくれる場所。電波の先の笑顔に今日も救われる。
今日も、わたしを受け入れてくれてありがとね。
いつも温かいご支援をありがとうございます💕サポートしたいと思われるような文章をこれからも綴っていきます✨
