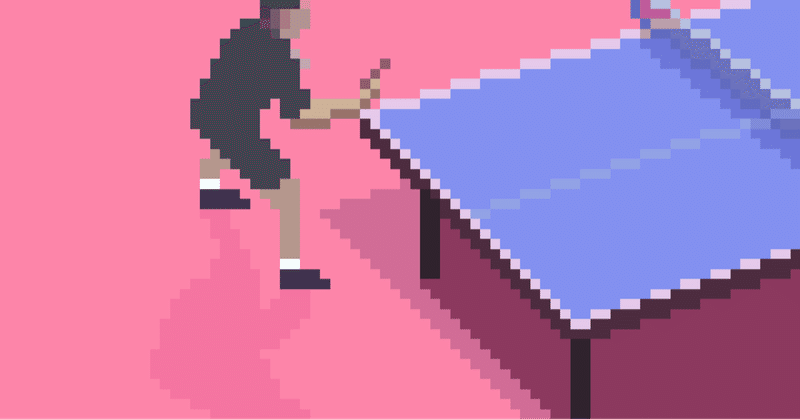
いつか、言葉をピンポン玉みたいに思えたら
父から荷物を送ったよ、とメールが来た。
メールを開く前に予想はついた。先日母と電話した際に聞いた、干し柿だろう。
『孫(私の長男)を喜ばせたくて、たくさん作ってる。もうすぐ送れるよ』
と言ってたし。
ここで、長い補足。
長男は食(特におやつ)の好みが狭いというか何なのか、『これ好きかな、喜ぶかな』と用意したものは大概ハズれ、『これは食べんやろ』というものに限って食いついてくる傾向がある。
そんな彼が、定番と言ってもいいくらい、好きなもの。
ドライフルーツと、ナッツ。
美意識が高いというより、素で、エリカ・アンギャルさん(ミスユニバースの栄養コンサルタント)が大絶賛してくれそうな好みをしておる…!
そう、最初はね…
私がエリカさんのご著書に感銘を受けて、ドライフルーツとナッツを各種取り寄せたことがあったのだ。
そしたら、まぁ子どもは食べたがるじゃないですか。物珍しいし。
でも長男にはどうだろう、生ケーキすら食べないっつって毎年誕生日の用意に苦労してるしなって見てたら、『オレ、これ好き!』とハマって。
参考までに、取り寄せたサイトはこちら。
ナッツとドライフルーツへの愛をひしひしと感じるお店。
ちなみに、長男が一番気に入ったのはマジョールデーツ。
初っ端から王様ランクが好みって、長男よ。
で、両親の干し柿も、ドライ(干して乾燥させた)フルーツ(果物)の一つだよね、と味見させたら『うまいうまい』と喜んで食べて。
そんなエピソードを聞いた両親も喜び、他にも色々と、地元で購入できるドライフルーツを送ってくれたことがあったのだが、それらにはご丁寧に砂糖の衣がついていて。
私が果物王国(だと私は思っている)の長野だからといって、果物そのものを活かしたドライフルーツが手に入るわけではないんだな、ということを学んでいる傍らで、長男は『オレ砂糖ついてないやつの方がいい』と結論を出していた。
この人、ものすごくシンプル。
そして、冒頭の『干し柿送るよ』につながるわけである。
実際、本当にたくさん送られてきた。
ザッと数えた限りでも、120個以上(!)
長男は大喜びして、毎日大事に食べている。
(大事に=ひと口で食べずに、ちみちみと少しずつ味わうスタイル)
.
祖父母と孫の、微笑ましいエピソードだと思われただろうか。
しかし、私は手放しで喜べない。
母が何かを送ってくれるときは、総じて『腹を満たせるように、美味しい物を』とチョイスするのに対して、父が独自で送ってくるものは、独自すぎるからだ。
↑
これには捨てるにはしのびない、あやこの周りで活かせる先を見つけてくれ、という明確な意図があったが
↓
鬼クルミは、散歩の途中にたくさん落ちているのを拾って、殻があまりに硬くて割れないのが興味深くて子どもたちにも送ってくるという…何度も。
↓
ウクライナの民話を元にしているという、子守唄の絵本(コピー)を送られてきた時には、私がもう、『意味わかんない!』となって、コロナの病み上がりに超超長文メールを送り合うことになった。
で、冒頭の父からのメール。
正確には、『干し柿と鬼クルミを送った』だった。
どうして鬼クルミ。
なんでそんなに鬼クルミを推すんだろう。
いや本当に。
研究者の父には、鬼クルミは興味深くて面白いだろう。
だけど私には、興味も持てないし、硬すぎて割れもしない、受け取って困るもの。
前にも要らないよ、とメールしてたのに。
ブワッとじんましんが出た。
あぁそうだ、メールの後、また送られてきてたな。
落ち着け、父には『心底要らない、受け取りたくない』が伝わっていないんだ。
私は父の携帯に、直に電話をかけた。
携帯はこちらの都合もお構いなしにすぐつかまる感じが好きじゃないとか、言ってた気もするがこれは今、直電で伝えた方がいいと思ったから。
お父さん。
私もう、鬼クルミは受け取らない。
それ以外の言葉が見つからなくて、言いながら胸がチクッとなったのだが、これは何の痛みだっただろう。
ただ、シンプルでストレートな言い方が、父には合っていたようで、アッサリ『分かった。もう送らない』という言葉が返ってきた。
これだけのやり取りだったけど、父に自分の意思を伝えて、受け取らせた、というのが、私にはとても大きな出来事だった。
.
ところで、最近読んだ本が。
入口は『韓国ドラマって本当面白くて大好きだなぁ、これを文化人類学的な視点で掘り下げてる本は無いのかな?』で探したはずだったのに、はからずもこのところずっと対面している『他者とのコミュニケーション』について考えさせられる内容だった。
鳥飼玖美子「異文化コミュニケーション学」(岩波新書 新赤版,1887)
異文化理解について。
学術論文のような(私にはカタい)論調で考察を述べる+海外(主に韓国)ドラマ・映画の内容を引用しながら考察を深める、の繰り返しで読みやすく、言わんとしていることを受け取りやすかった。
しょっぱなから、異文化感受性の発達モデル6タイプを説明するのに『愛の不時着』に登場する各キャラクターを用いていて、これが面白かったし、分かりやすかったのだ。
私が読みながら唸った箇所を拾ってみる。
異文化理解とはいっても、一つ一つ学ぶことは不可能だ。
必要なのは異なる文化と出会った時、どう対応するか(原理)、摩擦をどうやって回避する/修復するか(方法論)。
つまり、異文化理解とは異質性への対応であり、他者理解である。
その異文化理解において重要な概念、それは感情移入としての『共感』。
ただ感情移入(empathy)するだけでは、二人(以上)が出会った意味がない。
他者として出会うのでなければ、両者のあいだに新たな意味が生まれうる貴重な機会がみすみす失われるばかりか、当人の自己喪失にもつながりかねない。
他者として出会うのでなければ。
あぁ、私は前提を大きく間違えていた。
異質だからといって分かり合えない、同質だから摩擦もなく受け入れられるわけではなくて、『どのような場であっても周囲に合わせる努力はしつつ、自分らしく行動する姿』が必要だったんだ…
自分らしく行動するって、何ですかね。
悲しいかな、どうも相手に合わせに行ってしまうのがデフォとなっている私は、異文化適応能力が『統合レベル(どのような場であっても周囲に合わせる努力はしつつ、自分らしく行動する)』の夫に訊ねてみた。
アレッとか、自分の中に違和感が出てきた時点で、伝えることでしょ。
統合レベルの答えは、大変にシンプルであった。
私、2年前(2021年の始まり)にこんな記事を書いてるのに…
未だに、違和感がフレッシュなうちに伝えることが出来てない。それで、失敗ばかりしている。
そりゃ、父も鬼クルミを何度も送ってくるはずである。
.
ここで、会話というか、人と人との間を介する言葉というものに対する、私の身体感覚について補足しておく。
言葉。
私にはずっと、自分に向けて投げかけられるボールのようなイメージだった。
だから、その言葉というのは自分の元で一度受け止めるもの。
だから、何かと深く刺さりやすくて、また、抜けない。
私を刺すつもりなんて無く発する側(特に親)の、戸惑いや苛立ちはあると思う。常に。
肌感覚だけど。
相手の言葉に、痛い思いをしたら。
私は他人も、言葉に対して自分と同じ身体感覚を持っていると思っているから、言い返す前に(自分の言葉ももしかしたら相手に突き刺さり、痛い思いをさせるかもしれない)と考え、ためらう。
人との会話経験が増えるにつれ、(実際、私の言葉で傷つけたこともあった。私も傷つける側になることがあるんだし、偉そうなこと言えないな)と、ますます言いよどむようになった。
そして、もうこれ以上刺さらないように、何とかして回避するのに全力を尽くすのが私のデフォルトとなった。
この『回避』や踏み込まない感じ、実家の家族みんなが持ってる。
『回避』について、まるで私のことみたい、と思った詩を引用する。
ちびへび 工藤 直子
暖ったかいのだもの
散歩は したいよ
ちびへびは
おうちに鍵をかけて
ぷらぷらでかけた
こんちわというと
小鳥はピャッと飛びあがり
いたちはナンデェとすごんだ
あら おびに短したすきに長しねと
仲間は忍び笑いをした
ちびへびは急いで家にもどり
おうちの中から鍵をかけ
燃え残りの蚊取り線香のように
まるくなって、ねむった
でも……
暖ったかいのだもの
散歩は したいよ
ちびへびは
もういちど でかけた
誰もいないところまで
──こんちわ いわずに
──ぷらぷら しないで
「家にもどり おうちの中から鍵をかけ」
「でかけた 誰もいないところまで」
お分かりだろうか。
ちびへび、何も言い返したり、自分の思いを伝えていないのである。
そうして、他者との接触が無いところに出かけて行く。
ちびへびは、私だ。
本当、言葉を発すること、あるいは相手からやってきた言葉に対して、他のひとはどう捉えているんだろう…
とりあえず分かったことは、『私は、痛みの扱い方を知らなかった』のだなと。
さて、これからどうしよう。
.
今、意識してがんばっていること。
誰かと出会う際に、お互いが他者なのだという意識を持つこと(共通点が見つかれば嬉しいが、だからといって異質性を『無いものとして』扱わない)
そして、誰かと会話するときには、お互いの間に大きなテーブルをイメージすること。
言葉は、そのテーブルに置かれるだけ。
そう捉えることができたら、私はそのテーブルを眺め、『何について話しているのか』に注力すればよい。
ピンポン(卓球)みたいに思えば、気楽に打ち返せるかも。
ちびへびだって、的外れに自身を決めつけるようなことを言われても、それをテーブルに置かれたものとして見られたら。
ふーん、とその言葉を見やって、ただ手を出さなければ。
言葉は机の外に、バウンドしていくだろう。
いつか、言葉をピンポンみたいに思えたら。
ありがとうございます!自分も楽しく、見る人も楽しませる、よい絵を描く糧にさせていただきます!
