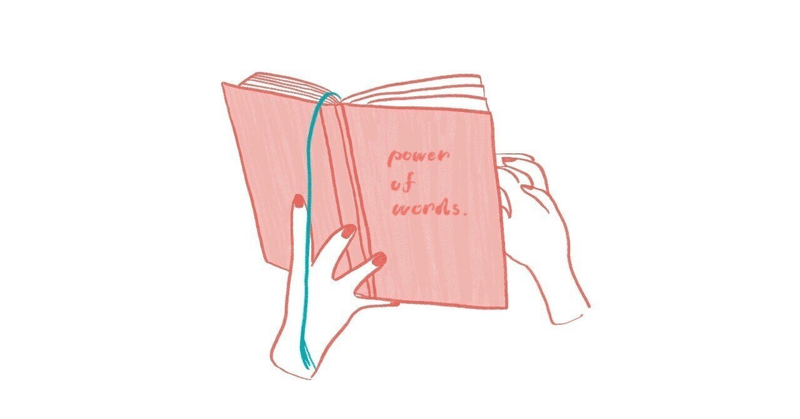
中野美代子「仙界とポルノグラフィー」を読んで/本の話
中野美代子「仙界とポルノグラフィー」を読んだ。

読んだといっても、つまみ読み。ところどころ、気になるところと考察の結果を。つまみ読みで十分面白い、というか素人はつまみ読みしかできない。これを精読するには中国への膨大な知識と深い造詣、そして熱い熱い情熱がいる。精読についていける人、果たしてどれくらいいるのだろうか。私には手も足も出ない。
でもそれが面白いというか、中野先生の研究者としての情熱にぶん殴れるのが気持ちいいというか。研究者ってすごいな、と途方もない尊敬の念を覚える。本にはいろいろな楽しみ方があるわけで。
中野先生の本は「中国の妖怪」に次いで2冊目。「中国の妖怪」は面白く読んだ。そしてこの時につまみ読みしかできないことも心得た。
「中国の妖怪」でもこの「仙界とポルノグラフィー」でも、中野先生が仮説を立てつつ色々な資料から考察をしてるんだけど、それに全くついていけない。資料名とか時代とか記載はあるのだけど、もう何が何やら。
AがこれでBはこれ、そしてCという資料によるとDと考えれるので、つまりE
なのではないか、、、、みたいな感じなんだけど、Aの時点で分かラナイので、残念ながら以後の考察が進んでいくのをなるほどと思いながら読みことはできない。ただ、論旨の流れは見えるので、それをへ〜と思いながら読む。その間に中野先生の溢れる探究心と知識が垣間見れる。それが、もう半端ない
。この些細な(私には些細に感じられるような)疑問から、よくぞそこまで調べますねと思わずにはいられない。徹底的に探求していく姿勢が凄まじい。しかも、これについてはここでは言及しないけど、とか、これについては別の著作で述べているので、っていう記述も多くて、それも調べてるんですか、、、と先生の溢れる情熱を前に立ちすくむしかない感じになる。
これぞ、研究者としての素質なんだろうなって。それを感じるのが中野先生の本。
本全体としてはそんな感じの印象なのだけど、内容の中で私が特に面白く読んだのは、「瓢箪の宇宙」という章で書かれていた「瓢箪」のシンボリズムについてと、「仙界とポルノグラフィー」の章で書かれていた「時間の相対性」「仙界のもどきとしての遊郭」について。
★瓢箪には、不老不死や再生産のシンボリズムがある。
・乾燥させて薬の入れ物にしていたことから、不老不死のシンボルとなった
・何かを生み出す「植物的な卵」として瓢箪の持つ容器性が永遠の時間を収納するシンボリズム
★仙界と俗界では時間の流れが違う
・仙界と流れる時間と俗界を流れる時間は異なるという、時間の相対性をめぐる中国文学史上の永遠のモチーフ
・遊郭は仙界のもどきだったので、隔離されていることが条件になる
仙界と俗界の流れる時間が異なる、は、浦島太郎とかまさにそうで。日本の童話とかも大いに影響を受けているんだなと再認識した。そして思うのだけど、浦島太郎ってつまるところどういう話なんだっけ、あれは何を、、、
と考え出したら、切りがなくなるので、今日はやめておこう。
とにかく、こういうシンボリズムの話は面白い。キリスト教の宗教画でも魚はキリスト教のシンボルであったり、アトリビュートと言ってこれを持ってる人は誰(百合の花と青いマントは聖母マリア、ラクダの毛皮と十字架なら洗礼者ヨハネ)みたいな寓意や暗喩的なものは、知ってると解像度が上がるから楽しい。小説やアニメを楽しむ時に、ちょっとした気づきがあったりする。
中野先生の著作は沢山ある。またそのうち何か読んでみたい。
本は面白い。
栫彩子(カコイアヤコ)関西が拠点のフリーのフローリスト。 店舗を持たず、受注制作でアレンジ・花束を制作し宅配便でお届けしています。書くことも仕事にしたい。趣味は読書と英語と3DCG。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
