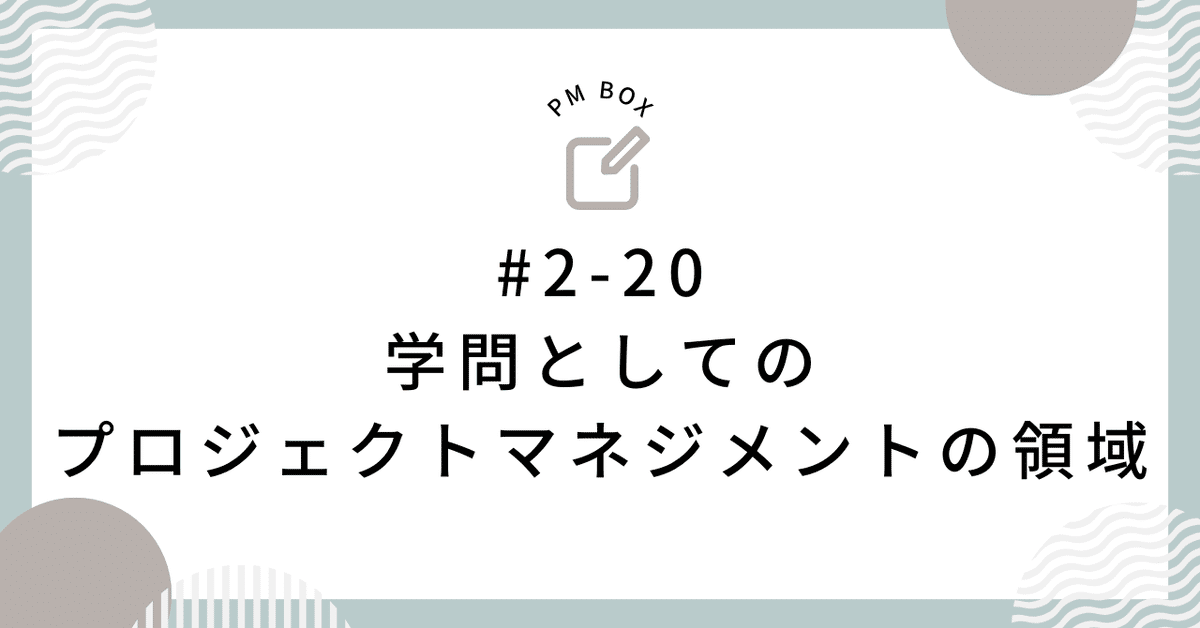
#2-20 学問としてのプロジェクトマネジメントの領域
一般的に「プロジェクトマネージャー(PM)」というと、システム開発やソフトウェア開発など、IT系の職種と認識されることが多いと思います。
何度か言及していますが、「独自の価値を創造する有期的な活動」であれば、どんなジャンルでもプロジェクトマネジメントの対象になります。
ただ、プロジェクトマネジメントという”学問”では、扱っている領域と扱っていない領域があり、職業としてのPMには、プロジェクトマネジメントの知識だけではなく、開発している専門知識や経験も求められます。
今回は、そんな、プロジェクトマネジメントという”学問”で扱う領域についてのお話です。
まず、プロジェクトマネジメントの教科書的な本『PM BOK』では、プロジェクトを「独自のプロダクト、サービス、所産を創造するための有期性の業務である」と説明しています。
「プロダクト」という言葉は、基本的には「製品」という意味ですが、他の成果物の一部となるプロダクトや仕掛かり中の作業プロダクトのことも含みます。
そして、プロジェクトマネジメントのことは、「プロジェクトの要求事項を満足させるために、知識、スキル、ツールおよび技法をプロジェクト活動へ適用することである」と定義しています。
そして、対立する制約条件を上手くマネジメントして全体最適を達成することが、プロジェクトマネジメントの精神だとしています。
英語で「Manage it!」という言葉がありますが、「管理しろ!」という意味ではなく、「なんとかしろ!」という意味です。
「問題が起きた時になんとかする人」、ということから、私自身は「PMは問題解決屋さんである」という持論があります。
業界や会社を問わず、「何とかする」ためのセオリーがまとまったのがプロジェクトマネジメント・プロセスです。
プロジェクトマネジメント・プロセスは、最終的な結果(目的)に向けて実行する一連のアクティビティで、ほとんどのプロジェクトにおいても、内容は変わりません。
言わば、どんなジャンルでも通用する内容です。
↓プロジェクトマネジメント・プロセスについて(少し丁寧に話している記事)
一方、業種や会社に毎に決まっている、プロジェクトのプロジェクトの仕様を決めるプロダクト指向プロセスがあります。
端的に言えば、業界特有のプロセスのことです。
ソフトウェア開発やシステム開発で存在するプロセスが建築や食品開発にはなく、また、その逆もあると思います。
このプロダクト指向プロセスに関しては、プロジェクトマネジメントの学問の中では扱いません。
職業としてのPMは、プロジェクトマネジメント・プロセスとプロジェクト指向プロセスの両方の知見をもって、仕事をします。

私のこのnoteでまとめいる内容も、ほとんど「プロジェクトマネジメント・プロセス」の話です。
私がソフトウェア開発のPMをしているので、たまに成果物指向プロセスの話も含まれるかもしれませんが、他のジャンルでも通用する話になるように心掛けています。
ただ、日本のプロジェクトマネージャー試験はITに関する出題が多く、また、プロジェクトマネジメントのプロセスを勉強する時点で、ITに関わりのある職業に就いている場合が多いと思います。
なので、一般的なプロジェクトマネージャー=IT職種 というイメージは、実態とそこまで離れていないのかな、と思います。
プロダクト指向プロセスについての知見を得るには、実務経験がほぼ不可欠になります。
私自身、働いている業界のソフトウェア開発以外の実務経験はほとんどないです。
しかし、だからこそ、どんなジャンルでも適用できるプロジェクトマネジメント・プロセスについての知見を深めることが大事なのかな、と思っています。
例えば、私はプロジェクトマネジメント・プロセスを学ぶ中で、自動車開発についての知見を多く得ることが出来ました。
「他の業界でも同じ問題は起こるんだ」
「他の業界で取り入れて有効だったソリューションを自分の仕事(業界)でも試してみて、有効だった」といったような発見をすることできます。
個人的な感覚ですが、プロジェクトマネジメント・プロセスは、PMにとってハブ(hub)になる大事な領域で、体系的な学習をすることで、プロダクト指向プロセスへの理解もより深まっていくと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
