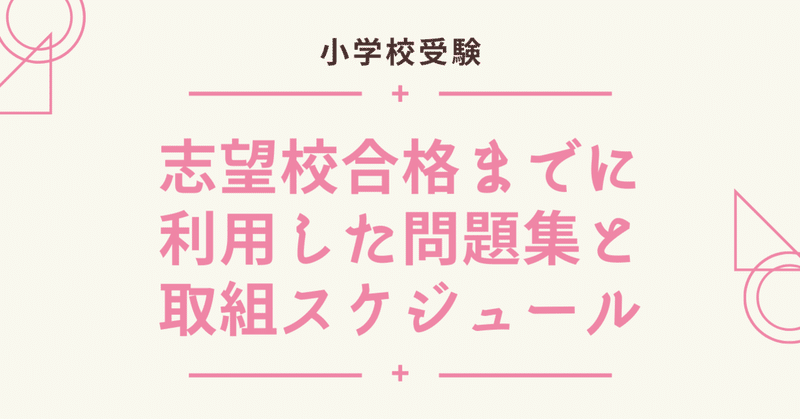
【小学校受験】私立小・国立小合格までに利用した問題集と取り組みスケジュール
こんにちは。
アイリス幼児教育のあやです。
一般的に受験や受験対策と言えばペーパー学習が必須ですが、小学校受験も例外ではありません。
そこで今回は、我が家が私立小・国立小含め受験した全ての学校からご縁をいただくまでに行ってきた学習内容とスケジュールをまとめていきます。
1:実際に利用していた小学校受験対策用教材一覧
早速ですが、我が家で利用してきた問題集と使用時期を1つずつご紹介していきます。
年少9月(新年中に入る2ヶ月前)から受験対応の幼児教室に通っていたこともあり基本的にはその宿題をやっていました。
ただ宿題の量があまり多くないお教室だったので、家庭学習に余力があったんです。
そこで、先生にどんな問題集を進めていけばいいかを確認しながら進めていきました。
1-1:有名小入試段階別ワークA・B・C
家庭学習用教材として年中春から秋にかけて取り組んだのが有名小入試段階別ワークA・B・Cでした。
この問題集はそれぞれの領域においてステップ1からステップ3までの問題が用意されており、基礎から応用まで無理なくレベルアップが狙える内容になっています。
収録内容は…
A:お話の記憶・図形の記憶
B:図形・推理力
C:比較・数量・知識・常識
となっていますが、早い月齢から取り組めるのは季節や理科的知識が学べるCです。
また、Aの記憶系はステップ1、2程度までなら年中さんから取り組みが可能です。
ただステップ3になると難易度がグッと上がるのでお子様が嫌がるようでしたら年長からの取り組みでも全く問題ありません。
ちなみに我が家はステップ1、2の問題を先に全て終わらせてから、ステップ3をやるという流れで進めていきました。
そして全てを一通り終えてみて思うのは、Bの図形・推理力は月齢(お子様の成長度合い)によってできる問題とできない問題がはっきり分かれるということです。
小学校受験において高月齢の方が優位なのは仕方のないことです。
そこは成長が追いつけばいずれできるようになると割り切りましょう。
脳が育っていない時期から無理にわからせようとするのではなく、月齢差が関係ないものから取り組みましょう。
年少、年中時代は学ぶ楽しさを感じてもらう、得意なものを増やすことに注力することが年長以降のあと伸びに繋がります。
<月齢差関係なくできる学習領域>
・季節の行事、季節の草花
・昔話
・社会生活のルールやマナー
・理科的常識
親にとっても、どの月齢でもできることから進めていくことで「うちの子は学習が進んでないんじゃないか」という焦りを軽減する効果もあります。
ペーパーは年長になってからペースを上げることも可能なため、無理をさせずに子どもの状態を親がしっかりと見極めることが必要ですね。
1-2:有名小入試段階別ワークBに取り掛かる前に終えておきたい問題集
有名小入試段階別ワークはA、B、Cいずれも幼児教室に通室しており、ある程度学習が進んだお子様向けの問題集です。
ただ、AとCは初めて小学校受験問題集に取り組む方でもあまりストレスなく進めることができる作りとなっています。
しかしBは、有名小入試段階別ワークに取り組む前にこなしておきたい基礎的な問題集があるのであわせて掲載しておきます。
しかしながら小学校受験対策は、ペーパー学習のみに留まりません。
むしろペーパー以前に具体物を使う、現地に赴いて体験させるなどの子どもの五感を刺激する機会をたくさん与えてあげるのが先決です。
COLUMN>>意外と時間がかかる、巧緻性対策
【指先を鍛えて賢く育てる】
— あや🌸教育ママ (@ayachin_edu) January 27, 2020
指先は第二の脳だと言われているのをご存知ですか?
生まれ持っての器用さは人によって違うかもしれないけど、日々の遊びの中で鍛えることもできます😊
☑️2歳〜:シール遊び、紐通し
☑️3歳〜:切り工作、粘土
☑️4歳〜:折り紙、ビーズ
☑️5歳〜:ちぎり
レッツトライ🙌 pic.twitter.com/nV6Gctwpb1
中学校受験や高校、大学受験とは異なり、小学校受験には巧緻性と呼ばれる制作や絵画の試験が含まれることがほとんどです。
小学校受験界の最難関私立小学校と言われる慶應義塾幼稚舎は、ペーパー試験はないものの、制作(絵画)が試験項目として毎年出題されています。
2019年秋の入試では、説明を聞いてカラー粘土で作品を作る、大きく・小さくなった自分を絵に描く等が課題として与えられました。
幼稚舎の制作(絵画)は大手幼児教室でも専用のカリキュラムが組まれるほどですから、一朝一夕では太刀打ちできないことがお分かりになるのではないでしょうか。
我が家では娘がもともと工作好きで園でも毎日のように何かを作っていたため、本番に向けて特別な対策は特にしていません。
しかしながら、完成度にこだわりすぎてしまい時間がかかりすぎてしまうので、その点は本番直前まで「とにかく時間内に終わらせるように」と何度も話しました。
またお子様によっては、工作や絵が好きでないという場合もあるかと思います。
この場合、まず苦手意識を克服するところからのスタートですので、相応の時間がかかることはあらかじめ親として覚悟しておいた方がいいかもしれません。
小学校受験に必要な巧緻性を把握するために役立った1冊もご紹介しておきますね。
娘が年中の頃は絵の苦手意識がものすごくありました。
自分の目標とする出来にならないと匙を投げたくなる気持ちはよくわかります。
そんなときは無理にやらせずに「お家に帰って少し休んでからもう一回やってみようね」と話して翌週に幼児教室の先生に提出していたのも、今となってはいい思い出です。
1-3:ハイレベ合格ワーク100[1]~[5]
有名小入試段階別ワークのほとんどが終わり、次に取り組んだ問題集が『ハイレベ合格ワーク100』シリーズです。
こちらの問題集はどの分野の問題も標準レベルとハイレベルの2パターンが掲載されているだけでなく、100問という大ボリュームなのが特徴的です。
我が家は年中秋に有名小段階別ワークが終了したので、その後にこのハイレベ合格ワークを年長春までに終わらせるペースで進めていました。
段階別ワークで小学校受験に必要な全領域を一通り押さえた後に、復習もかねて量をこなしたい人にもおすすめできる教材です。
ハイレベは領域ごとに[1]〜[5]と問題が分かれて収録されています。
1 お話の記憶
2 図形・注意力
3 推理・思考
4 比較・数量
5 知識・常識
有名小入試段階別ワークを全て終えている段階であれば、ハイレベ合格ワーク100シリーズの標準レベル問題はほぼ解けるようになっているはずです。
もし忘れているところ、理解が浅かったところがあれば、年長の春までに手当しておきましょう。
我が家の場合は、どの領域も標準レベルから先に終わらせ、2巡目にハイレベに取り組むようにしていました。
ハイレベは本番とほぼ同じ難易度の問題だと言われているので、こなすことよりもじっくりと時間をかけて理解させることが大切です。
また段階別ワーク、ハイレベ共に制限時間が記載されていますが、かなりシビアに設定されています。
お世話になっていた幼児教室の先生も時間内に終わらせることの方が難しいとおっしゃっていたので、我が家は気にしすぎないようにしていました。
1-4:年長初夏から志望校の過去問中心に、そして仕上げへ
小学校受験にも過去問が販売されていますので、秋の入試本番に向けて初夏から徹底的して過去問に取り組んでいきます。
過去問は複数の大手幼児教室、出版社から発売されていますので、可能であれば2種類用意し、過去10年分はさらっておきましょう。
特に国立大学附属小学校受験を希望される際は、複数社の過去問を手に入れるのは必須です。
その理由は、学校から過去問が提供されないため各社受験者の聞き取り調査を元に制作しているからなのですが、購入したものを見比べてみると内容はもちろん難易度にも差があることも多いです。
個人的には理英会のそっくり問題集がプリント形式でコピーも取りやすく使い勝手が非常に良かったです。
1-5:こぐま会「領域別毎日トレーニング」
3週間で「合格できる子」にレベルアップさせることに重きを置いた問題集です。
娘は私立小受験本番前にこの問題集を一通りこなし、無事にご縁をいただきました。
1-6:こどもめんせつれんしゅう
小学校受験はペーパーテストだけでなく、面接や口頭試問などコミュニケーション能力を高める練習も必要です。
我が家では隙間時間でいつでも取り組めるよう、持ち歩けるサイズのこちらが大活躍でした。
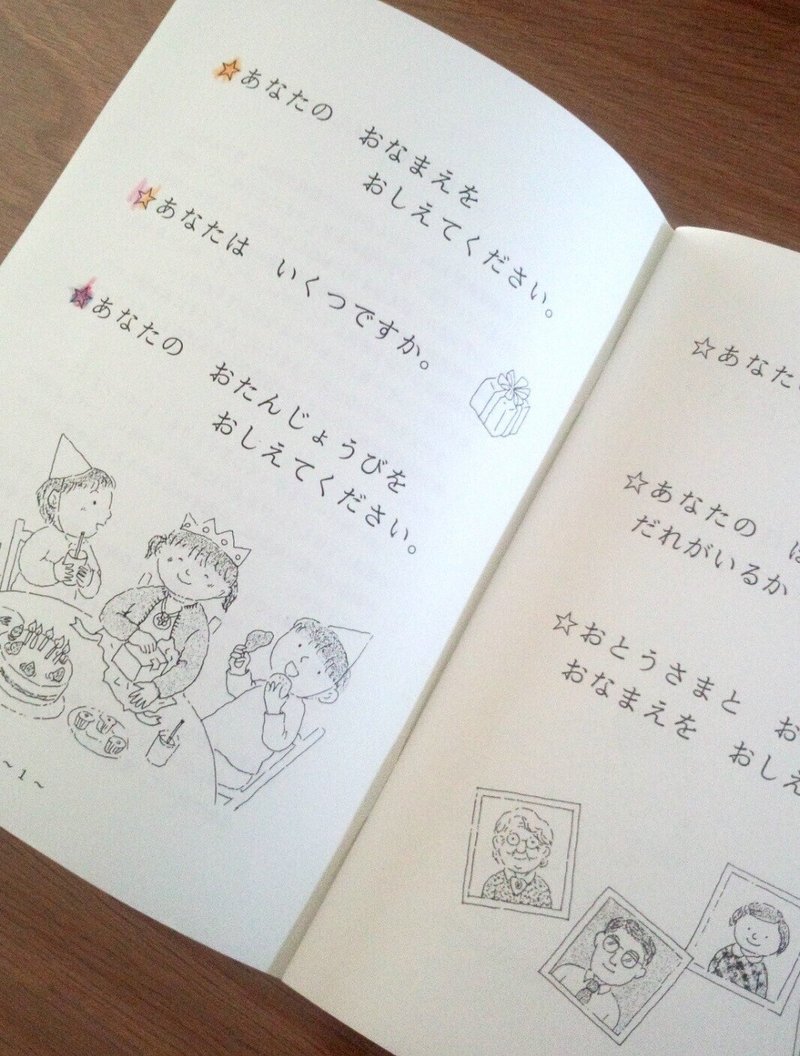
1-7:話の内容理解 口頭問題集1、2
ペーパー回答なしで「お話の記憶」領域対策ができるこちらの問題集も重宝しました。
Twitterでもつぶやきましたが、お話の記憶で高得点を得るために必要な力はイメージする力です。
お話の記憶が苦手=お話が聞けない
と思われがちですが、そうでない場合もあります。
もしお子様が「お話の記憶が苦手だな」と思うのであれば、まずその原因を把握するところから始めましょう。
小学校受験で「お話の記憶」が苦手な場合、お話の内容を頭の中で映像化できてないことが多い。我が家はこの【選択肢がない】【クーピーで書き込まない】問題集でまず頭の中で映像化する練習をたくさんしました。結果、5分を超えるお話を聞いてもあまり間違えはなかったです。https://t.co/RkcfHaB34k
— あや🌸教育ママ (@ayachin_edu) January 19, 2021
2:小学校受験成功のポイントは体験学習
ここまで小学校受験に合格するまでに必要な学習の内容とスケジュールをお伝えしてきました。
あくまで我が家の場合にはなりますが、これから受験を志すご家族にお役立ていただけたら嬉しいです。
しかし、小学校受験のペーパー学習は実体験の確認作業にすぎません。
理科的常識領域では、水に浮かぶもの、沈むものを選ぶ問題などがありますが、それらは知識としてペーパーで学ぶものではなく、自宅などで実際に試してみるのが一番です。
親子で楽しみながら経験したことは、いつまでも色褪せることなく子どもの心に焼き付いていますし、結局それが一番の小学校受験対策になるのだと感じています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
\続けてこちらもどうぞ/
もし「サポート」をいただけましたら、より役立つ記事を書くための、経験や学びに使わせていただきます。いつも読んでくださり、ありがとうございます。
