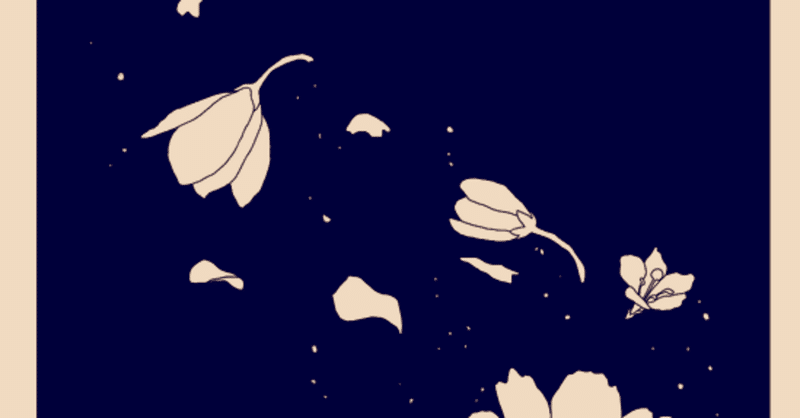
「惑ふ水底、釣り灯籠」第八話
【第四章 柊水】
廻神柊水《えがみしゅうすい》という男は、生まれながらにして神を祀る家系の当主の息子としての運命――言い方を変えれば、重荷を背負っていた。
神鎮の権利は、廻神家の血を引く者全てに与えられる。しかし、それを上手く扱えるかどうかは与えられた神鎮の才能に依る部分が大きい。当主の息子であるという時点で注目を集めていた柊水は、その才能が災いし、早くから次期当主候補であると騒がれるようになった。先に生まれた兄である銀志は柊水とは異なり神鎮の権利の扱いが下手で、神との意思疎通すら満足にできない状態であり――その分柊水は屋敷の人間に歓迎された。反対に、銀志や他の兄弟たちから疎まれていた。
父は当主として一年中水属性の神社を回っており滅多に屋敷にはいない。重要な神事の際のみ屋敷へやってきた。彼は自分のどの子供にも無関心で、帰ってきたところで一度も話しかけることはなかった。柊水は父が帰ってきた時、遠くからその背を見つめているだけだった。
そのようにほぼ他人に等しかった父とは違い、離れに隔離されている母は柊水を可愛がってくれた。母は病弱であまり激しい運動はできず寝たきりだった。しかし屋敷の人間はそんな母を乱暴に扱い、面倒も見ずに放置した。柊水は暴力を振るわれる母の姿を見て育ち、女という生き物が屋敷でどのような生き方をしていかねばならないのかを知った。死んだような目で媚びへつらい、神鎮たちの機嫌を窺う母を見て、幼いながらに女に生まれなくて良かったと残酷な安堵を覚えた。
柊水の話し相手は母だけだった。柊水は習い事の合間に毎日母の元へ通い、屋敷のことを話した。母も柊水との時間だけが癒やしだったのか、柊水といる時だけは笑っていた。柊水は自分の存在が母の心の拠り所であることを分かっていて、少しでも前向きにさせようとできるだけ楽しい話をした。
――そんな母は、ある日突然死んだ。病弱であるとはいえ、あと数年は生き延びるだろうと医者に言われた矢先だった。
その日を境に、屋敷にいる使用人たちもばたばたと倒れ始めた。明らかに異常事態だった。屋敷の人間が次々と死んでいくのだから、廻神家は大騒ぎだった。
「祟りだ」「黒龍様がお怒りだ」と大人たちが騒ぐ中、醜い姿で横たわる母の死体の横で、柊水は何日も動けずにいた。初めての身近な人間の死は、柊水にとって到底受け入れられないものであった。もしかしたら生き返るかもしれないと思った。目の前にいる母が、また笑ってくれるのではないかと思って一緒にいた。
柊水の母が死んだというのに屋敷の神鎮たちはそれどころではないのか、死体は何日も放置された。好きだった母の花のような香りも、腐敗した匂いに変わっていった。柊水は飲み食いもせずただその様子をじっと見つめていた。
「だからあれほど忌み子の捜索を中止するなと言ったんだ!」
「そもそもあの女が悪いんだ! あの女……なんと罰当たりな。忌み子を連れて逃げ出すなど」
「このままでは人手が足りなくなります。年末の神事ですら……」
「その……言いづらいのですが、父親の方は最期まで口を割りませんでした。愛した女とその子を逃したかったのでしょう」
「それで神の怒りに触れ、世がどうなってもいいと思っているということか!?」
「破門だ、破門! あんな奴は我が廻神家の人間ではない!」
「今頃忌み子のいる土地でも祟りが起こっているはずです。最近不審死が起こった地方を手当たり次第に探すしか……」
ばたばたと廊下を走り回る神鎮たちが言い争う声が聞こえる。
――これはかつて死んだ神様の祟りらしい。玉龍大社の奥宮に祀られていた、黒龍という神の意思は、忌み子が傍にいなければ怒り狂うのだという。その忌み子とやらは、他者への影響など考えない身勝手な母親によって産まれてすぐ連れ去られたそうだ。どこにいるのかはまだ分かっていない。
忌み子のせいで柊水の母は死んだ。そのうえ、かつて神を裏切った忌み子が我が身ばかりを省みて別の地域で隠れ住んでいるせいで、屋敷の何十人もが死んだのだ。何故何の罪もない母が、使用人たちが死ななければならなかったのか、柊水には分からなかった。
(そいつだけ死ねば良かっただろ。忌み子さえ、生まれてこなければ――)
祟りくらい一人で背負えよ、と柊水は忌み子に対する怒りを覚えた。
忌み子の父親は母と子が失踪した後も廻神家の屋敷に残っていたが、女児が産まれたという事実すら隠して平然と神鎮として働き、金と手紙を母と子に特殊な経路で送り続けていたと聞く。――忌み子が産まれたという事実が神の口から発覚して以来、牢に閉じ込められ長年尋問を受けていたそうだが、結局断固として忌み子の居場所は吐かなかった。そのため、捜査は難航していた。
屋敷ではここ数年、半ば諦めたような雰囲気が流れていた。忌み子の父親は賢い男で、母と子に繋がる手掛かりはほぼ消えていた。捜索にかかる労働力も小さなものではない。
何年も捜し続け、捜査を打ち切ったその時、この屋敷にも祟りが起き始めた。捜索を中止したことで神が怒ったのだ。
柊水には忌み子の家族のことも、神のことも理解できなかった。
忌み子の家族に関しては、たった一人を犠牲にすれば済む話であるというのに、自分たちに危険が及ぶと分かっていて愚かな選択をしたという点で理解できない。神に関しては、美しい女などその辺に転がっているであろうに、ただ一人の女に固執する意味が分からない。
(……馬鹿な奴ら。みんなみぃんな、愚かだ)
柊水は周囲を冷めた目で見るようになった。何に対しても興味が湧かず、世界が灰色に映って見えた。
そんなある日、柊水は初めて父親に呼び出された。
「神様がお呼びだ」
何を話すのかと思えば、それだけ言ってすぐに本殿の方へ連れて行かれた。
父に見られながら、いつものように目を瞑って古来の言葉で神に呼びかけた時――ふっと意識が遠のいた。
神と意思疎通をしたことは何度かあった。しかし、その時は声が聞こえるのみで、意識を失ったことはなかった。ほんの一瞬、眠ったような心地がしたかと思えばすぐに目が覚める。そこに広がっていたのは、壁一面金色の部屋だった。柊水は、水面のような冷たい透明の床の上に足を付けて立っている。この床は明らかに人の世のものではない。
御簾の向こうに龍の影が見えている。
『貴様と会うのは久しい』
声からして、何度か会話を交わしたことのある白龍に違いなかった。柊水は姿勢を低くし、次の言葉を待つ。
『もしやとは思っていたが、その瞳、やはり間違いないな』
龍の大きな尾が動いた。
『何の因果か、今度は神鎮の家系に生まれ変わったわけだ。そこまであの娘が恋しいか』
「……何をおっしゃっているのですか?」
『はは、そうか、人は生まれ変わると記憶を失うのだな』
白龍の言う意味が分からず、眉を潜める。すると白龍が続けた。
『お前は、太古の昔、俺から愛する女を奪った人間の生まれ変わりだ』
――歴史書で読んだことがある。黒龍と白龍が愛した神鎮の始祖、彼女は人間の男を愛してしまい、二匹の龍を裏切ったと。それが玉龍大社の神による祟りの始まりだったと。
『この千年間、俺はお前がこの世に生まれ変わるたび殺してきたが、神鎮となれば話は違う。神鎮の家系の者に手を出すのは神の世での禁忌だ。俺は今回のお前は殺せない』
「…………」
『嗚呼、憎い、憎らしい。俺はお前が嫌いだ』
白龍の口調から、確かに憎悪を感じた。――くだらない、と思った。自分たちが祀っている龍神は、本当に一人の女に懸想しているらしい。
「例え僕が其の者の生まれ変わりだとして、何だと言うのです。神に背いて忌み子を奪うなど、有り得ぬことです」
興味がない。理解できない。忌み子の父は忌み子を守ったかもしれないが、危険を省みず神に歯向かうなど、柊水には信じられないことだ。
身勝手な理由で無関係の人間を殺すようなものが、神だ。人の倫理では到底理解できない悪行も平然とやってのけるものが神だ。神であれば許される。祀られる。崇められる。であれば、それに抗うこと自体間違っている。少し考えれば分かることだ。無駄なことはしない。
『ほう……今までのお前よりも話が分かるようだな』
その態度を見た白龍が、御簾の向こうで感心したように頷いた。
『今日ここへ呼んだのは、釘を刺すためだ。俺から忌み子を奪うなどと考えるな、とな』
「有り得ぬことです」
柊水は同じ言葉を繰り返した。
すると、白龍は興味を失ったように柊水から顔を背けた。
『なら良い。忌み子はおそらく数日以内に見つかり、ここへ連れてこられるだろう。黒龍の意思の様子を見ていれば分かる』
「黒龍の意思というのは、目に見えるものなのですか」
『俺にはな。あれは死んだ神だ。いくら神鎮とはいえ人の世の者には見えん。しかし、黒龍の意思は奥宮と水晶宮に確かにまだ残っている。そして忌み子を、その周囲を殺そうとしている』
「忌み子もですか? 忌み子は二十になるまで死なないはずでは?」
『俺が守っているからだ。俺の力で黒龍の意思に反発している。しかし、忌み子が二十になると俺の力ではどうしようもなくなる。黒龍の意思の力が強まるからだ』
「何故……」
『あの女が人間の男を好きになった年齢が、二十だった。黒龍にとって不吉な年齢だろう。黒龍はそれ以後のあいつが人の世にいるのが許せないのだ。……とはいえ予想に過ぎんがな。意識のない死んだ神の感じることなど俺には分からん。意図も目的もなくやっているのかもしれん』
やはり神のことは理解できないと思った。白龍のこともだ。
「忌み子を守るのは白龍様にとって負担ではないのですか? そんなことをするくらいであれば、その力をこの地の民に還元してほしいのですが」
お前は神への言葉遣いも態度も失礼だと先輩の神鎮たちに怒られたことは多々あり、自覚もしている。だが、柊水は元より信仰心が強い人間ではなく、改める気もあまりなかった。だからこのように白龍にも意見することができた。
忌み子をさっさと殺してしまえば、祟りは起きない。正直なところ、白龍がしている忌み子の延命は無意味であり、周囲への影響を考えると迷惑ですらあるように感じた。
『俺は生きていた頃の忌み子を愛しているのだ』
しかし、白龍から返ってきたのは、柊水が予想していたよりも凡庸で他愛ない理由だった。
『死後、水晶宮に連れて行くことはできる。しかし死んだ人間は生きていた頃のそれとは異なる存在だ。水晶宮にいると、徐々に人としての意思や思考もなくなっていく。一緒に居ることはできても、それは俺の知る忌み子ではない』
「……それが嫌だと?」
『捨てられぬのだ。千年前、生きている彼女と過ごした頃の幸せを俺は捨てられない。だから何度も期待する、今度こそ、今度の二十年間こそ、あの時のように過ごせるのではないかと――』
恨むような、苦しむような、憎悪と憧憬の混じった声音だった。神でもこのような激情を抱くのかと思った。
そして、人間とは乖離した存在である神ですらこのように感情豊かであるのに比べて、自分は無機質であるように感じた。
本当にその数日後、忌み子が玉龍大社へやってきた。
泣き腫らした赤い目、ぼろぼろの髪、土で汚れた衣服――品のない格好をしているその少女は、奥宮の前に蹲っていた。
柊水が優しく微笑んでやると、少女は安堵したような表情をした。
その瞬間――その顔を踏み躙ってやりたくなった。そのまだ希望を持っているような目を、あの日見た母の死体のような空虚な目にしてやりたいと思った。
その小さな体を突き飛ばすと、翼妃という名の少女は呆然と見上げてきた。その時、柊水の心に歪んだ悦楽が生まれた。柊水の嗜虐心を煽る、真ん丸な瞳が揺れる。
憎い相手を傷付けるは気持ちが良い。母の死後、ゆっくりと感情を失いかけていた柊水は、翼妃が屋敷にやってきたことによってようやく人間らしい気持ちを思い出すことができた。――憎しみという、人という厄介な生き物しか持ち得ないであろう感情を。
それ以後、柊水は執拗に翼妃に構うようになった。屋敷の神鎮たちは風格が落ちるなどと言って柊水を引き離そうとしたが、神鎮の権利を使って少し脅せば黙った。翼妃をいじめることが、柊水にとって生きる上での唯一の楽しみだった。
しばらくして“鍛錬”が始まった。鍛錬とは、忌み子を迎えた時の廻神家が代々行っている儀式で、忌み子を苦しめ殺すことによって黒龍に許しを請うものだ。翼妃は何度も殺され、水に沈められ生き返っていた。
鍛錬は翼妃にとっては死ぬことのできない生き地獄だっただろう。最初に出会った頃にはまだ明るかった翼妃の目が、どんどん母の死体の目に似ていくのを見て、柊水は不快に思った。
(……つまらない)
自分ではない誰かの手によって変化させたいわけではない。自分の手で苦しめたいのだ。自分が壊す前に壊れてしまっては楽しくない。
そこで柊水は思い付いた。もう一度希望を与えてやればいいのだ。良い思いをすればまた元に戻るかもしれない。実験のような気持ちで、柊水は翼妃に自分のやれるものを与えることにした。
最初に与えたのは着物だった。女はこれで喜ぶと聞いたことがある。翼妃はぼろぼろの布のような服をずっと身につけていたため、きちんとした着物を着ると見違えるほどに美しくなった。
「何だ、それなりの格好をすればそれなりに可愛く見えるね」
思わず正直な感想が漏れた。翼妃は柊水の言葉が聞こえているのかいないのか、無反応だった。虚ろな目をしているのは変わらない。
もっと与えなければ直らないのか、と柊水は思い、使用人に命じて何着もの着物を着せた。
艶のある黒髪と、透き通るような白い肌、薄紅色の唇。翼妃の造形は元が美しかった。きちんと風呂に入らせ髪を梳き、化粧をさせればもっと美しくなった。屋敷の使用人に美しい女性は沢山いるが、これほど着物の似合う女を柊水は初めて見た。他の廻神家の人間と同様女という生き物を見下していた柊水は、それを見て初めて、翼妃に敵わないような、もどかしい気持ちになった。
この姿で外へ出せばおそらく嫁に迎えたいという者が出てくるだろう。そのような考えが頭を過ぎった瞬間――柊水の胸に苛立ちのようなものが生まれた。
「翼妃ちゃん。こんなことをしてあげるのは、僕が傍にいる時だけだからね」
「……うん」
「その格好で部屋の外へ出てはいけないよ」
翼妃は無表情のままこくりと頷いた。この屋敷での生活を経て、柊水に歯向かう気など全く起きないようだった。それも柊水にとってはつまらない。もっと生きる気力を持ってほしかった。それを自分で手折りたい、という気持ちがあった。
翼妃に心を取り戻させるため、柊水はそれ以外にも、翼妃を色んな場所へ連れて行った。玉龍大社は四季折々の景色で有名だ。神社の敷地内に咲く花は一通り翼妃に見せた。神社付近の甘味処や料亭にも連れて行った。
次期当主候補は忌み子に構ってばかりだと屋敷の人間が文句を言い始めたので、彼らを黙らせるために勉学にも励んだ。
かくれんぼや鬼ごっこなど、子供がする遊びについて調べて翼妃に教えた。翼妃が少しでも楽しめばいいと思った。
ある日のかくれんぼの最中、神社の裏手に隠れていた翼妃に声をかけると、翼妃は過剰に驚いてよろけた。咄嗟にその腕を掴んで引き寄せる。意図せず抱き締めるような体勢になった。
――その時、花の香りがした。懐かしい香りだった。まるで死んだ母親のような香りだった。母が翼妃と自分を見守っているのかもしれない、と柊水はぼんやり思った後、そんなはずがないかと自分の考えを笑った。
「は……離して。近い」
腕の中の翼妃が身を固くしている。男慣れしていない分緊張しているのか、顔も熱くなっていた。
その様子を見て、柊水はいくらか良い気分になった。
「忌み子のくせに、一丁前に僕を意識しちゃったの? 可愛いね」
からかうように言うと、かぁっと翼妃の顔が赤く染まる。このような表情を見るのは初めてだった。
久しぶりに人間のような表情をするところを見れたと思った。――そして、その顔をもっと見たいと思った。
背を曲げて翼妃と視線を合わせ、小さな唇に口付けをする。
「じゃあ、接吻をするのも今のが初めてってわけだ」
翼妃は呆然としていて、何をされたのかよく分かっていないようだった。
「せっぷん……」
「今のがそうだよ。仲の良い男女の挨拶のようなものだから、僕としかしちゃだめだよ」
何も知らない、教育を受けていない翼妃なら、何でも教え込めることに気付いた。
「柊水様、さっきここに誰かいたのを見た?」
ふと、翼妃が聞いてくる。表の方は混雑しているだろうが、こんな夕暮れ時、こんな場所に人など来ない。
「翼妃ちゃんはたまに変なことを言うね。頭がおかしな子だと思われるから、もう僕以外とは喋らない方がいいんじゃない」
柊水の中に新しい感情が生まれた。翼妃を洗脳し、自分の思想を擦り込み、他の誰かではどうしようもないほどに管理したい。自分なしでは生きていけないようにしたい。――それを独占欲と呼ぶことを、柊水は知らない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

