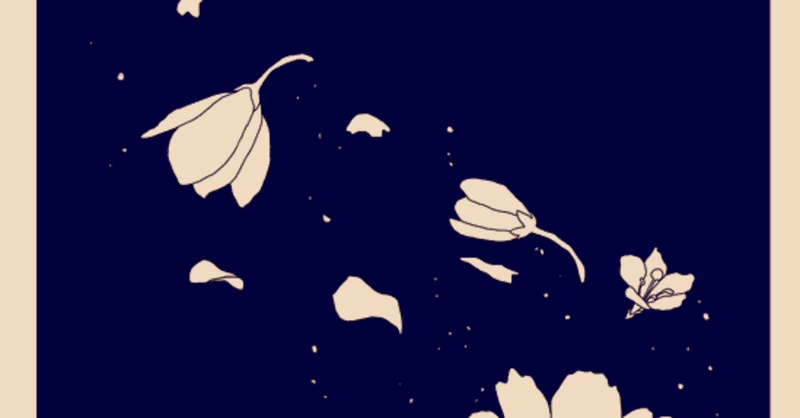
「惑ふ水底、釣り灯籠」第六話
◆
季節は巡る。屋敷の屋根にも雪が積もるようになった。
帝都も存外寒いのだと、柊水からの手紙で読んだ。
玉龍大社の冬は寒い。美しい庭も雪で覆われ、純白の絨毯が広がっているかのようだった。陽の光を浴びる時間も日に日に短くなり、吐く息も白くなる。
このような寒さの中外に出て鍛錬するほどの気力はないのか、いつしか何故か銀志からの干渉もぴたりと止んでいた。
(もう少ししたら、鹿乃子さんと一緒にこの屋敷から逃げるんだ)
僅かな希望を抱きながら、翼妃は柊水の次の長期休みを待っていた。
しかし、それを待たずして、翼妃の運命を変える出来事が起こる。
その日は一段と冷え込む日だった。空は曇っており、今にも雨が降り出しそうだった。遠くから雷の音も聞こえていた。
「何……してるの」
翼妃はその場に立ち尽くす。鹿乃子の苦しそうな声が聞こえて、本来は開けない他人の部屋の襖を開けたのだ。
銀志に組み敷かれている女性。
それが鹿乃子であることを理解するのに数秒。
鹿乃子の衣服が乱されていることを理解するのに数秒。
その衣服の中に、銀志の汚らわしい手が入れられているのを見て思考が停止する。
鹿乃子はぼろぼろと涙を零していた。明らかに同意の上ではない。
「あ? 何だお前、邪魔すんな」
「……いつも、こんなこと、してたの」
問いかける声が掠れた。
「いつもも何も、こいつは使用人だぜ? 使用人を好きに使って何が悪い。他の神鎮もしてることだろ」
翼妃はそこでようやく気付く。
女という性別を忌むべきものの象徴のように扱っているこの屋敷の人間が、どうして使用人には若い女性ばかりを雇っているのか。どうやらこの屋敷では、使用人の“使い道”は多様にあるらしい。
「こいつも最初は柊水に連れてこられたからってお高くとまってたが、体差し出せば忌み子に暴力振るわないっつったら身を呈して俺の言いなりになりやがったぜ」
ぎゃはは、と笑う銀志の顔が歪んで見えた。
激しい雨が地面を打ち付ける音がする。人の叫び声すらも掻き消してくれそうな、耳障りな雨音。
こんなに怒りを抱いたのは、雀を殺されて以来だった。
部屋の壁に立てかけられていた刀を手に取り、抜刀する。
その様子を見た銀志は鹿乃子から手を離し、翼妃を振り返って馬鹿にしたように笑った。
「っはは、何だお前、この俺に歯向かう気か? 無駄だよ、無駄無駄。何の力もねぇ忌み子のくせに刀なんか持って何ができんだよ」
銀志が翼妃に向かって手を翳す。たちまち水塊が生じ、翼妃を溺れさせようと迫ってくる。
しかし――ばしゃり、と、水塊は翼妃にぶつかる前に床へ落ちた。
銀志が目を見開いた。そして、もう一度手を翳す。水が翼妃に迫るが、それもまた、翼妃に届く直前で力を失ったかのようにただの水へと戻った。
何故そんな現象が起こるのかは翼妃にも分からなかった。考える余裕がないと言う方が正しいかもしれない。翼妃の心は今、怒りで煮え滾っているのだから。
「これは……黒龍の加護……?」
意味の分からないことを呟く銀志に、ふらふらと近付く。
「千年以上前に施された加護が黒龍の死後もまだ残ってるって言うのか?」
銀志が焦ったように後退りした。
「黒龍様、お待ち下さい! 違うのです! その者は忌み子です! 加護するお相手を間違えております!」
銀志と視線が交わらない。銀志は翼妃の背後を視ているようだった。何もないそこを見て命乞いのように叫んでいる。
けれど翼妃にとってはそんなことどうでも良かった。ただ目の前の相手が憎かった。
銀志が水を発生させようとする腕を切り落とす。凄まじい叫び声が室内を揺らした。血が飛び散る。鹿乃子が呆然とその様を見ている。
床に転がる腕。何度も翼妃を殺した腕だ。銀志はまだ動いている。翼妃は呻きながら床をのたうち回る銀志に近付き、その首に手をかけた。
「沈め……っ」
絞り出すように言うと、銀志の体から水が大量に発生していく。それは銀志の意思ではないようだった。
「沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め沈め!!」
翼妃が叫ぶと、水塊は銀志の体全体を包み、鼻と口さえ覆い、溺れさせていく。
――暴走している。確かに。
ごぼ、ごぼぼっと必死に足掻いて逃れようとする銀志を押さえ付ける。
そのうち、徐々に銀志の抵抗の力が弱まり、水も引いていった。
「どうしてですか……黒龍様…………」
銀志が掠れた声で問いかけてくる。
「其の者は、あなた方を裏切り……殺……した…………」
その言葉は途中で止まってしまった。銀志が絶命したからだ。
「翼妃様!」
切断された腕を見て腰を抜かしてしまった様子の鹿乃子が、刀を持ったまま部屋を出ていこうとする翼妃を呼び止める。
「どこへ行くのですか!? おやめください! わたくしのことは良いんです! こんなことをしたら貴女が罪人に――」
「――私が、良くないの」
鹿乃子の制止も無視して廊下へ出た。
鹿乃子は翼妃がここまで復讐心を募らせていたことを知らない。鹿乃子が協力すると言ってくれたのはあくまでも薩摩國への逃亡であり、殺人ではない。
だから“これ”に鹿乃子は関係がない。翼妃が単独で行う犯行だ。
刀の先から血がぽたりぽたりと落ち長い廊下を汚していった。
一番近かった部屋に寝ている神鎮から殺していった。雷雨が音を掻き消してくれた。被害者であろう使用人たちだけは活かし、何年も何年も翼妃を侮辱し苦しめた神鎮たちから暴走させていく。一度銀志を暴走させたからかやり方が掴めてきた。
「やめろ! やめろぉぉおおおお!!」
自分を見下していた屋敷の者たちの悲痛な叫び。みっともなく地べたに這い蹲り、命乞いをしてくる廻神家の人間。中には翼妃の雀を殺した者もいただろう。翼妃はどの神鎮が雀を殺したか見ていないが、それなら全員殺してしまえばいいと思って刀を振り続けた。
柊水に下手くそだと、一向にうまくならないと罵られ続けた剣術。
しかし現に、神鎮たちは翼妃に敵わず逃げ惑っている。翼妃が下手なのではなく、柊水が規格外であるというだけなのだろう。
神鎮たちの死体から制御できなくなった水が溢れ出している。血の海となった屋敷の中を裸足で走って鹿乃子を探した翼妃は、自室に移動していた彼女を見つけてその手を引っ張った。
何人もの神鎮の権利を暴走させたせいで、近くの川が氾濫している。このままでは黒龍に願った通り、玉龍大社やこの屋敷が水の中に沈むだろう。その前に鹿乃子を連れて逃げなければと思った。
――しかし、共に走っている途中で鹿乃子がぴたりと足を止めた。
「これを持ってお逃げください……翼妃様」
俯いたまま、紐で結ばれた袋を渡してくる。
そこに入っていたのは三年前、白龍からもらって初めて見た物――大量の貨幣だった。
「翼妃様と、薩摩國の神様との間に、縁を結びました。これで絶対に翼妃様は火の神とお会いできます。地の神のお力は、偉大ですから……」
縁を結ぶというのは、地属性の神鎮の権利だ。
「山を越えたところに駅がございます。そこから蒸気機関車に乗ることができます。何度か乗り換えれば薩摩國です。行き方は以前お伝えした通り。分からなければ、駅員に聞いてください。――翼妃様、貴女は、幸せになるべきお人です。どうか、お幸せに」
「鹿乃子さんは……? 一緒に行くよね……?」
こんな場所に残っていても不幸になるだけだ。翼妃は鹿乃子を無理矢理にでも連れて行こうとした。しかし。
「わたくしはもう駄目でしょう」
ぽつりと鹿乃子が呟く。その声は鹿乃子のものではなかった。
「――――――神のお怒りに触れました」
次の瞬間、鹿乃子の目が真っ赤に充血し、狂ったように高笑いを始める。
「あアよゐよゐよゐよゐよゐよゐよゐよゐ――汝良きことを為し給ヱり然るにコそ余が認ムべき女なり是非尚更に為すベキを願わば凡てを壊さンと為す汝こそ美し――」
その言葉は明らかに鹿乃子の意思を介して発せられたものではない。
(どういうこと……!? 神鎮の家系の人間は神様からの干渉を受けないんじゃ……)
取り憑かれたように気味の悪い声を出す鹿乃子を呆然と眺めていると、鹿乃子の拳が翼妃に襲いかかってきた。その勢いは人の力を超えており、鹿乃子が殴った廊下の床に大きく穴が開いている。あの拳が当たっていたら死んでいたかもしれない。
「……っ鹿乃子さん! 鹿乃子さん、お願い! 正気に戻って!」
屋敷全体に津波のように水が流れ込んでくる。早く行かなければならない。
鹿乃子がもう正気ではないことは翼妃にも分かる。けれど、どうしてもすぐに見捨てることができない。川に浸かればどんな傷も治ってしまうと伝えた時、涙を流してくれた鹿乃子の顔が頭に浮かぶのだ。
鹿乃子の顔が崩れ、異形のような見た目に成り果てていく。そしてその爪は凶器のように長く尖り、鹿乃子の体を揺らす翼妃の体を刺した。血が吹き出すが、水に浸かっているためにすぐにその怪我は治っていく。
「鹿乃子さん! 鹿乃子さん! ねぇ、応えてよ!」
「汝再ビ我らヲ遺しむか背信ノ者よ――」
翼妃が泣きながら叫んでも、鹿乃子はよく分からない言葉を喋るばかりで戻ってこない。
そのうち、異形と化した鹿乃子の目がぎらりと光る。その手が振り翳された時、翼妃は死の予感を覚えた。
――次の瞬間、視界が一気に揺れ、翼妃は水の中から出されていた。翼妃の体はどんどんと空へ舞い上がり、宙に浮いている。鹿乃子の姿が遠ざかっていく。
何が起こったのか一瞬分からなかった。誰かが自分の体を抱えて跳び上がったことに遅れて気付く。
卯の花色の着物と、月白の髪がよく似合う男性――白龍だ。会うのは実に三年ぶりであった。
「白龍、だめ! 鹿乃子さんが……っ」
「あれはもうお前の知る人物ではない。俺がここへ来られたことがその証だ」
鹿乃子が傍にいると、白龍は翼妃に近付くことができない、と柊水が言っていた。こうして白龍が翼妃を助けに来られたということは、鹿乃子はもう鹿乃子ではないのだ。その事実を突き付けられ、翼妃は白龍にしがみついて啜り泣いた。
白龍は山の上、水が来ないところに降り立ち、水の中に沈みゆく玉龍大社を眺める。
「白龍、ごめ……白龍が祀られてるところなのに、ごめん」
泣きながら謝るびしょ濡れの翼妃に、白龍は優しく笑った。その笑顔は昔見せてくれたものと何ら変わりなかった。懐かしくてまたぼろぼろと涙が出てくる。
「お前が謝ることではない。社が水に沈んだところで俺の力は衰えん。地震などで崩壊したのなら話は別だが、水はむしろ俺たちの力を増強させるものだ」
「本当に白龍だよね……?」
久しぶりすぎて実感が湧かず、ぺしぺしと濡れた手で白龍の顔を触る。すると白龍が少し意地悪そうな顔をした。
「信じられないのであれば、もっと深いところで俺を確かめてみるか?」
意味が分からず首を傾げる翼妃に、白龍は「お前にはまだ早かったな」と冗談めかして笑った。
「それにしても、まさかお前があんな大胆な行動に出るとはな。まぁ、現当主と次期当主までは殺せていないようだが」
現当主、柊水の父親は出張で不在だ。そもそも年末年始などの重要な祭事以外で屋敷に居ることの方が少ない。柊水も帝都に居る。確かにその二人は殺せなかった。白龍の発言が気になって聞き返す。
「白龍は、私に神鎮を殺してほしかったの……?」
神鎮の家系が絶やされれば白龍たち神々も困るはずである。神を祀る者、神と人間の間を取る者がいなければ神々は力を発揮できない。神は人からの信仰を力にするためだ。人に敬われず、見向きもされなくなった神の末路は悲惨である。神と人、特に神鎮は助け合って生きている。それなのにどうしてそんなことを言うのだろう。
「まさか。お前に手を汚してほしいなどと思うわけがないだろう」
白龍が翼妃に手を翳す。濡れていた翼妃の服や髪が乾いていった。
「これからどうするつもりだ? もう廻神家へは戻れないだろう」
「それは……」
「俺と一緒に隠れ住むか? お前を傷付ける者などどこにもいない場所で」
「え?」
「俺と二人で、小さな社を建てて暮らそう。お前が二十になるまで」
頷きそうになった。それはどんなに平和な暮らしだろうと思った。あの夢の中のように、誰にも虐げられることなく、白龍や白龍に仕える女性たちと遊んで暮らす――想像しただけで楽しい。
しかしその時、異形となる間際の鹿乃子の言葉が過ぎった。
――『どうか、お幸せに』。
気付けば、翼妃はふるふると首を横に振っていた。
「……何故だ?」
「まだやらなきゃいけないことがある」
翼妃は鹿乃子にもらった貨幣の入った袋を強く握り締め、白龍から離れて山道を歩いた。白龍は人間の姿のまま玉龍大社を離れられないはずだ。龍の姿になった場合も、そう長くは外の世界に居られないと聞いている。白龍にも付いてきてほしいが、おそらくここまでだろう。
翼妃の予想通り、少し歩き続けて山を登ったところで、白龍は立ち止まり付いてこなくなった。
そこで翼妃は、白龍を振り返る。
「――白龍、どうして私を祟るの?」
白龍が僅かに瞠目した。
――すぐに否定しない。その反応を見て暗い気持ちになった。
祟りはただの仕組みではなく神の意思を介在している。どれだけ書物を読み込んでも、それを否定する記述はなかった。
幼い頃翼妃を虐めた女児を殺したのも、翼妃の家族を殺したのも、柊水の母親を殺したのも、白龍である可能性がある。できれば考えたくなかった。しかし玉龍大社のことを知るにつれて、忌み子など元々おらず、歴史の途中で神の意思でできたものだと分かってきた。
「……祟っているのは俺ではない」
沈黙の後、ようやく白龍が否定した。
「何故あの次期当主が憎い俺を殺さないと思う? 俺がお前を祟りから守っているからだ。何度生まれ変わったお前も、俺が守っている。前のお前も、その前のお前もだ」
神を殺す。そんなことが人間にできるとは思わない。しかし白龍は、神鎮であればできるような言い方をする。
白龍でなければ自分は一体誰に祟られているのだ、と思った時、不意に黒龍のことを思い出した。奥宮を不在にしている神。銀志が死んだと表現したもう一体の龍神。奥宮に近付くと頭痛がする。であれば、翼妃を祟っているのは――。
しかしそれよりも先に、気になることがあった。
「……白龍は、祟りを止められるってこと?」
「ああ」
「じゃあ、どうして、私の家族が死ぬのは止めてくれなかったの」
違和感がする。白龍は何か隠している。
「俺はお前以外の全てがどうでもいいからだ」
夜風が、白龍の卯の花色の着物を揺らした。
「お前の家族など、俺にとってただのお前の付属品に過ぎなかった」
――祟りは止まらない。白龍は祟りを止めようとはしていない。
「……さよなら。白龍」
会えて嬉しかった。ずっと会いたかった。幼い頃から白龍のことが大好きだった。けれど、翼妃と白龍の間には、根本的に埋まらない深い溝があるように感じた。人間の倫理と神の倫理は違う。
翼妃が呟いた“さよなら”には、廻神家への別れの気持ち、更に言えば玉龍大社への別れの気持ちが入っていた。
「待て!」
踵を返して走り出す翼妃を、後ろの白龍が呼び止める。
「……お前はまた、俺たちを置いていくのか」
『汝再ビ我らヲ遺しむか背信ノ者よ――』
白龍の悲しげな声と、狂った鹿乃子の声が何故か重なる。
翼妃はぎゅっと目を瞑り、振り返らずに走った。
山を超え、駅へ向かった。
重厚感の真っ黒な蒸気機関車を見るのは、十歳の時以来だ。あの時は白龍と一緒だった。初めて外へ連れて行ってくれた白龍を置いて、翼妃は一人でそれに乗り込む。裸足のまま、擦り傷だらけで入ってくる翼妃を、乗客は不思議そうな目で見てきた。
しばらくすると汽笛が鳴り、蒸気機関車が走り出す。柊水もこれに乗って帝都へ行ったのだろうか、と翼妃はぼんやりと思った。
――廻神家への復讐は終わったと言ってもいい。最も憎らしかった柊水に何もできていないことが心残りだが、それでももうあそこには戻れない。
しかし、これでは“今回の”翼妃が救われただけだ。三百年後生まれる翼妃の生まれ変わりはまた忌み子となり、祟りによって苦しむ。
そして、周りの人間も悲劇に遭う。
鹿乃子の表情を思い出し、きゅっと唇を噛んだ。
(この祟りの輪廻から脱する)
次こそ誰も被害者にしないように。
あの屋敷の書物は全て読んだ。あの屋敷でできることはもうないと言っていい。
これから行くのは五家の中の一つ、宰神家。廻神家と並ぶほど古くからある神鎮の家系だ。そこへ行けば何か手掛かりがあるかもしれない。
幸いにも、最期に鹿乃子が火の神との間に“縁”を結んでくれた。必ず宰神家の元へは辿り着くだろう。
祟りの正体を調べ、廻神家の悪しき風習を根絶する。
これが、翼妃が初めて生きる目的を持った日だった。
一緒に乗り合わせた夫婦の乗客がぼろぼろの姿をした翼妃を心配し、履き物を貸してくれた。見たことがない作りの履き物だ。異国から輸入された靴らしい。夫婦は俯く翼妃を元気付けるように積極的に話し掛けてくれた。彼女たちは翼妃が外の世界のことを何も知らないことに顔を見合わせ、何か思うところがあったようだが、事情は深く聞かずに翼妃の質問に丁寧に答えてくれた。
この蒸気機関車も開通当初は神の力を介在しなければ火の粉で火事が起こるなどと言われ反対運動が盛んだったらしい。現在の日本國は基本的には鎖国状態だが異国との交流許可も少し降りており徐々に新しい文化を取り入れている。そして、異国の人間は日本國の神々の力についてやたら調べたがっているようである――外の世界の話は翼妃にとってどれも新鮮だった。
夫婦は途中で翼妃に「文字は読める?」と聞いてきて、翼妃が頷くと新聞という物を残してくれた。彼女たちは途中で下車したが、新聞のおかげで翼妃は薩摩國へ着くまで暇を持て余さずに済んだ。
現在の年号は明平六年。二月十五日。本来ならば、柊水の長期休みがもうすぐであるはずだった。
何も知らずに屋敷へ帰った柊水はあの惨状を見てどんな顔をするだろう。
私がやったと知られたら、私は大罪人か――ぼんやりとそんなことを思ったが、罪悪感は希薄だった。
本当にただ座っているだけで薩摩國へ行けるか不安ではあったものの、何度か乗り換えているうちにいつの間にか目的の駅に着いていた。
薩摩國にはとても高い活火山があり、周囲には火山瓦斯が噴出する火山地帯が広がっている。
翼妃の目的地である火紋大社《かもんたいしゃ》はこの火山の麓にある神社で、火山信仰の中心地だ。火を司る神である鬼神を祀り、拝殿は火山岩で作られているらしい。鬼神には火山を噴火させる力があり、古くから信仰されると共に機嫌を損ねてはいけないと畏れられてきたと言う。
凸凹した道を必死に歩いて山を登った。夫婦に貰った靴がなければ苦労しただろうと思い、改めてあの二人に感謝する。
山の中腹あたりに、大きな二体の鬼の像が見えてきた。青い鬼と赤い鬼だ。どうやってこんなに鮮やかな色を再現しているのだろうと不思議に思う。その鬼たちの間にある大きな鳥居に圧倒されながら、覚悟を決めてお辞儀をし、ゆっくりと潜った。
――その時、ばちりと静電気のような痛みが全身に走った。
火紋大社はちょうど神事の準備をしている最中らしく、立派な着物を着た筋骨隆々の男女が何人も居た。彼らは翼妃が足を踏み入れた途端一斉にこちらを見てきた。中には腰に付けていた刀に手をかけた者もいた。
――警戒されている。
焦った翼妃は一歩下がり彼らの表情を窺う。あれだけ立派な着物を召しているということは、身分が高い人たち――鬼神を祀る神鎮、宰神家の者たちだろう。廻神家の神鎮たちと比べると全体的に骨格が逞しく、全員かなり体を鍛えていることが推測される。
「貴様、何故ここへ来た」
中心に立っている顔に大きな傷跡のある中年男性が低い声で翼妃を威嚇してくる。
「……私の名前は翼妃といいます。玉龍大社からここへ来ました」
“玉龍大社”という名を出した途端、ぴりっと更に場の空気が張り詰めた気がした。
「火の神は水の神を嫌っておられる。それ故我々は玉龍大社と如何なる交流も持たん」
「私は玉龍大社で龍神の贄となるために育てられた者です。そこから遥々《はるばる》、身を削って逃げてきました」
翼妃は深く頭を下げて懇願した。
「お願いします。玉龍大社で私の大切な人が死にました。悲劇の原因はおそらく玉龍大社に祀られていた龍神にあるはずです。しかし、玉龍大社に残された記録には最低限のことしか書いてありませんでした。どうか、古くからあるこの神社で、神々の歴史を調べさせてください。ここに置いて頂けるなら、宰神家が保管している書物を閲覧させて頂けるのであれば何でもします」
「貴様! 龍の手先でありながらなんと無礼な……っ!」
先程質問をしてきた中年男性の隣にいた男が刀を抜き、大きく振る。その刀の周囲には炎が生じ、風に乗って翼妃の元へと襲いかかってくる。
ここは玉龍大社ではない。火が襲ってきても水に身を浸すことはできない。大火傷をしたとしても治らないだろう――そう予感して咄嗟に逃げようとした翼妃を炎が囲み、逃げ場を奪ってくる。
――燃える、と思って目を瞑った次の瞬間、炎はふっと消えていた。
その様子を見て、ざわっと神鎮たちが騒がしくなった。顔を見合わせ、何度も翼妃の姿を確認してひそひそと互いに何か話している。
「今、火を消したか……?」
「神鎮の権利による効果を消す……そのような者が現代にいるとは聞いたことがないぞ」
「何らかの加護の気配を感じるな……あまり良くないもののようだが」
最初に話し掛けてきた中年男性が、弾けるように笑い出した。
「がっはっは! 面白い娘が来たものだ!」
そして、毛むくじゃらの太い腕で翼妃を軽々と持ち上げる。翼妃はその力強さに驚いた。
中年男性は翼妃を抱えたまま火紋大社を抜け、更に山を登った位置にある大きな屋敷に着くと、そこで待っていた使用人らしき人々に「客人だ。もてなせ」と短く伝えた。
翼妃は奥の部屋へと連れて行かれ、濡れた布で全身を拭いて清められ、食事があると言ってだだっ広い畳の間まで移動させられた。そこには神鎮たちが大勢集まっており、豪華な食事の準備もされていた。
(本当に皆、体が逞しい……使用人まで……)
失礼にならない程度にちらちらと彼らの姿を見ていると、先程の中年男性が大きな音を立てて襖を開け、どかどかと足音をさせながら入ってきた。
「酒を持って来い!」
部屋中に響き渡るような大きなその声を聞くと、使用人たちが一斉に動き出し、いくつもの酒の入れ物が並べられた。次に、他の神鎮たちの前にも何本も並べられていく。心なしか他の神鎮たちがうんざりしたような顔をしていた。
長い木の台が整然と設けられ、白い布で覆われた。台の上に食器や細工の施された箸置き、金箔をあしらった酒杯なども置かれたかと思えば、新鮮な刺身や小鉢料理が登場する。続いて、煮物や焼き物、魚介類、山菜、肉など、多彩な食材が並べられた。
「新しい仲間に、乾杯だ!」
中年男性の一声で、皆が一斉に酒を飲み始める。翼妃が戸惑っていると、隣に座った見た目の怖い神鎮が「食べろ」と言ってきたので、おそるおそる箸を手に取って焼き魚を食べた。――凄く美味しかった。廻神家の屋敷ではほぼ残飯のようなものしか食べられなかったため、こんなに食べてもいいのかと思いながら頬張った。
――数時間後。神鎮たちはべろべろに酔っ払い、全員が眠ってしまった。年齢について伝えて水しか飲まなかった翼妃と、異常な程酒に強いらしい中年男性のみが意識を保ったまま座っている。
「自己紹介がまだだったな。わしの名前は炎寿《えんじゅ》。火紋大社の当主をしている」
「……そうではないかと思っておりました」
「本当か? わし、それっぽく見えるか?」
「はい」
嬉しそうな炎寿の問いに肯定する。炎悟はこの場にいる神鎮たちに無理矢理酒を飲ませていた。その結果がこの有様だ。当主でなければ他の神鎮もこれほど従わないだろう。
「この屋敷のご夕食に私もご一緒してよろしかったのですか?」
「何を言う。これは貴様の歓迎会だ。使用人など新しい者が屋敷へ来た時の恒例行事だ、気にするな」
こんな歓迎のようなことを使用人でもしてもらえるのか、と驚く。
「……廻神家とは大違いです」
「ほう。どう異なる?」
「廻神家では若い女性ばかりを使用人として雇っていて……それも、神鎮たちの気紛れで慰み者にもなっているようでした」
言いながら、自分はそれに気付くのが遅すぎたのだと悔しい気持ちになった。
「廻神家の神鎮は美形ばかりだ。好き好んで使用人になる者も少なくないようだぞ?」
「そんなこと……! ……例えそういう人がいるとしても、私の大切な人は、そのようなことを望んでいませんでした」
鹿乃子のことを思い出し、思わず即座に反論してしまった。ご飯を用意してもらった身でありながら不躾だったかもしれないと思い、俯いて黙り込む。しばらくすると、炎寿がゆっくりと口を開いた。
「貴様、廻神家では忌み子と呼ばれていただろう」
顔を上げる。忌み子を、廻神家の風習を彼は知っているのか。
「祟りが起こらないからここを選んだ。違うか?」
こくこくと必死に頷いた。これから説明しなければならないと思っていたことを、炎寿は的確に言い当ててくる。
「言い伝え通りだな。忌み子など眉唾物だと思っていたが……そうか、本当に生まれ変わっているのか」
言いながら自身の髭を撫で、酒をまた一口飲んだ炎寿は、興味深そうに頷く。
「神鎮の力を打ち消せる人物は過去に五人いた。大昔、それこそかつての天皇が地・水・火・風・空の属性を持った神々と対話できた五家に神々を管理する役割を与えた時期のことだ。千年以上前の人物だからな、五人とも既に死亡している」
「五人……ですか」
「神を管理する社を建設し、仕組みを作る上で、統率できる者がいなければいけなかった。強大な力を手にした神鎮たちが争いを起こさないかと神々は心配し、神鎮たちに力を与える前に、その抑止力となる力を神鎮の家系の中で特に信頼した一人の人物に与えたのだ。現在の神鎮の始祖と言ってもいい人物だな」
確かに、廻神家に置かれていた書物にもそのような人物が居たとの記述はあった。其の者についての話は数行で終わっていたことと、自分とは無関係だと思ったためにそこまで気にしていなかったが。
「その始祖の生まれ変わりではないかと伝えられる人物が最初に現れたのも大昔だ。五人いたが、生まれ変わったのはたった一人――廻神家の始祖のみだった。その辺りからうちと廻神家は交流を絶っていたから、正確な情報は流れてきていないが、廻神家がその存在を何故か忌み子として扱っているという噂は聞いていた」
息を飲む。それが本当であれば、自分は元々廻神家を今の形にするために貢献した人物の生まれ変わりということだ。
しかし、神鎮たちの力に反発できるようになったのはつい昨日のこと。それ以前の翼妃には何の力もなく、ただされるがままだった。
「正直、私がその人物の生まれ変わりとは思えません」
「だが実際にうちの神鎮の権利を打ち消していただろう」
「あれはたまたまというか……」
あれはおそらく、廻神家を呪うため、毎夜自分の髪と血を差し出して黒龍に祈っていた影響だ。しかし、そんなことを言ってしまえば危険な人物と見なされてすぐに追い出されてしまうかもしれない。翼妃はそれ以上何も言えなかった。
「――貴様のその力、鍛えてみる気はないか」
炎寿が言った。
「この屋敷に置いてやることも、書物を見せることも可能だ。うちのは勉強が嫌いな奴が多くてな。ほとんどが埃を被っているだろうが……それでもよければいくらでも勉強させてやる」
「どうして私なんかにそこまで……?」
本当にここに居させてくれるのであれば有り難いが、突然やってきた身元不明の少女を預かるなど無用心極まりない。どのような考えでいるのかだけは確認しておきたかった。
「わしはこの時代にも始祖が必要だと考えているのだ。昨今の神鎮はどうも驕り高ぶっている者が多い。火紋大社の連中はわしがきちんと躾けているからそうでもないが、例えば陸奥國《むつのくに》の風属性の神鎮たちはあの地で独裁状態のようではないか? 大きな反乱が起きたのを神鎮の権利で押さえ付けたという話も流れてきておる。我々は強大な力を手にしている分、力の使い方には気を付けねばならんというのに……」
ぶつぶつと文句を言った炎寿は、翼妃を指さして結論付けた。
「貴様にはこの日本國の世をより良くできる力がある。わしがしているのは、その力への投資だ。ただの何も考えていないおっさんのお節介ではない。ゆめゆめ忘れるな」
◆
その日から、翼妃の宰神家での生活が始まった。
廻神家に残されていた書物の記述が間違いで、また周囲の人が死に始めたらどうしようと不安で毎晩なかなか眠れなかったが、何も起こらずに一ヶ月も経つとようやく火の神の近くにいれば祟りが起こらないということを信じられるようになってきた。
昼間は宰神家の屋敷で使用人と共に洗濯や掃除を任され、空いた休憩時間で書物を読んだ。
宰神家の書庫は炎寿が言っていたように埃塗れだったが、書物の量は多く、翼妃はそれを引っ張り出してきて入念に目を通した。神々にまつわることだけでなく、世間一般の学習も翼妃にとっては楽しいものだった。これまで少しも知らなかった世界が見えてくる。忌み子としての生活の中では得ることを許されていなかった学ぶ楽しみを翼妃はようやく得ることができた。
夕食後は、炎寿の希望で他の神鎮たちと訓練のようなことをした。体を鍛えたり、武道を習ったり、神鎮の権利を打ち消す練習をしたり。向かってくる炎を打ち消すのは翼妃の意思ではなく勝手に行われるようだったが、自分に向かってこない攻撃を打ち消すことも始祖ならできたはずだと言われ、その練習をした。最初の二週間は何も起こらなかったが、書物の記述通りに繰り返しているうちに、神鎮たちが出す炎の大きさが小さくなっていくのを感じた。
その辺りから翼妃は、自分が現在の神鎮の始祖であるというのは本当かもしれないと思い始めた。
銀志は翼妃の力を“黒龍の加護”と呼んだ。これと同じ単語が歴史書にも出てきて、それは廻神家の始祖が与えられた力のことを言うようだった。同様の能力は他の四人の始祖にも与えられており、例えば宰神家の始祖に与えられた力は“赤鬼の加護”と呼ばれる。
「すげーよ翼妃ちゃん、もしも他属性の神鎮が戦を仕掛けてきたとしても翼妃ちゃんが俺等の味方してくれれば万事解決だぜ!」
屋敷の筋骨隆々な神鎮たちとも徐々に仲良くなってきた。神鎮同士が戦うとなれば日本國全土が潰れかねないため、戦が起こるなど有り得ないことなのだが、大袈裟に褒めてくれる神鎮たちのことを翼妃はすぐに好きになった。
最初は玉龍大社からやってきた翼妃を警戒していた彼らも、翼妃に火紋大社への敵意がないことが分かると積極的に声をかけてくれるようになったのだ。翼妃があまりに美味しそうに屋敷の夕食を食べるためか、たまに食事を分けてくれることもある。「翼妃ちゃん、見かけによらず大食いだよな」と失礼なことを言われたこともある。
ある日、翼妃は神鎮に誘われた。
「翼妃ちゃん、温泉行かねぇ? 近くに有名な温泉街があるんだよ。今日皆で行こうって話になってて」
行きたいと言えるものなら言いたかった。しかし、翼妃の祟りは終わったわけではない。火紋大社から離れれば何が起こるか分からない。身近な神鎮たちがもし死んでしまったらと考えると、どうしてもうんと言うことができなかった。
宰神家の神鎮たちは忌み子について何も知らない。他所の属性の神社のことなど興味がなくて当然だ。事情を知らない彼らに災いについて説明する気にもなれず、黙って首を横に振った。
「話に乗ってこないなんて珍しいな。大丈夫か? 腹痛ぇのか?」
「昨日食いすぎたんじゃねーの」
「……違うし」
からかってくる神鎮を軽く睨んだ後、「今日はまだ用事があるの。また今度誘って」と言って二人の前を通り過ぎた。
祟りを完全に止める方法が見つかれば、安心して彼らと外へ遊びに行くこともできる。そういう意味でももっと手掛かりを探さねば、と思った時、いつの間にかまた大切な存在ができていることに気付いた。
――『翼妃ちゃんの大事なものは、一つ残らず奪ってあげるね』
思えばこれまで奪われてばかりの人生だった。今度こそ奪わせない、この生活と幸せを守ってみせると覚悟する。
全てを諦め理不尽を受け入れ、無気力に生きてきたこれまでと比べるとまるで別人のようだと自分でも思った。
◆
いつにも増して沢山の書物を読み寝落ちてしまった後、夢を見た。
翼妃は谷の中にある歩道の上に立っていた。真っ赤な岩肌、黄色の岩丘の裂け目から瓦斯が噴出している。周囲には風呂のような穴があり、ぐつぐつと煮えたぎる湯から白煙が立ちのぼっている。空は真っ黒で月もなければ星もない。
(ここは一体……)
恐ろしくて動けずに居ると、傍の湯で何かが動く気配がした。
そちらを見ると、湯に浸かっているのは、赤い髪と瞳をした若い男性だった。
人間の髪の色としては、見たことのない鮮やかな赤だ。直感的に思った。――これは火紋大社に祀られている神であると。
「やっと来たか、待っちょったぞ。我が名は赤鬼。貪欲を表す鬼神じゃ」
ばしゃりと音を立てて湯から赤鬼が出てくる。
突然目の前に現れた男の裸体に翼妃は驚いて目を逸らす。その様子を見てげらげらと赤鬼が笑った。
「初い反応じゃな。てっきりあん龍に手を付けられちょっもんち思うちょったが。前回ん反省を活かして待っちょったところやったんじゃろうか」
――火の神との間の縁は、鹿乃子が結んでくれた物だ。いつか会うだろうとは思っていたが、何の前触れもなかったために驚いた。
独特の訛りだ。なんと言っているのか聞き取れない部分もあった。
「温《ぬく》うなかか?」
「ぬく……?」
「暑くないか? 我には人間の感覚が分からん。死ぬほどでなければ良かが……」
確かに、夢の中だと言うのに暑さを感じる。周囲に熱湯が沢山あるためだろうか。
「我慢できるくらいの暑さなので、大丈夫です」
翼妃が言うと、赤鬼はにっこりと笑った。翼妃より身長がうんと高く体格も良い割に、幼さを感じさせる笑顔だ。
人が良さそうな印象を受けるが、その気になれば火山すら噴火させられる力を持つ神だ。翼妃はごくりと唾を飲んだ。
「お前さん、本気で龍神の祟りを断ち切る気け?」
さらりと核心に迫られた。
神鎮たちは鬼神と頻繁に交流している。炎寿辺りから聞いたのだろう。
「はい。そのためにここに居ます」
宰神家で世話になることが決まった初日、翼妃はすぐに火紋神社の本殿に挨拶をしに行った。彼に届いたかは分からないが。
ずっと目を逸らしているのも失礼かと思い、翼妃はできるだけ視線が下に行かないように赤鬼の顔を見つめた。赤鬼は、全裸のままふむと頷く。
「あれは厄介な神じゃぞ。そう簡単にはいかん。それはお前さんも知っちょっじゃろ」
「……分からないんです。私が会ったことがあるのは白龍とだけで……今玉龍大社にいないと言われている、黒龍のことは知りません」
そう言うと、赤鬼は不思議そうに目を丸くした。
「何を言うちょる? 我が厄介じゃち言うちょるんは、白龍ん方じゃ」
「……え?」
「あれが一番拗らせよるじゃろ」
赤鬼が忌々しそうに顔を歪めた。
「あの神とは気が合わん。嫌いじゃ。忌み子なんていう制度を黙認しちょっ時点で好かん」
そして、濡れた手で翼妃の頭を撫でてくる。
「今までようきばったな」
「気張る……?」
「頑張ったな、ちゅう意味じゃ」
――その時、鹿乃子に初めて包帯を巻かれた時のような気持ちになった。もう忘れた泣き方を思い出しそうになるような、そんな心地だ。
「お前さんには、我の力を授けちゃる」
差し出された赤鬼の手を取ろうとした時、ばちんと音を立てて痛みが走った。
赤鬼が面白そうに笑みを深める。
「黒龍の加護が反発してきちょっな。我の統治下であるこの薩摩の地でわずかとはいえ力を発揮できよるんはさすがじゃ。じゃが――そげん反抗されると、嫌がらせしとうなるもんじゃ。龍神が一番嫌がるであろう方法で与えちゃる」
赤鬼が一歩踏み出し、翼妃に近付いてきた。翼妃の後頚部に手が回ってきて、僅かに引き寄せられる。
次の瞬間、赤鬼の唇が翼妃に重なり――――ふっと意識が遠のいた。
◆
太陽の光が差し込んできて目が覚めた。
上体を起こし、手の平を広げる。すると、炎がぼうっと翼妃の手から出た。びっくりしてひっくり返りそうになった。
――宰神家の神鎮の権利を使えるようになっている。
まだ夢から覚めていないのではないかと疑い、何度も手を結んだり開いたりしてみたが、やはり自分の手から炎が発生するようになっていた。
(あの神様、私に宰神家の神鎮の権利を与えたの……?)
神鎮以外の人間に神の力を貸すなど全く前例がない事態だ。
これが世に知らされたら暴動が起こるのではないか。そう思ってこの事実を隠そうと決めたその時、
「うわあああああ! 翼妃ちゃん、さっきの何!?」
「翼妃ちゃんの手の平から炎が出たぞ!」
隣から宰神家の神鎮たちが騒ぐ声が聞こえた。
――宰神家では、神鎮たちと使用人が同じ部屋で雑魚寝しているのだった。
不注意で早速力を与えられたことを知られてしまい、翼妃は気が遠くなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

