
【兵庫県点字図書館インタビュー】 オーディオブックで増えた読書の選択肢。利用者ニーズに寄り添った読書バリアフリーの推進
オトバンクは、オーディオブックで「誰もが読書をあきらめなくてよい社会」を目指し「SDGs読書プロジェクト」を推進。さまざまな企業と連携しながらオーディオブックの導入を進めています。
2022年5月からは丸善雄松堂株式会社と提携し、同社の電子書籍配信サービス「Maruzen ebook Library」を通して、全国の公共図書館、大学図書館等にオーディオブックを提供しています。今回は、2020年4月から「Maruzen ebook Library」でオーディオブックの利用が始まった兵庫県点字図書館を取材。オーディオブック導入の背景や期待、活用方法などをお伺いしました。
兵庫県点字図書館とは
名称:兵庫県点字図書館(運営団体:社会福祉法人兵庫県視覚障害福祉協会)
昭和50年4月に、兵庫県点字図書館運営業務を兵庫県より受託し、管理業務と施設の運営を行っている。協会全体では、生活支援や同行援護、情報提供施設など幅広い支援・サービスを提供。兵庫県福祉センター内にある点字図書館は情報提供施設に属し、視覚による読書が困難な方が利用する施設となっている。
Webサイト:http://kensikyo.sakura.ne.jp/library.html

お二人にお話しを伺いました!
社会福祉法人兵庫県視覚障害福祉協会
事務局長 柏原 俊朗 様(写真:右)
点字図書館班 班長補佐 宮本 知穂 様(写真:左)
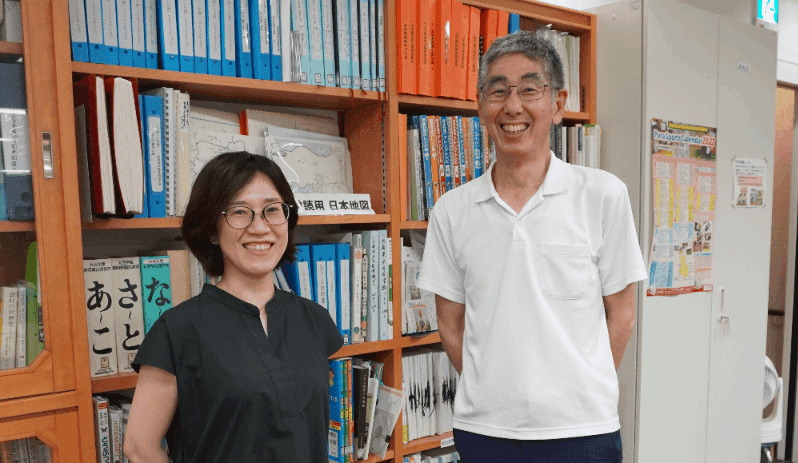
国を越えての交流が、オーディオブック導入を後押し
―点字図書館では主にどのような図書サービスを提供しているのか教えていただけますか。
柏原:点字図書館では主に「点字・録音図書」の貸し出しを中心に、オーディオブックデータの提供・対面を伴うサービス(対面朗読、触読教室等)や聴読室の提供(点字・録音図書・専門書オーディオブックの館内閲覧)も行っています。私達が提供するオーディオブックは大きく2つで、ボランティアスタッフさんの協力で自館で製作するオーディオブックデータと、丸善雄松堂さんの「Maruzen ebook Library」(以下MeL)で聴けるオーディオブックがあります。
―オーディオブックの導入はどのようなきっかけだったのでしょうか。
宮本:オーディオブックに力を入れ始めたのは2018年です。兵庫県とアメリカ・ワシントン州の姉妹提携事業のなかで、ワシントン州の全盲の副知事(サイラス・ハビブ氏)が兵庫県を訪問された際に、兵庫県点字図書館に視察に来られたことにさかのぼります。
柏原:サイラス副知事と井戸敏三知事(当時)との対談のなかで、サイラス氏が弁護士資格の勉強でオーディオブックを使っていたという話しをされたことから、導入の話が進みました。
―まさかアメリカがきっかけだったとは驚きです!オーディオブック制作は、具体的にどのようにスタートされたのでしょうか。
柏原:2019年に学術関係の書籍を中心にオーディオブックにしていこうと、私達だけでの製作は難しいので神戸大学、関西学院大学に協力いただきながら始めました。学生さんにも協力してもらっていましたが丁度、新型コロナウイルスが流行するタイミングと重なってしまいましてね・・・。
そんな時に丸善さんのMeLを知り、すでに市販されているオーディオブックがあるならそれを利用しようと専門書を中心にオトバンクさんで制作した450タイトルを購入しました。現在はオーディオブックだけで1.530タイトルを聴けるようになっています。(令和5年3月31日現在)

オーディオブックの二刀流。自館での製作とシステム導入でラインナップ数を拡充
―弊社のオーディオブックをMeLを通じて使っていただきありがとうございます!利用者さんの反応はいかがでしょうか。
宮本:貸し出しのほとんどは音声にうつってきていますね。実際にMeLでオーディオブックをいくつか聴かせていたただきました。さすがプロのナレーターが朗読しているのもあり、言葉も鮮明で聴きやすかったです。小説は物語の世界感を感じましたし、複数のナレーターが朗読しているオーディオブックもあり、聴くのが楽しかったです。これをもっと利用者さんに知ってもらって活用してもらいたいですね。
―オーディオブックを導入したメリットがあれば教えてください。
宮本:貸し出しできる本の数やカテゴリーが格段と増えました。
自館で制作するオーディオブックもありますが、図表が多い本や専門書を録音図書にするには、人の技術と時間が必要で早くお届けするのが難しいことが課題になっていたので、ラインナップが一気に拡充できたのは嬉しいですね。

―自館でもオーディオブック製作を進められているのはすごいですね。
宮本:私達が自前で製作を推進しているオーディオブックは、ボランティアスタッフさんの協力のもと、コンピュータ画像認識(OCR)を活用し、裁断した原本の内容をテキスト化して合成音声に変換したり、拡大表示したりできる特長があります。コンピュータを活用することで製作にかかる作業量を軽減させることができ、加えて利用者のニーズにあった形式で読書ができるようにもなります。

―例えば、どのような本をオーディオブック化しているんですか。
宮本:利用者のニーズとして勉強や学びに役立つ本が求められていると考えています。最近の事例だと、「日商簿記」の図書リクエストがありオーディオブック化しました。ボランティアの方が1名で、2~3か月くらいの期間で製作をしてくれて最近、利用者さんから簿記の検定に合格したという報告があり、私達も合格したような嬉しい気持ちになりました。
―すてきなお話ですね!!オーディオブック製作するうえで工夫していることはありますか。
宮本:兵庫県点字図書館の利用者以外にも利用してもらえるように、国会図書館にもデータを納めて、全国の視覚による読書が困難な方が利用できるようにしています。
生活点字の普及と音声の活用
―貴館でのオーディオブックを含む音声図書を聴く利用者の方は増えてきていますか?傾向があれば教えてください。
柏原:はい、増えてきています。貸し出しのほとんども録音図書やオーディオブックになってきていますね。
世の中の傾向として、緑内障や糖尿病などでの中途失明の方が増えています。50~60歳以上から点字を学び、読むということはハードルもあるので、録音図書やオーディオブックの需要が高くなっています。
一昔前で言えば、生まれつきや生まれてすぐの病気が元となり、目が不自由で子どもの頃から盲学校や特別支援学校に通い、点字を学び、点字を読み取ることでコミュニケーションをとる生活が主流でした。最近では医学の進歩もあって視力を回復される方も多く、盲学校や特別支援学校に通う人が減ってきているんです。
―時代の変化で、点字を読める人が少なくなってきているんですね。
柏原:そうですね。80~90歳に入ってくると昔は点字が読めても、指先の感覚がなくってきて点字を読むことが難しくなってくる方もいます。オーディオブックがあることで読書の選択肢の増えることはありがたいです。
ただ、点字を読むことができれば社会生活の質の向上、コミュニケーションの幅も広がるので、点字を守っていくことも私達の使命だと思っています。
―点字ができるとコミュニケーションの幅が広がるとは、具体的にどんなことでしょうか。
柏原:点字ができれば、自分でメモをとったり、点字で記録したことを読むことができます。例えば、会議の中で自分が発表する場面があるとします。晴眼者は資料を目で見て読むことができますし、カンペ的なメモもいれられますが、目の不自由な人たちは点字ユーザーでなければ、あらかじめ準備した資料をパソコン等でイヤホンを通して聞きながら、なぞるように話すことしかできないんです。点字ができると晴眼者と同じようにカンペ的なメモを指で読みながら話すことができるなど、便利になり、社会生活が広がります。
―点字の中でも単語だけなんとなくわかる、という状態でも生活は便利になるのでしょうか。
柏原:ちょっとした点字を覚えておくだけでも生活の幅が広がりますよ!皆さんの身の回りの生活シーンで言えば、缶ビールにある「お酒」、電子レンジの「スタート」のボタン、エレベーターの中にある「開け」「閉め」にも点字が使われています。小さいことかもしれないですが、この点字を読めるだけで、識別することができます。
大きな情報提供の流れとしては、今後「音声」が主体になってくると思いますが、点字はこれからもなくなることはないだろうと思っていますし、生活点字の普及にも努めていきたいです。

オーディオブック導入で読書の選択肢があることを伝えたい。利用者のコンシェルジュ的な存在を目指して
―点字図書や録音図書、オーディオブックなど、利用者さんにはどのようにして案内をしたり、貸し出しを行ったりしているのでしょうか。
宮本:周知方法はWebサイトのほか、隔月で「兵庫県点字図書館だより」を発行していて、録音図書・点字図書の新作を紹介しています。図書館利用のために登録している会員さんに届くようになっています。
貸し出し方法は、利用者さんはなかなか来館することが難しいので、電話やメールでお問い合わせいただき郵送対応しています。あらかじめWebサイトの情報を調べて本を指定してもらう時もあれば、電話だと「小説が読みたいんだけど、おすすめはある?時代劇的なものがいいな~」、「最近、面白い本はないか」など、ざっくりとした会話から一緒に選書するときもあります。
―職員の皆さんは、本のコンシェルジュのような存在なんですね!利用者さんの相談やリクエストを受ける中で、オーディオブックの課題はありますか。
柏原:オーディオブックで言えば、2つあります。
一つ目は、専門書に力をいれていきたいけど、視覚障がいを持つ高校生や大学生など若い人たちは、どんな本を求めているのか把握するのが課題です。ニーズを知りたいのですが、把握するのが難しい状況です。
二つ目は、図書館利用者さんは、年齢層が高めなのでパソコンや機器を使うことのハードルが高いということです。新しい機器よりかは、既存の再生機を使って気軽にオーディオブックが使えたらいいのに、という声もあります。
宮本:私たちがサポートしていきたいのですが、1回で覚えることが難しいと思うので、何度も同じ質問することがおっくうになってしまうのかもしれないですね・・・。
いろいろ課題もありますが、オーディオブックのおかげで、視覚障がい者の読書の選択肢が増えたことは良かったと思っています。点字図書、録音図書だけでなく、オーディオブックの楽しみ方を知ってもらって読書を楽しんでもらいたいです。
―私たちもその課題解決に向けてサポートできないか一緒に考えていきたいです。本日は、貴重なお話ありがとうございました!
■ 「Maruzen eBook Library(MeL)」について

Maruzen eBook Library は、丸善雄松堂が開発・運営し、学術書籍に特化した電子書籍を提供する、日本最大の学術・研究機関向け配信プラットフォームです。2023 年 7 月現在、国内・海外の出版社 300 社以上・計 16 万タイトルを超える電子書籍を取り扱い、大学図書館をはじめとする国内外の教育・研究機関・約 1,000 機関でご利用いただいています。充実した検索・閲覧機能のほか、読み上げ機能、動画配信機能、リクエスト機能なども備え、より高いアクセシビリティを実現しています。
サイト URL: https://kw.maruzen.co.jp/ln/ebl/ebl_01.html
■SDGs読書プロジェクト

オトバンクは「SDGs読書プロジェクト」を掲げ、他企業と提携し、公共図書館や学校図書館へのオーディオブック提供に取り組んでいます。
障がいの有無だけでなく、自身の好みも含め、誰もが自分に合った読書を選択できるように、今後もオーディオブックの拡大に努めてまいります!
⚫︎SDGs読書プロジェクトに関する詳細や公共図書館へのオーディオブック導入に関するお問い合わせはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
