
天文俳句(19) 山本健吉に学ぶ季語の変遷
山本健吉の『定本 現代俳句』
数年前、俳句や短歌に興味を持つようになった。その頃購入した俳句関連の本の中で印象に残っているのは山本健吉の『定本 現代俳句』である(角川選書、角川書店、1998年、図1)。山本(1907-1988)は文芸評論家であり、俳句のみならず、文学全般(古典文学から現代文学)に鋭い評論・解説を行なった人だ。『定本 現代俳句』の原著は1951年から1952年にかけて出版された。図1の帯にあるように、まさに「読み継がれて半世紀」の名著なのだ。

山本は正岡子規以降の48名の俳人を選んだ。そして彼らの俳句を紹介していく趣向になっている。そのため、現代俳句の全体像を見ることができる。この本については以前のnoteでも簡単に紹介したので参照されたい。
山本健吉の季語感
山本健吉が季語に関する本も書いていることは知っていた。『基本季語五〇〇選』(山本健吉、講談社学術文庫、1989年;単行本としては1986年に出ている)。
1000頁を超える大著!
文庫なのに3000円!
つい買いそびれて、今まで目を通したことはなかった。先日ようやく購入した(図2)。
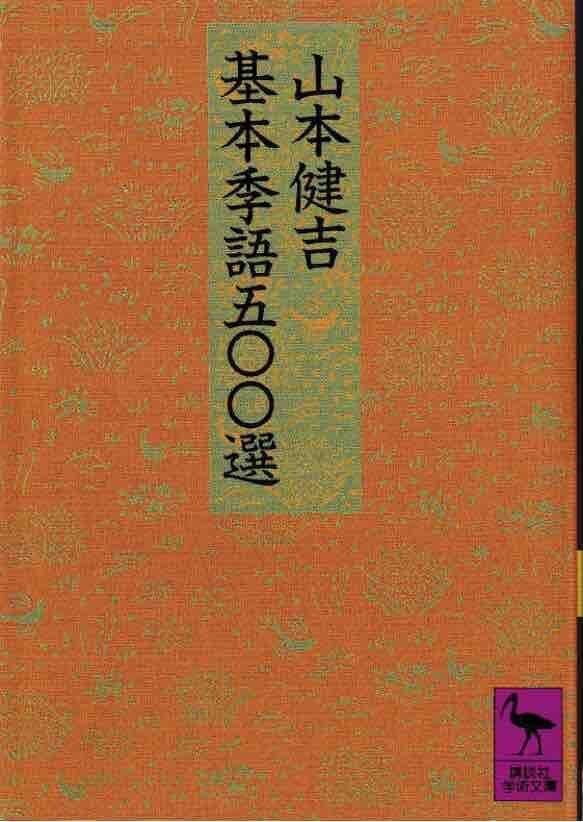
「天文」は季語の分類から消えた?
季語はいくつかの大きな項目に分類されている。時候、天文、地理、人事、動物、植物の6種類がよく使われる分類項目である。
次のnoteを参照されたい。
では、山本健吉の『基本季語五〇〇選』ではどうなっているか? 果たして6種類の分類項目なのか? と思って紐解いてみたら驚いた。なんと、14種類の項目に分けられているのだ(図3)。

14種類もの項目が挙げられていることにまず驚いた。しかし、もっと驚くべきことがあった。なんと、「天文」の項目がないのだ! ガーン・・・という感じだ。
「じゃあ、月はどの分類に入る季語なんだ?」
目次を見て分かった。なんと、気象の項目に分類されているではないか。
「天の川は?」
これまた気象に分類されている。
天文を「天の文(あや)」として、目線より上の世界のことは天文とするのが多くの歳時記で採用されているルールである。この場合、月や天の川は天文に分類されるが、厄介なことに雨、雲、風なども天文になる。つまり、気象に関わることは天文になってしまう。寺田寅彦が痛烈に批判したことだ。
俳句季題の中で今日の意味での天文に関するものは月とか星月夜とか銀河とかいう種類のものが極めて少数にあるだけで、他の大部分はほとんど皆今日のいわゆる気象学的現象に関するものばかりである。 (『科学と文学』(寺田寅彦、角川ソフィア文庫、角川書店、2019年、178頁;現代文に変更してある)
しかし、山本健吉の『基本季語五〇〇選』では逆の論理で分類している。目線より上の世界のことを、すべて気象に分類したのだ。そのため、天文が消えたのである。はたして、これは良いことなのか? 寺田寅彦は呆然とするかもしれない。
さらに発見があった。「名月」「十六夜(いざよい)」は「待宵」とともに暦日という項目に分類されているのだ。日本には古くから二十四節気七十二候という。気候と暦を結びつけた解釈がある。これに関連するものは暦日に分類されている。
「天文」の復活?
山本健吉の『基本季語五〇〇選』ではオリジナルな季語分類がされた。その結果、「天文」の項目は季語分類から消えた。
俳句では月も天の川も風景として見られている。天体物理学的な意味はない。その意味では、「天文」を廃止して、代わりに「気象」を使っても大きな問題はないのかもしれない。ただ、直観的な印象からはズレが生じる。天の川を見て気象現象だと思う人はいないし、実際、誤った理解だからだ。
書斎の本棚を見たら、山本健吉の本がもう一冊あった。『俳句鑑賞歳時記』という本だ(図4)。1993年の出版なのだ、『基本季語五〇〇選』の7年後に出た本だ。季語分類がどうなっているか調べてみると、「天文」が復活していた。「時候」「天文」「地理」「人事」「動物」「植物」。ごく標準的な6種類の季語分類になっている。この変化をどう思えばよいのだろう?

季語は季節と共に移ろう。桔梗の花が梅雨の前にたくさん見られるようになれば、桔梗を秋の花と思う人は減るだろう。気候変動によって桔梗は夏の季語になる日が来るかもしれない。また、季語の分類は項目をどう定義するかで変わる。目線より上の現象を「天文」とするか「時候」とするか、定義次第なのだ。
ふと、『平家物語』(鎌倉時代に書かれた軍記物語)の書き出しの言葉が頭に浮かんだ。
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者も遂にはほろびぬ、 偏(ひとへ)に風の前の塵におなじ。
やはり、季語も時と共に移ろうものなのだと思った。まだまだ勉強が必要だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
