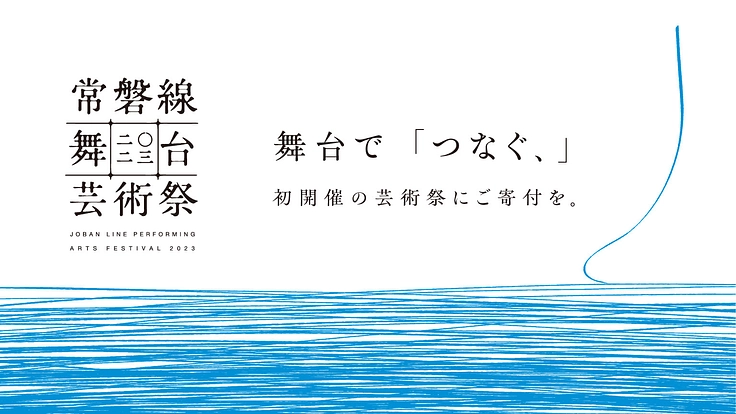常磐線、歌、つなぐ、
常磐線は、よく止まる路線だった。
私は千葉県柏市の実家から、常磐線に乗って大学に通っていた。水戸までは2時間半。教養の授業を受ける、1年生の1年間は、毎日この距離を通っていた。2年生からは県南のキャンパスに移ったけれど、入っていた大学合唱団の練習には、水戸まで通っていた。大学を出たあとも、茨城で合唱を続けた私は、引き続き実家から練習に通った。
学生時代は、同じく常磐線で通学する後輩と、電車に揺られながらよく話をした。そうやって過ごす常磐線が好きだったし、冬の寒い駅のホームで、全然来ない常磐線を「寒いね」と言いながら待つのもよい時間だった。
雨で止まる。風で止まる。雪で止まる。人身事故で止まる。目的地にたどり着けない。合唱の練習に間に合わない。あなたと会えない。常磐線は私にとって、物心両面のインフラだった。
東北地方太平洋沖地震が起きたとき、私は水戸で、大学合唱団の練習をしていた。大きく揺れた。サークル棟の練習室は、背の高い什器がなく、その揺れの大きさを理解するのに時間がかかった。窓を見ると、割れてしまうのではないかというくらいにガラスが震えていた。窓の近くにいた後輩に、「離れろ!」と言ったのを覚えている。揺れているうちに、電気が消えた。
経験したことのない大きな揺れだったとは言え、なんとなく、すぐにもとに戻れるのではないか、と思っていた。電気もなく、携帯もつながりにくい、なかなか事態の変容を把握できなかった。
常磐線が止まった。
私は帰れなくなった。電気と水が止まる中で、合唱団は数班に分かれて集団生活を送った。食料を融通しあい、各々の住まいの片付けを手分けして行った。発災から3日が過ぎ、水戸からつくばへのバスが走ることになった。私はバスとつくばエクスプレスを乗り継いで実家へ帰った。4日目のことだったか。
常磐線は4月までに上野から勝田までの運行を再開させ、県北のキャンパスを除いて、大学は4月の2週目に再開した。
東日本大震災によって、常磐線は分断を余儀なくされた。津波による沿岸部の壊滅的被害。そして、原子力災害による警戒区域の設定である。
常磐線は、なんというか、独特な路線だった。内陸を走る東北本線/新幹線と並行するように、東京都内から、利根川をわたり、茨城の真ん中を突っ切り、茨城県北部から太平洋を眺めながら、福島の浜通り、仙台平野を進み、岩沼から東北本線に入り、仙台に至る。
高校生の頃、父と二人で、青春18きっぷを使って、柏から常磐線に乗って、仙台まで行った。柏レイソルの応援のために。なぜ父と行くことになったのかは忘れたが、ともかく、常磐線は仙台までつながっていて、しかも、柏から仙台まで行ってサッカーを見ても鈍行列車だけで日帰りできた。
しかし、その長い長い線路は、地震で、津波で、原発事故で、分断されてしまった。
2017年。常磐線は、比較的線量の高い富岡-浪江間を残し、運転を再開していた。私は久々に仙台まで常磐線で行ってみることにした。富岡から浪江までは代行バス。帰還困難区域の中を国道6号線で進むバスである。車に限って通行は許されていた。線量が高いから、バスの窓は開けないように、と指示があった。途中にあるいくつものバリケードを横目に、もうこんなことはしてはいけない、と、それだけを思った。
常磐線でつながっていたものが、常磐線で断ち切られてしまった。ひとつの路線が止まるということは、そういうことなのだと思う。これまでのつながりも、これからあり得たつながりも。
常磐線が全線再開を果たした2020年は同時に、新型コロナ禍の始まりでもあった。
合唱をするようになって、一期一会のような出会いがいくつもあった。それでも、私のなかには「歌い続けていれば、また会える」という感覚があったし、「あなたにまた会うために」歌っているとすら思っていた。それが歌い続ける動機だった。
だが、新型コロナ禍は歌うことを封じた。今振り返れば、いささかセンチメンタルすぎるきらいもあるのだが、封じられたという感じだった。当時指揮をしていた合唱団があり、本番2週間前に最後の稽古を付けて、その直後に本番が飛んだ。歌手として所属していた合唱団は2020年6月に2年に一度の定期演奏会を控えていたが、3月頭の練習を最後に無期限休止に突入した。
歌い続けていれば会えると思っていた、でも、歌でしかつながっていなかった、かすかなつながりが、あっさりと断ち切られてしまった。
「等しく歳を取る」
ということをよく考えるようになった。歌を封じられたまま、私の所属する合唱団は3年間ほど開店休業状態で、最近になってようやく本格的に活動を再開したものの、アクティブな団員数はほぼ半減し、何名かは高齢から退団を決め、また何名かは亡くなった。わたしは20代から30代になった。数年会わずにいるというのは、そういうことなのだった。
原子力災害の被災地に足を運び、話を聞いても、同じふうなことを考える。2011年、50代前半で、おそらく地域の中では中堅どころであり、これからの地域活動の担い手であり、地域の将来構想をたくさん思い描いていた、そうした人たちが今、60代後半に差し掛かっている。それが12年の月日である。地域に彼らより若い人はなかなか戻ってこない。
つながりを断たれることのその重さを、あらためて考える。
「常磐線舞台芸術祭」というイベントが開かれる。その中の一プログラムとして、公募メンバーによる合唱コンサートが行われる――。
そのことを知ったとき、出なければ、と思った。それは、これが断たれた常磐線によるつながりを、歌でつなぎなおす試みのように直感したからだ。
取り戻す、とはまた違うと思う。取り戻せない時間の流れを思う。
例えば、水俣には「もやいなおし」という言葉がある。船と船をつなぐこと(舫い)、共同で何かをすること(催合う)に由来する。水俣病により分断されてしまった人と自然、人と人のつながりを、水俣の人々がともに見つめなおし、結びなおす取り組みのことを指すとされる。
一度断たれたものをつなぎなおすには、見つめなおす行為が必要だと思う。このことは小松理虔さんによる、常磐線舞台芸術祭のステートメント「手繰り寄せる、線を」にも表れているように感じる。
線を手繰り寄せた先に、何があるのか。常磐線と歌、20代の私をかたちづくってきたものを、そして私が仕事でフィールドとしている原子力災害の被災地を、今、もう一度みつめてみる。こんな、ごく個人的な動機で、コンサートへの参加を決めた。
私は合唱への参加に先立ち、常磐線舞台芸術祭のプログラムの一つである、青春五月党「JR常磐線上り列車 ―マスク―」のプレ公演を観劇した。
「マスク」の舞台となるのは、JR 常磐線の車内。
登場人物は、異なる時を生きる高校生たちである。
2020年5月15日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除された翌日、感染症対策のためにマスクを着用して登校する高校生たち。
2011年5月14日、放射線防護のためにマスクを着用し、避難先からサテライト校に通う高校生たち。
2011年3月10日、マスクを着用せずに下校する高校生たち。
出来事は過去に編入される際に正負や善悪に振り分けられがちだが、過去の今を生きる人々もまた、
現在の今を生きる私たちと同様に、これから何が起こるか全く知らされないまま未来を眼差していたのである。
彼らと私たちは、同じ時に揺られて、同じ方向に進んでいる。
『常磐線上り列車 -マスク- 』で描く時は、現在する過去である。
プレ公演は、ワークインプログレスと呼ばれる形式で行われ、平たく言えば、公開稽古のような形で進められた。日によって抜き稽古だったり、通し稽古だったり、出演者も必ずそろうわけではない。
私が観劇した日は、2幕の通し。この2幕は、2011年3月11日とは対照的に、"思い出せない"「3月10日」を、記憶をつなぎ合わせながら、演じなおす。
そこには、私が常磐線で出張先に向かう中で遭遇する高校生たちと、あるいは私が常磐線で大学に通うときにいっしょになる高校生たちの記憶と、重なる2011年3月10日の福島・常磐線沿線の高校生たちの姿があった。
戸惑いながらも普段、「震災前」「震災後」という言葉を使う。線を引いている。勝手に引いたその線を手繰り寄せたら、そこには、このプログラムの説明文にある通り「これから何が起こるか全く知らされないまま未来を眼差していた」人が立ち現れた。
断たれたと思った常磐線の中に、同じように生きている人が同居する。時空の境界線がぼやけて高校生の自分も記憶から引っ張り出される。そしてそこから今を、未来をもう一度見つめなおす。
さて、「日没、新しい夜明けに」である。第1部は詩と書と音楽によるインプロビゼーションライブ。第2部は公募合唱団と地元合唱団による合唱コンサート。
合唱団(通称「日没合唱団」)は「ツアー」として常磐線沿線の被災地をめぐり、実際に観て、感じ、考えながら、合唱曲と向き合う。企画は詩人の和合亮一さん。作品は、数多くの合唱曲のテキストにもなっている。
今回の演奏曲には、和合さんと作曲家・信長貴富さんとの協働によって生まれた「光の走者よ」「夜明けから日暮れまで」「なみえ創成小学校中学校校歌」が含まれる。加えて、原子力災害による避難で離ればなれになってしまった南相馬市・小高中学校の生徒の言葉を紡ぎ、音楽教師の小田美樹さんが作曲、信長さんが編曲した「群青」、浪江に詩の原風景があるとされる「大地讃頌」である。
今の住まいのある盛岡から、東北新幹線を経由して、仙台から、常磐線に揺られる。仕事でよく通っているコース。
8月4日、富岡駅に集合した約50名の合唱団。私が最北端で、最南端は鹿児島から。各々のモチベーションも、音楽経歴もさまざまで、ここまで多様性に富む企画合唱に参加するのは久々かもしれない。練習は、和合さんが詩を朗読し、時に作詩時の想いを述べながら進んだ。
練習中、指揮の西岡茂樹さんは何度も「歌ってから詩のことを考えていないか?」とわれわれ合唱団に問い続けた。そうではなく、風景の中にことばが、歌が立ち上がっていく。そして、時に感傷的になりすぎているきらいのあるわれわれに、詩の奥深くにある祈りへと導く。
とにかく、考えている時間が長かった気がする。本番の日、8月6日の午前中は、大地讃頌の原風景、浪江の大堀地区、群青の生まれた、小高中学校や村上海岸、津波が押し寄せた震災遺構の浪江町・請戸小学校をめぐった。時を分ける線を、生と死を分ける線のことを思う。線の先にあるものを想像する。私にはとうていわかりえないけど、ただひたすら想像する。
8月6日、合唱コンサートは日没がせまるなか、開演した。会場は双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館。ここで歌って、みんなと歌って、線を手繰り寄せてつかんだものは、手ごたえだった。
「私たちは震災から12年の歳月を経て、そして今でも、道を探していると思います。今日こうやって集まっているその意味も――私たちが、新しい、本当に小さな道でもいい。この今を生きて、この時を抜けて、この山道を抜けて、今を生きている。この手ごたえを分かち合いたい――そんな思いで今日も生きているんだと思います」
私の中の、常磐線がつないでくれていたつながり、歌がつないでいたつながり、そういうものが揺らいでしまう出来事があった。とっても脆弱な"インフラ"だと思った。心細かった。
だけど、ちゃんとつながっているじゃないか。そんなふうなことを思う。過去に起きたことをチャラにするわけではなくて、切れたように見えたものもつながっているという手ごたえ――。
この「日没合唱団」を通して、多くの人と出会って、それは刹那的な、一期一会の出会いに見えるかもしれないけど、この合唱団と別れるときに、私の中には実感として、歌い続ければまた会える、あるいは、常磐線に乗っていればまた会える、という気持ちが確かに残った。失いかけていた「つながり」への信頼が、今、この手にしっかりとある。
パーソナルな動機から始まり、たどり着いたところは、またとてもパーソナルなものだったけれど、それでいいと思っている。私ではないあなたのことを思う。想像する。このつながりの手ごたえを、その営みの中にいる人たちと、分かち合う。このごく個人的なところから始まる線が、普遍性を持って、多くの人をつないでくれるのではないか。常磐線舞台芸術祭から、たくさんの線が伸び、絡み、ほどけ、そしてつながっていく、そんな気が、今はしている。
事情は複雑そうなのですが、常磐線舞台芸術祭の運営費用は全然足りていないようなのです(!)。会期も終盤ですが、とても良い芸術祭になっていると思います。もしよろしければ、クラウドファンディング(2023年8月14日(月)午後11:00まで)にご支援いただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?