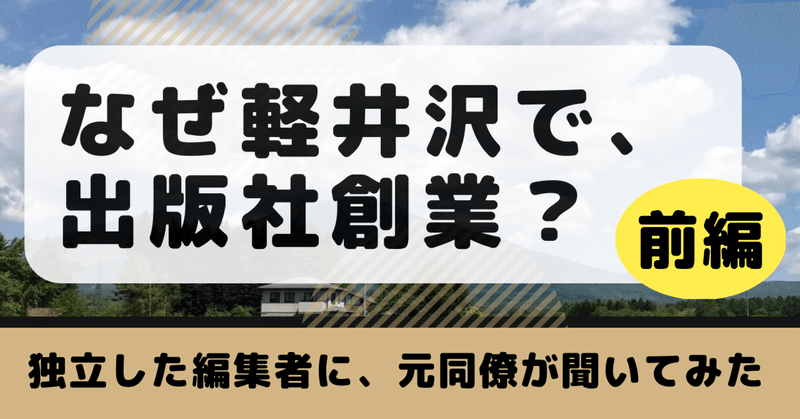
「なぜ、軽井沢に出版社をつくったの?」元同僚が聞いてみた【前編】
2022年1月、軽井沢に出版社が生まれました。その名も『あさま社』。
代表の坂口惣一さんは、2020年3月に軽井沢へ移住後、あさま社をひとりで立ち上げています。
なにがきっかけで、軽井沢に出版社をつくろうと思ったのか。あさま社とはどんな出版社なのか。元同僚が聞きました。
世田谷から軽井沢へ移住した理由
― 坂口さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
― 坂口さんとわたしは、編集者と営業という関係で、東京の出版社に勤務していました。
気になっていたことがたくさんあるのですが…まず、そもそもなぜ軽井沢に移住したんですか?
理由は、子育てです。
2016年に娘が生まれて、どんなふうに育てていけるかなと夫婦で話しあって。僕が暮らしていた世田谷区では、「中学校で私立受験をすべき」とか、「そのために小学生のうちから塾に入れて、21時まで勉強させるべき」とか、そういったムードがありました。幼稚園受験をする人も、多くいましたね。
でも僕たち夫婦は、私立の中高一貫校に入れたいとかは、思っていなくて。それよりも、大切な子どもの時代をのびのび楽しんでもらいたかったんです。
そのために東京よりももっと適した場所があるように思えて、漠然と移住を考えていました。その頃、家族で軽井沢に遊びに行く機会があって。
そのときたまたま、「軽井沢風越学園」という新しくできる学校について知ったのです。
― 軽井沢風越学園。どんな学校なんですか。
幼稚園から中学校まで、つまり3歳から15歳の子どもたちが通う学校です。敷地は2万坪以上あって、豊かな自然の中で、みんなで遊んだり、学んだりしながら、体験を積み重ねていく。
ここなら、娘にとっていい環境なのではと思いました。しかも2020年に開校するということで、娘が幼稚園に入る年とぴったり一致していて。
― ピンときた?
そうそう。でも、最終的な決め手になったのは、学校説明会での創業者の方の言葉でした。
軽井沢風越学園の学校説明会で、気づかされたこと
― 創業者の言葉とは。
「ここに預けたら大丈夫、とは思わないでください。そう考える人は合わない。たくさん失敗もすると思います」というもの。
つまり、先生だけでなく、保護者や子どもも一緒になって、失敗も視野に入れながら新しい学校をつくっていきましょうというメッセージでした。失敗すると言ってしまうあたり、僕は、すごく誠実だなと思いましたね。
軽井沢風越学園って、「つくる」ということをすごく大事にしている学校なんです。そのスタンスは、すごくいいなと思って。
創業者の方の言葉を聞くまで僕は「この学校に子どもを入れたら、子どもを成長させてくれるんでしょう?」というような、お客様的なスタンスでいたんですよ。でも、ああそうか、と。子どもも保護者も、当事者。コミュニティをよくするために、みんなで関わりあっていきたいよねと。
― 「サービスを受ける」ではなく、「つくる」へと意識が変わったということですか?
変わりました。これが僕の中では、大きな気づきでした。
というのも、この気づきが、編集者の仕事にも影響してきたからです。

「本をつくること」について、改めて考えた
―「つくる」を意識したら、本づくりが変わったということ?
そう。当時の僕は、東京の出版社で、ノルマに追われながら本をつくっていました。「年間に〇〇点の新刊を出す」という決まりがあったし、もちろん売れるかどうかは、企画段階からシビアに問われた。
本をつくるときって、まず企画書をつくって企画会議に出しますよね。そこで問われるのが、とにかくマーケティング思考。その方の過去の著作は売れているのかとか、SNSのフォロワーが何人なのかとか、類書は売れているのかとか。
とにかく、マーケットに需要があることをプレゼンで示す必要がありました。
マーケティング思考の本づくりが悪い、ということを言いたいのではないんです。本が売れていくことはとても大切。でも、そういう環境でずっと本づくりをしていると、「つくる目線」が弱くなっていくんですよ。自分がほんとうにつくりたいものを突き詰めるのではなく、売れている本を参考にして、「売れそうな本」をつくるというか。
― なるほど。
気づけば、受け身になっていました。もちろん、自分が純粋にいいと思える本をつくってはいましたよ。でも、すべてがそうではなかった。
そんなときに軽井沢風越学園のスタンスに触れたことで、自分が主体性を忘れかけていることに気づかされました。一言でいうと、今の僕は、消費に加担しているだけだなと思えてきて。
― 消費に加担。
編集者として「売れる本をどうつくるか」をつきつめると、結局「読者ってなにを読みたがっているんだっけ」とか、「どんな言葉を使うと読者が集まるんだっけ」というのを探していく作業になるんですよね。
そのセンスがとんでもなくいい編集者もいて、そういう人はヒットを連発できる。僕もずっと、そういう編集者になりたいなと思っていました。会社もそういう編集者を求めていたし。
でも、よくよく考えると、欲しがられる本、お金を出してもらえる本をつくるというのは、消費に加担しているだけという側面がある。少なくとも、マーケットに応えていたら、読者がまだ見たことのない本をつくるということはできないですよね。
風越学園への入学を決めて、軽井沢に移住するころには、そんなことを自覚するようになっていました。
― では、軽井沢に移住する頃には、退職して自分で出版社をやると決めていた?
いや、それが違うんです。
そのタイミングでは、正直ずっと会社にいようと思っていました。会社も協力的で、リモートワークを認めてくれたし、必要なときには新幹線を使っていいと言ってくれたし…。
でもたしかに、今のまま会社に所属して本づくりをしていていいのかなと、モヤモヤした気持ちもあって。
このまま東京の出版社に所属するのもいいけれど、なにか自分で始めるのもいいなという気持ちでしたね。どちらにも傾いていない、ニュートラルな気持ちは、1年くらい続きました。

自然のおかげで、意識が自分の内側に向くようになった
実は、ニュートラルな気持ちになったというのは、風越学園の影響だけでないんです。軽井沢で暮らして、自分の感覚が変わってきたことも、大きく影響しています。
たとえば軽井沢には、景観のガイドラインがあります。建物の高さが規制されていたり、チェーン店が24時間営業ではなかったり。コンビニの看板も、落ち着いた色合いになっている。東京と比べて、明らかに外部からの刺激が少ないのですが、そのおかげで、意識が自分の内側に向いてきたんです。
― なるほど。自分の気持ちにも、敏感になれたというか。
うん。実際、普段過ごしている中でも「自分は今なにしたいのかな」と丁寧に考えることが増えましたね。だから、編集者としてどうありたいかということについても、東京にいたころよりずっと考えられるようになりました。
あの時期は視野を広げてみようと思って、いろいろ動きました。
自分で書店を始めるための取次口座を開設してみたり、風越学園の保護者たちとブックイベントをやってみたり。
― 面白そう。
面白かったですよ。たくさんの人に話を聞けたし、いい出会いもあって。でも、なにをやっても単発で終わってしまっていたのが、ちょっとさみしかった。
そんなふわっとした感じで、移住最初の1年が過ぎました。このまま東京の出版社に勤めるのか、なにかを始めるのか、どうしようかなーとまだ思っていましたね。

転機になったのは、妻の言葉
― ニュートラルな時期を抜け出したのには、きっかけがあったんですか?
実は、転機になったのは、妻の一言なんです。
あるブックイベントの開催を妻と一緒に手伝っているときに、ほんとうに雑談として「軽井沢に出版社があったら面白いかもね」という話になって。
軽井沢という地場って、先ほど言ったように情報が上手に遮断されている。だからこそ、古くから文豪の避暑地になってきたわけです。そんな文化的な意味合いも含めて、軽井沢の地って本と相性がいいなと思っていて。
別に自分がやろうとかではなくて、単なる妄想として、「軽井沢出版か。いいね」なんて話していたんです。そのときに妻が、ふと言ったんですよ。
「それ、もし他の人が先にやってしまったら悔しいんじゃないの?」って。
僕はそう言われて、たしかに悔しいかもしれないと思って。なら、早く動いてしまおうと思ったのが、あさま社の始まりでした。
― 素敵。それで具体的に動き出したんですね。
最初は、まあ大変でした(笑)。長く出版業界にいたから、流通や営業についてもざっくり知っていたつもりだったんですけど、納品のことも、支払いのことも、会社をどうやって登記するのかも知らなかった。
だからいざ立ち上げが完了したときは、ホッとしました。イギリスから「世界の出版社のデータベースに登録します」みたいな連絡をもらったりして。
― そんなのがあるんですか。
あるみたいです。これでついに始まるなって、ワクワクしましたね。
けど、立ち上げたからといって、やりたいことが具体的にあったわけではなかったんです。「やったほうがいいだろうな」という感覚で、走り出していたから。
ただ、編集者としてどんなふうに本をつくればいいのかを示したいという思いはありました。
― というと?
売れるための本が、今の世の中には溢れています。でも、そこに寄せていくのではない、世の中のためになる本をつくっていこうよということ。
だから僕は、あさま社を立ち上げるときに、数ヶ月とか1年スパンで消えていく本ではなく、長く未来に残るような本をつくると決めました。わかりやすく言えば、娘が近い将来読んだときに、参考になるような本を。
そういう意味で、「みらいへ 届く本」。これをあさま社のミッションにしました。このミッションは軽井沢らしいなと思っています。長く残していくという発想を、実は僕は、軽井沢の野草から教わったんですよ。
― 野草?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▶▶後編(3月3日更新)に続きます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
