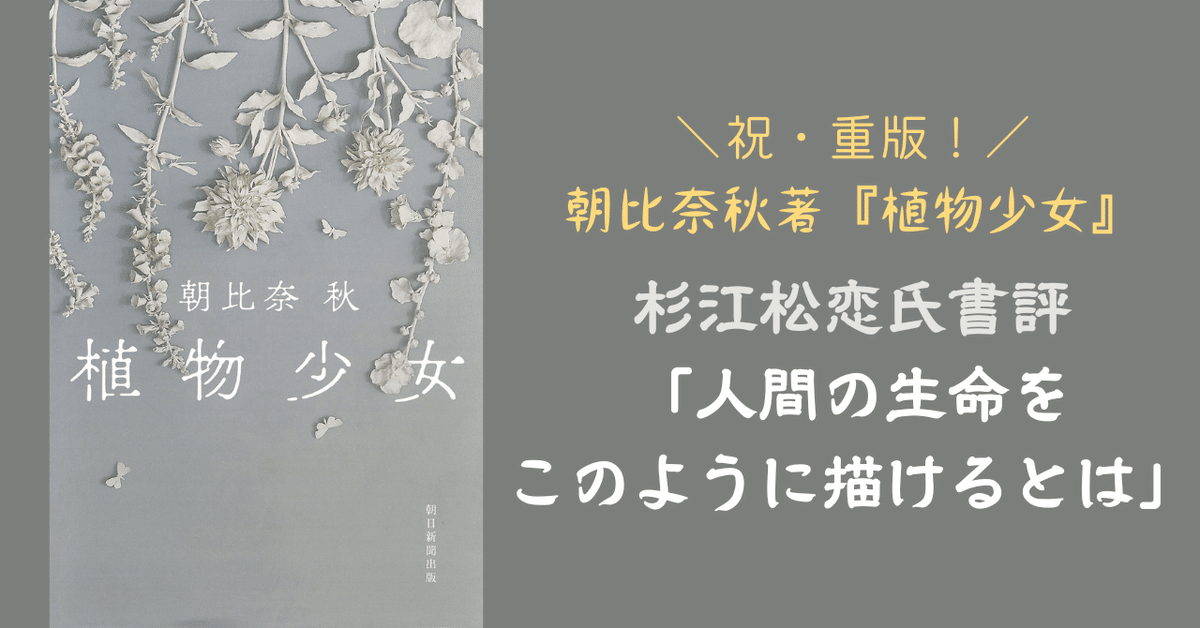
この社会の価値観の偏りを炙り出す…書評家・杉江松恋さんによる【朝比奈秋著『植物少女』書評】
「ここで描かれた母と娘の関係を称するのに、愛で結ばれたという以外の表現はあるだろうか」書評家・杉江松恋さんもこのように評した朝比奈秋さんの『植物少女』。「小説トリッパー」2023年春季号でご執筆くださった書評を特別掲載いたします。

人間の生命をこのように描けるとは
小説が息をしている。生きている。
耳を澄まし、それを聴こう。
朝比奈秋『植物少女』は三層構造を持つ小説だ。第一層にあるのは医療小説としての性格である。
朝比奈は第七回林芙美子文学賞に輝いた「塩の道」で2021年にデビューを果たし、同年に第2作の「私の盲端」(同題短篇集所収。2022年)を発表した。これは腫瘍のため直腸の切除手術を受けた大学生の女性を視点人物とする作品である。人工肛門を使用、つまり新米オストメイトとなった主人公には世界がそれまでとはまったく違ったものに見える。現役医師でもある朝比奈は主人公の目に映るものを説得力溢れるディテールで描き、それによってこの社会を成り立たせている価値観が、実は大きく偏っていることを示したのである。
『植物少女』の主人公、〈わたし〉こと高梨美桜の母親・深雪は、彼女を出産するときに脳内出血を起こした。以来生命維持に必要な機能以外、脳は死滅状態にある。いわゆる植物状態だが、作者はまず、この用語に対する読者の先入観を専門家の立場から否定してみせる。
病床の上で常に「首を左に捻ってそっぽを向」いた状態にある深雪の体はまったく動かないが、食事の時だけは別である。食べ物を載せたスプーンをあてがわれると深雪の唇はひとりでに広がり、入れられたものを咀嚼すると「まるでタイミングがわかったようにゴクッと飲みくだし」「唇をもごもごと動かして催促しだす」。そこだけ見れば一般人の食事風景となんら変わることはないのだ。第三者からすれば植物のように静止して見える患者たちの中にかけがえのない命が宿っていることがそうした描写で示されるのだ。
〈わたし〉は母親のいる病室に通い、そこを居場所として育っていく。物語は四部構成になっており、第一部で描かれるのは〈わたし〉の幼少期だ。まだ体の小さな彼女は、深雪の太腿を枕にして微睡む。2人の間に会話はないが、〈わたし〉にとって母親のそばがもっともくつろげる居場所である。深雪と呼吸のリズムが完全に同期したとき、「母がこうなってしまった経緯さえもどうでもよくなって、ただ黙って一緒に呼吸するだけにな」り、“ママの娘やから”“わたしも植物なんかも”と「声帯を使わずに」心の奥で囁くのである。第二部では美桜が成長して高校生になっている。学校の部活で不快な人間関係に巻き込まれた〈わたし〉は、母親に憤りをぶつけようとする。無言の深雪はすべてを受け止めるからだ。
医療小説としての技巧を尽くして、静止したままの深雪がまぎれもなく生きているということが示される第一層では、呼吸がモチーフとして用いられた。その下の第二層では〈わたし〉はさまざまな声に取り巻かれる。
学校で中傷に晒されて悩まされるだけではない。植物状態であり続ける深雪のことをさまざまに言う者がいる。たとえそれが同情から来た言葉であっても、〈わたし〉にとっては自分と母親の間に入ってきてもらいたくないものなのだ。父親と祖母から自分を生んで病に倒れる前の深雪について聞かされると、自分が肌を触れあわせている母親とその像が重ならなくなって〈わたし〉は動揺する。言葉は否応なく心に入り込み、時にはそれを上書きする。言葉によって失われるものがあることが第二層では示される。
静謐な小説だが、第二部では作品を覆う被膜が破れ、渦巻く感情が露呈する。声に追われた〈わたし〉は、逃れるように夜道を全力で走り、言葉が不要な呼吸だけの境地を体験する。「息だけをして生きる、この確かな実感の連続」の中に母親がいるのだとすれば、みじめでも空っぽでもないと考えることが救済となるのだ。しかし言葉から完全に解放されることはできない〈わたし〉は、再び声の渦巻く日常の中へと戻っていく。このように、第二層で『植物少女』は言語の小説という性格を露わにする。
第三層は時間の小説である。〈わたし〉はやがて成人し、自分も出産を体験する。逆に元気だった祖母は病を得て衰弱し、入院した。病院には祖母、母、〈わたし〉とその娘と一時的に四世代が揃う瞬間が訪れるのである。〈わたし〉が26歳のときに母親の寿命は尽きる。
プロローグは、〈わたし〉が葬儀屋に「生前から穏やかでいらっしゃったんでしょうね」と話しかけられ、答えに窮する場面から始まる。生前の母親を表現する言葉を持っていないのだ。本作は、〈わたし〉がその答えを見つけるまでの物語でもある。それが可能になったのは深雪が亡くなって、生の全貌が見えるようになったからだ。生命とはそういうものであり、完結しなければ誰にもそれを評価することはできない。〈わたし〉が亡き母に思いを巡らす結末は植物状態の入院患者たちが他と同様の生命を持っていることを示した病室風景とつながっていくだろう。
生命と言語、時間というものが、一人の女性を通じてこれ以上ない形で端的に示される。ここで描かれた母と娘の関係を称するのに、愛で結ばれたという以外の表現はあるだろうか。読んだ者の心に根を下ろし、いつまでもそこに居続ける。『植物少女』とはそうした小説である。
