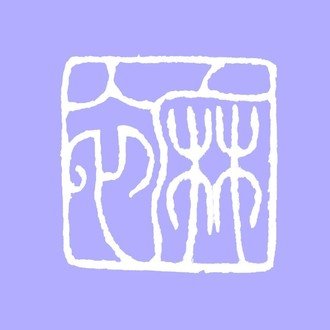ロータス
1.
カーテンを透かして差し込む朝の光がまぶたを刺した。ひどく悲しいのは夢だったのだろうか。目許に触れると睫毛が濡れていて、どうやら泣きながら目覚めたようだけれど、夢の残滓は跡形もなくかき消えて、悲しみだけが濃く残っていた。
空は雲ひとつなく晴れ渡っていた。開けた窓から爽やかな風が吹き込み、ピピピ、チチチと鳥のさえずりまで聞こえてくる。このうえなく美しい五月の朝だ。
目覚まし時計を掛けた時刻まではまだ二十分ちかくあったが、桃重はベッドには戻らず、足音を忍ばせてキッチンへ向かった。パジャマの上からエプロンをかけ、袖を捲って米を研ぎながら、これから作る予定のメニューと手順をおさらいしてみる。チーズ入りの卵焼き、ピーマンの肉詰め(蓮実は肉料理が苦手だが、挽肉は平気だ)、ほうれん草のミニグラタン、ゆかりと鱈子のおむすび。炊飯器をセットし、買っておいた食材を次々に取り出しているうちに、お茶を入れた魔法瓶もあったほうがいいかしら、と思いつく。天気が好さそうだから、飲み物は冷たいほうがいいだろうか。
恋人ができたら、お弁当を持って一緒に出かけてみたかった。何度も何度も架空のピクニックに備えてメニューを検討し、練っていたので、今日も少しも悩まなかった。でも、食べ盛りの健康な男の子はこれじゃ物足りないのかも知れない、と実際に調理に取りかかって桃重は思う。そもそも蜂屋洋介はピーマンが嫌いではなかったか。それなのにどうしてピーマンの肉詰めをメインにするつもりだったんだろう、ああ、あたしの好物だからか。何も考えていなかったんだな、まあいい、結局蜂屋洋介に弁当を手作りしてやる機会などなかった、あんな男のことなど考えるまい、蓮実はきっとおいしいと言ってくれるはず。今は蓮実に喜んでもらうことがいちばんだ。
そう思った途端に桃重は不安になった。蓮実と自然に接することができるだろうか。大学生になってからのこの一年あまり、二人で帰ることも、お茶を飲むこともなかったのだ。二人で出掛ける約束を最後にしたのは、もうずっと前のことになる。
2.
蓮実と桃重は、昨年揃って大学生になり、この春、二回生になった。
エスカレーター式に系列の女子大に進学しただけなので、大学生になったとはいえ学年が上がったという程の感慨しかなかった。何人かが「外」へ出て行き、かわりに外部生が加わるだけだ。華胥女子学院の大多数の顔ぶれは、幼稚舎から大学まで変わらない。蓮実と桃重も、そうして二十年近くを同じ学園で過ごしてきた。
尤も、お互いを認識したのは初等科の高学年に差し掛かってからで、親しく話をするようになったのは中等科になってからだった。蓮実は作文がずば抜けてうまく、学内・学外を問わずコンクールに出しては入選し、賞品の図書券を荒稼ぎしていた。朝礼でしょっちゅう表彰されるので、桃重が先に蓮実のことを一方的に知っていた。
ハスミリン。名前も、立ち姿もきれいな子。それが最初の印象だった。
蓮実は読みにくそうな岩波文庫をいつも手にして歩きながらも頁をめくり、休み時間の教室ではたびたび持ち込み禁止の音楽雑誌を堂々と広げていた。偶々その紙面が目に入って、「あ、デヴィッド・シルヴィアンだ。かっこいいよねえ」と何の気なしに桃重が呟いたのが、始まりだった。蓮実はきらりと光る目で桃重を見つめ、「ジャパンを聴くの」と問うた。
「お兄ちゃんがね。いつもでっかい音でレコードかけてるからあたしの部屋まで聞こえてきて、それで覚えちゃった。ポスター見せてもらったら、めちゃめちゃかっこよかったし」
「デヴィッド・ボウイは?」
「あ、知ってる知ってる。その人もハンサムだよね」
実のところ、桃重はそれほど真剣にデヴィッド・ボウイやジャパンを好んで聴いていたわけではなく、彼らの美貌に目を奪われた程度でしかなかったのだが、それまで事務的な会話しか交わしたことがなかった級友が自分の好きなものを知っていて、話しかけてきた喜びは大きかったのだろう。蓮実は雑誌をめくりながらいつになく饒舌に喋り、熱中しすぎてチャイムに気づかず、数学の教師に雑誌を没収されるという憂き目にあったのだった。放課後、雑誌を返してもらうために反省文を提出する羽目になった蓮実に、桃重もつきあった。蓮実がレポート用紙に心にもないことを並べ立てているあいだも、それを持って廊下を歩いているときも二人のお喋りは尽きず、職員室の前まで来て急いで声を潜めなければならなかった。
蓮実が貸してくれるレコードや本はどこかカルトな匂いがした。蓮実の偏愛している、桃重が全く知らなかった世界をわかちあうことは愉しかった。何より、蓮実が密かに書いていた物語に桃重は惹かれた。授業中にレポート用紙の手紙を回そうと蓮実を窺って、教科書の下に隠すように置いたノートに一心不乱に何かを書きつけているところを見たのだ。渋る蓮実にさんざんねだって見せてもらったノートには、二人の少年の恋とも友情ともつかない淡い感情の交流が綴られていた。少し前に流行った『ポーの一族』や『トーマの心臓』にも似た背徳的で耽美な世界観に桃重は夢中になり、熱心な読者になった。
そんなふうにして二人は親密な時間を共有してきた。高等科三年の夏までは。
昨日、三限めの授業が始まり、昼時の混雑が落ち着いたのを見計らって学生食堂に入ろうとした桃重は、窓ぎわの席に蓮実を見つけて躊躇った。学内で見かける蓮実は、座っていても歩いていても大抵ヘッドフォンを被って文庫本に目を落としていたが、このときもそうだった。たまらなく話しかけたい衝動を振り切り、桃重は足早に注文レーンの方へ行こうとした。
ちょうどそのとき蓮実がごく自然な動作で顔を上げ、二人の目線はすっと合った。桃重が動揺するより先に、蓮実が微笑んだ。桃重は吸い寄せられるように蓮実のテーブルに近づき、真向かいの席に鞄を置いた。
「久しぶり」
重たげにヘッドフォンを外しながらそう言った蓮実の声は、相変わらず低く掠れていた。今まで、背中のすぐ後ろやそれこそ俯いている目の前を通っても、蓮実は桃重に気づかないふうだった。あるいは気づかない振りをしていたのかも知れないが、だとしたら大した演技力だ。姿は日々キャンパスのあちこちで見ていたが、そういえば声を聞くのは随分久しぶりだった。
「ほんとだね。ここ、いい?」
「どうぞ。食事、これからなの?」
「うん、ちょっと買ってくるね」
蓮実は既に昼食を終えて皿を片付けたのか、テーブルにはコーヒーカップだけだった。桃重がトレイにナポリタンを載せて戻って来ると、蓮実は読んでいた文庫本に栞を入れて閉じた。
「それ、なあに?」
「君の嫌いな森茉莉」
蓮実はにやりと笑った。嫌いだなんて言った覚えは桃重にはない、ただ文体が装飾的すぎてあまりぴんとこなかったので、あたしはお父さんの文章のほうが好きかも、と言っただけだ。旅先で女を身籠もらせたあげく袖にして発狂させておきながら、まるで自分が悲劇の主人公みたいな小説を書いた男がいいの? とその場で散々に言うだけでは飽きたらず、やがて桃重本人も言ったことを忘れてしまうような些細な言葉の端々を蓮実はいつまでも覚えていて、こうしてことあるごとに持ち出す。
蓮実が持ち上げて見せた表紙は、新潮文庫の『恋人たちの森』だった。
「『枯葉の寝床』が読みたくて買ったんだけど、『日曜日には僕は行かない』が良かったよ」
「ふうん。どんな話?」
「深い仲の男友達がいるのに、何も考えずに女の子と婚約するどうしようもない男の子の話」
フォークを持つ桃重の手が止まる。桃重が今までどんな状況にあったのかを薄々察していたとしても、このタイミングで蓮実がそんな小説を読んでいるのは皮肉すぎた。
「最近はどうしているの」
追い討ちをかけるように訊ねられて、桃重は答えに詰まった。恋人と別れてようやくひと月経ったところだ、とは言いたくなかった。けれど自分の近況を話そうとすればどうしても蜂屋洋介を抜きにはできず、蓮実に話せるような出来事はなかった。
蓮実となんとなく距離ができてから、ということはつまり蜂屋洋介とつきあいはじめてから、ということなのだが、音楽を聴いたり本を読んだりしなくなった。音楽が縁で出会ったのに。高等科の二年の秋に、軽音部に所属している一つ年上の兄が文化祭でジャパンをカバーするというので、蓮実を誘って見に行った。普段、家で寝癖だらけのままごろごろしている兄を見慣れている桃重は、彼がそれなりに女の子にキャーキャー言われながらギターを弾く姿を不思議な思いで眺めたのだが、そのバンドでヴォーカルをとっていたのが、兄の一年後輩で桃重たちと同い年の、蜂屋洋介だった。
桃重が蜂屋洋介を気にかけたのは、外国の美形ミュージシャンか、そうでなければ物語に登場するクールな男の子にしか興味を示さない蓮実が珍しく彼を褒めたからだ。お気に入りの曲を軽音部の学生にチャチなノリで演奏されることを徹底的に嫌がる蓮実の前で、彼らは「クワイエット・ライフ」に加えて蓮実が大好きなデヴィッド・ボウイまでカバーしたのに。「うまくはないけど声が良いね。何とも言えない声だよね」と蓮実は頻りに言った。
洋楽は桃重の兄につきあって聴いているだけで、自分が今本当にいちばん好きなのはデビューしたばかりのサザンオールスターズだ、と後になって蜂屋洋介は打ち明けた。彼に合わせてサザンを聴くうちに、いつのまにか蓮実に教えられた洋楽を部屋でひとりで聴くことがなくなっていた。
続けているのが苦痛で、終わらせたいと願っていた関係だったのに、実際に終わってしまうと心のどこかを切断されたような痛みがなかなか消えなかった。理性とは別の部分でダメージを受けている自分に、桃重は二重に傷つけられていた。今また、蜂屋洋介以外の話題がないということが、傷口に薄く張ったかさぶたを一枚剥がす。
「……どう、っていうほどのこともない。まあまあ元気にしてるよ」
「痩せたね。少し」
「そう? ありがとう。でも、蓮ほどじゃないよ。相変わらず細いね」
蓮実はもともと細かったけれど、いちだんと痩せたように見えた。鎖骨など痛々しいほど浮いているし、肘も尖っている。長い筋ばった指にごついシルバーの指輪がはまっていた。全身黒で固めた服はワイズだろうか。
「……いいお天気だね」
話したくて仕方がなかったのに、いざ向かいあうと何を話していいかわからなくなって、当たり障りのない世間話のようなことしか言えなかった。窓の外に目をやれば、ベンチでも芝生でも学生たちが日向ぼっこしていた。眠くなりそうにのどかな土曜日の昼下がりだ。
「明日も晴れるって」
「いいねえ。ああ、どっか行きたいなあ。日曜日だし」
「行く?」
高校生の頃のようなさりげない調子で、蓮実が言った。今日、行く? 蓮実と桃重のあいだはそれだけで事足りた。毎日のようにレコード店と書店をはしごして放課後を潰したものだ。つられて、桃重も当時の気安さで応じた。
「行く行く、暇だし。でも、どこ行く?」
「そうだなあ……、せっかくだからピクニックしようか。新宿御苑なんかどう」
「行きたい!」
桃重は間髪入れずに返事をした。それは、現実に恋人ができても叶うことのなかった、夢のデートコースだった。天気の好い日に新宿御苑でピクニック。大温室を一緒に見て、芝生でお弁当を食べる。それだけのことだが、言い出せもしなかった。
「あたし、大温室にずっと行ってみたかったんだ」
「うん、前にそう言ってたなと思って」
「え? 蓮に話したことあったっけ?」
「あるよ。桃重はいつも自分で言っといて忘れるけど」
さて、と呟いて蓮実は立ち上がった。
「私、授業があるからそろそろ行くよ。詳しいことは夜電話する。……今日、家にいる?」
「うん、大丈夫」
「会えてよかったよ。楽しかった。じゃ、また」
軽く手を振ってすたすたと歩み去る蓮実の後ろ姿を、桃重はぼんやり目で追っていた。つめたく冷えきって動かすのも億劫だった体が、お湯に浸かってじわじわとぬくもってくるような感覚に、口許がふっと緩む。
布団を被ってやり過ごしていたこともある電話のベルを、その夜桃重は久々にわくわくしながら待った。蓮実からの電話は、鳴り方さえ違うようだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?