
- 運営しているクリエイター
2020年5月の記事一覧
中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説
中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] 5月22日-1965年 [昭和40年] 5月3日) 小説家・詩人・随筆家。
🔍 青空文庫 中勘助の作品
🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」(1946年改訂版 [初版は1919年])
七章、二十一章に出てくる、奈良帝室博物館 (現・奈良国立博物館) にほぼ毎朝行き、東大寺に宿泊し、當麻寺の塔の風鐸をどう思います、と聞くN君が
板蓋宮遷都 (645年5月21日 [皇極天皇2年4月28日])
板蓋宮に遷都 (645年5月21日 [皇極天皇2年4月28日])。
蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) 自害 (大化5年3月25日 [ 649年5月15日 ])
蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) 自害 (大化5年3月25日 [ 649年5月15日 ])
📖 本ブログ内関連記事「薬師寺金銅仏」
(年代推定の基準作として) 上リンク先記事で述べた「山田寺仏頭」(国宝。冒頭画像は近鉄奈良駅ビルで撮影 [19年6月20日] した模造。[本記事下部▽にもリンク有り]) は、
蘇我倉山田石川麻呂が飛鳥北東の地に創建した氏寺の山田寺 (やまだ
「三世一身の法」発布 ( 723年5月25日 [養老7年4月17日] )
三世一身の法 さんぜいっしんのほう ( 養老七年格 [修正法令] ) 発布 ( 723年5月25日 [養老7年4月17日] ) 。
開墾者から三世代(場合により一代)墾田の私有を認めた法令と言われます。
📖 本ブログ内関連記事
東大寺大仏開眼供養(752年5月26日[天平勝宝4年4月9日])
東大寺大仏 (盧舎那仏像) 開眼供養(752年5月26日[天平勝宝4年4月9日])
🔍 東大寺公式ページ「東大寺の歴史」
🔍 霊山寺公式ページ 「縁起と沿革」「16. 菩提僊那供養塔」
📝 インドの僧侶菩提僊那 (ぼだいせんな) が東大寺大仏の開眼導師を務めました。
菩提僊那供養塔がある霊山寺の名は、インドの釈迦所縁の霊鷲山 (りょうじゅせん) に地形が似ていると菩提僊那が聖武
東大寺聖武天皇祭 (5月2日、3日)
東大寺聖武天皇祭 (5月2日、3日)
前回、祭列が大仏殿前に来た時、急に雲間から日光が強く射して来たこと、
鏡池での能楽が終わった瞬間、鯉が飛び上がったことが印象的でした。
(どちらも写真に撮っています。[注1.])
昨年は本坊の天皇殿が5月2日の法要後の一定時間公開されていました (今年は行事に変更の可能性あり。後貼の東大寺公式ページ参照)。
📷 東大寺本坊 (旧東南院 [聖宝創建。国指
最澄と空海が遣唐使として入唐 (804年5月10日 [延暦23年3月28日])
最澄と空海が遣唐使として唐に入る (804年5月10日 [延暦23年3月28日])
📖 本ブログ内関連記事 (最澄創建の比叡山延暦寺)
📖 本ブログ内関連記事 (空海創建の高野山金剛峯寺)
高野山奥の院の弘法大師空海の廟堂 (墓所) に毎日、弘法大師が今も生きていると見做して食物を捧げる「生身供」のメニューに、
パスタやコーヒーなどが有るのがユニークに感じます。
多分、今のお坊さんが
法然 ほうねん (1133年 [長承2年] - 1212年 [建暦2年]) の誕生日 (5月13日) 僧・浄土宗開祖
法然 ほうねん (1133年5月13日 [長承2年4月7日] - 1212年2月29日 [建暦2年1月25日])僧・浄土宗の開祖と後世仰がれる。
(13日更新)
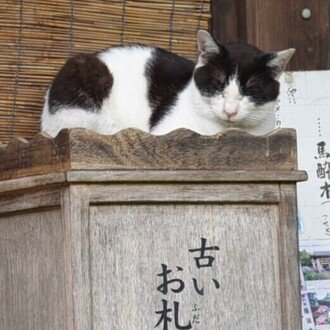

![中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41799545/rectangle_large_type_2_4556d0cef7fff55eaf8a225b9e86f7e4.jpg?width=800)
![蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) 自害 (大化5年3月25日 [ 649年5月15日 ])](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/71018679/rectangle_large_type_2_49e92b5b8c3412fdd760320b117c7e5f.jpeg?width=800)
![東大寺大仏開眼供養(752年5月26日[天平勝宝4年4月9日])](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/26697954/rectangle_large_type_2_d055692a4e30db1a97bdf4c8efe471ed.jpg?width=800)
