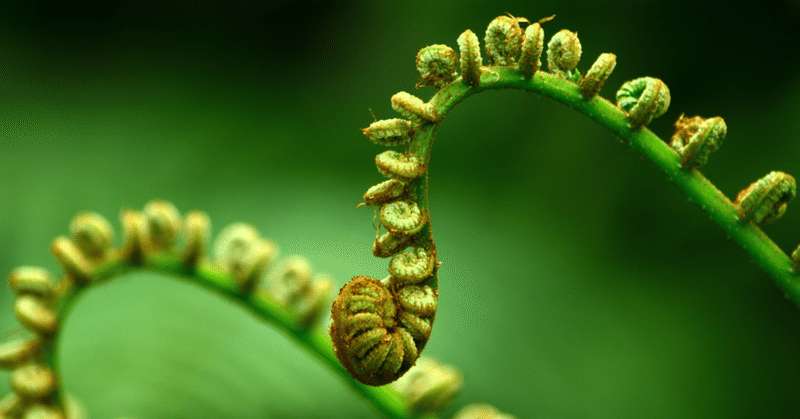
熱帯夜
2日前にエアコンが壊れたままの家で迎えた熱帯夜。
もちろん、寛げるはずがない。
修理業者にも夏休みが必要なのはわかるけど、全国的に猛暑続きのこの時期、せめて1人くらい稼働できるスタッフを用意してくれてもいいのではないか。
まあ、ここは自分の家じゃないし、家主はこの蒸し暑さをそこまで気にしてはいないようだけど。
昨年エアコン付きのアパートに引っ越す際に、今まで使っていた年季ものの扇風機を処分したらしい。
窓を開けてもほとんど風のない今夜は、いつもなら余裕で飲み干す白ワインもそれほど進まず、汗の止まらない体に必要なのはアルコールではなく、純然たる水なのだと身をもって実感する夜。
『ほんとさぁ、うち暑くてごめんね…帰る?』
絶対にイエスと言わないのを見越して、左隣から上目遣いで憎たらしい一言を放つ、5つ年下の恋人。
『帰ってほしいの?』
絶対にイエスと言わないのを見越して、部屋着の短パンから勢いよく伸びる真っ白なむちむちの太腿に指を這わせながら、一応確認する。
『…やだぁ』
軽く口を尖らせて、そう呟く彼女。
ついでに言えば、この《やだぁ》は、イコール《続きしようよ》であることも知っている。
だから、太腿に置いた左手は、当然のようにさらに内側に攻め入りつつ、この暑さでどこまで体力がもつか…そんなことを考えながら、右手で彼女の顎を引き寄せ、軽く口づける。
それからの小一時間、組んずほぐれつで互いの体内から様々な液体を放出したあと、わずかに残った気力で冷蔵庫からビールを出して半分ずつ飲み、並んで横になる。
窓は開けっ放しだったから、彼女は頑張って口を押さえていたけれど、そんな健気さをぶち壊したい衝動が沸き上がり、わざとゆっくりめに動きながらときどき口内を探るようなキスを仕掛け、合間に耳元で中の圧力や質感について具体的に囁いてやったら、堪えきれずに何度も甲高い声をあげた。
我ながら悪趣味だと思うし、おそらくちょっとした近所迷惑にもなっただろうけど、こんなやり方が一番互いを熱くさせることも知っているから、仕方ない。
…それにしても、暑い。
二人で寝るにはいささか狭いセミダブルベッドの左側で、黒いタンクトップとTバック姿の彼女が背中を向けて寝ている。
何度も舞い上がっては落ちて、体力を消耗しているのもわかるけど…この暑さで眠れるのは羨ましい。
そこそこ疲れているのに暑さで寝付けない中、Tバックから大胆にはみ出た白桃のごとき膨らみを撫で回したくなる悪戯心。
もう1回、もう1回…と、どこかで聞いたフレーズが頭の中に流れる中、さすがに今からもう1回戦仕掛けたら怒られるよな…と葛藤しつつ、いつしか自分もまた、夢の世界に片足を突っ込んでいたらしい。
若い頃に住んでいた、築30年を超える5階建の社宅。
その4階で一緒に暮らしていた2つ年上の妻と、まだ赤ちゃんの息子。
懐かしく感じながら、ふと足元に目線を移すと、全長10cmほどの赤い胴体に無数のオレンジ色の足を持つムカデのような虫が、部屋の床をゆっくりと這っていくのが見えた。
不思議と気持ち悪さは感じないが、妻も息子もなぜか全く気づいていない。
一瞬の間があった後、玄関から外に出て階段を降りる途中、短い髪の女性とすれ違う。
今のは、彼女だ。
なぜ、ここの階段を昇っている?
5秒後、彼女が玄関のドアを開けたのを目にして、慌てて引き返す。
何が起きている?
次の瞬間、耳をつんざくような大声で泣きわめく息子を抱いて走り去る彼女の姿が目に入る。
慌てて追いかけようとしたら、さっき見た赤いムカデが視界に入り、本能的な恐怖で一歩を踏み出せない。
『ちょ、待てって!』
自分の叫び声で、リアルに目が覚めた。
首から背中にかけて、びっしょり汗をかいている。
…俺は、今さら何を恐れている?
妻は、おそらく、気づいた上で放置している。
息子は今年、就職して一人暮らしを始めた。
10年前に建てた家は、今やすっかり妻と年老いた義母のための城と化しており、そこから離れた街で単身赴任中の自分に居場所はない。
だから、これでいいはずなんだ。
『…どしたの?寝れない?』
どうやら、彼女も起きてしまったらしい。
『…ごめん、なんか変な夢見てさ』
振り返って正面を向き、心配そうな顔の彼女。
『暑いからだよね…ごめんね』
『いや、大丈夫』
『ほんとに大丈夫?…あっ、いいものあった』
そう言うなり、彼女は起き上がってキッチンに向かい、冷凍庫から何かを出して持ってきた。
『アイマスク、冷やしてたの。使う?』
『…目につけるの?』
これだけ暑かったら、ないよりマシか?
ありがたく受け取り装着してみると、思いのほか瞼に密着して、視界が完全に塞がれる。
『…お!?』
見えない中で、彼女のひんやりした手が首筋に触れた。
その手は気まぐれに耳や胸の真ん中、脇腹あたりを通過して下がり、腰骨をくるくると撫でる。
『…ふふっ』
次の瞬間、思わぬ感触に声をあげてしまう。
『…えっ、氷!?』
『ぴんぽ〜ん♪』
おかしそうに笑いながらひんやりした塊を体のいろんな場所に当ててくるのだが、なにせ暑くてだんだん氷が溶けていくのか、冷たい水が体を伝ってシーツに染みていく。
『ねぇ、涼んだ?』
『てか、冷たいって…もう!』
なんだかもういろいろ我慢ならなくなり、アイマスクを外して彼女の手から氷を奪い、逆襲に入る。
『やっ、つめたあぃっ』
体をよじって逃げようとする彼女を後ろから押さえ込み、タンクトップの隙間から手を入れ、半分溶けた氷を右胸に押し当てて転がす。
『せっかく、涼しくしてあげようと思ったのにぃ』
『うん、涼しくなったから、お返ししてあげる』
再び近所迷惑な行為になるのを承知で、かろうじて形を保った小さな氷をTバックで隠れた割れ目に差し込む。
氷が溶けた水とは明らかに違うぬるみを感じ、そこを中指でゆっくりとかき回すと、彼女は口を押さえるのも忘れ、途切れ途切れに甘い声を漏らし始める。
『やっ…また、あっつくなるぅ…』
『でも、嫌じゃないでしょ?』
暑さが見せた妙な夢は、この柔らかく濡れた温もりに包まれながら上書きして、今度こそ深い眠りにつこう。
さあ、今度は、どんな風にいじめてやろうかな…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
