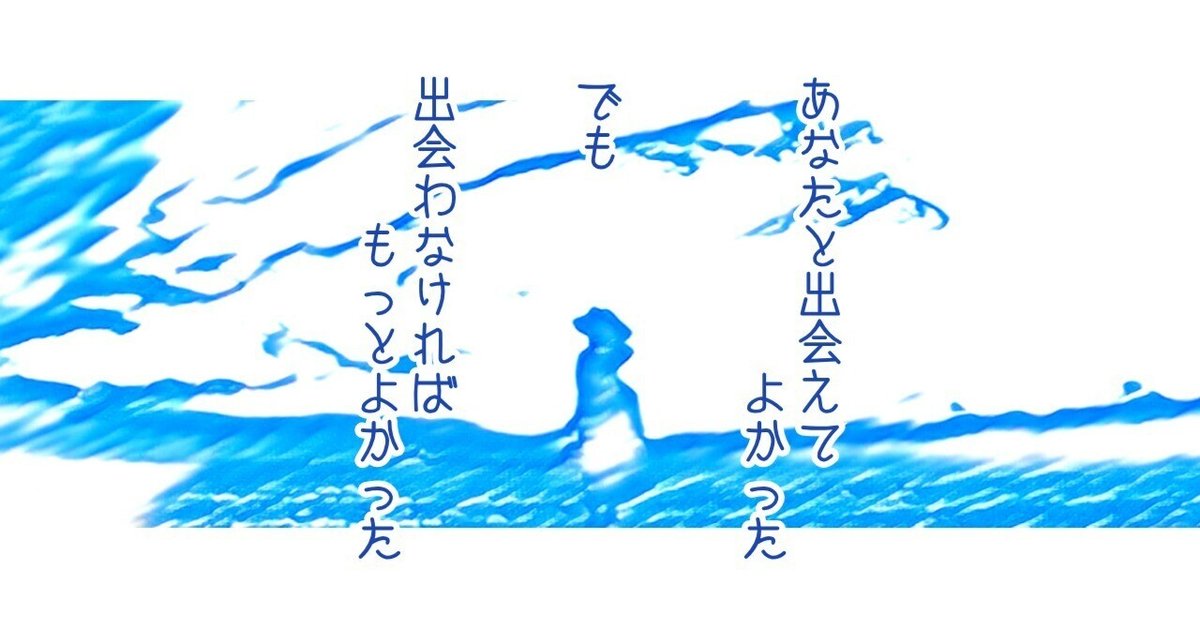
海の青より、空の青 第35話
女難の相
目覚ましのスヌーズ機能を使わずに起きたのはいつ振りだろうか。
六時ちょうどに布団から抜け出すと、すぐに朝食と身支度を済ませて玄関で靴を履く。
荷物でパンパンに膨らんだスポーツバッグを車のトランクに積み込み、自身も後部座席に乗り込んで母がやってくるのを待った。
程なくしてやってきた母に道順を伝えると、白いボディーを朝露に濡らした車は軽やかに動き出す。
「あ、お母さんあのコンビニ」
運転席と助手席の間から身を乗り出してその場所を指差す。
コンビニの軒先には、自らの背丈ほどもありそうな巨大なバッグを足元に置いた美沙の姿があった。
彼女はミーアキャットのように背伸びをしながら、辺りをキョロキョロと見回していた。
やがてこちらの存在に気づくと、まるで朝顔が花開くように笑顔を咲かせて見せ、運転席の母に向かって丁寧に頭を下げた。
「夏生あんた、友達って女の子だったの?」
母には『ついでに拾っていって欲しい友達がいる』とだけ伝えていたので、呆れ顔でそう言われるのも仕方がないのかもしれない。
「あんたが生まれた時、おばあちゃんの知り合いで占いが出来るっていう胡散臭い人に視て貰ったことがあったらしいんだけどね。その時は水難の相が出てるって言われたそうだけど。あれって女難の相の間違いだね、きっと」
日曜の早朝ということもあってか一人の客もいないコンビニで彼女を乗せると、車は学校に向けてふたたび走り出した。
「はじめまして。葉山美沙といいます。遠回りさせてしまってすみません」
後部座席の俺の横に座った美沙は、シートからわずかに身体を前に出してそう言うと、栗色の頭を小さく下げた。
ルームミラー越しに彼女を見た母は「夏生あんたやるじゃん」と一言だけ言い、ヒューとかなんとか口笛を吹いてみせる。
この手の空気は久しぶりだったこともあり、車内が一気に居心地の悪い空間へと変貌した。
そんな俺の胸中など露ほども知らない母と美沙は、ひと言ふた言の会話を交わしただけで、早速仲良くなってしまっていた。
「美沙ちゃん、うちの子の面倒見てくれてありがとね」
「面倒だなんて。それに私、ナツオくんのことが大好きですから」
――ああ。
そういえばそうだった。
美沙は俺と同じタイプの人間なのだった。
美沙の言う『好き』は母が思っているそれとは違うのだが、果たして今の会話からそれを汲み取ることのできる人間などいまい。
「あら……そうなのね」
あまりにあっけらかんとした美沙の言い様に、珍しく母が引いていた。
「夏生あんた、ケジメだけは付けなさいよ」
少しだけ声のトーンを落とした母のいうケジメとは多分、従姉のことを言っているのだろう。
ただ、それすらも母や伯母が勝手に思いこんでいるだけでしかないので、俺には取らねばいけない責任など存在しないのだが。
「ねえナツオ。けじめってなに?」
「さあ? なんのことだろうね」
嘘が苦手なだけありとぼけることも下手くそだった俺は、とにかく早く学校に着いてくれることだけを願い、車が信号に引っかからないよう神に祈りを捧げ続けた。
「夏生、美沙ちゃん。気をつけていってらっしゃい」
「うん。送ってくれてありがとう。それじゃ行ってきます」
学校の正面にある県道は、六台から連なる大型バスの列に占拠されていた。
トランクから二人分の荷物を出すとそれを両肩に下げ、集合場所である校庭まで移動する。
美沙を迎えに行く関係で少し早めに家を出たこともあり、どうやら俺たちが一番乗りだったようだった。
早朝の校庭にはうっすらと朝靄が立ち込めており、入学してから一度も見たことのない角度から校庭に差し込む陽の光と相まって、そこはかとなく非日常的な雰囲気が漂っている。
教頭と学年主任が立ち話をしていたので挨拶をし、集合時間が訪れるまで校庭の隅にある丸太のベンチに腰を掛けて時間を潰すことにした。
つい先ほどまでは元気いっぱい夢いっぱいな様子であった美沙だが、ここに来て急に眠たそうに目を擦りはじめる。
「ナツオごめん。ちょっとだけ寝ててもいい?」
そう言うやいなや、彼女はさも当たり前といったふうに俺の肩に体重を預けてくる。
「ちょっと美沙マズいって流石に! 教頭と学年主任いるし!」
焦りまくる俺を尻目に、すでに彼女は夢の中の住人と化していた。
俺は今しがた祈りを捧げたばかりの信号機の神に、今度は教頭がこちらを振り向かないよう心のなかで一際熱心に手を合わせる。
そんな俺の願いが通じたのかは定かではないが、教頭と学年主任は互いに礼をすると校舎の方へと去って行った。
自身の日頃の行いに感謝していた時だった。
教頭を見送っていた学年主任が突然振り返り、そしてバッチリと目があってしまう。
距離にして、おそよ三〇メートル。
俺は今までの人生であまりしたことがない作り笑いを浮かべると、学年主任に向かって首を小さく傾げてみせる。
お嬢様の挨拶のような俺のその行動を彼がどう受け取ったのかはわからないが、苦笑いをするとハエを追い払うように二度手を振り、教頭の後を追いかけるように校舎の方へと歩いていく。
どうやら今度こそ俺は助かったようだった。
「……疲れた」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
