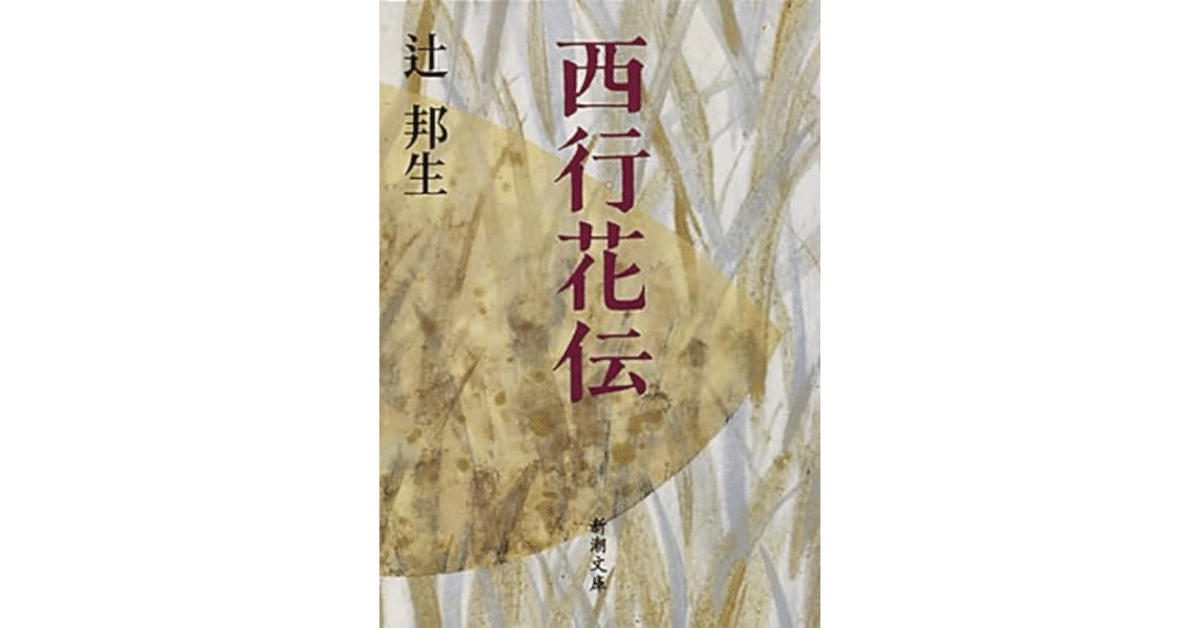
辻邦生『西行花伝』ー西行の桜と月の歌物語
『西行花伝』辻邦生 (新潮文庫)
【谷崎潤一郎賞受賞作】不世出の天才歌人、西行の生涯を多彩な音色で歌いあげた交響絵巻。全身を震わせ全霊を賭けた恋だったのに。
花も鳥も風も月も――森羅万象が、お慕いしてやまぬ女院のお姿。なればこそ北面の勤めも捨て、浮島の俗世を出離した。笑む花を、歌う鳥を、物ぐるおしさもろともに、ひしと心に抱かんがために……。高貴なる世界に吹きかよう乱気流のさなか、権能・武力の現実とせめぎ合う“美”に身を置き通した行動の歌人。流麗雄偉なその生涯を、多彩な音色で唱いあげる交響絵巻。谷崎潤一郎賞受賞。
辻邦生が書いた西行の歌物語。『源氏物語』から『平家物語』へ橋渡しする西行の歌を中心とする歌物語。藤原秋実(西行を尊敬する弟子のような僧)が西行の生まれ故郷紀の国の乳母(92歳)を訪ねて西行の幼い頃のエピソードを聞き書きするところから始まる。
乳母は蓮照尼だが乳母時代の呼び名は「葛の葉」という。谷崎潤一郎『吉野葛』を意識しているのか、『吉野葛』が西行のことも描いていたのか(そこは記憶がさだかではない)。多分辻邦生『西行花伝』の方が後の作品なので、谷崎を意識したのだろう。それは母恋いという話を含んでいるからだか?
母方の血筋が今様の師範の祖父と伝説的遊女(今様舞)の娘である母の舞と祖父の舞で芸能の血を引いていることと父は奥州藤原家の血筋であることが描かれる。
藤原秋実が西行(義清)が出家の理由とした亡き友佐藤憲康の霊を黒禅尼に呼び出して西行の少年時代を語ってもらう。黒禅尼は芥川『羅生門』に出てきそうな乞食婆だった。義清の天才的な運動神経と母思いの気持ち。そして母の死。桜は『源氏物語』の世界の歌であり雅な貴族社会、月は『平家物語』の歌世界で貴族社会から武士の世の中になりかつての雅の世界も滅んでゆく。歌で世界を変えるというのが仏教的で、現実世界があまりに惨いから幻想世界に逃避するというような感じで読んでしまう。それが西行の末法思想で歌=仏の道というような。
藤原秋実が西行の親友の僧西住から母を無くしてから鳥羽院の北面の武士になるまでの経緯を語る。前半は鳥羽院の妻であり崇徳院の母である待賢門院との愛(桜)の物語なのだ。
西行は西住と知り合い母の喪失の悲しみを自分本位のものとして反省する。そして流鏑馬の極意を教えた源重実を通して、貴族と武人が交わる雅な世界へ(影響された様々な人物が出てくる)。そこで歌会を通して貴族の娘たちとも交流するようになる。そして、後鳥羽上皇の北面の武士に徴用されてゆくのだった。
母方の血筋が今様の師範の祖父と伝説的遊女(今様舞)の娘である母の舞と祖父の舞で芸能の血を引いていることと父は奥州藤原家の血筋であることが描かれる。
堀川局の聞き書き。西行の和歌の師匠でもある源顕仲の娘。
白河院の破廉恥な様子とか、鳥羽院の関係とか暗部を語る。そういう権力世界に嫌気が差して歌の力で鳥羽院を支えるという西行。その西行と清盛が同時代で同じ北面の武士として知り合っていたとは知らなかった。清盛が力こそすべてであるというのに対して西行はそれは虚しい(虚無)であるという。そこはフィクションなんだろうけど、清盛と西行が同じ職場(北面の武士)として同僚(親友とは言えないかもしれない)だったのは興味がある。
鳥羽院に仕えていた西行は歌の力で鳥羽院を支えたいということだった。それは現実世界は幻想だから、確かな言葉の力(真言?)で歌として土台を作るのだと言っているのだが、出家したあとも性欲は断ち切れないでいるようだ。ただの歌僧としての西行なのかと思ってしまう。
散るを見で 帰る心や 桜花 昔にかはる しるしなるらん 西行
皇族の歌会の上座に招かれてありがたやみたいな。そこで藤原俊成と知り合うのだった。
花に染む 心のいかで 残りけん 捨て果ててきと 思ふわが身に 西行
女院(待賢門院璋子)の絶頂と凋落が桜の鑑賞会で描かれる。
西行が語る観桜の宴での待賢門院(たいけんもんいん)璋子との出来事。この女院がとんでもなくエロスの女王という感じで白河院と関係して崇徳を産ませたり(鳥羽院の后なのだ)、そんなこところに西行の雅な愛欲の世界が浮島の世界のように漂うのである。
一方で平清盛の言う武力の世界があるのだが、清盛が言うには見えざる力というもの(神の力のような)に支配されているから、なかなか権力者(公家)たちは侮れないというのだ。それに同調したかに見えた従兄弟の憲康の突然死。それが出家の理由だという。
いざさらば盛り思ふもほどもあらじ藐姑射(ほこや)が峰の花にむつれし 西行
「藐姑射(ほこや)が峰」は流鏑馬などをしていた北面の武士時代か?花は院の観桜の宴の思い出だろうか?そういう雅な生活を捨てて出家しようというのである。
捨てがたき思ひなれども捨てて出でむまことの道ぞまことなるべき 西行
柴の庵(いお)と聞くはくやしき名なれども世に好もしき住居(すまひ)なりけり 西行
知らざりき 雲居のよそに 見し月の かげを袂に 宿すべしとは 西行
捨てしをりの 心をさらに 改めて 見る世の人に 別れ果てなん 西行
出家の辛さを歌っているのだが、泣いてすがる娘を足で蹴り上げたという伝承の元になった歌だろうか?『西行花伝』にはそのシーンは出てこない。この歌から導かれてくる話は女院(藤原璋子)との愛欲と彼女の立場の問題で鳥羽帝に新后に藤原泰子が来て、女院の立場が危うくなるのだ。このへんの天皇家のドロドロした関係性はわかりにくい。源氏物語でもそうだが天皇の権力の移行が複雑だった。権力争いの醜い部分であり、それが北面の武士として仕えていた義清(西行)の出家の理由かもしれない。
惜しむとて 惜しまれぬべき この世かは 身を捨ててこそ 身を助けめ
西行藤原清隆が女院御所別当になると、女院が帝の妃を呪いをかけていると噂がひろがり、女院の立場が悪くなる。女院は引きこもって読経などの日々を過ごす。西行はかつての花の宴での一夜を思い出すのだった。
(女院)
今日ぞ知る 思い出でよと ちぎりしは 忘れんとての 情なりけり
(西行)
おもかげの 忘れるまじき 別れかな 名残を人の 月にとどめて
西行は女院が忘れがたく、出家したのも女院との関係を断ち切る為だったが思うように行かなかった。
恋しさや 思い弱ると ながむれば いとど心を くだく月影 西行
堀川局(待賢門院堀河)が語る女院(藤原璋子)の最期。後鳥羽院が新しい后を娶り過去の后となって、いろいろな陰謀も渦巻く世界に出家を決意する。堀川局も出家する。そして女院が亡くなり堀川は最期まで看取った女御だった。
君こふる なげきのしげき 山里は ただ蜩ぞ ともに鳴きける 堀川
女院が出家したときに堀川の妹の兵衛は出家せずに女院の娘の統子(むねこ)内親王の女御になった。そのあっけらかんな性格が西行に好かれる。また歌人としても姉に劣らず歌も上手かった。
(中納言尼ー女院と共に出家した女御)
山おろす 嵐の音の はげしさを いつならひける 君がすみかぞ
(兵衛)
うき世をば あらしの風に 誘われて 家を出でしに すみかとぞ見る
出家しても歌会が開かれ西行はそこに誘われることも多かった。
春風の 花を散らすと 見る夢は さめても胸の さわぐなりけり 西行
その頃に崇徳院とも出会う。崇徳院に対しては鳥羽院の新しい后と執権の策略が行われていたのだった。鳥羽院と崇徳院の争いは崇徳院の母(女院)も絡んでの政権争いでもあった。そして女院が亡くなる。
(堀川)
限りなく 今日の暮るるぞ 惜しまれる 別れの秋の 名残と思へば
(崇徳院)
限りありて 人はかたがた 別るるとも 涙をだにも とどめてしがな
(兵衛)
散り散りに 別るる今日の 悲しさに 涙しもこそ とまらざりけり
(崇徳院)
ありがたき 法(のり)にあふぎの 風ならば 心の塵を 払へとぞ思ふ
(西行)
ちりばかり 疑ふ心 なからなん 法(のり)をあふぎて 頼むとならば
そして西行はまた旅立っていくのである(みちのく一人旅か?)。
鈴鹿山 うき世をよそに ふり捨てて いかになりゆく わが身なるらん 西行
女院が亡くなって陸奥一人旅にでる西行なのだが、無目的なわけではなかった。奥州藤原氏の藤原秀衡に会いにいくのだった。
都出でて 逢坂超えし をりまでは 心かすめし 白川の関
そこで一人の自害しよとする女を助けるのだが、また西行の助平心が起きたというわけでもなかった。
白川の 関屋を月の もる影は 人の心を 留むるなりけり
その女の夫は清原通季(みちすえ)という武官(国衙使)であり藤原氏の領地を攻めてきたのであった。その時に西行が幼少の頃に出会った氷見三郎と諍いになり討たれたという。西行の従兄弟である佐藤憲康が加勢に行く前に病死した因縁があったのだ。そんな武力の時代よりも藤原秀衡は西行のように出家して歌僧にでもなりたいと西行に告げるのであった。
年月を いかでわが身に おくりけん 昨日の人も 今日はなき世に
語り手が西行を尊敬する寂然と寂念の兄弟僧になり、崇徳院の保元の乱が語られる。西行の歌の師匠藤原為忠の四兄弟は西行と親友なのだが、彼らも西行の考えに惹かれて出家している。その四兄弟の寂然の語り。鳥羽院と新院(崇徳院)との争いはますます激しくなって、ついに鳥羽院が崩御すると新院への風当たりが強くなる。新院は近衛天皇の崩御で自分の息子が天皇になることを望んだが、後白河天皇になり信西の策謀でますます立場が悪くなり、時代も貴族社会から源平の武士争いもあり、天皇側には平家(清盛)が付き、新院には源氏に警護されることから立場を悪くしていく。
最初は桜(自然)=雅な世界を支えていくということだったのだが、後でそうした桜の世界から山奥の世界へ、島流しになった崇徳院を諌める役なのだが、怨念化して鬼(天狗)になると西行も手がつけられなくなってしまう。『源氏物語』でも「もののけ」は重要な概念らしいが、崇徳院という怨霊伝説を物語を組み込んでいて、息子を帝に出来ない無念さが自身を歌よりも欲望へと向かわせるのだった。+
崇徳院が狂気に陥っていく(天狗になったとか)。これは有名な絵にもなっていた。
崇徳院と西行の歌のやり取り
(崇徳)
みづぐきの 書き流すべき かたぞなき 心のうちは 汲みて知らなん
(西行)
ほど遠み 通ふ心の ゆくばかり なほ書き流せ みづぐきの跡
「みづぐき」は水茎という木で手紙を付けることから手紙の枕言葉になったという。崇徳は心乱れて西行に救いを求めたのだろう。西行は山におり修行中だった。その後に西行の高野山での「山深み」10首があるのだが、それは歌に導いてくれた徳大寺実熊が亡くなったことの歌で、まだ崇徳院は讃岐で生存していたのだが、西行は新院を歌で守るといいながら態度が冷たいような気がする。しかしその山の歌こそ、西行が貴族の宮廷歌から僧侶の山の歌への変化として読めるのかもしれない。山を降りて新院のことを尋ねるが新院はすでに天狗になっていた。それから間もなく新院が自害する。
その前に西行が讃岐へ尋ねたときの新院との歌のやり取りがあった。それが百人一首に入った崇徳院の歌なのだが、史実ではこのとき読まれたのではないという。
(崇徳院)
かかりける 涙にしづむ 身の憂さを 君ならでまた 誰か浮かべん
(西行)
ながれ出づる 涙に今日は 沈むとも 浮かばん末を なほ思はなん
新院は欲を捨てきれなかった。西行は末法を説く僧侶として新院に返しているのだが、それは新院には届かず怨霊となっていく。
そこで自然と一体化する歌を秋実に語る。月と桜の歌だ。
ゆくへなく 月の心の すみすみて 果てはいかにか ならんとすらん
吉野山 こずゑの花を 見し日より 心に身にも そわずなりにき
そうした自然との一体感が仏性なのだと説く。歌はその手立てであり、そうした生命の源も保存する力なのだという。歌無き宮殿はもはや傀儡師(執権政治か)に操られたものでしかない。歌の世界こそが真実なのだという。これは歌に現を抜かしていたから政治力を失っていったのだと思うが、逆転の発想だよな。歌こそすべてだという歌の政治なのだということか?
新院が自害した後に残された新院の第二子・宮の法印を語る。その印象が『源氏物語』の若紫と重なる。新院の崩御の後出家したのだった。
(宮の法印)
あくがれし 心の道の しるべにて 雲にともなふ 身とぞなりぬる
(西行)
山の端に 月すむまじと 知られにき 心の空に なると見しより
そして宮の法印から、新院が大乗経を血書している知らされ西行は新院が怨霊に乗っ取られたと知る。新院は歌の世界ではなく怨霊の世界にいるのである。そして死後に怨霊の魂を鎮めるために白峰に旅立つのだ。
よしや君 昔の玉の ゆかとても かからん後は 何かかはせん
西行が讃岐院(新院)の墓に捧げた歌。
その権力が美よりも武力に移行していく時代の物語だった。『西行花伝』はそうした貴族社会の怨念を鎮める文学というもので、『平家物語』にも通じていると思う。その中で西行が歌によって雅な世界を築くということは、桜のように散ってしまう世界でありながら月影に照らされた自然と一体化していく鎮魂の歌なのだろうと思った。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
