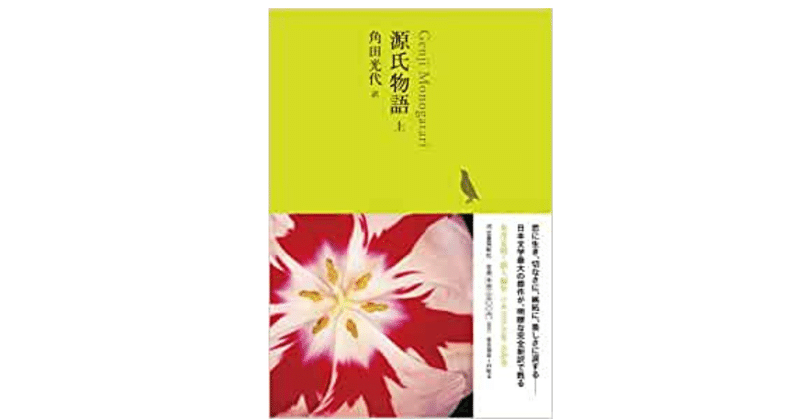
推しは明石の君か源典侍か?
『源氏物語 上 』(翻訳)角田光代(池澤夏樹=個人編集 日本文学全集04)
恋に生き、切なさに、嫉妬に、美しさに涙する――
日本文学最大の傑作が、明瞭な完全新訳で甦る!
<原文に沿いながらも現代的な自然な訳文で、もっとも読みやすく美しい角田訳の誕生。
上巻には、第一帖「桐壺」から第二十一帖「少女」まで、たっぷり二十一帖分を収録! >
世に優れて魅力ある男の物語が、たくさんの登場人物を連ねて際限なく広がる。その一方で人の心の奥へも深く沈んでゆく。いうまでもなく日本文学最大の傑作。――池澤夏樹
とりかかる前は、この壮大な物語に、私ごときが触れてもいいのだろうかと思っていた。
実際にとりくみはじめて、私ごときが何をしてもまるで動じない強靭な物語だと知った。
――角田光代
解題=藤原克己(国文学 東京大学)
解説=池澤夏樹
月報=瀬戸内寂聴
大和和紀
帯写真=荒木経惟
<出版社から>
【角田光代訳『源氏物語』は、何より読みやすさと、昔も今もつながる感情を重視! 】
角田訳は、物語としての面白さが堪能できる『源氏物語』です。これまでの現代語訳で挫折した方も、この角田訳なら必ず最後までたどりつけることをお約束します。
【読みやすさの工夫を凝らした角田訳の特徴】
●原文に忠実に沿いながらも、読みやすく、感情に引きつけて読める自然な訳文
●主語を補い、地の文の敬語をほぼ廃したことで、細部までわかりやすい
●現代的で歯切れがよく、生き生きとした会話文
●作者や第三者の声(草子地)を魅力的に訳して挿入
●和歌や漢詩などの引用はほぼ全文を補って紹介
平安時代中期の11世紀初めに紫式部によって書かれた『源氏物語』は、五十四帖から成る世界最古の長篇小説。輝く皇子として生まれた光源氏が、女たちとさまざまな恋愛を繰り広げる物語であると同時に、生と死、無常観など、人生や社会の深淵が描かれている。四百人以上の登場人物が織りなす物語の面白さ、卓越した構成力、細やかな心情を豊かに綴った筆致と、千年読み継がれる傑作。上巻には一帖「桐壺」から二十一帖「少女」まで、光源氏の誕生から若き日々を描く。
【目次】
桐壺(きりつぼ) 光をまとって生まれた皇子
帚木(ははきぎ) 雨の夜、男たちは女を語る
空蝉(うつせみ) 拒む女、拒まぬ女
夕顔(ゆうがお) 人の思いが人を殺める
若紫(わかむらさき) 運命の出会い、運命の密会
末摘花(すえつむはな)さがしあてたのは、見るも珍奇な紅い花
紅葉賀(もみじのが) うりふたつの皇子誕生
花宴(はなのえん) 宴の後、朧月夜に誘われて
葵(あおい) いのちが生まれ、いのちが消える
賢木(さかき) 院死去、藤壺出家
花散里(はなちるさと)五月雨の晴れ間に、花散る里を訪ねて
須磨(すま) 光君の失墜、須磨への退居
明石(あかし) 明石の女君、身分違いの恋
澪標(みおつくし) 光君の秘めた子、新帝へ
蓬生(よもぎう) 志操堅固に待つ姫君
関屋(せきや) 空蝉と、逢坂での再会
絵合(えあわせ) それぞれの対決
松風(まつかぜ) 明石の女君、いよいよ京へ
薄雲(うすぐも) 藤壺の死と明かされる秘密
朝顔(あさがお) またしても真剣な恋
少女(おとめ) 引き裂かれる幼い恋
訳者あとがき
解題 藤原克己
解説 池澤夏樹
感想
読みやすいということなのだが、本の分厚さと携帯性がないのでほとんど与謝野晶子訳で読んでいた。ただ最初に系図と和歌が翻訳されているのでそこは参考になった。それと、あとがきと解説ですね。
角田光代は『源氏物語』にそれほど思い入れもなく、池澤夏樹の「日本文学全集」の編集方針である古典の新訳ということで今回の『源氏物語』の翻訳となったようだ。その選択眼として、角田光代のエンタメ性の読みやすさや感情表現の上手さにあったと思う。それは『源氏物語』を物語よりも小説として楽しむことにあったと思う。かく帖は短編小説としての、おもしろさとして読むことが出来るのではないか。
与謝野晶子は『源氏物語』に思い入れもあり、自身の『源氏』論もあるような感じだったのか、光源氏には厳しいようである。まあ、そういう読み方をしていたわけだが。
与謝野晶子『源氏物語』
『源氏物語』和歌
『源氏物語』は歌物語と言われているように和歌は登場人物の内面の発露であり物語の中でも重要である。
全部は無理だから、重要な和歌だけでも。
桐壺(光源氏の母親)が帝の宮中に入ったが娘が亡骸となって戻ってきた。桐壺の母親の和歌が帝に対する精一杯の抵抗のようで胸を打たれる。
いとどしく虫の音しげき浅茅生に露おき添ふる雲の上人
光源氏が空蝉のもとへ空蝉の弟である小君を遣わして姉との取次を計る。その時に交換される和歌。
(光源氏)
帚木の心を知らでそのはらの道にあやなくまどひぬるかな
(空蝉返し)
数ならぬふせ屋におふる名の憂さにあるにもあらず消ゆる帚木
「空蝉」のタイトルにもなった和歌。
(光源氏)
うつせみの身をかへてける木(こ)のもとになほ人がらのなつかしきかな
(空蝉の返し)
うつせみの羽に置く露の木隠(こがく)れ忍び忍びに濡れる袖かな
「夕顔」のタイトルになった和歌。
(夕顔)
心あてにそれかと見る白露の光そへたる夕顔の花
(返し、光源氏)
寄りてこそそれかと見めたそかれにほのぼの見つる花の夕顔
中将の君(「朝顔」と呼ばれる光源氏のいとこ『朝顔』参照。)を朝顔に例えて光源氏との相聞歌。朝顔は高貴なお方で、夕顔は中位の妻。
(光源氏)
咲く花にうつるてふ名はつつめども折らで過ぎうきけさの朝顔
(中将の君の返し)
朝霧のはれまも待たぬけしきにて花に心をとめぬとぞ見る
その後の夕顔との逢引。
(光源氏)
夕露に紐とく花は玉鉾にたよりに見えしえにこそありけれ
(夕顔の返し)
光ありと見し夕顔の上露はたそがれどきの空目なりけり
夕顔が亡く怨霊に憑かれて亡くなったばかりなのに、「空蝉」との相聞歌を交換している。どういう神経をしているのだ、この男は。寂しさを紛らわすために女を利用しているしか思えん!
(光源氏)
空蝉の世はうきものと知りにしをまた言の葉にかかる命よ
(空蝉の返し)
ほのかにも軒端(のきば)の荻をむすばずは桐のかことをなにかけまし
(すかさず返信する光源氏)
ほのめかす風につけても下荻のなかばは霜にむすぼほれつつ
夕顔の四十九日の法要でしらじらしい光源氏の和歌。
(光源氏)
泣く泣くも今日(けふ)はわが結ぶ下紐をいづれの世にかとけて見るべき
逢うまでの形見ばかりと見しほどにひたすら袖の朽ちにけるかな
(女官の返し)
蝉の羽(は)もたちけへてける夏衣かへすを見てもねは泣かれけり
空蝉のことがバレていて、二股交際の成れの果てに光源氏が詠んだ和歌。
過ぎにしもけふ別るるも二道にゆくかた知らぬ秋の暮れかな
若菜のタイトルになった夕顔の母の和歌。
生(お)ひ立たむありかも知らぬ若草をおくらす露ぞ消えむそらなき
それを盗み見(聞き)した光源氏の和歌
(光源氏)
初草の若葉のうへを見つるより旅寝の袖も露ぞかわかぬ
(尼君の返し)
枕ゆふ今宵ばかりの露けさを深山の苔にくらべざらなむ
なんとか若菜(若紫)を連れて行きたい源氏と尼君のやり取り。
(光源氏)
夕まぐれほのかに花の色を見てけさは霞の立ちぞわずらふ
(尼君の返し)
まことにや花のあたりは立ち憂きと霞むる空のけしきを見む
藤壺(義理の母)を妊娠させてしまうが、お構いなしに若菜が欲しいと詠う光源氏の和歌。
手に摘みていつしかも見む紫の根にかよひける野辺の若草
「末摘花」からタイトルの元になった和歌。一夜を共にした後に正月の贈り物として、末摘花から色あせた衣服が届く。
(末摘花)
唐衣君が心のつらければ袂はかくぞそほちつつのみ
(その文にいたずら書きする光源氏の和歌)
なつかしき色ともないしに何にこのすゑつむ花を袖に触れけむ
末摘花はべにばなのことで、色褪せた(古びた)赤ということで、若紫は梅の花の蕾に喩えていた。鮮やかな花になることを願ってはいるが赤い花だけは紅梅でも好きになれないと詠う光源氏であった。だから紫なのか?
(光源氏)
紅の花ぞあやなくうとまるる梅の立ち枝はなつかしいけれど
ライバルの頭中将の愛人、源典侍(オールドミスの女官)と浮気をし、三角関係になる光源氏の和歌の交換。
(頭中将→光源氏)
つつめる名やもり出でむひきかはしかくほころぶる中の衣に
(光源氏返し)
かくれなきものと知る知る夏衣きたるを薄き心とぞ見る
(源典侍→光源氏)
うらみてもいふかひぞなきたちかさね引きてかへりし波のなごりに
(光源氏返し)
あらだちし波に心は騒がねど寄せけむ磯をいかがうらみぬ
(光源氏→頭中将)
なか絶えばかことやおふとあやふさにはなだの帯はとりたてだに見ず
(頭中将返し)
君にかく引き取らせぬる帯なればかくて絶えぬるなかとかこたむ
頭中将と光源氏の関係性はより強固なものとなるのである(ライバル物語は続く)。なんせふたりには世間には公表出来ない共通の秘事が出来たからなのだ。
「朧月夜」のあだ名の由来となった和歌。
照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしく(似る)ものぞなき 大江千里
『源氏物語』はそれまでの和歌や物語の影響を受けつつ、後世の文学にも影響を与えた。
(光源氏)
深き夜のあはれを知るも入る月のおぼろげならぬ契りとぞ思ふ
(光源氏が名前を問う。朧月夜の歌)
うき身世にやがて消えなば尋ねても草の原をば問はじとや思ふ
(光源氏の返歌)
いづれぞ露のやどりを分かむまに小笹が原に風こそ吹け
この『花宴』の朧月夜の和歌は、藤原俊成が「源氏見ざる歌詠みは遺恨の事なり」と注釈した和歌で、『古今集』の「雅」から「幽幻」という和歌の根本を述べている。「草の原」は死んだ後のこと。
朧月夜は帝の妻となるべき女性で、それに弓引いてしまった光源氏だった。それが須磨行きの原因となっていく。
(光源氏)
あずさ弓いるさの山にまどふかなほの見し月のかげや見ゆると
(朧月夜の返歌)
心いるかたならませばゆみはりの月なき空にまよはましまやは
光源氏に唯一対抗できるとしたらこの人だろう。源典侍と光源氏の和歌の交換。
(光源氏)
かざしける心ぞあだにおもほゆる八十氏人(やそうじびと)になべてあふひを
(源典侍)
くやしくもかざしけるかな名のみして人だのめなる草葉ばかりを
葵が六条御息所の怨霊に殺されて、光源氏の心無い和歌と葵の母君の無念の和歌。
(光源氏)
あまた年今日(けふ)あらてめし色ごろもきては涙ぞふるここちする
(母宮の返し)
新しき年ともいはずふるものはふりぬる人の涙なりけり
葵の死後、六条御息所は伊勢の斎宮になった娘と共に信仰生活に入ろうとするが光源氏は邪魔をする。次のターゲットは娘か?
(六条御息所)
神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れる榊ぞ
(光源氏の返し)
少女子(をとめご)があたりと思へば榊葉の香をなつかしみとめてこそ折れ
(光源氏から斎宮へ)
八洲(やしま)もる国つ御神もこころあらば飽かぬわかれの仲をことわれ
(斎宮の返し)
国つ神そらにことわる仲ならばなほざりごとをまずやたださむ
藤壺も尼になり、光源氏から逃れるのは信仰しかないのだろうか。そして、朧月夜にちょっかいを出したことによって弘徽殿大后の恨みを買うのだった。
花散里との橘の和歌のやり取りは、『伊勢物語』の影響が見られる。
五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする
(光源氏)
橘の香をなつかしみ郭公花散里(ほととぎすはなちるさと)をたづねてぞとふ
(花散里の返し)
人目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒のつまとなりけれ
『源氏物語 12 須磨』は京にいられなくなった光源氏が須磨に逃亡するのであるが、その騒動の中でも女たちに手紙を書き和歌を贈り合う光源氏のまめまめしさを伺える。
(光源氏)
鳥部山もえしけぶりもまがふやと海士(あま)の塩焼く裏見にぞ行く
(葵の母上の返し)
なき人の別れやいとど隔たらむ煙となりし雲居ならでは
(光源氏)
身はかくてさすらへぬとも君があたり去らぬ鏡の影は離れじ
(紫の君の返し)
別れても影だにとどまるものならば鏡をみてもなぐさめてまし
(光源氏)
月かげのやどれる袖はせばくともとめても見ばやあかぬ光を
(花散里の返し)
ゆきめぐりつひにすむべき月かげのしばし曇らむ空なながめそ
(光源氏)
逢ふ瀬なき涙の河に沈みしや流るるみをのはじめなりけむ
(朧月夜の返し)
涙河うかぶ水泡(みなわ)も消えぬべし流れてのちの瀬をも待たずて
(藤壺)
見しはなくあるは悲しき世の果てをそむきしかひもなくなくぞ経(ふ)る
(光源氏の返し)
別れしに悲しきことは尽きにしをまたぞこの世の憂さはまされる
(光源氏)
生ける世の別れをしらで契りつつ命を人に限りけるかな
(紫の君の返し)
惜しからぬ命にかへて目の前の別れをしばしとどめてしがな
(光源氏)
こりずの浦のみるめのゆかしき塩焼く海士やいかが思はむ
(藤壺の返し)
塩垂るることをやくにて松島に年ふる海士もなげきをぞつむ
(朧月夜の返し)
浦にたく海士だにつつむ恋なればくゆるけぶりよ行くかたぞなき
(紫の上の返し)
浦人のしほむ袖にくらべ見よ波路へだつる夜の衣を
さらに東宮や腹心の者にも数多く手紙と共に和歌を添えているのだ。光源氏は言葉を巧みに使う能力が際立っていた。
『澪標』の表題となった和歌(ターゲットは明石の君)。
(光源氏)
みをつくし恋(こ)ふるしるしにここまでもめぐり逢ひけるえには深しな
(明石の君の返し)
数ならでなにはのこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ
光源氏の和歌は、元良親王(色好みで退位しなければならなかった不良の元帝)の和歌を元にしている。
わびぬればいまはた同じ難波なる
みをつくしてもあはむとぞ思ふ 元良親王
「末摘花」が「蓬生」となって光源氏の心を射止める和歌。
(光源氏)
尋ねてもわれこそとはめ道もなく深き蓬のもとの心を
藤波のうち過ぎがたく見えつる松こそ宿のしるしなりけり
(末摘花の返し)
年を経て待つしるしなきわが宿を花のたよりに過ぎぬばかりか
空蝉との逢坂(関所)での再開。
(光源氏)
わくらはに行き逢あふみちを頼みしもなほかひなしや塩ならぬ海
(空蝉返し)
逢坂(あふさか)の関やいかなる関なれば繁しげきなげきの中を分くらん
この帖も百人一首の蝉丸の和歌を踏まえている。
これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂(あふさか)の関 蝉丸
須磨から明石に移った光源氏は明石の君を見初めて子供を産ます。その子供を引き取って帝の中宮にしようと計画をする光源氏は明石一家を引き裂くのだった。
(入道)
行くさきをはるかに祈る分かれ路(ぢ)に耐えぬは老いの涙なりけり
(母君)
もろともに都は出(い)できこのたびやひとり野中の道にまどはむ
(母君)
身をかへてひとり帰(かへ)れる山里に聞きし似たる松風ぞ吹く
(明石の君)
故里(ふるさと)に見し世の友を恋(こ)ひわびてさへづることを誰か分くらむ
明石の君の娘を紫の上に面倒を見させるために明石の君と娘を引き離した時の和歌のやり取り。
(明石の君)
末遠き二葉の松に引き別れいつか小高きかげを見るべき
(光源氏の返し)
生(お)ひそめし根も深ければ武隈の松に小松の千代をならべむ
『薄雲』の題は藤壺崩御により光源氏の喪の様を詠んだ和歌から。
(光源氏)
入り日さす峰にたなびく薄曇(うすぐも)はもの思ふ袖に色やまがへる
その哀しみが冷めないのに梅壺(養女)にちょっかいを出す光源氏であった。
(梅壺)
いさりせしかげ忘られぬ篝火の浮舟やしたひ来にけむ
(光源氏)
浅からぬしたの思ひをしらねばやなほ篝火のかげは騒げる
朝顔の君(いとこ)との再会で光源氏はむらむら。
(光源氏)
見しをりのつゆ忘られぬ朝顔の花の盛りは過ぎやしぬらむ
(朝顔の返し)
秋果てて霧の籬(まがき)にむすぼほれあるかなきかうつる朝顔
(光源氏)
いつのまに蓬(よもぎ)がもととむすぼほれ雪降る里と荒れし垣根ぞ
源尚侍とのやり取りは、朝顔の君と対応させている。光源氏に対等に和歌をやり取りしているのは、源尚侍ただ一人かもしれない。
(源尚侍)
年経(ふ)れどこの契りこそ忘られね親の親とか言ひし一言
(光源氏返し)
身をかへてのちも待ち見よこの世にて親を忘るるためありかやと
光源氏は紫の上と寝ながらも藤壺を思い出す。
(光源氏)
かきつめて昔恋しき雪もよにあはれを添ふる鴛鴦(おし)の浮寝か
とけて寝ぬ寝覚さびしき冬の夜にむすぼほれつる夢の短さ
「五節の舞」がこの帖のタイトル『乙女』にもなっている和歌。
天つ風雲の通ひ路吹き閉ぢよをとめの姿しばしとどめむ 僧正遍昭
(光源氏)
をとめごも神さびぬらし天つ袖ふるき世の友よはひ経ぬれば
光源氏の青春時代を振り返って、かつて宮中の「春鶯囀」を舞った(『花宴』)が今は演奏者として「春鶯囀」を引き立てる身になった。
(光源氏)
鶯のさへづる声は昔にてむつれる花の陰ぞかはれる
(帝)
鶯の昔を恋ひてさへづるは木伝(こづた)ふ花の色やあせたる
参考本
『源氏供養〈上巻〉』橋本治 (中公文庫)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
