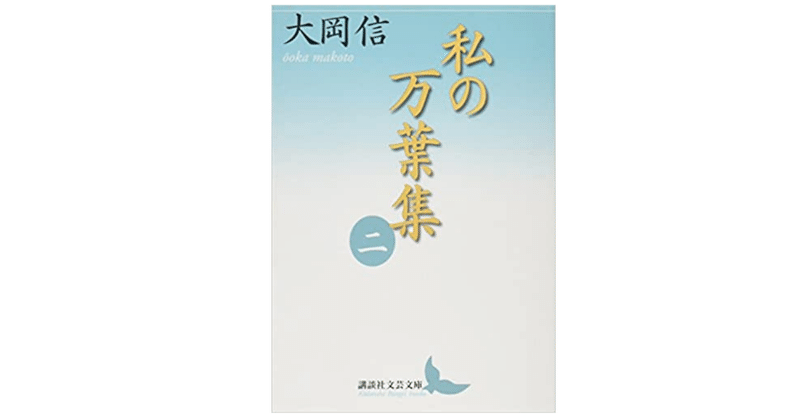
山上憶良は「万葉」のラッパーだった
『私の万葉集 二(全五巻) 』(講談社文芸文庫/2014年)大岡信
現代詩人・大岡信の『私の万葉集』第二巻。巻二の補遺及び、巻五から巻七までを取り上げる。巻五は、『万葉集』全二十巻の中でも特異であり、大伴旅人と山上憶良の二人に尽きるといっても過言ではなく、しかも、濃密かつ心に残る和歌の抒情の魅力が詰まった巻として有名。『万葉集』の面白さを存分に感じる一冊
第2巻(補遺)相聞、第5~7巻。第5巻は、「令和」の語源になった「梅花の宴」とその主催者であった大伴旅人ともう一人の万葉歌人の中心人物、山上憶良中心。「梅花の宴」は中国の詩宴(唐詩)を日本で模倣し、日本化された風雅意識の意味づけ、歌合や連歌の和歌伝統がここから始まるとした(筑紫歌壇)。漢詩ではない「ヤマトの文学としての和歌」の自覚的表現があり、「和する歌」という本質的属性がここに現れている。「桜を見る会」もこのぐらいの気合をもってやっていたら良かったのかもしれない。芸能人ばかり集めても、そこまでの芸はなし。
参考図書『うたげと孤心 』(岩波文庫)大岡信
また長官大伴旅人に仕えていた山上憶良は、老博士という感じ。旅人の妻が亡くなったときに送った挽歌(長歌)は旅人と妻に成り代わって気持ちを読み込み、さらに当時の日本の死生観(仏教以前の)を織り込んでおりユニークな散文と化している(大伴旅人のファンタジー性と文献学者たる論理性の融合)。億良の長歌は叙情的な詩情よりも文献を読み漁りその上に築き上げた散文(論文ではなくエッセイの部類)でその中にリアリズムの私的感情を織り込んでいて鴨長明や紀貫之の随筆のさきがけのような気がする。
そのもっとも有名なのが「貧窮問答歌」なのだが、「沈痾自哀(ちんあじあい)文」はさらにその上を行く壮絶なエッセイだった。「沈痾自哀(ちんあじあい)文」は「痾(病)に沈みて自ら哀しむ文」と訓読される億良74歳の晩年に病気で苦しんでいる億良がその生を引っさげて、天に不合理を訴えている長歌で、『ヨブ記』に匹敵する個人の私情発露だろう。すでに和(詩)歌であることを超えてしまっている散文。
億良のリアリズムに対して、酒を愛し日本の和歌の中心となる宴会を主催し、自らも抒情詩人として、幻想世界(フィクション)へと彷徨った大伴旅人の亡き妻に送る挽歌と藤原房前(藤原氏の天下で大友氏は衰退していく中で)に琴と共に送った「謹状」は、ファンタジー・ポエムだった。琴の精である乙女の宿る木から作られた琴が、大伴旅人の長官である藤原房前に弾いてもらいと願う贈答で、それが功を奏したのか、後に旅人は都に呼び戻される。
関連図書、
『私の万葉集 一(全5巻) 』(講談社文芸文庫/ 2014年)
『私の万葉集 三(全5巻) 』(講談社文芸文庫/ 2014年)
『私の万葉集 四(全5巻) 』(講談社文芸文庫/ 2015年)
『私の万葉集 五(全5巻) 』(講談社文芸文庫/ 2015年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
