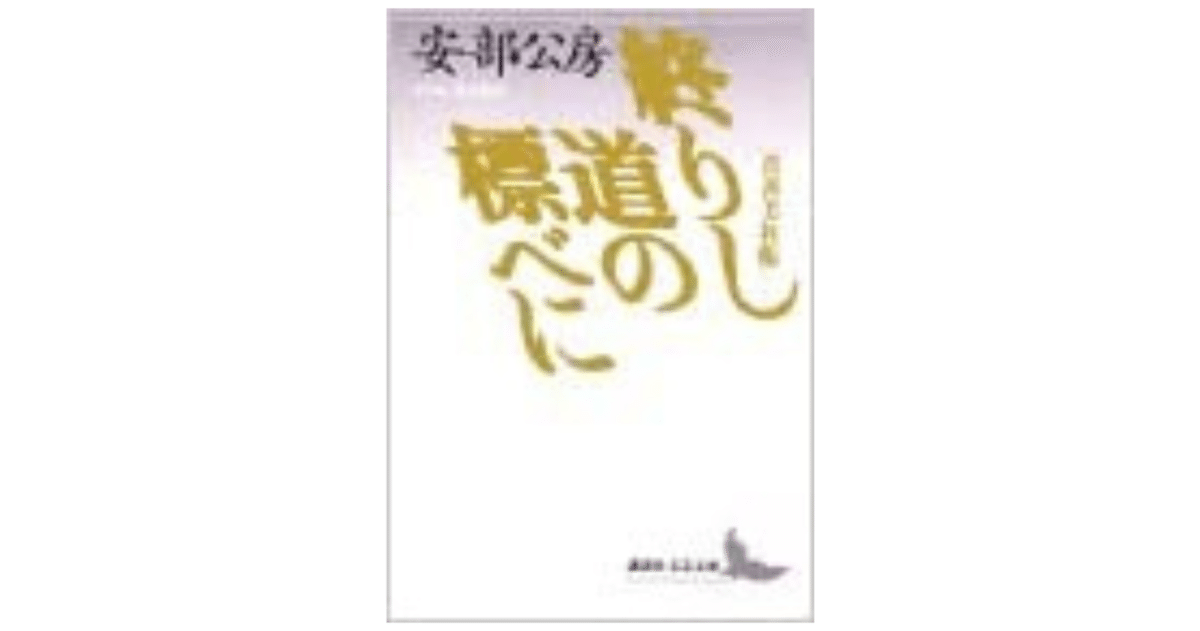
「終わりし道の標べに」から書き始めた安部公房の文学
『終りし道の標べに』安部公房 , 真能ねり (講談社文芸文庫)
幻の処女作。ここに新しいリアリティーがあった。異民族の中で培った確固とした他者。埴谷雄高は何かの予感を禁じ得ず雑誌「個性」に持ち込んだ。青年公房の生身の思索は17年後書き換えられ、もはや読むことはできなくなった処女作。読者の期待に応え甦った処女長篇小説真善美出版。
第一のノート(終わりし道の標べに)
第一のノートの副題が総題になっているが、全部で三つのノートが残され、それぞれの副題が付いている。
その言葉から推測されるのは、哲学的手記ということだ。語り手は日常的な描写よりも観念的論述を好む。それが物語を見えにくくしている。
おぼろ気ながら私は二つの故郷を見極めたように思う。一つは偉大なもの永遠なものが住む肯定の拠所、即ち生の故郷であり、今一つは更に遠い存在の故郷だ。今の陳の行為も、それが意味を持ち正当な結果として現れるのはやはり存在の郷愁を裏づけしているのではあるまいか。もしかしてその標べには《故郷の無い心理はない》と書いてあるのかも知れぬ。
陳というのは語り手行動を共にする仲間だが、ただの友人でもなく哲学的思考の相手、敵でさえあるかもしれないが彼の思考を探っている。それはもしかしたら、敗戦間際に中国へ消えていった亡き友金山時夫のことかもしらない。
何故そうしつように故郷を拒んだのだ。
僕だけが帰ってきたことさえ君は拒むだろうか。
そんなにも愛されることを拒み客死せねばらなかった君に、記念碑を建てようとすることはそれ自身君を殺した理由につながるのかも知れぬが.........。
真能ねり(安部公房の娘)のあとがき「著者に代わって読者へ」によると、安部公房は生まれてから植民地奉天で15歳まで過ごした。粘土塀で囲まれた村はその外はゴビ砂漠へ続いていく。そこは馬賊が出没する無法地帯でもあり、塀で囲まれた奉天こそは日本の植民地であったならば金山時夫と安部公房を二分する壁があったように思える。そして、敗戦間近のある日、新京(満洲国の首都)に戻っていく。そこは日本に敵対する八路軍が跋扈する所だったが、そこで金山時夫は病死する。
その金山時夫の墓標として書かれた経緯が伺われる。
金山について語るには詩でも小説でもいけない、哲学を語らねば.........。
と書かれた「小説」を埴谷雄高に紹介されて、雑誌『個性』に掲載された。安部公房の第一作であり、七年後に文体を書き直して、献辞(《亡き友に》)を付けて再発された。
人間は稀に生まれ故郷を去る事は出来る。しかし無関係になる事は出来ない。存在の故郷についても同じ事だ。
悩み、笑い、そして生活する為に、人間は故郷を必要とする。故郷は崇高な忘却だ。(略)そして思いやり深く故郷をみつめながら《斯く(かく)在る》と呟くだろう。そして私は《斯く在る》のは存在の象徴だと考える。そのように《私は在る》のだ。私も亦(また)《斯く在る》とつぶやこう。
あゝ、人間は何故に斯く在らねばならぬのか?
安部公房の「存在論」的な、当時の言葉を借りれば「実存」としての小説だろう。簡単なストーリーを紹介すると技師としてそこ(奉天だろうか?)にやってきた語り手は、別の目的地(新京だろうか?)に向かう途中で友人でもある陳と共に馬賊に襲われて幽閉を余儀なくされる。その時の心境を綴ったノートを記すのだが、それは未来の者への書き置きだった。忘却の中に忘れてしまう故郷に陳と共に向かっていく喪失の故郷について書き残した手記なのだろうか?やがて語り手は阿片を飲まされ混沌としていく。
第二のノート(書かれざる言葉)
青い手帳(ノート)に記された言葉は語り手が語る相手は恋人のお前(二人称)に変わっている。
「是(これ)は名もない、ひっきょう悪魔のことさえものにすぎない自分の魂との戦い、そして戦い破れた男の物語である.........」
スーパーヒーローのイントロシーンのような出だしである。それを女に咎めれるのだ。
「うらやましい話ですわ。戦う相手になる自分の魂を持っていたなんて.........私のその魂は、皆がよってたかって取り上げようとするばっかりなんですわ」
『砂の女』のプロトタイプの原型である。男の精神性に対する魂を取り上げられた女。それは、あの時代の女に言えることなのかもしれない。親の言いつけで結婚させられ、別の男に捧げられる(例えば敗戦時の満州で起きたことを想像せずにはいられない)。
そした志門という親友に再会する。志門とお前(与志子)私(T.........)の関係は、漱石『こころ』の三角関係のようでもある。愛を巡る手記であることが明らかだ。志門は与志子の母親(尿毒症から分裂病)に遺書を書かせて結婚しようとする。
与志子の家はもともと資産家だったが没落していた。そこに私と志門が出会ったのだが、志門は私に与志子の兄として後見人になってもらいたいと告げる。私の意志次第では結婚しても構わないとさえ言う。
私は阿片の意識の中でそれらの出来事を記す。
手がかりとなるのは、与志子の手紙だ。与志子は母の遺書通りには従いたくないので、それを私に委ねるとする。しかし、私は与志子を置き去りにして逃げてきたのだ。それが青い手帳で明らかにしようとした、与志子への思いと私の精神ではないのか?
小さな神について、イエス・キリストが偉大な神にもなれたのに弱い人間の側についたと述べている所がある。イエス・キリストは私と重なるのではないのか?
志門は与志子を愛という名でコントロールしようとした。私は愛は絶望しかないと思っている。恋でしかないのだ。志門と私の違い。志門は日本的な思考を持った人かもしれない。
第三のノート(知られざる神)
私のノート(第一ノート?)を読んだ高(高は日本語が読めた)の信仰告白。私を神として崇め始める。最初は悪魔だと思っていた。ノートを読んでその錯綜した晦渋さの在り処を知った。神の問題。私の戸惑い。阿片の作用かもしれない。
荒野は神なき世界(共産党の世界か?)。その中で囚われの身となり存在論を語るノートはキリスト的に読まれたのではないのか?高の信仰告白は、さらし首になるよりも逃げることを選択した。しかし私はその決心がつかない。
高によると陳はチンギスハンの末裔だと信じ込んでいる。しかし、そこいらの馬賊と変わりがない。八路軍(共産党)に加わったことで自分を見失っている。高が陳を私が持っているピストルで撃てば二人で逃げられる。キリストの手助けをしたいのだった。
高と陳の関係も一人の女性(香春)を巡って三角関係になっている。八路軍を指揮する実権は李が握っている。陳は逆らえない下っ端にしかすぎない。
高の身の上話。もともと高の家はクリスチャンだった。そこから社会キリスト教徒して、八路軍の幹部にまでなる。そのときに敵対する陳の部族が香春の村を襲撃する。香春の父は資本家で高の妹は香春の下で働いていた。陳はあらん限りの悪をし尽くすので、凌辱する女を物色して資本家は高の妹を差し出した。そのとき香春が陳の前に進み出て手を合わせたのだ。それから陳は香春の虜になった。高は自ら犠牲になって妹たちを守れない不甲斐なさを悔いいた。
それが高の陳への殺意となって十字架を背負い込もとしていた。しかし私はすでにこの私の生存を終わりにしたいのだ。だから高が背負う十字架は陳ではなく、この私(私のノート)だという。
十三枚の紙に書かれた追録
高は陳を殺さずに逃げていった。秘密の地下道があったのだ。そこから八路軍は攻めてくだろう。陳は八路軍の李を殺害していた。陳の精神性は私と近いものがある。むしろ反転させた私かもしれない。陳は私に阿片を与えながら共感性を語る。
安部公房はこの作品を書いている時はリルケ『時禱集』を読んでいたという。リルケの詩に伺える絶望の闇の世界から書くことについて、それはドストエフスキーやカフカの文学にも通じていくことだろう。安部公房は満州に渡って五族協和の夢を信じていたのだそうだ。むしろそれが敗戦とともに瓦解していくなかで、親友である金山時夫(在日朝鮮人のような)の寄る辺のなさ、故郷喪失者としての生き方を重ねていたのではないか?金山時夫は、私(T.........)である。その絶望の淵で《斯く在る》中で言葉を書き続けることこそが彼の存在だった。そうして安部公房は、黄砂の上に彼の墓標を書き建てた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
