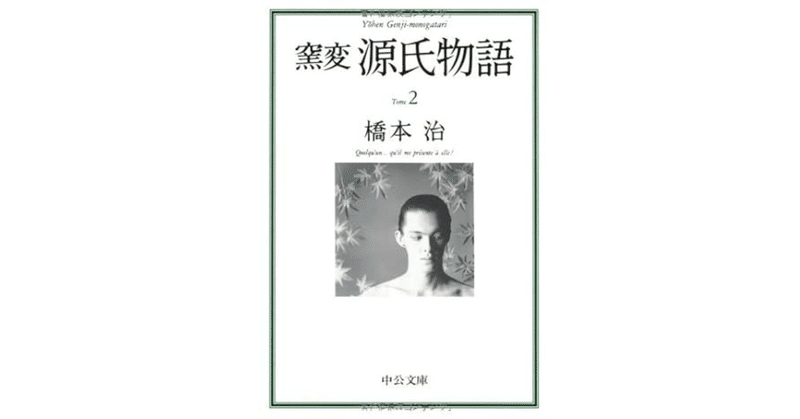
ダースベイダーとしての光源氏
『窯変 源氏物語〈2〉 若紫 末摘花紅葉賀』橋本治
現代では、人と人との繋がりが希薄になってしまった。人と人との間には、安全という名の距離ばかりが広がった。しかしその平和な時代に、人はどれだけ残酷な涙を流すことが出来るのか。それを1千年前に見据えてしまった女性がいる。その物語をもう一度、“豊か”と言われる時代に再現。最も古い近代恋愛小説の古典。
天皇が太陽ならば光源氏は月。さらにその天皇の妻(義理の母)を愛してしまったのだから、欲望のはけ口は他にむかうしかなく、それが月影となって当時の女たちを照らす物語だったのが、月そのものの影の部分、つまり暗黒光源氏として描いている。闇堕ちしたダースベイダーかと思ってしまった。「若菜」でも「末摘花」でも本人は動かない。自分の思い(欲望)を伝えるだけ。それに右往左往する惟光だったり大輔の命婦だったりする。従者は常識人であるが王の命令は絶対であるわけでその非常識な命令とのやり取りが喜劇になっているから面白い。
「若菜」
橋本治の光源氏は、月の影の部分、闇堕ちしたダースベイダーのような光源氏だ。特に「若菜の帖」とかその暗黒源氏さが良く出ている。しかし、橋本治はさらに酷い!若紫(紫の上)の祖母の尼のボロクソ発言には驚いた。娘よりもエロ婆さんにモーション掛けているのかと勘違いババアがというような。
姫たちを匿っている僧侶の兄に対しても手ひどい非難を浴びせる。この時代の僧侶は数奇を求める堕落坊主が多かったというが。昔からの老人僧と対比して、これもボロくそに言っている。
それは光源氏の思うように物事が上手く進まないので、怒っているのである。常識外れは光源氏の方なのに、それまでなんでも者を物のように自由に出来た地位だったからか、かなり自分勝手なわがままな性格になっているのだった。それでも、もう天皇という最高の地位は望めなく、また光源氏が愛している女(義理の母)との情事も上手く行かないので、他の女は身代わりなのだ。その欲望がわずか十歳の少女に向けられている。
その手はずを整えるのが惟光だった。惟光は光源氏の乳母の息子であるから兄弟のように育ち、上に立つ光源氏にもずけずけ物申すのだった。それが惟光を一番信頼している家来なのかと思わせる。
世間的に見ても不条理なことなのだが、自分中心に世界は回っているのだという十代の光源氏にはそれが不条理とも思えず王が求めるものは絶対なのであった。その間に立って右往左往する惟光は喜劇的であるが、それは光源氏をも喜劇(コメディ)に巻き込む漫才のようでもあった。
「末摘花」
ここではでは奥手の姫である「末摘花」よりも、恋の侍従「大輔の命婦」にスポット(月影?)が当たっている。彼女は光源氏とも関係がすでに出来ているのである。それで光源氏の思いを何とか叶えてあげたいと思う乙女心を持つ人なのだ。これは「恋」よりも「愛」かもしれない。
しかし、クソガキの光源氏にそんな乙女の気持ちなどわかろうはずがなく、ただ己の欲望を満たせたいのだ。そこで四苦八苦手を打つ「大輔の命婦」の身代わりの恋の駆け引きなのだが、それが叶えば彼女は用済みの女であるわけだった。
その女の部分として男である光源氏に抵抗してみる(口では)がほだされるのである。これは光源氏の地位である以上に魅力なのだ。それを知っている彼女であるから、捨てられた男のためにさらにひと肌脱ぐようなことをしなくてはならない。恋の奴隷とは彼女のことか?奥村チヨだな。
「紅葉賀」
その光源氏がみごとな舞を見せる章で、ここでステージに立つスターとしての実力をまざまざと世間(宮廷)に見せつけるのだが、本人は凄いともあまり思っておらず、むしろ天皇の位置にいない自分の不甲斐なさを独白するのである。それは「紅葉賀」というのが天皇の父(光源氏の兄に当たるとか)の50歳の祝う行事であるから本人は従者に留め置かれているから不甲斐ないのだ。その鬼神性を感じているのは右大臣の妻である弘徽殿女御だけなのだった。それを光源氏は知っていて、むしろその魔王こそ自分なのだと言う。『源氏物語』を反転させた暗黒皇子の「源氏物語」がここで明確かされる。
次代の帝が弘徽殿女御の息子である宮なので、(国母)の右大臣家の天下になるのだがその中で鬼神として光源氏を恐れているのである(息子を思う母としては当然の気持ちだろう)。その中で藤壺の出家と出産(光源氏の息子)、死という光源氏が求めていた人が消えてしまうのである。これが十代の光源氏の話なのだから凄い。先はまだ長い?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
