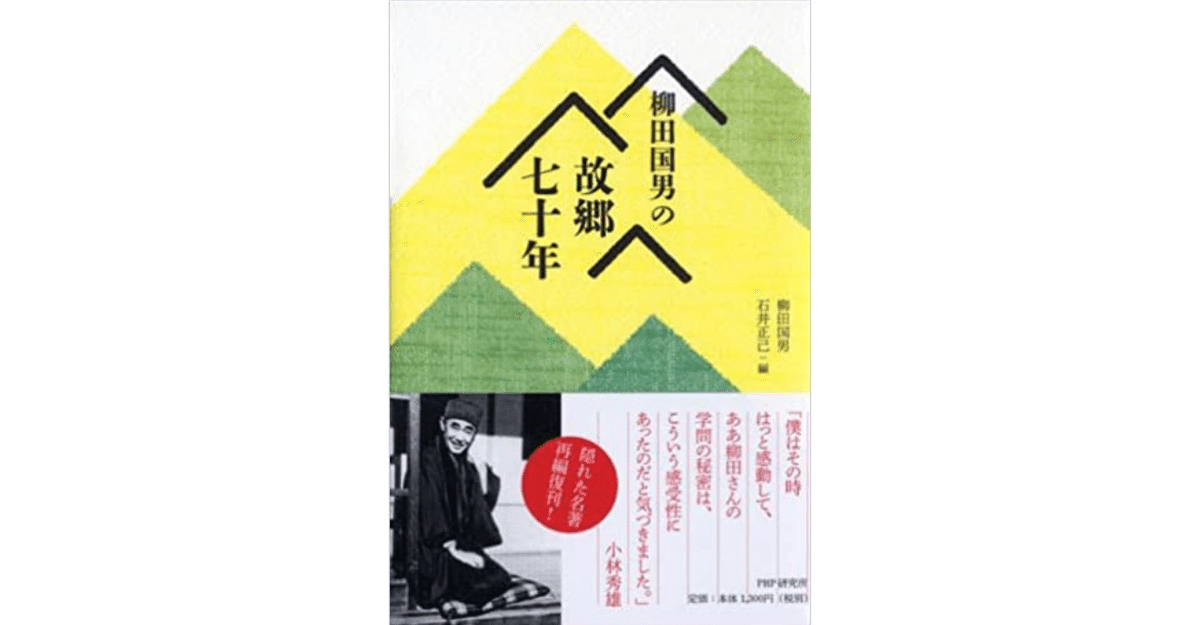
柳田民俗学の入門書
『柳田国男の故郷七十年』柳田 国男 (著), 石井 正己 (編集)
稀代の民俗学者・柳田国男の著作のなかでも隠れた名著といわれ、小林秀雄も度々取り上げている口承自伝『故郷七十年』。いまは手に入りづらい同書から、読みやすく面白い話をより抜き、手に取りやすいボリュームに再編集して復刊します。
収録作品には、観察力・感受性に秀でた少年期の体験談(「幼時の読書」「ある神秘な暗示」「神隠し」「嫁盗み」など)から、作家や評論家との交友録(「鷗外に知らる」「泉鏡花」「藤村の詩「椰子の実」」「南方熊楠先生のこと」など)まで、多彩な登場人物とエピソードが語られています。さらに、他に類を見ない柳田国男の学問は一体どのようにして生まれたのか、その起源をかいまみることのできる話が満載です。
柳田国男の目を通して語られる日本は、現代を生きる私たちにとって、神秘的でどこか懐かしさを帯びています。『遠野物語』を読んで関心をもった方にとっても、柳田国男の入門書としておすすめの一冊です。
NHK朗読で聴いていて面白かったのでKindleの読み放題でラジオと一緒に読んでいた。神戸新聞に連載された聞き書きが元になっているので、けっこう記憶違いや正確じゃないところもある。また柳田国男の保守的な面も出ていて沖縄に対する日本と同じとする(琉球を国としない)記述とかあるのだが、全体的に明治の文豪との交友録や民俗学の興味についての問いとか学ぶべきことは多い。柳田民俗学(文学)の入門書として読みやすく興味を持てる本だった。
朗読「柳田国男の故郷七十年」[終](25) - NHK テキスト:「柳田国男の故郷七十年」 PHP研究所 2014年 https://www4.nhk.or.jp/roudoku/x/2021-10-15/06/75036/4669179/
柳田は法制局に努めていたので恩赦などの刑事事件を上げるために書類などを作成していたことから、明治期の時代を背景とした事件を田山花袋などに話していた。ただ田山花袋は、あまりにも怪奇過ぎる事件であると小説化は出来ないとした(田山花袋の自然主義文学は日常的なものを描く)。それを「山の話」として記述したのが、やがて民俗学に繋がっていく。
文学者との交流は、島崎藤村「椰子の実」や芥川龍之介の「河童」などにも影響を与えた。田山花袋も柳田の話から小説化することがあったが、田山花袋の自然主義文学とは相容れないものがあったようである。『蒲団』とかは、事実ではなく想像で書くのはけしからんと、けちょんけちょんに貶している。堂々と批判出来ることも田山花袋との友情に於ける証なのだった。
熊楠も変わり者として描かれている。あの時代はそういう個性がいたのだろう。
民俗学的興味は風に対する各地の言葉から海風が果たした役割、例えば海からの風は大漁をもたらすものとか、風を巡って日本列島の交通網が出来ていくのを方言から探る。日本人の死後の世界観も転生観が元だったり、だから地下の地獄という考えはなく、基本生まれ変わる。
それと学問の学び方も、学ぶは真似るで、問うほうが大切だという考え方は暗記教育に警鐘を鳴らす。そのへんの自由な発想法が柳田民俗学を面白いものにしているのだろう。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
