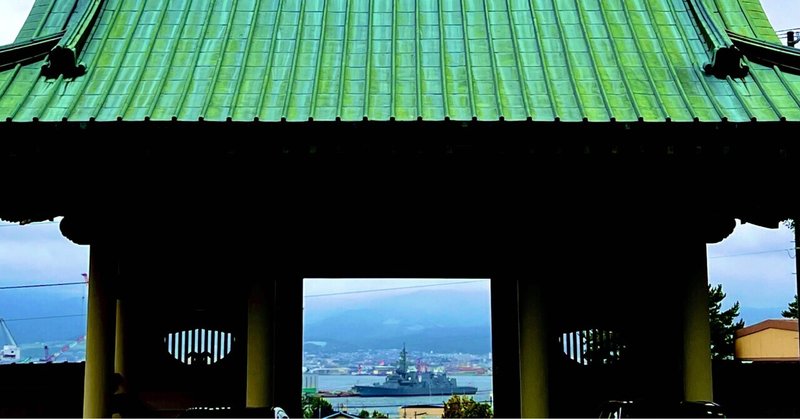
カウンセリングへの偏見はなぜ消えないか?
医学教育学会でフロアの方とのディスカッションで、学生相談の形でのカウンセリングに関して話が出た時、多くの学生はカウンセリングをポジティブに受け止めていると思ってもらえるという意見がある反面、カウンセリングを受けることに渋る学生もいるという話になりました。
その点に関して、シンポジストの主として学生のカウンセリングを担当している方が答えてくれましたが、私自身も学生相談を行っているので、それについての意見や考えを共有したいと思います。
多くの学生は、カウンセリングを受けることに対して、何らかの抵抗を感じると思います。
その背景にはさまざまな理由があるかと思いますが、特に「スティグマ」というものが挙げられます。
これは、カウンセリングや精神疾患に対する誤解や偏見が原因となっているもので、特に日本では「カウンセリングを受ける=心が弱い」という価値観が根付いていたこともあります。
しかし、時代は変わり、このような認識も変わってきています。
研究データによれば、日本人の3/4以上が「うつ病は心の弱さの表れではない」と認識しています。とはいえ、残る1/4の人たちは依然として「うつ病=心の弱さ」と捉えていることがあります。
このような認識の人たちは、自分が心が弱いと認識されるのを避けるため、カウンセリングを受けることに抵抗を感じるかもしれません。
私たち専門家としては、カウンセリングや心理的なサポートといったものが「心の病気」を連想させるものではない、ということを理解してもらうことが必要です。
イメージや認識は徐々に形成されていくもので、周囲のけっこう影響も大きいです。
私は臨床心理学者として、人々の悩みや心の健康に関しての考え方や知識を持っています。
それだけじゃなく、人間はもともと偏見を持つ傾向があることも知っています。そういった偏見を持つことは、必ずしも変なことではありません。
一方、精神疾患の知識を伝えることで、それらの偏見は取り除かれるのかと思っていましたが、実際には、まだ多くの課題が存在します。
シンポジウムで話にあがったのは、カウンセリングは「心が弱いから」という理由で受けるものではないということです。
カウンセリングは、誰もがその悩みを少しでも解決し、より良い生活を送るためのサポートです。
私たちの役目は、病気を治すだけではなく、その人の生活の質やウェルビーイングを向上させることです。
もうひとつは、心理学に関しての一般的なイメージについてです。
多くの人々は、心理学=マインドリーディングや心を読む能力だと思っているようです。
実際に私自身が何人かの人に聞いたところ、そのようなイメージが強く、心理テストや血液型占いのようなものと結びつけて考えていることがわかりました。これは大きな誤解です。
私は、このような誤解が生まれる原因として、一般の人々が心理学を扱う専門家に会う機会が少ないことを挙げます。
メディアに出てくる心理学のイメージは、残念ながらそのようなものばかりです。
私自身も学生のころ、心理学のイメージはマインドリーディングや占いのようなものが強かったです。
これらの誤解や偏見を解消するためには、私たち専門家が知識を発信することが重要です。知識の発信は、偏見を取り除く鍵となるんだろうなぁと思います。
続きはこちらから!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
