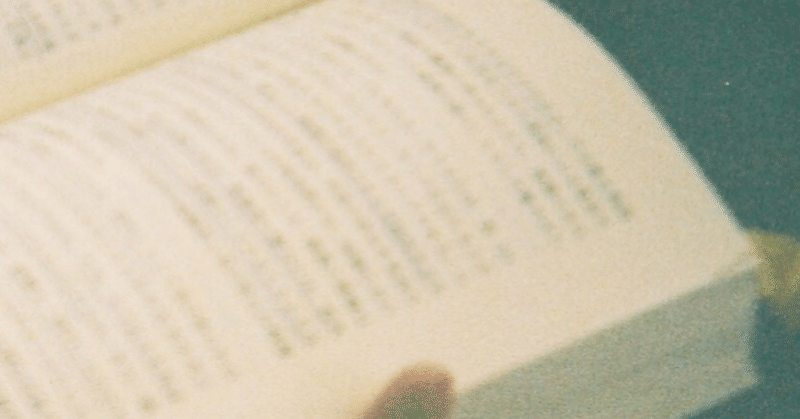
一円小説(短編小説)
今この時私はどうやら決心をしたようである。
今年十八。私は第二志望の、だらしない高校に通っている足元が薄暗い少年である。行く先の道中では必ず水たまりがある。それもドブのような匂いのものである。このドブを毎日のように吸っているものだから、人の木香のような、綺麗な香りに対して鼻をつまむ。
そんな時、私には将来という、分かりきったけれどもおぼろげな、ゴミでいっぱいの霧島の形状についての話を、先生と呼ばれる者から突き出された。たいへん狼狽した。なぜこのような頭の痛くなる、ドブよりも汚いことに真剣にならなきゃいけないのだと思った。しかし、先公は親切なもので立派な大学とその先のことまでも紹介してくれた。しかし私はそれをはねのけた。ポチ公は顔をしかめて、丸い眉毛を上にのせあげて言った。なにかやりたいことでも有るのか?思わず苦笑しそうになった。ハチ公さんよわたしゃあそんなことが有るなら有るでこんなドブで足踏みなんてしてやいませんよ。という本音を押し殺して、甘い香りにほいほい誘われる蚊のような愚かな芸をしようと試みたが、なにやらドブ本能のせいで、良からぬ返事をしてしまったようである。
私は犬が嫌いである。犬アレルギーというものがあるらしいが、私は重度のそれである。よくあるのが忠犬の毛が矢鱈目に入る時、私の目はいつも赤く濁る。むず痒くて気味が悪い。そう私は特に忠犬とかいうのが嫌いなのだ。飼い主なんて噛み殺してやれ、と会う度に思う。卑しく舌を出して、給料を貰おうと必死なのが、私からすると到底見てられない。しかし、仔犬はなぜか愛くるしく思う。犬アレルギーなんて忘れてしまうほど触れたくなる。
たしか祖母の家に仔犬がいた気がする。そいつは体が小さいくせして、一家の王だ。庭を走る、舌を出す、おれが水を出す。庭を走る、舌を出す、母が餌を出す。これじゃまるで私達が下僕のようじゃないかと思ったのだが、まだそいつには率直な美しさがあったから、ついつい言うことを聞いてしまう。そいつは私が知らぬ間にぽっくり死んだ。私はそいつを弱い犬だとは思わない。それにまだ仔犬を卒業していない間に死んだから、あいつは永遠に美しい仔犬だろう。
そんなことなどどうでも良いのだが、私もようやく仔犬を卒業しなければならない頃合になってきた。私は大人にはなりたかない。いっそあいつみたいに死んでやろうかと思ったが、いけないところに私は足を踏み入れたようである。なにドブではないから良いであろう。しかし、なかなか抜け出しにくいところであって、文学という沼に入ってしまった。不思議とドブの臭いはないしなんだか心地が良かった。問題は前述同じく、抜け出しにくいことである。
私はその沼でまごまごしていると、とうとう承認欲という愛欲よりも物欲よりも卑しいものが湧き上がってきてしまった。私はソレを得るためには手段を選ばなかった。いよいよ私は汚い舌を出したりすらしてしまったから、どうやらもう仔犬を卒業してしまったらしい。そして私の承認欲は限度を超えに超えて、汚い筆遣いで小説誌を作ることに決めた。承認欲にまみれた汚い平民は、無茶をすることすら構わず、いつでも前途無考、汚れに汚れて、ついに新しくなる。そこらへんの忠犬よりはましだと願いたい。まずは仲間をつくろう。同志、求む。
ということを呟くところで呟いたのだが、なかなか同志が私のところに来てくれやしなかったから、悔しくなった。これもまた承認欲のせいであろう。仕様がないから、幼なじみの一番の親友に、まずは夢を語ってから、これかれのことを甘ったるく味付けしてはむりやり彼の胃の中に押し込んだ。しかし彼は食ったは食ったが、何も言ってこないから実に困った。のほほんとしていやがる。そして数分経った後に突然、面倒だから無理とかなんとか、ろくな言い訳も付けずに言ったからしめてやろうかとも思った。言い訳とはあくまでも他人を守ることだと思う。しかしこいつは私に対して遠慮のひとつもしなかったから、私を丸裸のまま撃墜しやがったから、友達をやめようかとも思ってしまった。友達間としての礼儀を忘れていやがる。交差点ですれ違っただけの他人と接していやがる。しかし、こう思ってしまうのも、これだけで怒ってしまうのも、やりきれない承認欲の卑しい一面で、汚れているのはあくまでも自分の方だということにも気付かされた。これはこれで私から離れていってくれよ君。
しかし、いよいよ私はどうしよもなくなってきた。家に帰ってから、ドタバタした。悔しい悔しい。こうなれば、腐れ根性でも仕方がない。仮にあいつが私から離れようが離れまいがどうでも良い。ドブ根性をあまり舐めない方が良い。
他人を睨みつけて歩いていると(コンビニに行こうとしてると)彼が店の中に居たから、私もどういう衝動か、恐らくドブを避ける衝動が今になって動いたらしく、店の中へ飛び込んだ。
どうやら彼はもう会計してるらしく、せこせこ財布から金をだして、得意げな様子で、紙幣を店員に渡しているところだった。しかし、店員になにか言われて、顔を赤からめて、まごまごしていた。僕は目にも止まらぬ速さで彼の背後をつき、どうした?と聞いてみると、目を大きく見開いて、大失態を犯したような、なんとも見る方も顔が赤く濁る様なつらで、
「一円足りねえ」
と呟いた。僕は思わず笑ってしまった。別に悪気はないが、いや悪気しかないが、彼の赤面的羞恥顔が仕上がったのを見届けてから、様を見ろと心の中で呟いた。是非讃美歌でもなんでも歌ってみやがれ。
「一円だけなら貸してやるよ。けれどもあの件は飲み込めよ」
彼は驚いた、ドブ根性めとかどうとか思ったのだろう。ああ分かった、という風な顔でその契約金を受け取った。
店から出た時、彼に殴られた。僕はへらへら笑った。ああもうこいつとは友達じゃねえのか、と思った。この卑しい、珠玉ノ魂のせいである。この欲を満たすためには親友なんぞ捨てたってかまわない。
そして僕は後にこう叫ぶだろう
Nothing anymore
近所の喫茶店で、好き放題食べ散らかしてからようやくその小説について話し始めた。隣の席の男は煙草を飲んでいたから、その煙が僕の目の前に漂ってきて実にむせた。またその煙がなんだか僕達の仕切りになっていたから余計に邪魔くさかった。元来僕は煙草は嫌いである。幼い頃、叔父にむりやりセッタを飲まされ、死にかけた記憶があるからである。だから少し副流煙を吸うだけで、死にかけた小鹿みたいな顔になる。やはり今回もそうなってしまって、彼に笑われた。鼻のレモンを食った後みたいだな、などと卑劣で汚ない比喩をしたから余計に腹が立った。
まずはこいつに文学というものを語ってやった。ついでに僕の文学愛も添えておいた。僕が文学というものは孤独の芸術であると言ったら、あいつはなら君一人でやればいいじゃないかと無駄に口答えしやがった。そこからぐだくだ雑談にそりあがってしまって、いよいよ面倒臭くなってきて、この卑しい承認欲もようやく収まってきた頃合いだと勘づいて、さっそうと家に帰ってきてしまった。大人しく寝るつもりでいたから、読みかけの太宰のダス・ゲマイネにしおりを挟んだままにして寝た。なんだかすぐ寝付けなかった。何も考えずに、右へ左へねっとりしていたら、ようやく夜に溶けることが出来た。
翌日また僕達は集まった。昨日の喫茶店だと飯がうまいから集中出来ない、しかもタバコを吸うおっさんがいるからなおさらだ。あいつあ赤Larkでも吸ってるのじゃないかしら。副流煙が鼻にきたのもあったから、今度はファミレスに集まった。左右を見てみるとカップルであったから実に胸が苦しくなった。僕は最近振られたばっかなんだぞ、と言ってやりたいほどであった。しかも挙句の果てには浮気までされたのだ。一生涯で一番臭くて大きいドブを踏んだようだったから、一生忘れるつもりはないし一生恨むつもりである。だから僕はそれと引き換えに愛という根本を否定しなければならないこととなった訳である。しかしそれは案外にも苦ではない。むしろおのれの生き方を肯定しているようで大変心地良かった。けれども左右に居るなんて神様も酷な奴だな。楽しそうに喋っていやがる。僕はいずれ双方の一人が浮気することまでも祈ってしまった。こうなることならラークの残りカスを吸うほうがましだ。けれども相方は相変わらずのほほんとしていた。僕からしたらその態度は今になっては慣れてきた方だと思うのだが、しかし時期が時期だ。こいつには案外にも女がいるから、左右におかれたくらいじゃなんてこともないという事実とその顔は、僕を傷つけるからやめておくれ。そしていよいよ自分が呆気に取られたような感じになってしまった。急に小説の事をあいつから話してきたから、驚いた。驚いてしまったのは二つの理由があった。
しかしまた、こいつは文学というものを知らなさすぎているような気がする。
道徳と一緒なら誰でも書けるわい。いや僕の場合だと文学が道徳なら到底書けないであろう。なぜなら僕は母からもよく言われた屁理屈者で道徳もしくは綺麗事というものは自分のドブのような汚い心に反するからである。それに僕が思えば、綺麗事が綺麗と思える人はそれ相応の綺麗な心が必要不可欠なのである。もしかしたらこいつの心は綺麗かもしれないと思うと、これから僕と歩む文学道中のドブによって(僕のせいによって)いよいよ汚れてしまうのではないかと心配した。
僕達は小説のタイトルから決め始めた。僕はタイトルなんて深い意味を持ち合わせていなくても、話が面白ければ良いと一人合点していたから、なるべく人を惹き付けるような、神秘的なタイトルにしようと言った。彼はなるほど!と分かっても無いくせして、大声で言った。しかし左右がうごめいたからまあ良いだろう。そんなこんなで、まごまご練り繰りしているとようやく決まった。「海創」
なに深い意味はないが、ないにせよ神秘的だろう。もちろん舞台は夏であることは暗黙の了解であった。そしてまあタイトルが決まれば、ぼちぼち良いだろうと思い外して、そのまま食い散らかして家に帰った。なんだかワクワクしたから飯が上手く感じたし風呂も心地良かった。ただ問題なのはなかなか寝れなかったことである。
翌日僕達はより夏を感じるために海に行った。僕にとって海に行くことはたいへん煩わしいかった。太陽に焦げるまで焼かれ、阿呆猿みたいにきゃっきゃっ騒ぐのは、僕の鼓膜に無礼だ。しかし題材のためなら仕方あるまい。レッツ海、と彼が叫んだ時はとうとう暑さで頭がまいったかと思った。しかし、あの野郎は滅茶苦茶泳ぐのが上手かった。僕にとってはこの海中の砂の感覚がたいへん気味が悪かったから、なかなか海水に浸からなかった。僕は、阿呆猿と、彼の泳ぐ姿と、サーファーとを暑さで押しつぶされた幅の小さい目で睨み回した。そうしてその奥の、唯一の空気から外れた孤独の入道雲を見た。僕は感動した。これをゴッホやらなんやらに描かしたら五十億はするだろう。僕は歓喜と感動とを左の心臓に流し込んでから、もう一度阿呆共を見てみたら虚無に打ち砕かれた。僕が間違えであったことを思い知らされた。たった一円ごときと彼一人で、とうてい名小説は出来まいとさえ思った。僕が虚無に打ち砕かれたのも、高きを目指し、低きを愚かだと思ってしまったからだ。僕は馬鹿だ。僕は小さいことからコツコツとなんぞ出来ない性格だった。そんな分かりきったことまでを僕の夢幻は忘れさせていた。しかしその時の僕は自分の性格すら、分からなかったのだ。僕が夢に心を踊らしていた時に、僕より僕を分かっていたのは、この入道雲であったのだ。
入道雲は土台がしっかりしている。土台を創るとは孤独の作業だ。お前はそれを俺に教えたかったのだな。にやりと俺は笑った。俺は右の心臓でなにかを流し込んだ。その心臓はとうていドブなんぞで汚れるものではなかった。
彼を呼んだ。彼は頷いた。にっこり笑った。また海に戻った。
良い小説は、孤独でないと書けないのだ。そして俺は彼の背を見つめた。たくましい背だった。
入道雲はどんどん俺の方へ近づいて来た。さようならを言おう。俺はおまえを尊敬する。俺は今日からまたいつものようにドブを踏む。ただ俺は汚れない。それにドブの中にはあの入道雲にもあるような一円サイズの砂金があるらしいのだから。
今この時私はどうやら決心をしたようである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
