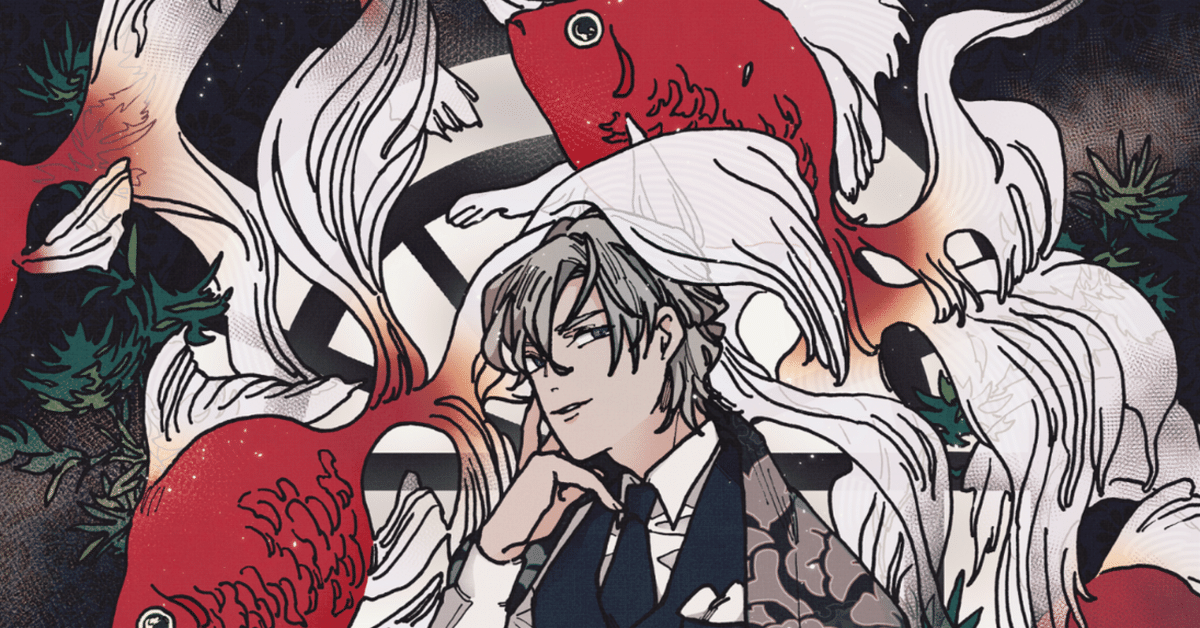
「金魚屋の徒然なる日常 御縁叶冬の邂逅」 第十一話 魂の片割れ
玄関を開けて家に入ると、また母がはしゃいで出てくるだろう――と思ったが、存外静かだった。静かどころか声も物音もしない。対面を望んでいた息子が帰ってすぐ、韓国ドラマ配信に没頭したのだろうか。それはそれで腹立たしかったが、父が見せてきたものは、その考えを吹き飛ばした。
リビングの床で母が横になっていた。目をつむって、寝床にするには苦しい場所で眠っている。スリッパは履いたままで、髪は後ろで結ったままだ。エプロンをしていて、とても寝ようとして寝たとは思えない。
「なに、これ。どうしたの。病気って本当だったの?」
「……とりあえず手伝ってくれ。一人じゃベッドまで運べなくてな」
「わかった。店長、座って待っててください」
痩せ型でインテリタイプの父には、人ひとりを抱き上げるのは難しかったようだ。鞄を床に置き母を背に乗せ寝室へ運んだ。背負うまでは父と奮闘してぐらぐらと揺れたが、それでも母は全く起きなかった。これだけ動かせば目を覚ましそうなものだ。まるで睡眠薬でも飲まされたかのような眠りは不安を掻き立てる。
母をベッドに寝かせると、父に連れられリビングへ戻った。店長はノートパソコンでなにかを入力していたが、俺たちが戻ると同時にパソコンを閉じた。
「秋葉。冷蔵庫に麦茶が入ってるから出してくれ。ちょっと、持ってくるから」
俺は店長と顔を見合わせて、ひとまず、麦茶を淹れて父を待った。
戻ってきた父は、小さな木箱を二つ、大切そうに持っていた。高さも小指の第一関節くらいしかない、収納としてはいまひとつだ。父がゆっくりと木箱の一つを開けると、中には枯れたような物体がころんと治まっている。
「何これ。木? なにかの実?」
「へその緒だ。お前が生まれたときにとっておいた」
「……へえ」
覗き込んだ上半身を引いた。子どもを持ったことがないのでわからないが、自分としてはなんの感動もない。気味悪くすら感じる。親という生き物はなぜへその緒なんて大事にするのかわからないが、店長はじっと見ていた。だが、見ていたのはへその緒ではなく、父が開けなかった木箱のほうだった。
「なぜ二箱あるんですか?」
そういえば、なぜだろう。へその緒を保管するという話はよく聞くが、何個もとっておくものなのだろうか。
父は店長が指さした箱も開けた。中には、やはりへその緒が入っていた。
「これは春陽という、秋葉の双子の兄のものです。生まれてすぐ亡くなりました」
「はあ?」
意味も目的もわからない発言に呆れた。可もなく不可もなしな内容しか話さない父の嘘は、非常に残念だった。
だというのに、店長は真剣な顔をしていた。目を細め、真っ直ぐ父を見ている。俺の非常識な話も聞いてくれた人だ。嘘を疑うことを知らないのかもしれない。
「俺はともかく、上司まで妙な嘘に巻き込むのやめてほしいんだけど」
「本当だ。お前には教えないことにしたんだ。葉子も、忘れてしまったからな」
「出産した子が双子だったのを忘れたってこと? 死んだショックで?」
「いや。それはたぶん、金魚のせいだな。病気でもショックなんかでもじゃない」
「……は?」
金魚のせい、と、さらりと言われ、自然すぎて違和感すら覚えなかった。
人生で一度も父は俺も金魚も否定しなかった。信じていない、口にすら出したくないだけだと思っていた。なにも言わなかったのは、知っていても母の前では言えなかったということなのか。俺の一人暮らしを勧めたのも、金魚に関して思うことがあるからか。
思考が迷走したが、店長はうろたえることなく冷静に父に向き合っている。
「詳しくうかがわせてください。金魚について、どの程度をご存じなんですか」
「詳しく知ってるわけじゃありません。ただ、なんと言ったらいいか。秋葉も春陽も健康に生まれてくれたんです。でも春陽は生まれてすぐ、病院でウイルス感染症にかかって亡くなりました。一時大流行したでしょう? 葉子はそりゃあ落ち込んで、毎日泣いてましたよ。私たちは秋葉だけが支えだったんです」
聞いたこともない話だった。嘘でするには、たちが悪い。それでも店長は真剣に聞いていた。父は、もしかしたら、店長と話をしているときの俺と同じ気分なのかもしれない。
「出産したのは、葉子の実家のある京都です。気分を変えようとなって、全く違う土地へ引っ越すことにしました。そうしたら、あるとき突然、葉子は春陽のことを忘れていた。春陽の仏壇を見て『これ誰の?』と言ったんです。人が変わったように明るくなって、それで俺は、仏壇を隠して秋葉にも春陽のことは教えなかった」
話の内容はともかく、最後の言葉は気になった。
以前、店長に「会話がかみ合わなかったり、あるとき突然気分が変わったことはなかったか」と聞かれたことがあった。父が語ったかつての母は、それに合致する。店長を見ると、出目金のように目を大きく見開いていた。
「でも秋葉が金魚がどうとか言い出して、それで思い出したんだ」
父は春陽のへその緒の木箱の蓋を閉じた。俯いたまま木箱を撫でて、両手で包み込むように握った。
「母さんは春陽を忘れる直前、『金魚が消えた』と言って倒れたんだ」
身体が強張った。俺と、おそらく店長も。
「それからすぐに目は覚めたんだが、金魚と言ったことは忘れていた。なあ、金魚ってのはなんなんだ? お前たちはなにを視てるんだ」
店長は母も金魚と関わっていたと予想した。まさに本当にそうなのか。店長を見ると、机の下でぐっと拳を握りしめている。
「葉子さんは、なにもない場所で驚いたり、存在しないなにかを目で追ったりしたことはありませんか」
「……ありました。春陽が亡くなってから忘れるまでの間だけですが」
「では行方不明になったことはありますか? ほんの一瞬でも」
「え、いえ、そんなことは……」
「よく思い出してください。部屋にいるはずなのに外から戻ってきたとか、行った場所のことを忘れていたり。葉子さんが春陽くんを忘れた直前です」
「ああ、そんな程度ならありました。寝室で寝ていたのに、どうしてか玄関に座ってたんです。それで『金魚が消えた』と言ったんです」
「それだ……!」
店長の拳が震えていた。父はわけが分からないような顔をしているが、俺はわかった。
――店長は金魚の真実を知っている、もしくは明確な仮説が立っている。俺を通じて仮説の立証をしようとしている。
「金魚が悪い影響を及ぼすのなら、なんとかしたいと思ってました。でも、奥様の事例をうかがう限りでは、悪いものでもないのかもしれない」
「ええ。葉子は金魚に出会い、消えたら元気になりました。春陽を忘れることは、葉子に必要だったんです。秋葉もそのうち元気になるかと思ったんですが、それらしい兆候もない。だから一人暮らしをさせました。葉子の金魚が消えたのは引っ越した後だったんで」
「なるほど。秋葉くんを実家から出したい理由があったんですね」
いつも面倒で適当なことを言ってると思っていた。興味がないわけでも突き放したのでもなく、金魚を受け入れるのが良いという、現実的な判断だったのか。
母は愚かで、父はいい加減だと思っていたが、一番考えなしなのは俺だった。
父は椅子から立ち、身体を九十度に曲げて頭を下げた。
「秋葉をよろしくお願いします。私は葉子の傍を離れるわけにはいきません」
「もちろんです。お話をうかがえてよかった。なにかあればすぐにご連絡します」
「有難うございます。秋葉。しっかりやるんだぞ。たまには顔を見せてやってくれ」
「……うん」
俺は頷くだけだったのに、どうしてか、店長は深く頭を下げていた。父は「いやいや」などと言って店長に頭をあげるよう促していた。
その光景をみて、ふと気が付いた。いつも俺の傍を離れない金魚のうちの一匹が、父の傍をくるくると回っていた。そういえば、母をベッドに寝かせたときも、母の傍をくるくると泳いでいた。まるで、子どもが親にじゃれているようだった。
――この金魚は、きっと春陽だ。
感情を見せたことのない金魚がなにを喜ぶのかと、大人二人が頭を下げ合う横でそんなことを考えていた。
家から出てのんびり駅に向かって歩いていると、ぽつりと店長が言った。
「アキちゃんに憑いてる金魚は春陽くんだろうね。やっぱり、なんらかの条件を満たした人間は、金魚になり現世へ留まるんだ」
やっぱり、店長は金魚が人間の魂だと知っていたんだろう。俺を通してあやふやな情報の裏付けをしている。
騙されたようで少しばかり腹は立ったが、それ以上に、俺の知らない真実を知っている人がいるのは心強く感じた。
「母さんを助けたのは春陽なんでしょうか」
「それは金魚屋だと思うね。生まれたての赤ん坊がそんな思考をできるとは思えない。春陽くんだとしても、アキちゃんに憑いてる理由がわからないね。それに二匹ならもう一人、アキちゃんの周りで死んだ人がいるってことだ」
「母さんは金魚を視てたふうですよね。聞けば知ってるかもしれないですけど、春陽ごと全部忘れてるっぽいからな……」
「それが金魚と金魚屋の規則なんだよ。金魚が憑いてる間は金魚を認識する。なにかの拍子に視えなくなり、忘れてしまう。『なにかの拍子』を与えて記憶を消すのが金魚屋だ」
「……だから『人間の魂が金魚になるって』情報は、世に出てこないんですね」
こんなに非現実的な話が、よくあるできごとのように思えてきた。いるかどうかもわからないのに、金魚屋は実在すると断言できる。
「そうなると、お母上はどうやって金魚屋と接触したのかが気になるねえ」
「父さんがなにも知らないなら、こっそりやってたんですよね。そんな怪しいことしてたら目に付きそうですけど」
「金魚屋も目に視えないのかもね。それか、目を合わせるだけで摩訶不思議なことをするなら周囲は気付かない。もしくはただのプログラムか」
「店も社員も存在しなくて、魂の理自体が金魚屋ってことですか?」
「可能性だけどね。問題が発生したら修正する、常時実行されるデバッグプログラム」
「俺はその考えが一番フィットします。だって全人類を対象に金魚退治なんてやってられないですよ」
「そうなんだよね。けどプログラムっていうのは、エンターキーを押す人間が必要だ。エンターキーを押すのが金魚屋なのかもしれない。プログラムでは対処できないバグが起きたら修正に行くんだ。お母上はバグが起きた人なんじゃないかな。おそらく君も」
それならば、バグの原因はやはり春陽であるように思われた。母になにかが発生し、俺に引き継がれた。代替わりしたときに忘れたのかもしれない。
「お母上が出産した病院に行ってみよう。アキちゃんが生まれたときに、病院でなにかあったはずだ。病院の場所はわかるかい?」
「わかりますよ。ただ、京都は新幹線代が厳しいかも……」
母の仮病で四万円が飛んだ。折り返してもらってくるしかない――と思ったのだが。
「旅行! いいね! 旅費はぜぇんぶ経費で落としてあげるから気にせんでよろしい!」
「えっ、経費って店長の会社のですか? 俺は社員じゃないからよくないですよ」
「ええい! アキちゃんは金カネ金カネうるさあい! 行くんだよ! なぜなら僕が行きたいから! チケットを取りまあす! 何時につくかな⁉」
「今から行くんですか⁉ 明日は授業があるんです! 次の土日にしてほしいです!」
「んえ~⁉ この盛り上がりで週末まで待つのかい⁉ はやく授業やっておしまい!」
「授業やるのは俺じゃなくて学校側です! 受けるだけの俺にはどうもできません!」
さっきまでの真面目で誠実な社長はどこへ行ったのか。けれど、週末まで待たなければいけないのは嫌だな、と俺も思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
