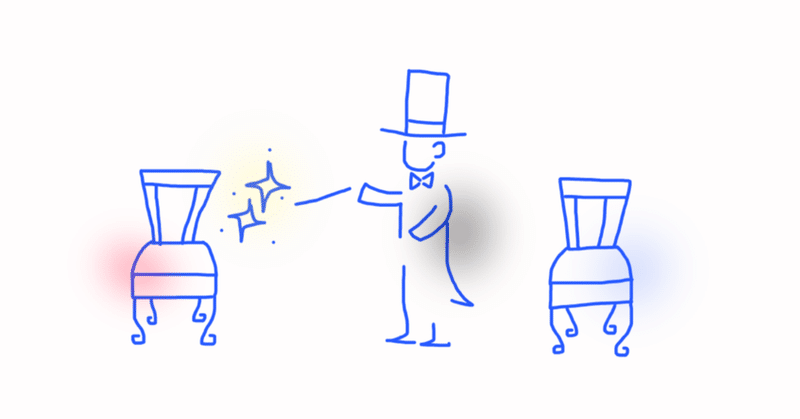
手品
今年の冬は寒い。
いや、冬ならば寒いのは当たり前なのだが、今年の寒さは肌を刺すように痛む。
雪が轟々と降り積もる中、結露した窓をぼんやりと見つめた。
僕の父は手品師だ。
でも、その事を人前で言った事はない。
小さい頃まではたくさん手品を教えてもらった。
父が得意だったのは、自分が箱に入り、箱を閉じ、次に箱を開けると、中に父の姿はなく、別の場所から出てくると言う手品だ。
定番といえば定番かもしれないが、僕も初めて見た時は驚いた。
小さい頃は父が誇らしかった。
周りの友達に手品を父が見せて、キャッキャ言われる。
そんなのは毎日だった。
でも、学年が上がるにつれ、父のことを恥ずかしく思うようになった。
それもそうだ。
周りの友達のお父さんはみんな会社員。
手品師だなんて、仕事だとは思えなかった。
流石に僕もそこまで馬鹿ではない。
自分の家が貧しい事くらい薄々感じていた。
いくら腕の良い手品師だとは言え、路上のパフォーマンスだけで十分に稼げるわけがない。
気がついた頃には僕は父を嫌っていた。
そんなある日、学校で課題が配られた。
家族への感謝の手紙だ。
無論、中学校を卒業するのだからいずれは書く羽目になるのだろうと予期していたが、いざ配られるとなると、書くことがない。
いや、書きたくなかった。
ここまで男手ひとつで育ててくれた父に感謝する。書くのならそんな内容か、いや、父の仕事に感謝などしていない。
寧ろ、今の仕事をやめて欲しかった。
その事を書くか、いや、問題になりかねない。
父のせいで問題を起こすのは尚更だ。
そんな事を悩んでいるうちに締め切りの期限がきた。
「はい、じゃあこの前配ったお手紙回収します。」
僕はまだ何も書いていなかった。
「あれ、手紙は?」
「いや、ちょっと…書きたいことが多すぎてさ、まとまんなくて…」
飛んだ嘘をついた。
それでも先生は笑って僕のことを褒めた。
「良いお父さんなのね」
ドンッ!
話し声でざわついていた教室に異質な音が響いた。
自分でも驚いた。気づけば机を叩いていた。
一瞬の静寂の後、何事もなかったかのようにまたざわつきが始まる。
「父親なんていなくなれば良いのに」
そんなことを思いながら、灰色がかった雲に自分を重ねた。
その日の放課後だった。
部活の途中顧問の先生が髪を乱して、部室に駆け込んできた。
「君の父親が倒れた」
「早く、病院へ」ハァ、ハァ、と息を切らしながら一息でその言葉を先生は言い終えた。
半ば強引に腕を掴まれ、先生の車で病院へと向かった。
その道中は複雑な気持ちだった。
喜怒哀楽全ての感情が僕の中で混ざり、渦となって消えなかった。
その日の夜、父は息を引き取った。
側にいる僕を残して。
後に父の部屋からは日記が見つかった。
叔父の家で引き取って貰う事になり、荷物をまとめに家に買った時に見つけた。
この後、父の葬儀が行われる。
その前に早く荷物をまとめなければならなかったが、少しくらいなら良いだろうと、日記を開く。
日記は不定期で書かれていた。
最初はこう綴られていた。
少し堅苦しい書き方になってしまうが、これから不定期に私の半生を綴りたいと思う。
4/12
最近、息子が私を遠ざけているように感じる。
成長したのかな?笑
私の仕事に不満を持っているのかもしれない。
昔の私に似ているな笑
僕が中学一年生になったこの日から一年近くは仕事のことが書かれていた。
パラパラとめくっていく中で、ある一日が目に留まった。
僕が二年生になった年の秋だ。
10/18
初めて吐血をした。
自分でも薄々体の弱りを感じていたが、改めて感じる。
息子に心配はかけられない。
これから日記を書くのはやめようと思う。
その代わりに死ぬ前に一度、僕の幼少期を振り返りたい。
1枚の空白の頁をめくると、次の頁からまた手書きの文が書いてあった。
僕は、本当は医者になって多くの人を救いたかった。
でも、それは叶わなかった。
高校生の頃に、家の経済が破綻した。
父親はギャンブルに出て、借金を返すどころかどんどん溜まっていく。
こんな生活を続けているのだから、僕は当然高校には通えない。
かといって、高校も出ていない僕を雇ってくれる場所はなく、駅前でのパフォーマンスで稼ぐしかなかった。
手先が器用だったこともあり、手品は地元でも評判だった。
でも、その時から思っていたよ。
「なんてみっともないんだ」ってね。
多分息子もそのうち私にそう思う時が来るだろう。
いや、そう思ってほしい。
息子には私のような人生を送ってほしくない。
そのためになら嫌われても良い。
みっともなくても良い。
不器用で良い。
僕はみっともない父親になれたかな?
その後も続きはあったが、読むことができなかった。
時間がなかったからか?
そう自分に言い聞かせたかった。
本当は読めなかったなんて言えない。
冬ならば寒いのは当たり前なのだが、今日の寒さは一層肌を刺すように痛む。
空を覆う雲も今日だけは同情してくれなかった。
北風だろう。体の内から込み上げる嗚咽をより冷酷に感じさせるのは。
自分が憎い。恥ずかしい。情けない。
僕が全て間違っていた。
その夜、葬儀に出る。
茫然とした心を御焼香の香りがくすぐる。
参列している人も、冷え切った風も、誰も僕の心の埋め合わせなんか出来やしない。
…に …後に …最後にお顔を見ますか?
特に考え事はしていなかったにも関わらず、言葉が耳に入ってこなかった。
少しだけ背の高い低反発の椅子から重い腰を上げ、棺に入った父の顔を覗く。
そのまま立ち尽くした。
10分…20分……
気が付けば声を上げて泣いていた。
残酷にも時の流れは誰の味方もしてくれない。
どんなに得意でも、もう父は手品ができない。
一度棺を閉じる。そして、開ける。
期待とは裏腹に父は棺で眠っている。
もう、あの日のように、生きていた日のように箱から消える事はできない。
予期せぬ場所から出てくる事はできない。
「お父さん…みっともねぇよ……」
家に着くや否や、手紙を書いた。
書いている途中で眠気に襲われ、一度引き出しにしまう。
明くる日、引き出しを探っても手紙は見つからなかった。
ふと、父の声が聞こえた気がした。
「みっともねぇな」
今日は冬にしては暖かい。
手紙が無くなったのも偶然じゃないような気がした。
もう一度紙を出して手紙を書く。
みっともない親父に、みっともないほど稚拙な文で。
結露した窓をぼんやりと見つめた。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
