
【塾長連載】第9回 総合型選抜(AO)・推薦入試はワンランク上を狙おう
こんにちは。AOアカデミー塾長の武田です。
一般選抜(一般入試)も国公立大の後期日程と私立大学の3月入試を残すだけとなりました。
AOアカデミーでも合格者の喜びの声が続々と寄せられています。
新高3生向けの講座もスタートし、今月中旬からは春期講習が開講いたします。総合型選抜(AO)・推薦対策の志望理由書・小論文の講座も開講し、志望校合格に向けて塾生は真剣に取り組んでいます。
なぜその分野を目指すのかについて、自分のこれまでの経験をもとに考え、着々と準備を進めているようです。
同時に保護者の方を交えての学習・進路相談を行っており、第一志望校及び併願校についての考え方、さらには総合型選抜(AO)・推薦入試と一般選抜(一般入試)のW対策について具体的なスケジューリングをお話させております。
今回のテーマは、総合型選抜(AO)・推薦入試ではどのレベルの大学を狙うべきか?ということです。
総合型選抜(AO)・推薦入試ではどのレベルの大学を狙うべきか
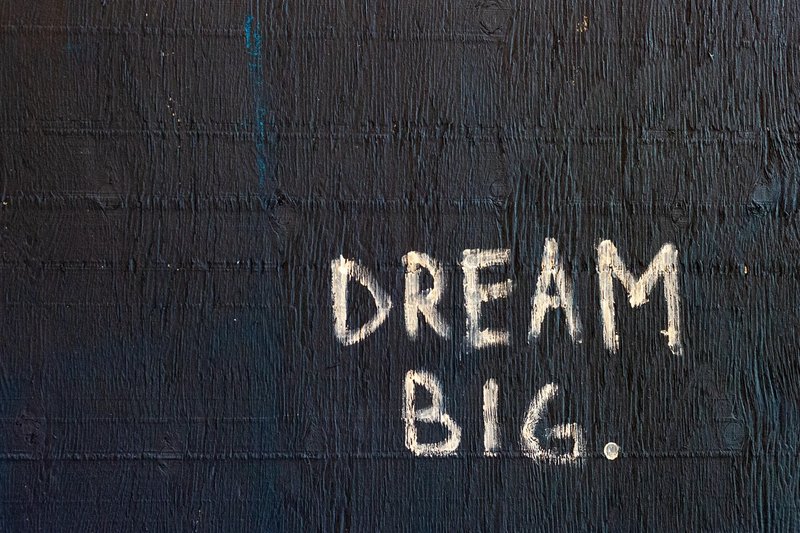
結論から言うと、総合型選抜(AO)・推薦はワンランク上を目指すべきです。この一番の理由は、モチベーションの維持です。
一般選抜を受ける場合、例えば高3の4月の段階で模擬試験の判定がA判定(合格可能性80%)の大学を第一志望にする受験生はほとんどいないでしょう。
おそらく第一志望の大学はC判定(合格率50%)以下の受験生が大半だと思います。
そこから懸命に努力して何とか志望校の合格を勝ち取ろうとします。この努力の過程があるからこそ、合格の喜びもひとしおであり、入学後も真剣に学ぶ姿勢が維持されるのです。
さらに、頑張りぬいた経験が自信となり、その後の人生において何とか乗り切っていこうとする力を与えてくれるのではないでしょうか。
総合型選抜(AO)や推薦についても同じように考えるべきです。
ラクに入ろうとすること=リスクになる

模試の判定が良くないからといって、ラクに入れそうな学校を選ぶのは、入学後の学修を考えた場合、逆にリスクになります。また、こうした安全校を選んだのが受験生本人でなく、保護者や学校の先生だった場合、その大学についての情報はどこまで正確なのでしょうか。
塾生の多くは志望校について時間をかけて調べ、自分なりの志望動機を持って臨もうとしています。その大学を志望するにいたった「ストーリー」があるのです。
このストーリーには「将来こうなりたい」という夢やヴィジョンも含まれていて、これがモチベーションの源になっています。
総合型選抜(AO)を実施する大学が増えている理由は、こうした夢やヴィジョンを明確に持っている受験生をできるだけ集めたいからです。
大学入学後を見据えよう

第一志望で入学した学生は、授業や実習でリーダーシップを発揮します。
大学の教員からすれば、授業を盛り上げてくれる学生がいるのは本当に助かります。やる気がない学生たちを前に講義するよりも、熱心に耳を傾けてくれる学生たちが多ければ、その分講義に熱が入るのは当然でしょう。
当たり前のことですが、これは学生側にとってもメリットがあります。最近、多くの大学では授業に対する熱意を学生の成績評価に利用しています。従来の評価項目である「出席」「試験・レポート」以外に、授業への「積極的な参加・貢献」が評価されます。担当教員は、受講生の発表や質問回数を記録し、それを成績評価に加えているのです。
大学の授業に積極的に参加できるかどうかは、もちろん教員の力量にも左右されるでしょう。興味があまりなかった分野も、教授の講義がきっかけとなっておもしろさを発見することもあるかもしれません。
けれども、貴重な4年間の大学生活で、学生自らが主体的に学問のおもしろさを発見し、追求していくのが大切ではないでしょうか。
ワンランク上の大学を目指し、合格を引き寄せる努力をする経験は、大学入学後もその先もきっと皆さんを支えていくと信じています。
前回の塾長連載はこちらから↓
AO入試(総合型選抜入試)に関する他の記事はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
