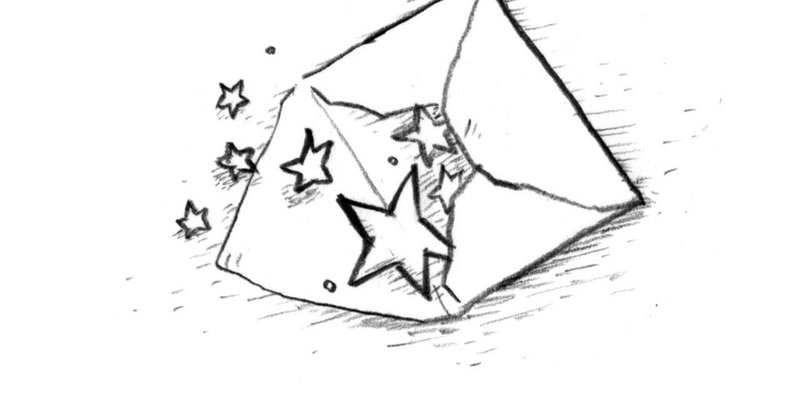
父からの手紙
今年に入って、はじめての雪がちらつく寒い朝、静かに高潔に旅立った父。
ここ数日、二月にしては暖かい日が続いていたのに、その日の朝は、冷たい雪が降り始めていた。雪は、桜の花びらのように、私の凍えた頬に、その冷たさを感じさせることなく、ひらひらと舞い落ちる。ぼんやり立ち尽くす私の背中を、娘の温かい手が、そっと促すように車の運転席まで導いてくれる。私は、車のエンジンをかける前に、大きく深呼吸をしてから、父を乗せた互助センターのワゴン車の後に続いた。
前日までかすかに意識があった父。
顔につけられた酸素マスクが、無造作に装着されていて、細く、痩せ細った顎にくいこんでいる。本人は、痛みすら感じないのかもしれないが、見ているこちらの方が、あまりにも痛々しくて、医師の許可なくマスクを外したのだった。ベビーオイルを含ませたオーガニックコットンで、乾燥しきった目頭と、目尻と、口元をそっと拭く。いつから顔を拭いてもらっていないのか。目頭と目尻には、涙の残骸であろう大量の目ヤニが、小さく細くなった父の目を塞いでいた。もうだいぶ前からだろう。口から食べ物をとっていないために、動かさなくなった口元には、白くカビのようなものが生えている。
当初入院していた病院から、ひと月前にここに移ってきた。ここに来てからは、更に別人のように変貌している。いわゆる、末期患者が送り込まれるホスピスである。ホスピスと言ってもピンキリで、この施設はどちらかと言えばキリに近い。
三日ほど前までは、一日だけでもいいから自宅に帰りたいと、かすれた声で母に懇願していたらしい。母は、父よりも八歳年上で、母自身も持病の糖尿と高血圧を抱えている。そんな事もあり、父を自宅に連れて帰るのを拒んだそうだ。自分の健康に自信がない事と、自宅にいる間に、父の病状が急変する事を恐れていた事もある。しかし、本当はそれだけではない。実は他にも性格上、無理な理由があったのだ。歳は父よりも上だったが、結婚してからは専業主婦の経験しかなく、会社勤めも未経験だったことから、何をするにもずっと父を頼りにしてきた。精神的にも、経済的にも、父なしでは生きてはいけない人だったのだ。家庭人としては完璧だった母も、社会人としてはなんの免疫もない、箱入り妻だった。その上、父とは比べものにならないほど、人見知りときている。
仮に父が自宅に帰ってきたとしても、当然のことながら自宅には、介護のスタッフサービスが、入ることになる。母一人では、到底父の世話はできない。しかし、人見知りの母は他人を家に入れるのを嫌がる。それがほんの少しの間であっても、無理な人なのだ。
父の具合が悪くなってからは、病院の入院手続きから、何から何まで、次女である私の妹が全てやってくれた。あいにく、私が遠方に暮らしていて、なかなか実家に帰る事が出来ないので、すべて妹任せにしているのが現状であった。(妹も母に似て人見知りだが、母のそれよりはマシであった。)
私の方も、遠方という理由だけではなく、一人娘を抱えて暮らすシングルマザーでもあり、日々の仕事や雑事に追われ、それどころではない。父が病に倒れてからも、頻繁に見舞いに行くことは容易ではなかった。ただ、この日に関してはなぜか、夕方から胸騒ぎがして、無理を言って職場の上司に車を借りた。塾が終わるのを待って、高校生の娘と共に深夜、父の入院しているホスピスを訪れたのだった。
一週間前にここに来た時に見た父。その姿に、哀しみとも怒りとも言い表せられない感情を覚え、今度来る時は、必ず汚れた顔をキレイにしてあげようと決めていた。一体、ここのホスピスの看護はどうなっているのか。そう遠くない死に、直面する患者に対しては、身体を拭く事も無駄だというのか。それ以前に、うちの母や妹は、毎日見舞いに来ているにもかかわらず、この状況をどう感じていたのだろう。黙って見過ごしていたのだろうか。いや、妹も母も人見知りときているから、医師や看護師に意見する事自体が、おっくうだったのかもしれない。そして壊れそうな父の身体に触れることに、実は、もっとも恐れていたのだろう。もともと痩せ気味だった父の身体は、もうそれは、骨と皮という表現がぴったりで、持病の乾癬という皮膚病もあり、全身はミイラのように乾涸びていた。決してこの表現が父に対しての冒涜だとは思わない。事実、その通りなのだ。
入院してからは病院の空調のせいもあり、余計に肌の乾燥がひどくなっていたに違いない。ベビーオイルを含ませたオーガニックコットンで、細心の注意を払いながら、キレイに顔を拭き取ると、元のように酸素マスクを小さくなった顔にもどした。今度は顎にマスクがくいこまないよう、柔らかいガーゼを間に挟むようにして。目ヤニで塞がれていた目をのぞくと、それまで意識が薄れていたはずの、父の瞳が力強く私の顔を捉えた。
その瞳は、少し白く濁っているように見えたが、強く穏やかで満たされた表情に曇りはなかった。これが、私にできる最後の親孝行であるように、父はそれを喜んで受け入れてくれたのかもしれない。
「明日も来るからね。」
そう言って父に挨拶をして私は娘とホスピスを後にした。
一時間半、高速を飛ばして自宅に戻り、翌日の(正確には零時を過ぎているので今日になる)支度を終えて、シャワーを浴びようと思ったその時に電話が鳴った。時刻は午前一時をまわっている。嫌な予感とは、だいたい九割がた当たるときている。予想通り、妹からの電話で、父が危篤状態だとのことだ。ソファーの背もたれにかけっぱなしの服を、そのまま着て、娘の部屋に声をかけた。妹との電話のやり取りで察したらしく、娘も身支度を終えている。二時間前に帰ってきた道を、そのまま引き返し、再び高速を飛ばして父の待つホスピスへ向かった。ひょっとしたら、もう、父との最後のお別れに、間に合わないかもしれない。心臓がどきどきする以上に、ハンドルを持つ手が震えているのが自分でもよく分かった。その動揺に気が付いたのか、私の膝にそっと手を置く娘。聞こえるか、聞こえないほどの声で「大丈夫だよ」そうつぶやいた。気を取り直した私は、助手席に乗せている娘の安全を、第一に考える余裕を取り戻し、再び運転に集中した。もう、ハンドルを握る手の震えは収まっていた。
病室に入るや否や、母と妹が父の枕もとで嗚咽を上げて泣いている。一足遅かったのか……いや、まだ人工呼吸器のグラフィックの波型が確認できる。こんな時でも意外と冷静に判断ができた。コートを着たまま、父のそばに行こうとしたが、母も妹も私が来たことにすら気づいていない。その場を離れようとしなかった。しかたなく、母と妹がいる方とは反対側のベッドの狭い幅の方に回った。そして、もうすでに意識がなくなってしまっている父の顔を覗いた。息も、かすかに確認できるほどの音しかしない。そう、その時は静かに、確実に、目の前まで来ている。
「心配ばかりかけて、あまり親孝行できなかったけど、お父さん、ありがとう」
そう言って、父の冷たくなった手を握り締める。一瞬、私の手を握り返したかと思ったが、同時に人工呼吸器のグラフィックの波型が一本の線に代わった。そして、ピーーと言う無機質な音が病室に響いたのだった。
父の通夜は、ごくごく限られた親族だけで執り行われた。それは、母の意向でもあり、父の望みでもあった。父という人は、母という人をよくわかっていた。人見知りからくる対人アレルギーや、疲れから血圧が上がるのを予測した上の事。自分の事よりも常に母への配慮が先にたつ。生前はよく夫婦げんかもしていたが、それも仲が良い証拠だろう。
父は、早朝に息を引き取ってから、二時間ほどして、通夜の執り行われる互助センターの施設まで運ばれた。亡くなってから、病院でキレイに拭いてもらったんだろうか。畳に設えた薄い敷布団の上に、横たわる父のカラダは、やけに美しかった。黒く焼けた肌の色は、持病の皮膚病治療のために照射された紫外線の副作用によるもので、それも見かたによっては美しい。改めて横たわる父を見下ろすと、いとおしさがこみ上げてきたのだった。私のカラダの中に、この人の遺伝子が、血が、魂が、引き継がれているんだと。
数少ない弔問客が訪れ、ひと通り通夜が終わると、明日の葬儀まで仏さんのおもりを、交代でしなければならない。一晩中、ろうそくと線香の火を絶やさないために。何より父を一人きりにさせないためにも。母は、高齢で持病もあるし、妹にはまだ小さな幼子がいる。結局私が、その役を買って出た。今まで親孝行らしいことは、何一つとしてできていなかったし、最期に父との思い出に浸りたい気持ちもあった。名残惜しそうにしている母と妹たちを別室へいざない、ひとり父の傍らに身を寄せる。幼いころ、寒くなると、いつも父の布団に潜り込んで、冷たくなった手や、足を温めてもらった。父の太ももの間に足を入れると、「冷えとるなぁ。よしよし、もうすぐあったこうなるさかいなぁ」そう言って、自分の方に抱き寄せてくれたものだ。八歳下の妹が生まれるまでは、父を独り占めにできた私も、それ以降は「お姉ちゃんだから我慢しなさい」の言葉に、お姉ちゃんとしての人生を歩んできた。久しぶりに、こうして父を独り占めにできるのが、四十年以上も経った今日になるとは、思いもよらなかった。
枕元の、ろうそくの火がジリジリと音をたてて、もうすぐ消えようとしている。新しいろうそくにその火を移し、燭台に据える。これでしばらくは大丈夫だろう。再び父の傍らで、幼かった頃の思い出を、頭の中で巡らしていると、入り口の扉をトントンと叩く音がきこえた。この建物は平屋で、入り口の自動ドアが二重扉構造になっている。外に面している自動ドアの扉は、電源を落としているが、開けようと思えば手で引くことができる。
部屋側の扉には鍵をかけているので、内側からしか開けられない。もちろん夜は、中が見えないようにガラスドアの内側を、パーテーションで遮っている。トントンという音は、部屋側の自動ドアを叩く音のようだ。叩くと言っても、軽いタッチの叩き方で、不愉快な感じはしない。ひょっとして弔問客かもしれないと思い、乱れた髪を手櫛で整えて、パーテーション越しに様子をうかがうと、ひとりの青年が立っている。背丈は百七十五㎝はあるだろう。色白だが、弱弱しい雰囲気はない。ほっそりとしたカラダに紺色のスーツ姿が清潔感を醸し出す。寒くはないのか、コートは着ていない。きっと、車の中に置いてきたんだろう。父とはいったいどういう間柄なのか。父という人は、神経質ではあったが、それは相手を気付かうがゆえの事で、とても面倒見がよく、人当たりのいい人だった。きっとこの青年も、父が可愛がっていた部下の一人に違いない。父が勤めていた会社は全国に支店があったので、この時間になったのは、遠方から駆けつけてくれたからであろう。
パーテーションを除けて、自動ドアのロックを外し、室内に招き入れると、青年は深々と丁寧にお辞儀をして、黙って白い何も書いていない封筒を差し出した。たぶん、急な知らせで、手持ちの封筒に香典を入れて持ってきてくれたんだ。そう思うと、取るものも取り敢えず、急いで来てくれた事になぜか、愛おしさを感じた。初対面のはずなのに、懐かしささえ感じる。まぁ、普段から職場の上司に、若い男性には甘いと釘をさされている私なのだが。
青年は父の霊前にしばらくの間手を合わせると、すすめたお茶も飲まずに帰ろうとした。引き止める私に、優しい微笑みを浮かべると再び、丁寧にお辞儀をして帰って行った。時間にして十分も経っていない。いったい今は何時なんだろう。腕時計を見ると、午前四時になろうとしている。そっか、こんな時間だもの、迷惑をかけてはいけないと思ったんだ。それに今日もきっと仕事があるはずだし。ふと、外を見るともう雪は止んでいたが、二月のこの時間はまだ暗かった。
それから、又二回ほどろうそくの火を付け替えた時に、別室で休んでいた母と妹たちがこぞって父の傍らに集まってきた。朝の挨拶を交わすと、妹も少し落ち着いたのか、お腹が空いたと言って、昨日、買っておいたコンビニのおにぎりを食べだした。母は何やら、小さな紫いろの風呂敷包みから、中の物を取り出して、まじまじと眺めている。私はというと、そんな二人を横目にしながら、青年から預かった香典の金額を、香典帳に書くために封筒の中身を確認した。しかし封筒の中にはお金は入っておらず、一枚の便せんが入っているだけだった。
便せんには、一言「ありがとう」そう書いてある。
私は胸の奥深いところから、何か得体のしれない熱いものがこみ上げてくるのを感じた。でもそれが何なのかわからない。わからないのに自分の頬をぽろぽろと涙が伝う。
「ありがとう」
その文字は紛れもなく父のものだった。
母は、私のそんな姿に気づきもせずに
「お父さんの若いころの写真もここに飾ってあげましょう」
そう言って、紺色のスーツを身にまとった、色白の、しかし決して弱弱しくはない、
爽やかに微笑む、自分の愛した夫の写真を父の枕元に置いたのだった。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
