
憧れと暴力:Anizine
「目の前に人がいる」という事実にできるだけ多く触れた方がいいと思っている。『こどもの埋葬』という仮のタイトルで本を書いているんだけど、それが理由で最近はすべてのことを子供の目から見ているようだ。
人格の土台は小学校4年生くらいの頃にはもう固まっているような気がするんだけど、だからこそソクラテスや「孟子の母」のように幼少時の教育環境が大事になる。検証できるサンプルは自分しかないと言い訳したうえで振り返ってみると、横浜の中心地という異文化や格差の多様性が存在していた土地ゆえ、割と早めに「自我のポジショニング」ができていたのではないかと感じている。
単純に言ってしまうと、同じ価値観を持った狭いコミュニティで育つと、濃縮された純粋さが育つ一方で、それ以外の考えが存在しないと感じる、もしくは意図的に排除されていくのではないかと思う。継承されるべき伝統工芸などのソリッドな分野でそれがうまく機能することもあるが、「自分とは違う生き方の人がいる」という客観的な視点がすっぽりと抜け落ちてしまう危険がある。
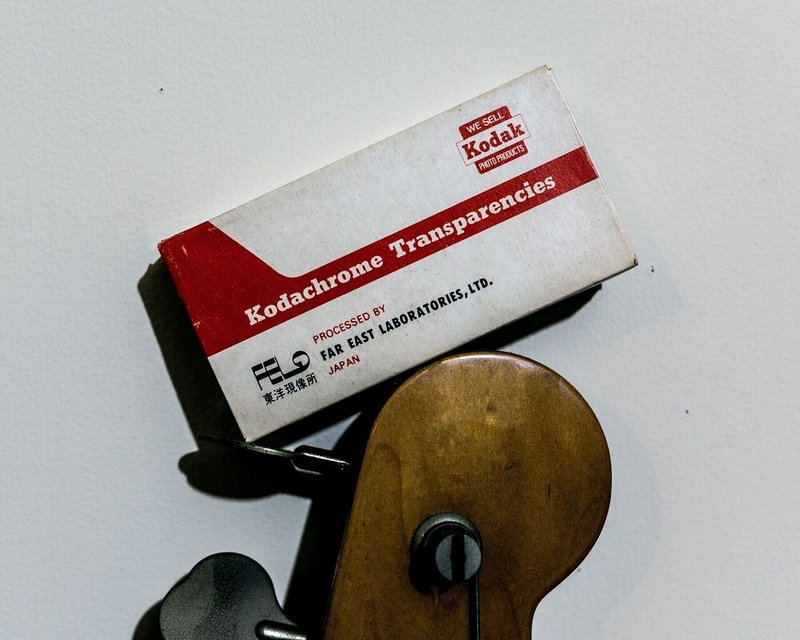
これを便宜的に「田舎臭さ」と呼ぶけど、自分のコミュニティとそれ以外、という短絡的かつ暴力的な区別がテレビを見ている自分と、テレビに映っている異文化を分断してしまう。テレビに映っている人は幻想であり、アニメの主人公と変わらないと思っているから実際に目の前にスポーツ選手やタレントが現れたりすると驚くのである。「本当に存在したんだ」と言う。当たり前だ。その分断の弊害である「憧れと暴力」は他人に向かうのではなく、自分の尊厳と関わっている。自分と自分以外の存在を知るのが自我の目覚めだけど、幼少時に気づくはずの理性的な分離をこじらせたまま大人になっている人をよく見かける。
多分、俺の方がお金は持っていると思うんだけど、どうしてもと言うならありがたくいただきます。
